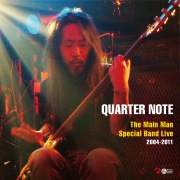くじら、結成34年にして初のライヴ・アルバムーーニューウェイヴを通過して産まれた歴史に残る“うた世界”

1982年に杉林恭雄(Vo, Gt)、キオト(Ba)、楠均(Dr)の3人により結成され、1985年にエピックソニーよりメジャー・デビュー、サポートを得ながら現在も精力的に活動するバンド、くじら(Qujila)のライヴ音源が、結成34年にして初めてリリースされた。祭囃子のようなエスニックなサウンドと、歌謡曲のようなうたごころが絶妙におりなす楽曲は、いまも強烈な光を放ち続けている。本作には、1986年12月、清水靖晃プロデューサーに迎えて行われた2ndアルバム『たまご』発売記念のライヴからアンコールの1曲をのぞいた全曲と、1stアルバム『パノラマ』発売直前のライヴから表題曲を選出した全27曲を収録。日本の音楽史実に刻むべく重要なバンドについて、杉林恭雄へのインタヴューで迫った。
サウンド・エンジニア藤井暁ワークス・シリーズ第6弾
くじら / ライヴ
【収録曲】
1. KAPPA (live 1986)
2. ハートビート (live 1986)
3. ヴェロナアル (live 1986)
4. ドラゴン (live 1986)
5. ランドリー (live 1986)
6. 夜明け (live 1986)
7. よそみ (live 1986)
8. ピアノ (live 1986)
9. たまご (live 1986)
10. 賛美歌 (live 1986)
11. NUDE (live 1986)
12. 星期天早晨 (サンデー・モーニング_好版) (live 1986)
13. こいこい (live 1986)
14. 青空 (live 1986)
15. ヨコハマ (live 1986)
16. 鋼 (live 1986)
17. エア・アタック (live 1986)
18. ひまわり (live 1986)
19. パノラマ (live 1985)
20. たまご (live 1987)
21. ドラゴン (live 1987)
22. 賛美歌 (live 1987)
23. ランドリー (live 1987)
24. 夜明け (live 1987)
25. よそみ (live 1987)
26. NUDE (live 1987)
27. ツイスト・アンド・シャウト (live 1985)
【配信形態】
16bit/44.1kHz(WAV / FLAC / ALAC) / AAC / MP3
【配信価格】
単曲 154円(税込) / まとめ価格 2,469円(税込)
※アルバムをまとめ購入いただくと、OTOTOY限定のボーナス・トラック「島」「ヴェロナアル」「ひまわり」のLIVE音源がついてきます。
INTERVIEW : 杉林恭雄(くじら)
「くじらは僕にとってひとつの究極のバンドだった」。カメラマン、マネージャー、イベンターなどの立場で、東京ロッカーズに70年代後半から深くかかわり、テレグラフレコードを主宰している地引雄一がそう言ってのけたバンド、くじらによるライヴ音源が、約30年の時を経てリリースされた。
ニュー・ウェイヴを通過しながらも、歌に重きを置いたスタイルと、どこかエスニックなアンサンブルで、シーンに属することのなかった彼ら。本ライヴ音源は、2ndアルバム『たまご』の発売記念で、同作のプロデューサーでもある清水靖晃が参加した、3人によるアコースティックに徹した最後のライヴとなる。くじらの持っている祭囃子や歌謡曲といった本質がつまった貴重な音源といって過言ではない。
また、彼らはノンPAによるライヴを行い、3人が客席を練り歩いたり、客席の真ん中をステージに観客が周りを囲むなど、いまでも珍しがられるパフォーマンスを当時から行っていたバンドでもある。それにもかかわらず、くじらのことを記した原稿は少ない。これほど独特で衝撃的なバンドをこのタイミングでスルーすることなど、どうしてできよう? 本音源のリリースを機に、フロントマン・杉林恭雄にくじらについて話を訊いた。
取材&文 : 西澤裕郎
曲を作るうちに、小さい頃に聴いたお祭りの太鼓のリズムが自分の音楽から聴こえてきて、不思議で
ーー杉林さんは、地元の名古屋にいらっしゃったとき、サザン・ロックタイプのバンドを組んでいたそうですね。
杉林恭雄(以下、杉林) : ザ・バンドが好きだったので、大学のサークル友達のような人たちと、そういうバンドを組んでいました。当時、周辺のバンドたちで一緒にPAを持ちましょうっていう動きがあって、共同でPAを買って運営しながらライヴをしていたんです。
ーーPAを持つ?
杉林 : ライヴハウスじゃない会場を借りるとPA機材がないので、自分たちで機材を買ってライヴをやろうって話になり、3バンドくらいで一緒に運営していたんですよ。そのなかの別のバンド(サタデーナイト・スペシャル)に、のちに一緒にバンドをやるキオトがいたんです。

ーーそれはおもしろい動きですね。当時、名古屋の音楽シーンは、どのような状況だったんでしょう。
杉林 : 総本山として、センチメンタル・シティ・ロマンスというバンドが西海岸風の音楽をやっていて、他にも色々なバンドがいたんですけど、東京のニュー・ウェイヴ・ムーヴメントに激しく影響された人たちが動き出したのが、僕が東京に出てくる少し前の名古屋シーンの動きだったと思います。
ーーフリクション、LIZARD、ミラーズといった、東京ロッカーズ周辺のバンドは名古屋においても影響が強かったんですか?
杉林 : そうですね。名古屋にもライヴに来ましたし。あと個人的に大きかったのが、小学校から知り合いだった古澤(隆弘)が東京の美大に行って、新宿ロフトで結成されたバナナリアンズというバンドに入ったんです。そのつながりで、個人的に東京の音楽シーンが身近になっていって。
ーー東京ニュー・ウェイヴ周辺の音楽は、それまでやっていた杉林さんの音楽とは趣が違いますよね。
杉林 : 全然違いましたね。それまでブリティッシュでもアメリカンでも、自分が好きな音楽をバンドでやるってことをしていたんですけど、ニュー・ロック的なものは一度捨てたほうがいいのかなと思ったんです。自分の内側に何があるのか探りたいと思って、シンセサイザーを買い、東京に出てきて秋葉原かどこかで多重録音できる機械を買ったんです。
ーーいわゆる宅録のような形で自分の内面を探っていったわけですね。
杉林 : そうですね。ちょうどその頃、東京で自主制作盤が盛り上がってきていたので、僕も自主制作盤を作って名前も何にも書かずに輸入盤屋さんにないまま買っていたので、そういう人たちがいっぱいいるんだろうなと思いましたね。
ーーその自主制作盤はインダストリアルなノイズ音楽だったそうで、それもまたくじらのイメージとは違いますよね。
杉林 : 当時のシンセサイザー音楽って、ある種、テープ・ミュージックだったので、現代音楽のひとみたいにテープを切ってループさせたりしていました。というのも、最初に買ったシンセサイザーの本の最初の章が「テープ・ミュージックとは何か」という内容だったんですよ。ちょっと毛色の違う人が書いた本だったと思うんですけど、自分にとっては初めて知ったので「そうか!」と納得してしまって(笑)。それで、シンセサイザーで曲を作っているうちに、小さい頃、親戚の家に行って聴いたお祭りの太鼓のリズムとか、そういうものが自分の音楽から聴こえてきて、それが不思議だったんです。さらに辿っていくと、歌謡曲もすごく強く影響していることがわかって。当時、うちにはシンセサイザー、テープ、レコードしかなかったんですけど、友達がラジオぐらい聞いたらどう? ってラジオをくれて、つけてみたら松田聖子が流れたのがきっかけになりました。それに気づいてから、歌ものもちゃんとやりたいなと思いました。
ーー別のインタヴューで、リスナーとしての杉林さんと、ミュージシャンとしての杉林さん、その架け橋になったのが、バナナリアンズだったということを拝見したんですけど、バナナリアンズは、どういうバンドだったんですか。

杉林 : どういうバンドだったんでしょうね(笑)? 僕が最初に聴かせてもらったテープは、リズム・ボックスとシンセとベースとギターで、響いてる質感が世界の他のどこにもないように感じてすごく独特だったんですよね。のちに東京に出てきて、いろいろやっているうちにギター手伝ってよとかそういう感じで、バナナリアンズに加入することになったんですよ。そのあと、バナナリアンズが解散して、藤井サンスケと2人でポマードっていうデュオでやったんですけど、そのときにすでにくじらっぽい曲を作り始めていて。ポマードは3、4回やって終わったんですけど、今回のジャケット写真は渋谷LIVE INNでやったとき、サンスケが撮ってくれた写真です。

ーーこれ、どういうシチュエーションで撮っているんですか? あきらかに、ステージ上ですよね(笑)?
杉林 : 彼にライヴのプロデュースをお願いしたんですよ。そのとき僕らはPAを使わずにライヴをしていたので、お面をかぶったダンサーの人たちが踊ったり、無謀なことをしていて、ステージ後方からぱちっと撮ったんだと思います。この写真のことは忘れていたんですけど、今回、思い出して探し出したんです。
ーー当時、くじらはノンPAでライヴをやっていたという話がでましたけど、なんでそうしたスタイルをとることになったんでしょう。
杉林 : 名古屋では自分たちでPAを持っていたくらいで、ライヴハウスのPAの音がよくないと思っていたのが1つ。あとは、中野に田中泯さんの舞塾が使っていたplan-Bっていう場所があって、くじらの初期メンバーの佐藤幸雄(すきすきスウィッチ)が舞塾に入っていたことで、plan-Bの企画に1回くじら出てみない? って誘われたのがきっかけです。plan-Bでバンドがやる場合、PAを持ち込んでやるってことだったので、ないなら、なしでやってみようってのが最初なんですよ。完全に舞台もなにもない、舞踏をやるところなので、お客さんの間に入って演奏しましたね。
ーーその演奏が、思った以上に手応えがあったと。
杉林 : そうなんですよね。それまで、なにか違うなと思ってやっていたんですけど、こういうことなんじゃないかと思えたんです。それまで、ステージに立っていても、自分が求めていたものを掴めていない感じが強くあったんですよね。
僕の顔がおもしろかったみたいで、次なにか一緒にやりましょうっていわれて(笑)
ーー今回、くじらの音源を聞いて、祭り囃子の感じだったり、ヴォーカルのゆらぎとか、普通のロックとは違う異質な要素を感じたんですけど、活動初期からそうしたものが反映されていたんでしょうか。
杉林 : それは最初からあったかもしれないですね。もともと、シンセを使って、昭和歌謡だったりお祭りが浮かび上がってきているので、結果的にロックっぽい形になったとしても、いきなりロックに入る人とは全然違うものになっているんですよね。
ーーシンセサイザーで産まれたノイズから抽出されたというのが興味深いです。
杉林 : 最初の「KAPPA」のデモは多重録音で作ったんですけど、それもシンセのなかで歌っている音なんですよ。どうしてああいう曲を作ったのか、今ではわからないんですけど、くじらというバンドがある前からある曲ですね。
ーーこの曲は本当に中毒性があります。意識して作ったわけじゃないんですね。
杉林 : 全部無意識です。シンセで多重録音しているなかで、出てきました。
ーー1983年には東名高速浜名湖SAでゲリラ・ライヴをされたり、ノンPAだったり、型にはまらないことをされています。他にはないものをやろうという思いが強かったんでしょうか。
杉林 : 他というよりは、自分ですね。自分がやったことと違うことをやりたかった。ただ、あまりそれをやっていると行き詰まるので、そんなにも変わることはやっていないです。そんななかで、新宿LOFTで地引雄一さんと知り合ったんですよ。曲を聴いて云々というよりは、僕の顔がおもしろかったみたいで、次なにか一緒にやりましょうっていわれて(笑)。それがラッキーだったというか。
ーー地引さんとは密に行動を共にしていたんですね。
杉林 : しょっちゅう一緒にいるような感じでしたね。いまだによく会うんですけど、彼も当時のニュー・ウェイヴを型で聴いていないんですよね。全体をおもしろがっている人で、そのなかにくじらもいたってことなんだと思います。
ーー『ストリート・キングダム』など地引さんの著書を読むと、くじらに対して相当強い思い入れを持っていたことが伝わってきます。
杉林 : テレグラフから、くじらの音源を出しましょうって時期に、地引さんが倒れちゃったんですよね。そのタイミングで、メジャーのレコード会社からオファーがあって、ディレクターの福岡智彦さんと知り合ったこともあり、彼のいるレコード会社から出しましょうってことになったんです。
ーー福岡さんはどういう方なんですか。
杉林 : もともと太田裕美さんやチャクラのディレクターだったんですよ。板倉文さんがやっていたキリング・タイムとくじらが一緒にライヴをしたことがあって、それを観てビックリしたそうで、くじらのライヴに来るようになって。
このライヴ音源はほんとに3人が全力で歌っていて、PAを使うようになってすぐの音源

ーーくじらはメンバーが増えたり、形態を変えたり、様々な変化をしていきますが、今作はどういった時期のライヴ音源なんでしょう。
杉林 : 今回のライヴ音源は3人でアコースティックをやっている最後のライヴだと思います。このあとは、こんなに歌わなくなりますし、ミニマルなファンクっぽいリズムを指向していきます。それからベースが入って4人になり、やがて9人編成のくじらドラゴンオーケストラに発展していきます。このライヴ音源はほんとに3人が全力で歌っていて、PAを使うようになってすぐの音源ということになります。まあ PAを使いだしたのでこの音源も残っているとも言えます。
ーー曲によって音の印象が違いますけど、PAからの2ミックス音源が基本になっているんでしょうか。
杉林 : 基本ラインからとっていますね。藤井(暁)さんはマイクとラインの両方で録っていたんですよ、だからバランスがおもしろくて、遠くのほうで歌っているやつはどっかのラインのマイクで録った音だと思います(笑)。
ーー曲の響きが全然違いますよね。
杉林 : それは会場の性質ですよね。FM東京ホールは天井が広くてポーンと音が広がっている。一方の横浜ビブレホールはちっちゃいので、デッドな感じで録れていますよね。演奏もアプローチが違いますしね。
ーー節目的なライヴでもあったんでしょうか。
杉林 : そうですね。この後、何回かやったあと、僕はエレキ・ギターになっちゃいますし、もっとストイックな感じでファンクになりますしね。次はなにやろうって感じでいました。
ーーアルバムはスタジオ・レコーディングですし、音源とライヴでは大きく違ったんでしょうね。
杉林 : そう。だからアルバムを作るとき、どうやって作ろうかって、すごく悩んだんですよ。今回のライヴ・アルバムは貴重で、1枚目、2枚目と打ち込みでつくっているので、それしか知らない人はびっくりすると思うんですよね。当時のライヴは、音源とは全然違う世界だったので。
ーーFM東京ホールでのライヴは、2ndアルバム『たまご』の発売記念で、同作のプロデューサーでもある清水靖晃さんが参加されています。『たまご』のレコーディングは、どういうふうに行われたんでしょう。
杉林 : そのとき、靖晃さんはパリに住んでいたので、パリのスタジオで録音しようってなって、こっちは浮かれている状態でしたね。当時、日本のスタジオはどんどん最新機材が入ってきていたんですけど、パリは本当に古くて汚いスタジオで、いい感じでしたね。機材もアナログなもので。もちろん、靖晃さんは当時サンプラーとかも買っていたので、そういう機材も使いながらレコーディングしました。
ーーさきほどおっしゃっていた、杉林さんが求めていた音の質感は再現できたんでしょうか。
杉林 : 不思議なもので、『たまご』には再現されているんですよね。1枚目はパリッパリの打ち込みみたいな音なんですけど、2作目である『たまご』は、たまごっぽい質感だと思います。靖晃さんが入っていることもあるんでしょうね。
ーーこのあとも作品を作っていかれますが、創作を重ねるなかで、シンセサイザーのノイズのなかから浮かび上がってきた祭囃子など、杉林さんの根幹にあるものは生き続けていると思いますか。
杉林 : 生き続けていると思います。もうちょっと広がって、アジアっぽいというか、そういうイメージになっていきました。もっと大きく捉えられるかなってところまで広がって、それを音楽にしていった感じですね。
ーー2000年前後にはメジャーを離れて、キオトさんと2人でウテナというユニットをはじめましたが、これはどういう経緯ではじめたユニットだったんでしょう。
杉林 : 軽くなれないかな、と思っていたところがあってやっていました。それは、キオトのテーマだと思うんですよね。それって結局、過去を引きづってやってきましたし。
ーーくじらは、活動休止だったり、解散をしたわけではないんですよね。
杉林 : 結局、解散したことも、停止したこともないんですけど、EPICを離れる前に9人編成になった後、メンバーが離れていったんですよ。最終的に僕1人になっちゃうんですよね。そこで、自分としては一旦終わろうかと思っていたんです。1人でやっていてもしょうがないと思っていて。それからちょっと後の話になるんですけど、MUTE BEATにいた松永(孝義)くんっていうベーシストに練習スタジオに来てもらって、2人でくじらの曲を何曲かやっているうちに、もうちょっとやりたいなって気持ちになって。そのあと、ドラムの楠が戻ってきてくれて、淡々とやっている感じですね。
歴史に埋もれてしまっているのかなって。このあとにくじらのようなことをやっている人もいないし
ーー2016年現在のくじらは、どういうスタイルで動いているんでしょう。
杉林 : いまは、基本4人編成です。僕と楠と中原信雄くんっていうヤプーズのベーシスト、あと近藤達郎っていうキーボードです。みんな忙しいので、僕1人のときは1人くじらっていってやってますけど(笑)。
ーー今回、約30年前のライヴ音源をリリースすることに対しては、どういうお気持ちでいらっしゃいますか。
杉林 : 藤井暁の部屋にあったテープの山の中に、くじらのライヴ音源があったっていう連絡をディスクユニオンの方からいただいて。「聴いてください」って、だいぶ前に送られてきたんですけど、当時の音源を出してどうなるのと思って、聴いてなかったんですよ。それで放っておいたんですけど、いよいよやりたい! って話になったので、聴いてみたら悪くないなと思って。これだったら、ちゃんと関わって出したいなと思ったんです。
ーー30年前の音源を聴いて、やはり根幹の部分は変わっていないというか、しっかり納められていると感じられたわけですね。
杉林 : むしろ、当時の自分たちがこんなアイデアでやっていたんだなっていうのが、客観的に伝わってきましたね。
ーーこんなにすごい音楽をやっていたくじらというバンドの情報が、Webもそうですけど、ちゃんと伝わってなかったり記録されていないのがショックでした。
杉林 : 僕のせいもあるんですけど、日本のロック・シーンみたいなどこにも入れなかったんですよね。バンドに対して申し訳ないなと思いますし、歴史に埋もれてしまっているのかなって。このあとにくじらのようなことをやっている人もいないし。メジャー・シーンに行ってしまうと、なんなのかわからないって人たちも多かったでしょうし。
ーー後追いの僕の世代からしたら、じゃがたらを聴いたときのような、原始的で血肉が騒ぐような感じがしました。
杉林 : のちに、じゃがたらのサックスを吹いていた篠田昌已が、9人時代のくじらに入りましたからね。
ーーそうだったんですね。最後に。2016年の杉林さんが追い求めているものってなんなんでしょう?
杉林 : うまく言えないんですけど、「うねり」みたいなものなんですよね。そういうものがある場所にいたい。いま、高円寺の円盤で2ヶ月に1回、初めてお会いする人と、その場で曲を作るってことをしていて、つい数日前もやったんですけど、すごく楽しいんですよね。終わってみるまで、どうなるかわからない。この間も、紙芝居の人と一緒で、あれはどうしようかって悩みました(笑)。絵を見ながら曲を作りまし たけどね。そんなことをやったりしつつ、くじらもすごくいい感じだと思うんですよ。昔の音とは違うけど、やっていることの本質は全然違わないと思います。
RECOMMEND
戸川純とのユニット、ヤプーズの中原信雄をメンバーに迎えて、バンド編成としては約15年ぶりとなったオリジナル・アルバム。
PROFILE
くじら(QUJILA)
杉林恭雄(Vo, Gt)、キオト(Ba)、楠均(Dr)の3人により1982年結成。1985年、エピックソニーよりメジャー・デビュー。凛としたヴォーカルとサウンドによる不思議なポップさが評判を呼び、松永孝義、中原信雄、近藤達郎のライヴ・サポートを得ながら現在もなお精力的に活動中。