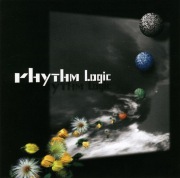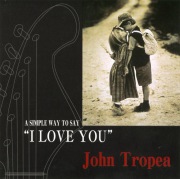それまではロックに夢中だった。中学3年の時だったか、高校1年だったか、ジェフ・ベックのアルバム『ブロウ・バイ・ブロウ』と『ワイアード』を聴いて完全にやられた。凄い衝撃だった。この2枚のアルバムがきっかけとなって、当時クロスオーヴァーと言われた音楽に一気にハマった。

リー・リトナー、ラリー・カールトン、ジョージ・ベンソン、デヴィッド・サンボーン、グローヴァー・ワシントンJr.、トム・スコット、ボブ・ジェームス、アール・クルー、ジョージ・デューク、スタッフ、クルセイダーズ、ジョー・サンプル、ウェザー・リポート、マーカス・ミラー、チック、・コリア、ダン・シーゲル、渡辺貞夫、渡辺香津美、プリズム、カシオペア…。これらを聴いたのは78年〜81年に集中していた。当時のクロスオーヴァーは、そのほとんどに歌がなく、楽器だけでの演奏曲。その時ジャズやロックやR&Bなんかが歌なしで融合された音楽がクロスオーヴァーなんだなと理解し、ミュージシャンの演奏力の凄さ、メロディーの良さ、音楽スタイルの新しさ、全体から伝わるあまりのかっこ良さから、最強の音楽だと思ったものだ。そして80年代前半くらいからクロスオーヴァーはフュージョンという呼び方に変わっていった。この“フュージョン”という言葉は鳥山雄司さんのインタビューにもある通り、日本人のクロスオーヴァー・ミュージックを総称する意味合いが強いと思う。
アメリカでは、80年代半ば頃からSmooth Jazz(スムース・ジャズ)というラジオ局が使い始めたフュージョン・スタイルの一つで、アドリブ・パートが少なく、よりメロディーを聴かせることを重視させた音楽が主流になった。要はラジオ局が仕掛けた音楽フォーマットだ。根っこはジャズやフュージョンだけど、より洗練され都会的でかっこ良く、曲の時間も短くて聴き易いスタイルの音楽。楽器のみの楽曲だけではなく、歌入りの楽曲も混ざっている。さらに、カテゴリーの解釈が広くなる。R&B、ソウル、AOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)といったジャンルの音楽もSmooth Jazzには含まれる。日本では中々Smooth Jazzという言葉は浸透しなかったが、当時アダルト・コンテンポラリーとかブラック・コンテンポラリーと言われた類がSmooth Jazzと言っても過言ではない。まあ、クロスオーヴァーが登場して以降、クロスオーヴァーが源流にありながら少しずつ音楽のスタイルが変化していったという訳だ。音楽のスタイルや解釈が変化することによって、それらを総称する呼び方が増えたということだ。間違いなく言えることは、クロスオーヴァーもフュージョンもSmooth Jazzも音楽が上質であるということ。これらを演奏するミュージシャンには高度な演奏力や音楽知識が不可欠だ。いい音楽、上質な音楽は絶対に廃れないし、永遠に聴き継がれる。
昨年25周年を迎えたビデオアーツ・ミュージックには、これらと、そして一般的に言われるジャズの音源が豊富にある。(ここでは、これらをジャズ/フュージョンと呼ばせてください)ジャズ/フュージョンを初めて聴くという方に7枚の分かり易いコンピレーションをご用 意させて頂いた。既に良く知っている方にも充分楽しんで頂ける内容だ。また、ジャズ/フュージョン系のアーティストのアルバムも第1弾として約30タイトルご用意させて頂いた。以降、その他のタイトルも順次アップさせて頂きたいと思う。いずれも 上質な音楽ばかりだ。是非好きになって頂いて大いに聴いて頂きたく思う。
J-POPを批判する訳ではないが、テレビやラジオなどで耳する昨今の多くの音楽は正直言って質が悪いと思う。今の若いリスナーやこれから音楽を聴く子供たちが可哀想だ。それらばかりがフィーチャーされ過ぎて、上質な音楽に中々スポットが当たらない。音楽が消費物のように扱われている現状をみるのが辛い。周囲に流されずに自分自身で聴いて見定めて、自分の好きな音楽を見つけて聴き続けて欲しい。そして、いい音楽を沢山聴いて欲しいと切に願う。(text by Yukihiro Hattori)
まずは、これを聴いてみよう。selected by Yukihiro Hattori
鳥山雄司と『Guitarist』について
本特集では、1981年にデビューし、日本のトップ・ギタリストであり続け、アレンジャー/プロデューサー、そしてJ-waveでナビゲーターも務める鳥山雄司に「フュージョンってなに?」って単刀直入に聴いてみた。さらには上記にあるように、日本のジャズ/フュージョン界を見続けた服部幸弘にototoy特製のジャズ/フュージョン・コンピを選曲頂いた。まずは特製コンピを聴きながら、鳥山雄司のインタビューを読んで欲しい。そうすれば、あなたが感じるジャズ/フュージョンは、全く違った価値観を持つだろう。(interview and text by Jinichiro Iida)
——昨年出された『Guitarist』は、どういうきっかけで、何故出そうと思われたのですか?
インストゥルメンタルのアーティストであるという再認識をしたかったんです。僕は、作曲家、音楽プロデューサーとか編曲家という仕事が、年間の音楽活動の8割を占めています。でも根本はギタリスト。30年以上仕事をしていると、今まであるものをぐるぐるやってても仕方ないし、やっぱり自分から発信しないと先はないよねって思う。誰と組むとか、コンピューターを使うとか、そういうのを離れて「ギター一本でやってみようか?」 っていう話をスタッフとしたこともあったんですね。もともとボサ・ノヴァのバーデン・パウエルっていうブラジル人が、小学生の時からずっと好きだったんです。それをただコピーしていたときもあるんですけど、単純にコピーするんだったら、ショーロとか、完全にブラジルをやっている人もいるわけで、かぶってもしょうがない。ゲッツ・ジルベルトとかね、ジャズのスタン・ゲッツがジルベルトと組んで、あれは一種のクリード・テイラーの作品だと思うんだけど、そういう噛み砕いたわかりやすいものが1960年代にあったなと。だから、AORとか自分の聴き育った、アラウンド40〜50代の人達が20代のティーンエイジャーのときに「おお、これよく聞いた! 」っていう青春の蘇るAORっていうジャンルを、ギター一本でやってみようかなって。結果論でもあるんですけど、ゲッツ・ジルベルト的な手法ですよ。
——自分的にも挑戦的な一枚だったと?
そうですね。曲はたくさん候補を出しましたが、30曲位にまで絞り込んで、ギター用に全てアレンジをしました。曲はいいんだけど、ギター一本でやるとその感じが出ないとか、意外とあるんですよね。噛み砕いて、リハーモナイズしてギター用に作ると2、3日かかるんです。で、録ってみたけどダメだからボツ、みたいなことも何曲かあって。
——新たに挑戦しようとしたきっかけと、そのモチベーションは何だったのでしょうか?
ギター一本で、っていうところにすごいこだわったんです。アルバムのコンセプトはそこなんですけど、長いこと音楽を演奏してきて、さらに4、5年ずっとJ-WAVEで番組をやっていると、ジョー・パスとかの、無伴奏ギター・アルバムとかあるじゃないですか? ああいうものに憧れるんですよね
——きっかけはあるのでしょうか?
なんでしょうね。アンサンブルの中では、この曲はギターがグルーヴをだすとか、ハーモニーを重点的に出すとか、各楽器の曲の中での役割があるじゃないですか? でも無伴奏、つまり一人で完結させるには、グルーヴもだしてメロディもたたせて、ハーモニーを響かせる、っていうポップスの三大要素を全部同時に自分でできる。超並列思考ですよね。それにすごく憧れる。クラシックのミュージシャンとフラメンコの人達に影響されていると思いますね。ヨーヨー・マの無伴奏のバッハとかね。今だとスパニッシュギターはトマティートとか。ミュージシャンとして憧れますよね。
——独立しているところに憧れる?
自分で表現しきれる。自分の音楽観はアンサンブルじゃないと出来ないっていう前提は、プロヂューサー/アレンジャー的な俯瞰的な立場だと思っているんですね。一ミュージシャンとして、自分のすべてを表現するには無伴奏が一番手っ取り早いかなと。

——なるほど。今回オーバー・ダビングはなしっていうところも、こだわりがあったのでしょうか?
クラシック・ギターって、ピアノと同じで全部指番号がふってあって、その指番号で弾かないと次にいけなかったりするんですよ。4小節目はその指使いじゃなくいけたとしても、5小節目に絶対にいけなくなっちゃう。フリー・クライミングみたいなもの。あれも3点支持で、4点目をどこに動かすかで先に進めなくなったりするじゃないですか。直感で行くんじゃなくて、次の手次の手、って考える頭の使い方が、30年以上ギターをやってきてなかったんですよ。今だったらDVDやビデオがあって、「あ、ヴァン・ヘイレンのライト・ハンドってこういうふうにやるのか!」って視覚で入ってくる。でも僕たちがギターを始めた中学、高校の頃ってそういう視覚的なものがなくて、レ→ミって動く音は、3弦の7→9フレットなのか、2弦の3→5フレットなのかどうかって、全部耳で聴きわけていたんですよね。だから運指がどうのっていうより、きっとこの人はこうやっているんだろうって、直感でフォームを身に付けた。わりかしものすごい無茶なことをしてギターを弾いてたと思うんですよ(笑)。それが指使いとかロジックを知ったことによって、どうやって弾くんだろうっていうところが簡単に弾けたり。普通だったらオーバー・ダビングをしないとハモれないけど、こういうふうに弾けば3度つけられるよねってわかった。ある程度ロジックなんですよね。それを使いはじめたから、披露したかったんですよ(笑)。
——どうやって学ばれたのですか?
クラシック・ギターの教則本をみながらとか、その指使いを見ながら練習していったんです。
——ロジックを学ばれたのは最近なんでしょうか?
そうですね、音楽理論はもちろん勉強していましたけど。ピアノとか全体のアンサンブルの中で、こういう響きだから、ギターはこうでなきゃいけないみたいなことに関するロジックはあったけれど、ギタリストの奏法に関するロジックは持ってなかったんです。
——『Guitarist』は、どうやって録音したのですか?
ブースにマイクを6本くらいたてて。トップとボトムと、内蔵のコンデンサー・マイクをひとつと、オフのステレオLR。それにラインも録って。失敗したら頭からやり直せるんで、基本自分で録りました。
——一曲録るのにどのくらい?
ライヴで通して弾けるようにならないといけないから、譜面かいてアレンジして練習して、2日半くらい。そこから録りはじめて… 1曲4日間くらいですかね。
——ほぉ! 自分的な合格点はどこになるんでしょうか?
まずは、メロディがきちんと伝えられているか、ということです。ベースの間でハーモニーを入れながらメロディを入れて行くじゃないですか。ベースとハーモニーが強過ぎると、メロディがたたなくなってしまう。自分ではメロディを弾いているつもりなんだけど、客観的に聴くとメロディがたってなくて、わかりにくい。基本的に今回インプロバイズは除外しているんです。だから、サイズ、流れやコードのプログレッション等、きちんと枠をきめて録り始めたので、それを譜面から離れてちゃんと弾ければ一応合格ってしましたね。
——実は、会社で『Guitarist』を聴いていたら、22歳の子が「これ誰ですか? 」って聴いてきたんですよ。パンク、メロコアとか聴いてたような子なんですけど。誰のカバーなのかすら知らない人に届いたことが印象的でした。このアルバムを、誰に聴いて欲しいって思いはあるのでしょうか?
僕らと同世代の今50歳くらいの女性って、それこそメロコア聴いている子達のお母さんってそのくらいじゃないですか。お母さんが聴いていた音楽を、小さいときに耳に入っていたかもしれないですよね。アース・ウィンド&ファイヤー「ファンタジー」とか...。だから同世代とその子供に聴いてもらいたいとは、何となく考えていたので、AOR等のメロディが良いものを重視しました。『イマージュ』ってヒーリング関係のCDで、コンピレーションなのに150万枚売れたんです。要するに、お茶の間サイズで、歌詞が無くて、なんとなく毎週繰り返し聴いていると、記憶に残るって事なんですよ。理屈じゃなくて、体でわかったんでしょうね。
——鈴木祥子さんに話を聞いた時に、20年超えたら、自分に挑戦しないと楽しいことがないとおっしゃられていました。それが自分のモチベーションだと。鳥山さんも、音楽を続けられる上で、そういう部分はあるのでしょうか?
僕はねぇ、サービス精神が旺盛なので(笑)、聴いてもらって人が幸せになってくれることがモチベーションなんです。例えば、水泳で毎日一キロ泳いで、次は二キロ泳げるようになる! みたいな自分への挑戦はあると思うんですけど、そこに自分を追い込むきっかけは、やっぱり聴いてくれる人が幸せになってくれないと。自分だけがどんどん上がって行くと、孤高の人になってしまうじゃないですか。ジェフ・ベックみたいな(笑)。あれはあれで悪くないんだけど、あれをずっとやっているとつらいかなって。
——鳥山さんの活動って、ライヴがメインなわけでもないじゃないですか。ライヴは楽しんでいるかどうか、お客さんとの距離感でわかると思うんですけど、それ以外では、どういうところで感じ取っているのでしょうか?
これは本当に下世話な話で、数字でしか表せないと思うんですよね。それ以外の部分でいうと、パッケージの売上が下がっている中で、配信のレビューとか、書き込みとかで満足してくれているのをみていくしかないかな。昔は売上の数字でしかわからなかったけど、今は誹謗中傷も含めて、パーソナルではあるけど反応は見れますもんね。そこはウェブの力を信じようかなって思っていますね。
フュージョンて何?
——今回、フュージョンというものを紹介したいんですね。フュージョンは、ブレイクした時期があって、それを体験していない人たちにとっては、とても入りにくいジャンルだと思うのです。まず、どうやって楽しんだら良いのでしょうか?
歴史的な話になってしまうんですけど、フュージョンっていうカテゴリーを紹介する前に、クロスオーバー・ミュージックっていうジャンルがあって。そこから説明しないと、偏った話になってしまうと思うんです。フュージョン=ジャパニーズ・クロスオーバーなんですよ。わかりやすい例でいうと、マリーナ・ショウっていうR&Bのシンガーが70年代に出した超有名なアルバム『Who is this bitch, anyway?』があるんですけど、それはハーヴィー・メイソンっていうドラマーとか、ラリー・カールトンとか、デヴィッド・ティー・ウォーカーとか、チャック・レイニーっていう、いわゆるR&B、ジャズやソウルのアメリカを代表する有名ミュージシャンとマリーナ・ショウが組んだことによって、R&Bを超えた、エンターテインメントなものが出来たんです。誰かと誰かが組んだことによってできる化学反応がクロス オーバーなんですけど...。なんか、歴史の授業みたいだな(笑)。
——大丈夫ですよ(笑)。
元を正すと、マイルス・デイビスが、ジャズなのにアコースティック楽器を捨てたんですよ。捨てたというか、これだけじゃダメだと。ここだけでぐるぐるしていちゃ先へ行けないと。彼のバンドにはチック・コリアがいたんですけど、「明日からエレクトリック・ピアノを弾け」と。ロン・カーターっていうベーシストには「エレクトリック・ベースを弾け」と。「まじすか! 」ってなりますよね(笑)。響きが変わっちゃうから、大変なことですよね。マイルスはトランペットにピックアップをつけて、WOWOWペダルを通して、電化させたわけです。メンバーを変えないで、楽器を変えて挑戦したんですね。で、『マイルス・イン・ザ・スカイ』っていうアルバムを作った。これが多分クロスオーバーっていわれるものの走り。エレクトリックだったら、他が音量が大きくても大丈夫だから、ドラマーもシンバルのレガートなものじゃなくて、パワフルに叩けるからリズムがたってくる。そこにパーカッションも入れて、ギターも入れようぜって話になったんです。
一方で、ウェス・モンゴメリーのバーブっていうレーベルのプロデューサーだったクリード・テイラーっていう人がいて。ウェス・モンゴメリーは元々フル・アコースティックのジャズ・ギターを弾いてコンボ編成でやっていたんですけど、彼はそこに大編成のストリングスを入れて、イージー・リスニング・ジャズを作ってしまった。コアなものよりビートルズのカバーをやっちゃえみたいな感じで大当たりしたんです。そのクリード・テイラーが独立して、CTIっていうレーベルをつくった。そこからボブ・ジェームスとデオダートとか、アレンジャー/キーボード/コンポーザーだった人達をばんばん引っ張ってきて、曲を作らせた。衝撃的だったのは、デオダートが、2001年宇宙の旅のリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」を、エレクトリック化して、ビートを付けて、10分くらいの組曲的なものに仕上げたんです。ある意味プログレッシブ・ロックだったんですよね。
また、イギリスのプログレッシブ・ロックのエマーソン・レイク・アンド・パーマー(ELP)が『展覧会の絵』をやっているときに、アメリカではデオダートとかボブ・ジェームスが『禿山の一夜』とかやっていたんですよ。シンクロニシティというか。アプローチは違うんだけど、同じ年代でロックもジャズの人も動いていたんです。そこにジョン・マクラフリンのジャズ・ロック・バンド、マハヴィシュヌ・オーケストラっていうのがでてきて、『火の鳥』っていう強烈なアルバムを作った。それもやっぱりフュージョンとは言えなくて、クロスオーバー・ミュージックなんですよね。全く関係ないイギリスでは、ELPとかピンク・フロイドとかが、クラシックの要素やロックの要素も混ぜ合わせて。アメリカでは、ジャズの要素やクラシックの要素を混ぜ合わせてって各地で同じようなことをやってた。アメリカのほうがゴージャスで、弦をたくさん入れたりして、聴きやすいことはやってましたけどね(笑)。そして、75年にジェフ・ベックが『ブロー・バイ・ブロー』っていうアルバムを出しちゃった。やってくれちゃいましたねって(笑)。あれがすべてのはじまりな気がしますね。
——そうなんですか!?
それまでジェフ・ベックって、ロッドスチュワートをひっぱってきたりとか、やっぱりボーカリストがいたんですよ。でもこれは、インストゥルメンタル・アルバムだったんです。そして、アメリカでは、ジョージ・ベンソンもポスト・ウェス・モンゴメリーとして、イージー・リスニング・ジャズをはじめた。アメリカではジョージ・ベンソン、マハヴィシュヌ・オーケストラ。かたやイギリスはジェフ・ベックが『ブロー・バイ・ブロー』をリリースして、どんどんインストゥルメンタル・アルバムがビルボードのトップ10に入りだしたんです。
——すごいですね(笑)。
今だったら、考えられないじゃないですか(笑)。インストがビルボードのトップ10に半年間いたっていうことがあったし、その頃は、インストと唄ものがチャートの中で共存していたんですよ。けれど、そこからインストの人達は孤高の人になっていくんですよ。より自分たちをブラッシュ・アップするために、スキル・アップしようとしたんですよね。昨日までは、このテンポで1小節に32個しか音を入れられなかったけど、2ヶ月後には64個入れるぞ! みたいなね(笑)。
——なるほど。
すると今度は一糸乱れぬタイトなリズムに、非常にテクニカルなものになった。それを始めたのがチック・コリア。彼は60年代末にリターントゥフォーエバーというストレートアヘッドではないジャズとブラジリアンやスパニッシュ・ミュージックをクロスオーバーさせたバンドを作ってクロスオーバー・ジャズを牽引していました。80年代になってチック・コリア・エレクトリック・バンドっていうのを作ったんですけど、それが一糸乱れぬマス・ゲームみたいな感じ(笑)。ついて行けない人は、全くついて行けなかった。時を同じくして日本のミュージシャンたちも、よりタイトで難易度の高いものを目指すようになって、日本のフュージョンができたと思うんです。そこにたどり着くまでのネタは『ブロー・バイ・ブロー』やジョージ・ベンソンの『Breezin'』だったりするのは間違いないんだけど。
——そうなると、リスナーはもっとついていけないですよね。
そうなんですよ。リスナーは、インストといっても、グルーヴィーで歌詞がなくても楽しめる内容だったらいいわけじゃないですか。もちろん、かっこよくて。そのかっこよさの矛先が、テクニックとか、ものすごい難しいフレーズのユニゾンとかになっちゃった。その反動でT-SQUAREのF1(Truth)等の、メロディが浪々としていて、8ビートのシンプルな作品みたいなのもでてきた。極端にどっちかにいっちゃったんですよね。つまり、70年代中盤のいろんなものが混じっているっていう時とは、完全にかけ離れたものになっていったんです。85年くらいの話でしょうか。
——フュージョンの歴史で面白かった時期っていうのは70年代で、そこから分かれてしまったんですね。
やっぱり、マイルス門下と、クインシー・ジョーンズですよね。要するに、今レーベルを持っていたり、フュージョンの大家と呼ばれている人を育てたのは、この二人なんですよね。ブラザース・ジョンソンもクインシーが発掘してきたし、70年代後半にウェザーリポートのバードランドって曲がヒットしたんですけど、80年代最後に、クインシーがカバーしてもう一度ヒットさせたりとかね。だから、まずクロスオーバー/ジャズ・ロックっていう分野から入ったほうが、楽しい。R&B色の強いクロスオーバーとか、ジャズ色の強いクロスオーバーとか。
——なるほど。
しかも、そのクロスオーバーの時期って、曲やメロディが良かったんですよね。それでヒットしたところもあると思う。あとは、サブ・カルチャーに関して、敏感なミュージシャンが多かったんです。ハービー・ハンコックだったら、ディスコが流行っているから、ボコーダーを使ってディスコ・チューンの曲を作ってヒットさせたり、ヘッド・ハンターズっていうバンドに至っては、完全にダンス・バンドなんですよね。今、はやっているものを取り込む力があった。
——時代と一緒に進んだんですね。
音楽がどうのこうのっていうよりは、音楽と文化の擦り合わせ。それが上手くいっている時って、音楽も面白いじゃないですか?
——フュージョン=T-SQUAREっていう印象になったのはなんでなんでしょうか?
日本特有のものだと思うんですけど、やっぱりF1じゃないですか。F1ものが流行る前後って、日本語で楽しめるものって、以外とロックのBOOWYとかしかなかったと思うんですよね。そんな時期に、T-SQUAREは、逆にインストでわかりやすいメロディの8ビートのものを作ったんですよね。
——誰がフュージョンって言ったのでしょうか?
これは、ジャパニーズ・フュージョンですっていう打ち出しをしたんですよ。この道では、カシオペアのほうが老舗なんだけど、彼らは、スキル・アップと孤高の道にいってしまったと思うんです。でも世界的には、レベル42とか、ロンドン系のABCとか、カルチャー・クラブとか、カジャグーグーとか、80年代のネオロマンのバンドってみんなカシオペアのファンなんですよね。
——へぇ!
デュラン・デュランとかもね。ヨーロッパにはカシオペアのようなスマートでタイトなインストものがなかったんですよね。アメリカだともっとハービー・ハンコックとかチック・コリアのような脂っこいもので。わりかし日本の文化って、ヨーロッパでは刺激的にうつるじゃないですか。
——では、僕らよりももっと下の年齢の人達に、ジャズ/フュージョンを聴いてもらうには、どうしたらいいのでしょう? これをまず聴いたらいいとかってありますか?
今ほんと景気悪いじゃないですか。文化って言ってるよりは、まずは仕事だよねっていう若い人が多いと思うんですよ。TPOにあわせて音楽を聴くって言う感覚をどこかで身につけてもらわないと、なかなかジャズ/フュージョンに目がいかないと思うんですよね。仕事もお金もないから、「頑張るぞ! 」って、自分を元気づけてくれる音楽が多いけど、それだけじゃないだろうと。今だったら、ルーツをみてほしいかな。2年前くらいにすごいと思ったのは、ジャネット・ジャクソンが、ハービー・ハンコックの「ハング・アップ・ユア・ハング・アップス」の超有名なギターのリフを使っているんですけど、そのリフって、オリジナルは一拍目から始まっているのに、半拍ずらしてサンプリングして使っているんですよ。知っている人からすると、相当気持ち悪いんだけど、こんな風に、音ネタって、たくさん使われているじゃないですか? その音ネタがかっこいいと思ったら、それを辿って行くのが一番入りやすいかなって思うんです。
——そうですよね。ヒップホップとか、今それが主流ですもんね。
この前もクラブで、ものすごくレアな、ラルフ・マクドナルドっていうパーカッションの人のアルバムの一部だけ使ってる曲がかかってて。そういうネタになっているものを掘り下げて欲しいと思うんです。あとは、ユニクロじゃないところに行って欲しいんです。
——ユニクロ?
つまり、もう少しセレクト・ショップというか文化の匂いのするところ。ビームスでもユナイテッド・アローズでもどこでもいいんですけど。置いてある洋服自体が単一のブランドではないってことが大事なんです。自分でちゃんと考えてコーディネートをしないと成り立たない服をおいてある店。なぜかそういうところでクロスオーバー・ジャズってよくかかっていたりするんですよ。ユニクロでは多分かかっていない(笑)。セレクト・ショップの魅力って、自分の好きなものをじっくり選んでドレスアップやドレスダウンができるところだと思うんです。クロスオーバー・ジャズも聞き手次第でカジュアルな気分になったりフォーマルな気分になることも出来る…。とても自由度が高い音楽だと思います。
——その話を聞くと、クロスオーバー・ミュージックを聴いてみよう、って提示したほうがわかりやすいんでしょうね。
そうかもしれないですね。フュージョンっていうジャンルを確率した功績は、T-SQUAREとカシオペアはすごいあると思うんですよ。日本のフュージョン史をある種作った。アマチュア・バンドでもやりやすい、難しくないっていうものを率先してやっていたし、バンド・スコアもバシバシ売れていた。これならうち等のバンドでもできるかも! って。先週まではツェッペリンをやってたんだけど、ボーカルは今ひとつダメだし、俺ももう少しちゃんと楽器弾きたいしってなったときに、T-SQUAREの音楽はちょうど良かったんですよ。フュージョンっていうのは、一種のムーブメントだった気がするんですよね。ジャンルで押し並べて、「これいいよ」って言うには、クロスオーバー・ミュージックのほうがいいかもしれないですね。でも今クロスオーバーっていうと、ポップスとクラシックの融合のことを言うんですよ。ジョシュ・グローバンっていう、オペラ的な発声をする人がいて。あとサラ・ブライトマンとか、スーザン・ボイルとか。ああいう人達って、クロスオーバーって言われているんですよ。
——へぇ。
クラシックとポップスの融合が2000年に入ってからのクロスオーバー・ミュージックと言われているので、元々の意味合いとは違ってしまっているんです。フュージョンって言葉が出てきたのは83、4年とかですよね。なんかフュージョンっていうと音楽的に決めがばしばしあって、わーって盛り上がれる印象がある。普通のロックのコンサートにも行けないし、ディスコにも行けないけど音楽が好きな人たちが盛り上がっていた場所っていうイメージがありますね。
——アニメ音楽のニュアンスを含んでいるところがあるんですかね? あのきらびやかさとか。
ああ、おっしゃる通り、アニソン自体が、T-SQUAREからパクっている部分がありますよね。その流れはそっちに行っていますね。 70年代後半にクリサリ スっていう尖っているものしかやらないレーベルが あって、そこから、ミシェル・コロンビアっていうフランス系のブラジルの人のコンポーザー/アレン ジャーの人が音源を出しているんですけど、参加ミュージシャンが、ハービー・ハンコック、ジャコ・パストリアス、ラリー・カールトン、リー・リトナー、ランディ・ブレッカー、マイケル・ブレッカー、スティーヴ・ガット。
——ものすごいメンツが何を!
曲によってメンバーは色々だけど一堂に会してセッションをしているの。全部の曲 が、素晴らしく良いんですよ。それは、廃盤になっちゃったので、その復刻を望んでいます。ラリー・カールトンのルーム335って、まさにフュージョンのはしりみたいなアルバムだけど、そのルーム335っていう曲は、このアルバムのために書いたんだって。しかもジャコ・パストリアスとスティーヴ・ガッドとセッションをしたらしい。でもその頃ラリーはワーナー・ブラザーズと契約していて、曲を提供することが出来なくて、お蔵入りになっちゃっ た。軽いウィキペディアでした(笑)。そんな面白い音源も、まだまだあるんですよ。クロスオーバー・ミュージックにはね。
ビデオアーツ・ミュージックのタイトル一挙配信開始!!!
PROFILE
鳥山雄司
1959年生まれ。1981年慶応大学在学中に、セルフ・プロデュースによるソロ・デビュー・アルバムを発表。その後1996年にスタートしたTBS系ドキュメンタリー番組「世界遺産」にテーマ曲「The Song of Life」を提供、大ヒット・オムニバス・アルバム『image』にも収録され、自身の代表曲となる。現在までにソロ・アルバム15枚、神保彰(ds)、和泉宏隆(key)とのユニットPYRAMIDによるアルバム2枚を発表している。また、アレンジャー、プロデューサーとしても松田聖子、吉田拓郎、葉加瀬太郎等を始め、クラシック界の宮本文昭、ジャズ界の伊東たけしやタンゴの小松亮太等、幅広いジャンルのアーティストを数多く手掛ける。
服部幸弘
86年、ビデオアーツ・ミュージックに入社。90年代からA&Rディレクター/プロデューサーとしてジャズ・フュージョン系のアーティストを中心に手掛ける。担当した主なアーティストは、国内アーティストでは寺井尚子、アン・サリー、ピラミッド、伊藤君子、鈴木良雄、川崎燎、ケイ赤城、上田正樹。海外アーティストは、ジョー・サンプル、ラルフ・マクドナルド、リチャード・ティー、ジョン・トロペイ、リズム・ロジック、ジェナイ、マンハッタン・ジャズ・オーケストラ、マンハッタン・ジャズ・クインテット、アル・マッケイ・オールスターズなど。今年7月21日にリリースされるボサノヴァ・シンガー・ソングライターの犬塚彩子のニュー・アルバムも手掛けている。