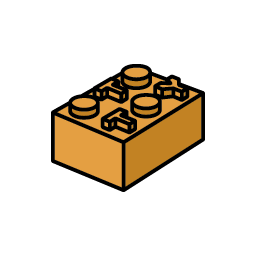REVIEWS : 008 海外インディー(2020年9月)──井草七海

毎回それぞれのジャンルに特化したライターがこの数ヶ月で「コレ」と思った9作品+αを紹介するコーナー。今回は、先日公開した羊文学のインタヴューも担当した、音楽ライターの井草七海が登場。音楽メディア『TURN』での執筆をはじめ、最近では海外アーティストのライナーノーツを担当する井草七海が選んだ9作品はこちら。
Blake Mills『Mutable Set』(2020年5月8日リリース)
LAを拠点に、売れっ子プロデューサーとして活躍中のブレイク・ミルズ。今年は特に、フィービー・ブリッジャーズ、パフューム・ジーニアス、そしてボブ・ディランの作品にまでも参加し、時の人となった感がある中でリリースしたのが、ソロ作4枚目となる今作。彼がそのように求められるのは、なんと言っても、楽器の響きを生々しく録り、それ自体を楽曲の聴きどころとして、ダイナミックに構成してしまう手腕によるところが大きいわけだが、今作こそその極致と言える作品だ。 耳の中で鳴っているかようなアコースティックギターの精細な響き、ヴォーカルの鮮明さ。そして、鼓動する心臓の中にいるような、バスドラムの強烈さ。ささやかな室内楽的な作品にも思えるのに、一方で、壮大な広がりを持ったサウンドにも聴こえる、という音響処理に静かな凄まじさを感じる。そのサウンドは、個人的には、自分が小人になって楽器の中に入り込んでしまったかのような感覚のようにも思えた。いずれにせよ、今作を聴けばミルズがシーンにもたらす斬新な器楽の音響世界を堪能できることは間違いない。
Phoebe Bridgers『Punisher』(2020年6月19日リリース)
美しく牧歌的ながらも、憂いを湛えたSSW、フィービー・ブリッジャーズのセカンド・アルバム。今作での彼女は、両の足をしっかりと地につけ、ソングライターとして新しいスタートを切ったと言えるだろう。前述の、引く手あまたのプロデューサー、ブレイク・ミルズや、共にユニットも組むコナー・オバーストら、アメリカのインディー・シーンの重要アーティストたちと手を組んだ今作では、静謐さを保ちながらスケールの大きさをも感じさせてみたり、デジタルサウンドを取り込んだアップリフティングな曲に挑戦してみたりと、アレンジの幅も多彩になった。
ブレイクのきっかけとなった代表曲“Motion Sickness”では、束縛的なパートナーとの決別を歌ったが、今作での彼女は、周りに振り回され“乗り物酔い(Motion Sickness)”していた過去を払拭し、参加アーティストたちを引き連れ、自分の手でドライブしていく。絶叫し駆け抜けるラストの“I Know The End”では、"終わりを知っている"と歌いながらも、そんな彼女の本当の"はじまり"を感じさせるのである。
Jessie Ware『What's Your Pleasure?』(2020年6月26日リリース)
この夏、最も“ブチ上がった”1枚。デビュー時にはそのソウルフルな歌とクラブライクなトラックとの融合が賞賛されながらも、近作は王道ポップ路線が続きやや評価が鈍っていたUKのR&B / ソウルシンガーのジェシー・ウェア。そんな中での4枚目のリリースとなる今作は、起死回生の鮮烈なディスコ・アルバムだ。ダイアナ・ロスやマドンナの1980年代を思わせるファンキーなグルーヴはどこまでもアッパーながら、Kindnessらのプロデュースの妙だろうか、トラックはユーロ・ビートやハウス風のシンセで構成されており、無機質でモダンな作品にまとまっているのが面白い。作品を通じて、あくまでクールさを保つジェシーの歌唱もあいまって、熱さと冷たさの間を焦らされながら、少しずつ高揚感が高められていく秘密めいた雰囲気に、ゾクゾクせずにはいられない。
キャリアの停滞に悩んでいた彼女自身が、「音楽は楽しいものなのだ」という気持ちを取り戻すために制作されたという今作。その刹那的なロマンは、ステイホームの重苦しい気分を、あっという間に吹き飛ばしてくれた。
HAIM『Women In Music Pt.Ⅲ』(2020年6月26日リリース)
コロナ禍においてエリアごとのシーンの盛り上がりが見えづらかった今年ではあるが、その中でも話題に事欠かなかったのが、LAのアーティストたち。本記事で取り上げている、フィービー・ブリッジャーズ、ブレイク・ミルズもその一角だが、このハイム三姉妹の3枚目となるアルバムは、「ニューヨークは寒すぎる」と、NYとの対比を通じてLAへの愛情を歌う“Los Angels”からはじまるなど、とりわけ地元愛が深い。
元来、フリート・ウッドマックが引き合いに出されるなど、西海岸らしい煌びやかなコーラスワークと躍動感のあるリズムワークが持ち味の彼女たちだが、今作からはとりわけ、クロスビー・スティルス&ナッシュなど、1960年代~1970年代のウエストコースト・ロック直系のソングライティングに踏み込んでいるのが興味深い。ともすれば「男臭い」そうしたルーツと真正面から向き合った今作には、彼女たちの“女性たちだって、隠し立てせずに、いなたいロックをやっていいのだ”という強い意志を感じさせる。だからこその、“Women In Music”というタイトルなのだろう。
Lianne La Havas『Lianne La Havas』(2020年7月17日リリース)
R&Bやソウルにルーツをもつロンドン拠点のSSW、リアン・ラ・ハヴァスの約5年ぶりとなる3枚目のアルバム。セカンド・アルバムを出して以降、個人的な人間関係の変化や破局を経てアルバム制作に取り掛かる気力を失っていたという中での再起の作品にして、最高傑作と呼べそうな作品だ。
信頼の置けるバンド・メンバーと共に作ったという今作は、サウンドそのものが非常に親密さに満ちている。オーガニックなリズムセクションはクラシカルな雰囲気をまといながらも、音の粒はクリアに、また歌と同じくらい大きめにミックスされ、濃密な存在感を放つ。ブラジル・ギターが軽やかな“Seven Times”や、Radio Headの“Weird Fishes”の迫真のカヴァーも珠玉だが、やはり冒頭とラストの“Bittersweet”がとにかくすばらしい。〈Bittersweet summer rain / I'm born again”と、スモーキーな声に哀愁や苦々しさを滲ませながらも、自らを熱く奮い立たせるような歌に、聴いているこちらも、熱いものが胸にこみ上げてくる。
Jessy Lanza『All The Time』(2020年7月24日リリース)
Burial擁するレーベル〈Hyperdub〉に所属する、カナダ出身のトラックメイカー / シンガー、ジェシー・ランザの3枚目のアルバム。これまでの作品はアンビエント~テクノを守備範囲としていたようだが、今作はバレアリック・ハウス風。クラップやハイハットのサウンドには、軽やかなリゾート感がたっぷりだ。アンビエンスのきいた煌びやかなシンセサウンドづかいは、明からさまな80年代オマージュでノスタルジックな雰囲気も漂わせるが、それらを、知的さを宿すトラックメイクでまとめるあたりが、さすが〈Hyperdub〉と思わせるポイント。
他方、ファンキーなグルーヴを繰り出すベースラインと、ジェシー本人のアーバン、かつミニー・リパートンのような歌唱には、ブルーアイド・ソウル的なニュアンスも息づいており、その引き出しの広さに唸らされる。そんなトラックとは裏腹に、歌詞の内容自体は、個人的な“怒り”がテーマになっているらしく、これまた不思議な取り合わせ。10年近いキャリアを持つが、その多彩さが一気に開花した1枚と言えるだろう。
Madeline Kenney『Sucker's Lunch』(2020年7月31日リリース)
オークランドを拠点としているSSWの、3枚目のアルバム。前作に引き続き、Wye Oakのジェン・ワスナーとアンディ・スタックが参加している。特にジェン・ワスナーは、近年Bon Iverのバックを務めるなど、元来のWye Oakらしいドリーム・ポップとしての持ち味に加え、フォークやカントリー由来のアレンジに親しみのある人物。それもあってか、マデリーンのドリーミーな音づくりと、牧歌的なソングライティングとの両立に手腕を発揮している。
特に今作は、自由なギターワークを生かしながらも、躍動感と厚みを増したリズムセクションや、空間をぐっと広く感じさせるコーラスを取り入れ、青々と伸びやかながら、白昼夢にまどろむような、絶妙な夢見心地を展開。ピアノやサックスといった生楽器の、主張しすぎない彩りも絶妙だ。“Sucker”や“White Window Light”などのメロディにはフォークを感じさせながら、“Double Hearted”なんかの、ケレン味のあるアレンジも抜群。一緒にツアーを回ったという、ジェイ・ソムが好きな人に、ドンピシャな作品だろう。
Angel Olsen『Whole New Mess』(2020年8月28日リリース)
フォークロック畑出身ながら、オリジナル・アルバムとしては4作目にあたる前作『All Mirrors』(2019年)で、大掛かりな生のオーケストラ・アレンジを取り入れ、オペラ歌手のような風格をも手にした、エンジェル・オルセン。近年活躍めざましい若手の女性SSWたちからも特に羨望の眼差しを向けられているが、前作にはなんとなく近寄りがたさを感じた人も少なくないだろう。そんな彼女が今回リリースしたのが、その『All Mirrors』収録曲の弾き語りヴァージョンを中心に収めた作品。もともとダブル・アルバムを予定していた前作の、片割れにあたるものと思われる。
古い教会で、ギターとマイク数本のみでレコーディングされたという自然なリヴァーブがかかったサウンドに宿る、前作にはなかった聴き手との近さに、どこかほっとさせられる今作。と同時に、コードをラフにざっくりと鳴らす恐れのなさや、媚びの一切ない歌声がもつ歌い手としてのむき出しの情感には、どこまでも打ちひしがれる。ごくシンプルな楽曲にもかかわらず、ギターと声だけで説得させてしまうその気迫と包容力には、やはり頭が上がらないのだ。
Samia『The Baby』(2020年8月28日リリース)
ニューヨーク出身、現在23歳のSSWのデビュー・アルバム。ファンを公言するファーザー・ジョン・ミスティ(Father John Misty)にも似たフォークロック志向のソングライティングと、透明感のあるしなやかな歌声が魅力だが、今作では、これまでのシングル曲以上にいちソングライターとしての才能が開花。柔らかなホーンで壮大さを演出したり、ヴァイオリンのトレモロで軽やかさを表現したりと、細やかなアレンジを施し、感情の繊細な機微と見事に呼応させている。その内省的ながらも伸びやかなエモーションには、ビッグ・シーフのエイドリアン・レンカーやジュリアン・ベイカーをも思い起こす。
今作で特にインパクトを残すのが、ラストの“Is There Something in the Movies?”だ。両親が俳優である関係で、幼い頃に親交のあった俳優が若くして亡くなった経験から、遺されたものを妄想と共に褒めそやすばかりの世の風潮に対して、「映画の中に私の(その人への)想い以上のものがあるのだろうか?」という失望を歌う。若い才能の死が立て続くこの頃、彼女のその憤りと悲痛さは、とりわけ強く胸をうつ。