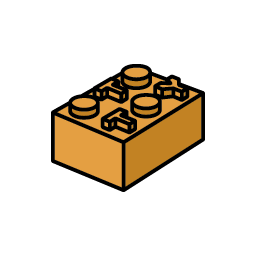REVIEWS : 075 現代音楽〜エレクトロニック・ミュージック (2024年3月)──八木皓平

"REVIEWS"は「ココに来ればなにかしらおもしろい新譜に出会える」をモットーに、さまざまな書き手がここ数ヶ月の新譜からエッセンシャルな9枚を選びレヴューするコーナー。今回は八木皓平による、現代音楽〜エレクトロニック・ミュージックを横断する、ゆるやかなシーンのグラデーションのなかから9枚の作品を選んでもらいました。
OTOTOY REVIEWS 075
『現代音楽〜エレクトロニック・ミュージック (2024年3月)』
文 : 八木皓平
Arone Dyer 『Arone x s t a r g a z e』
LABEL : Transgressive
アローン・ダイアーといえば、ザ・ナショナルのデスナー兄弟にその才覚を認められ、彼らのレーベル〈ブラスランド〉と契約を結んだデュオ、ビューク・アンド・ゲイスの片割れだ。このデュオはソー・パーカッションとコラボ作品をリリースするなど、インディー・ロックに留まらないユニークなアプローチをしていることで知られている。そのアローン・ダイアーが今回コラボ相手に選んだのはベルリンで結成されたアンサンブル、s t a r g a z eだ。このアンサンブルはオーウェン・パレットやジュリア・ホルター、アイスエイジとコラボを展開しており、こちらもまたジャンルレスな活動をしている。そんな両者のコラボは実にうまくいっている。アローンのヴォーカルと調和したかと思えば、時に拮抗してみせるホーンとストリングスが、アグレッシヴかつシンフォニックなサウンドで、リスナーを圧倒する。時折差し込まれるエレクトロニクスの要素が楽曲にモダンな質感をもたらしており、じつに繊細なアレンジメントが行き届いている作品だ。
Jerskin Fendrix 『Poor Things』
LABEL : Milan
2024年におけるアカデミー賞作曲賞で、ジェースキン・フェンドリックスが劇伴を担当した、ヨルゴス・ランティモス監督の『哀れなるものたち』が受賞できなかったのには少なからず落胆した。ビクトル・エリセの新作『瞳をとじて』のような劇伴が極端に少ない映画を観ると、映画にとって劇伴はほんとうに必要なのだろうかという気分になることもあるが、『哀れなるものたち』の劇伴を聴いたとき、やはり映画と音楽が嚙み合った時はすごい威力を発揮するものだと痛感した。ゴシックでビザールな映画のアンビエンスを、曲によっては無音部分もあるほどミニマルな構成で、ストリングスやホーン、エレクトロニクス等の音色を極めて的確にアレンジし、ユーモア溢れる作曲センスと鮮烈なイメージ喚起能力で、映画と絶妙なハーモニーを奏でてみせた。そんな彼はブラック・ミディの楽曲を手伝ったり、ブラック・カントリー・ニュー・ロードとも繋がりがあったりと、面白い繋がりを持っている。今後の彼の動きに注目したいところだ。
OTOTOYでの配信購入はコチラへ(ハイレゾ配信)
OTOTOYでの配信購入はコチラへ(ロスレス配信)
Philip Glass『Philip Glass Solo』
LABEL : Orange Mountain Music
ジューク~フットワークを起点としたエレクトロニック・ミュージックのフィールドで圧倒的な才覚を見せつけるJlinは昨今、現代音楽のフィールドでも活躍していることは以前、この連載記事でも書いたことだが、彼女の待望の新作『Akoma』に収録されている楽曲にフィリップ・グラスが参加しており、そこでは『Philip Glass Solo』で繰り返し聴けるフレーズを耳にすることになる。このタイミングではじめて、もしくは改めてフィリップ・グラスのミニマル・ミュージックに触れようという方に本作をオススメしたい。80代のフィリップ・グラス自身がピアノを奏でるという、ある意味では作曲家/演奏家としての彼の魅力がむき出しになっている。本作を聴けば、彼のミニマル・ミュージックが、スティーヴ・ライヒのシステマティックで明瞭、それでいてマシーナリーなそれとは違い、作曲自体は精密であるにも関わらず、柔らかで陰影のある人肌のエモーションを宿していることがわかる。35年前の彼が弾く『Solo Piano』(1989年)と聴き比べて、その違いを楽しむのも一興だ。