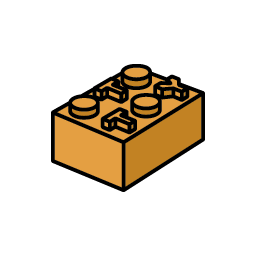REVIEWS : 027 SSW (2021年7月)──井草七海
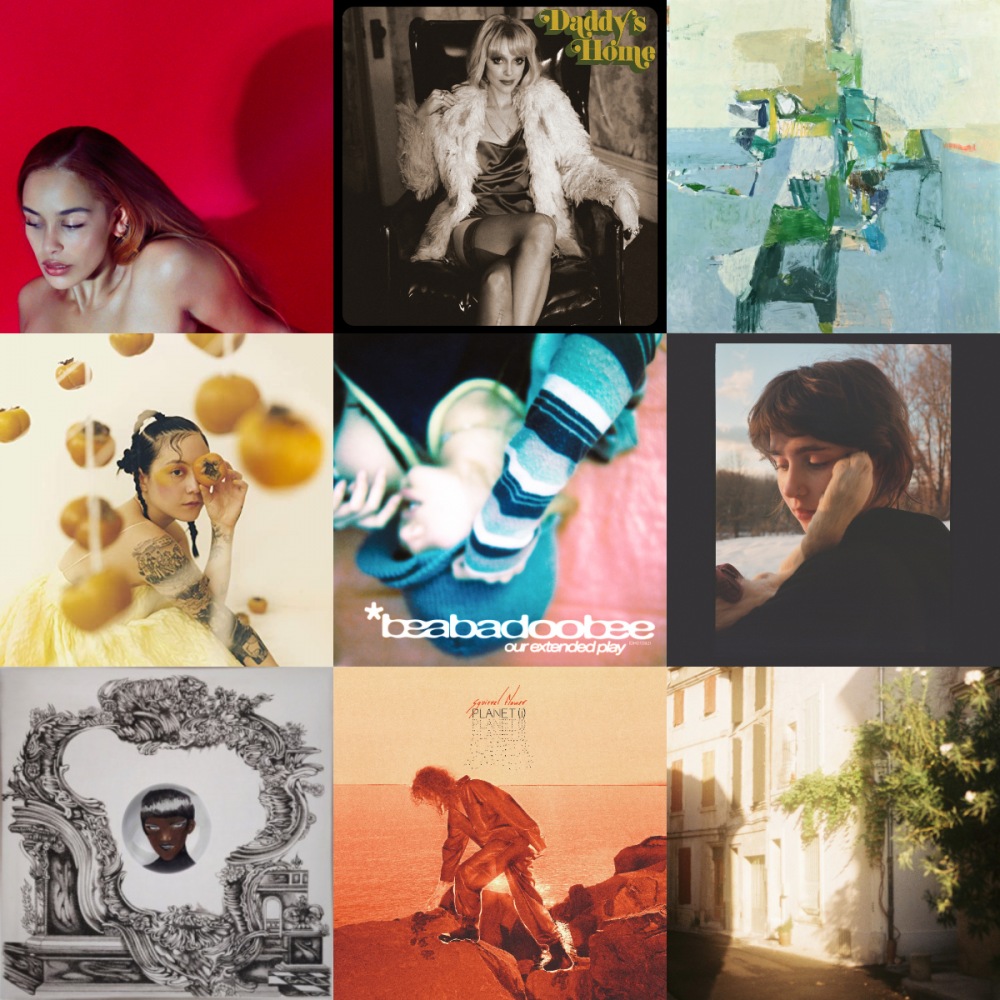
"REVIEWS"は「ココに来ればなにかしらおもしろい新譜に出会える」をモットーに、さまざまな書き手が新譜(たいたい3ヶ月ぐらいのターム)を中心に9枚(+α)の作品を厳選し、紹介するコーナーです(ときに旧譜も)。今回は井草七海による9枚。今回はオーソドックスなバンド・サウンドから、エレクトロニクス、R&Bまである意味でさまざまなスタイルのSSWを中心に新譜をエッセンシャルにセレクト。
OTOTOY REVIEWS 027
『SSW(2021年7月)』
文 : 井草七海
Ryley Walker 『Course In Fable』
シカゴ出身のギタリストの、約3年ぶり5枚目のソロ・フル・アルバム。2014年のデビュー当時は素朴なシンガーソングライター然としたアーティストという印象が強かったのだが、その後はジャム・セッション的な作品づくりに傾倒。2019年には同郷シカゴのジャズ・ドラマー、チャールズ・ラムバックとのコラボ・アルバムをリリースしてもいるが、今作ではそうした元来のセッション・ミュージシャン的な気質と歌モノ・シンガーとしての側面がバランス良く融合している。ところどころインプロヴィゼーションと思しき前衛的な箇所もあるが、流麗なギター捌きが光るフレージング、肩の力が抜けた歌声が繊細にレイヤードされたサウンドを軽やかに聴かせる場面では、実験精神とポップネスの絶妙なバランス感覚を見せる。トータスのジョン・マッケンタイアのプロデュースの賜物だろう。本人は現在NY在住だそうだが、バストロ、ガスター・デル・ソルからウィルコへと受け継がれてきたシカゴのオルタナ・カントリー~ポストロックの系譜を濃く実感させる1枚。
Jorja Smith 『Be Right Back』
2018年のデビュー・アルバム『Lost &Found』以降、まとまった音源が出ていなかったジョルジャ・スミス。その久々の新作となった『Be Right Back』は、これまでの彼女のイメージとは逸脱した、アルバム外のプロジェクトと位置付けられたEPなのだそうだが、いわゆるオーセンティックな「UKネオ・ソウルらしい」一定のトーンで保たれた前作アルバムに比べ、はるかに多面的で、刺激的な作品に結実しているのが好印象。波打つようなサブベースを効かせたり、UKガラージ風のビートなど、エレクトロニックなビートでサウンドに奥行きを持たせながら、レゲエのリディム、クラーベのようなリズムを用いたりと、自身のルーツである南米の音楽へも接近。細さと不安定な青さを残していたヴォーカルもすっかり深みを増しており、余裕と成熟を感じさせるように。デビュー時のある種の「優等生」的なイメージを自ら逸脱しようとする意図も、本作にはあるのかもしれない。すでに予定されているというセカンド・アルバムにも自ずと期待が高まる。
St.Vincent 『Daddy’s Home』
服役していた父親の出所をきっかけに制作され、1970年代のNYをテーマにしたという6枚目のアルバム。その自体の空気を演出するのは、ディスコ&ファンクのバックヴォーカルのようなやたらとソウルフルなコーラス、ハード・ロックやグラム・ロック風のドラムやベース・ライン。また、複数の曲に登場するシタールの音色はパンク以前のニューヨークに漂ういかがわしい空気を表現しているかのようだ。そしてNYは、デビュー以来彼女の創作の拠点となってきた特別な場所だ。そこに、70年代=73歳になる彼女の父親の「青年時代」という舞台セットを用意して迎え入れるということ。罪を犯した人間が、新しい人生を生き直すことを肯定するということのように思えるのだ。セイント・ヴィンセントがデビューしてからの14年間のディスコグラフィーを振り返ると、サウンドから本人のビジュアル・イメージに至るまで、作品ごとに常に変化していることに驚かされるが、今作こそがこれまでの中で“アニー・クラーク”という人間の素に最も接近した作品なのかもしれない。