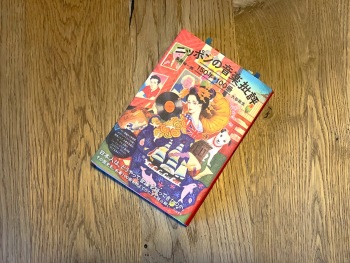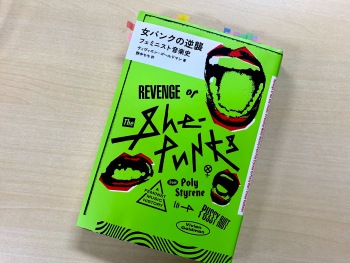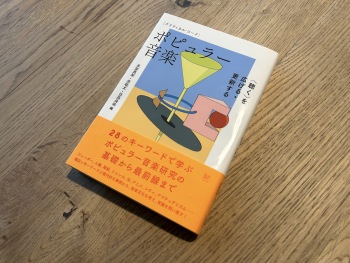DJカルチャーとダンス・ミュージック、その歴史を理解するための決定的な1冊───書評『そして、みんなクレイジーになっていく』

オトトイ読んだ Vol.26
文 : 河村祐介
今回のお題『そして、みんなクレイジーになっていく 増補改訂版 DJカルチャーとクラブ・ミュージックの100年史―』
ビル・ブルースター、フランク・ブロートン : 著 / 島田陽子 : 訳
DU BOOKS : 刊
OTOTOYの書籍コーナー“オトトイ読んだ”。今回はDJカルチャーとダンス・ミュージックの歴史を描いた『そして、みんなクレイジーになっていく 増補改訂版 DJカルチャーとクラブ・ミュージックの100年史―― Last Night A DJ Saved My Life』。以前にも訳出されていたものの、ながらく絶版かつプレミアが付いてた書籍が、大幅な増補を伴って再訳出されました。編集部の河村による書評でお届けします。(編集部)。
コミニティから生まれる音楽の連続体
──書評 : 『そして、みんなクレイジーになっていく 増補改訂版 DJカルチャーとクラブ・ミュージックの100年史―』──
文 : 河村祐介
朝7時、ダンスフロアには昨夜がまだ続いている。DJが繰り出す永遠のビートとストーリー、身体を、精神を、ひととき実社会から解脱させる刹那なコミニティ。さて、これを文化とするならば、この文化はどこから来たのか? 本書はそんな疑問に対して明確な答えを出せる決定的な1冊だ。
本書はイギリス人ジャーナリスト、ビル・ブルースター&フランク・ブロートンによる『Last Night a DJ Saved My Life(原題)』の訳出である。DJカルチャーとそこから生まれ出たクラブ・ミュージックに関する、その通史を描いた1冊。初版は1999年、直後の2003年に日本語版も『そして、みんなクレイジーになっていく―DJは世界のエンターテインメントを支配する神になった』として訳出されている(この邦題……カタカナで『ラストナイト・ア・DJ・セイヴド・マイ・ライフ』でいいのにと毎回思うのだが)。その後、絶版となり長らく邦訳版は入手困難な状態が続いていたが、このたび増補改訂版としての待望の再訳出となった。クレジットによれば2022年に海外で出版された増補版を底本としている。
今回、新たに日本語増補改訂版のサブ・タイトルとして追加されたのが『DJカルチャーとクラブ・ミュージックの100年史』。本書のその射程はそのサブタイトルの通り、現代のダンスフロアのためのDJだけではなく、20世紀初頭に勃興した新たなメディア=ラジオからその記述をはじめている。徐々にポップ・ミュージック・シーン全体にも影響力を増していくラジオのDJの存在、楽団いらずのボールルームの選盤係、パリやNYのディスコ前夜のナイトクラブ・シーン、ジャマイカのレゲエを生んだサウンドシステム・シーン、UK北部においてその後のDJカルチャーの下地を作ったノーザン・ソウル・シーンなどを経て、現代のダンス・ミュージックへと通じる1970年代のディスコ、ヒップホップ、1980年代のハウスやテクノなどの誕生を描きつつ、UKのレイヴ・カルチャーの勃興をひとつ媒介にして、1990年代に爆発的に世界に広がり産業化するDJカルチャー、そしてその先にある現代の巨大エンターテインメント産業の一躍を担うまでになったEDMや、一晩で数百万ドルを稼ぐスーパー・スターDJたちの2010年代以降のシーンまで。まさに100年の歴史を描いている。心ない音楽ファンから投げつけられるDJへの批判のクリシェ、その言葉を借りて皮肉めいて本書を説明するならば、“他人の曲をかけるだけ”で、音楽シーンに対してDJはなにをもたらしたのか? それがここには書かれている。
DJカルチャーの決定的な通史
本書の意義と言えば、まずDJカルチャーにその通史としての歴史を与えたことだろう。それまでのロックなどの他のポピュラー・ミュージックのジャーナリズムが触れてこなかった、多くのアンダーグラウンドなナイト・コミニティ、そこに基づいたシーンをしっかりと系譜立て、さまざまな証言とともに紹介することで本書は成立している。これはある意味でシーンが最初にあり、音楽がそこから生まれる副次的なものであるという実態を持つクラブ・ミュージックならではの歴史の記述だ。ある夜の記憶を元に、次の夜のための音楽をDJが選びとり、その音楽がガイドとなり、次の夜のために(時に革新的な)音楽が作られる。これによってシーンは前進ししてく。次の夜のための音楽、そのヒントはダンスフロアに漂っている。これを(時に偶然に)捕らえた者が新たなサウンドを作っていく。時にDJたちのその経験と閃きによって、こうしてできた、もしくは発見してきた革新的なサウンドをもフロアへと投下していく。このサイクル、ダンス・ミュージックはこうした動きによって、ダンスが導く多幸感とともに絶えず生み出される音の連続体だ。
例えば、ダンスフロアでの快楽を増長するビート・キープのために成されたテープ・エデットや2枚使いがディスコのミニマルな構造を強化し、さらにその要素がそぎ落とされ電化され、クリエイターとしての参入のハードルが下がることでハウスが生まれていった。DJとクリエイター(両方をかねることもある)、そしてダンスフロアの三すくみの関係値=ある種のコミニティが新たな音楽を作り出していく、各地のさまざまな類型を通してこの動きを当時の証言などを元に丁寧に描き出している(例外はデトロイトの3人の黒人によってコンセプチャルに発明されたテクノぐらいだ)。
ダンス・ミュージックはどこからきたのか?
本書で著書たちが現代DJカルチャーのその直接の祖として描いているのは、1960年代末、NYアンダーグラウンドの、黒人やヒスパニックたちも入り交じるゲイやクィアたちのコミニティ、彼ら / 彼女たちのアンダーグラウンドなナイトクラブ・カルチャーだ。ダンス・ミュージックの、そのルーツをここに定義している。実際に現代のDJミックスのテクニック──2曲以上の曲をビート・マッチングし(スピードを合わせて)、途切れなくミックスし、サウンドのストーリーを作る──は、ほぼこのシーンで発明された。〈ザ・サンクチュアリー〉というゲイ・クラブのレジデントDJであったフランシス・グラッソによって生み出され、その詳細は本書にも詳しい。またこうしてDJミックスが様式化することで、ダンスフロア用にサウンドは最適化され、ジャンルとしてのディスコのサウンドが整えられていったのもこの時期だ。ポップ・チャートを目指した踊れる曲ではなく、ダンスフロアを目指した踊るための曲、つまりダンス・ミュージックの誕生である。
こうしたDJテクニックの整備とディスコという音楽の誕生とともに著者たちが本書でこのシーンを重要視しているのは、なによりそのあり方であろう。前述のグラッソなどの活躍を描き、1960年代末のNYアンダーアンダーグラウンドのクラブ・カルチャーを描いた『ディスコのルーツ』と題された第5章は、アメリカでのLGBTQ+当事者らによるはじめての抗議行動と呼ばれるストーンウォールの反乱の描写からスタートすることも示唆的だ。本書後半でも、もはや消費主義的な産業となりはてたスーパースターDJたちのシーンへの批判として「それはダンス・ミュージックの起源、疎外された人々に残酷な現実から逃れる術をDJが与えていたその元々の形とはまるで違う世界になっている」(P.724)と著者達が逆説的に語っているように、ダンス・ミュージックとは、現実社会からある種の逃避を作り出してくれる居場所を作り出す契機となる、もしくはそこで生み出される音楽であると彼らは定義している。
こうしたあり方、その起点は、1969年にデヴィッド・マンキューソが自宅のDIYなパーティとしてはじめた〈ザ・ロフト〉にまで遡る。当時、公の場所で存在すら許されなかったゲイの人々が集い、踊るということができる場所としてある意味で革命を起こした(坂本慎太郎の「ディスコって」の歌詞は、おそらくこうした初期ディスコ・シーンの精神へのオマージュだ)。1970年代末になるとディスコは、メジャー・シーンに取り込まれ、ゲイ・シーンというルーツすらないがしろにされ、先鋭性を失って、そして1980年代の到来とともに失速する。しかし、〈ザ・ロフト〉の門下生たちがNYやシカゴのゲイ・アンダーグラウンドのシーンを通じて、現代のハウス・ミュージックまでのひと続きの歴史を作っていく。ある種のDJの精神性を通して、まるでマジックのようにこれらは繋がっていく。特に、それがはじまった当時の時代背景を考えれば、差別主義者だけでなく一般的なイメージにおいても、単なる快楽と放蕩の連なり(実際にそういう面があったにせよ)といったイメージに押し込まれていた可能性のあるシーンを、ある人々にとって音楽を介した重要な居場所=コミニティを提供したカルチャーであり、そこで発揮された音楽のクリエイティヴィティが、現代のエンターテインメント産業の巨大な一部を担うようになる音楽の、その正統なルーツであることを事細やかに立証している。
DJカルチャーがいかに、どのように成立したのか? その正体を知るには唯一無二の1冊である。ふだんDJブースやダンスフロアに立つことがあるのであれば、そのカルチャーのルーツとその精神、進化の歴史を学ぶことによって、いま目の前にある情景がいかなるものであるのかより深く理解できることもあるはずだ。
旧版から大幅に追記された増補部分
さて最後に今回の増補部分について。初回の日本語版との比較を記しておくと、増補版の追記分はUKのベース・ミュージック、商業化し大規模になるEDMやトランスのスーパースターDJのシーン、シーンの拡大における問題点といった、初版出版以降におきた事象をまとめたものがまずひとつ。さらにこうした新たな事象の章立て以外にも、過去のことに関しても細かな追記が各章にもなされ、以前は章内の単なる記述だったものが、追記され新たな章として独立している事象も多い。特に1980年代後半以降についてはかなり細分化されている。最初の日本語版を読んだ人は、その情報量に面食らう可能性すらある。それほど新たに大量の追記がなされている(本文部分の追加ページ数だけでみれば100Pほどだが、恐ろしいことに今回の日本語版は2段組かつ文字が小さくなっている)。また現在のその活躍を考えれば当たり前だが、女性DJたちを描いた19章も新たに追加されている。とはいえこれは新たな章立てだけでなく、既存の章にも、各シーンにおける女性のDJやシーンの立役者の存在の加筆も多い。そして性加害が発覚するなど失態を起こした男たちの記述も追記されるなど、さらなる現代的なアップデートもなされている。
こうした大規模な情報の追記は、著者たちが初版のリリースとともに立ち上げたDJカルチャーの歴史を追うウェブ・メディア、djhistory.comでの取材がまずあり、さらには各地のマニアや証言者たちによるフォーラムやSNSでの情報収集という、インターネットの集合知による影響は大いにあるだろう。各地のシーンの大幅な追記といえば、アメリカの西海岸のディスコ・シーンや14章にはUKのレイヴ・カルチャーにも影響を与えたジャズ・ファンク~ウェアハウス・パーティのシーンが追加されているが、これ以外にも、特に非英語圏に関していくつか掘り下げられているのも特徴的だ。例えば18章の「バリアリック」という章。これはUKのアシッド・ハウス・シーンのヒントとなった1980年代のDJアルフレッド(つい先日、急逝)などによるスペインはイビサ島でのロックやハウスも混ざった折衷的なDJプレイのスタイルに関する章だ。また同章にはベルギーのポスト・パンク~インダストリアル~EBMといったシーンから派生したニュー・ビートのシーン、さらにはその掘り返しが、現在のニューエイジ・リヴァイヴァルに強い影響を与えたイタロ・ディスコのプログレッシヴなミックス・カルチャー、DJモーツァルトのアフロやダニエル・バルデッリのコズミックと呼ばれるDJたち / シーンの記述も追加されている。これらの章はハウスやテクノなどが、ある種のダンス・ミュージックの各地のスタンダードとなる1990年代を迎える以前に、各地にも折衷的で先鋭的なDJカルチャーがあったことを伝えている。