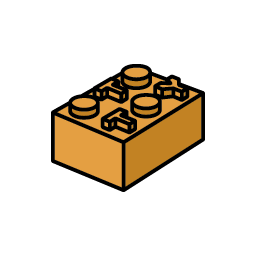断絶と継承を経てたどり着くインディーの美学──WOOMAN『A NAME』2週間先行ハイレゾ配信

つい先頃、記念すべき5周年パーティを終えたばかりの気鋭のレーベル〈KiliKiliVilla〉。まさに役者揃い、ここ、東京のシーンのある一部をまさに体現するレーベルだ。このたび新たなバンドがこのラインナップに加わった。そのバンド・ヒストリーはインタヴュー本文に譲るが、インディー・シーンの重要局面にて活躍した、いくつかのプロジェクトを経たメンバーたちによって2014年に結成されたバンド、WOOMANである。そんな彼らが〈KiliKiliVilla〉からリリースするアルバム『A NAME』は、まさにそのキャリアを結晶化させたようなサウンドが広がっている。そのサウンドはバンド自体の方向性はもとより、2019年のこの国のインディー・ロック・シーンを見渡す意味でも重要な作品になる、そんな予感をも内包した作品だ。OTOTOYでは本作をハイレゾ、2週間先行配信とともに、ここにインタヴューをお届けしよう。
2週間先行ハイレゾ配信
INTERVIEW : YYOKKE (WOOMAN)
2019年の年明け早々、アニマル・コレクティヴの金字塔『Merriweather Post Pavilion』のリリース10周年を伝える記事を読み、「もうそんなに経ったの?」と呆れてしまった。10年前の自分は大学生で、無邪気に音楽を掘りまくっていた時期だから、いろんな思い出がある。Twitterが一般化するのはもう少しあとで、音楽ブログに書きまくる人がたくさんいた頃だ。海外でも同様で、チルウェイヴというムーヴメントもそこから生まれている。さらに、2000年代にかけて質/セールスの両面で上昇曲線を描き続けたUSインディー・ロックのピークタイムであり、10年後の耳にもエッジーに響く『Merriweather〜』の曲が、日本のラジオでも普通にかかっていた。
そんなシーンの中心地となり、数多の人気バンドを輩出してきたNYブルックリンにて、2008年に設立されたのが〈Captured Tracks〉だ。チルウェイヴの隆盛ともリンクするように、ドリーム・ポップ、ギター・ポップ、シューゲイザー、ガレージ・ロック……と多角的にリバイバルを促し、のちにマック・デマルコも送り出すこのレーベルは、その後しばらくまで、もっともクールな目利きとして君臨していた。その同レーベルと契約した唯一の日本人バンドが、本稿の主人公であるWOOMANのヴォーカル兼フロントマン、YYOKKEもかつて在籍していたJesse Ruinsである。
USインディーと共鳴するような動きが日本で起こっていることを、自分は海外の音楽メディアを通じて知った。その先鋒役を務めていたのが、Jesse Ruinsを擁した〈Cuz Me Pain〉だ。彼らの周辺にいたバンドは、かつてコーネリアスが〈Matador〉と契約したように、海外のレーベルとも繋がりつつ独自の展開を見せたものの、ガラパゴス化が進行していた日本国内で注目を浴びるには至らず、やがて自然消滅していく。その時期のやるせなさについて、「みんな音楽を聴かなくなったのかな、と思うこともあった」とYYOKKEは述懐している。
しかし、この後のインタビューでも語られているように、彼らが青春時代に遺したものは、東京のインディー・シーンにしっかり受け継がれていた。そして、現在はミツメやDYGLのグラフィックデザインも手がけるYYOKKEが、紆余曲折を経て結成した4人組、WOOMANの最新作『A NAME』は“第二のスタート”というべき快作に仕上がっている。しかもそれが、〈KiliKiliVilla〉からリリースされるのも感慨深い。インディーの純潔を貫き続ける人たちが、このタイミングで巡り合うなんてドラマチックですらある。
前置きが長くなった、YYOKKEとのインタビューをお届けしよう。『A NAME』で突き抜けた理由と、音楽活動の挫折から再生までを語ってもらった。
インタヴュー&文 : 小熊俊哉
写真 : 佐藤祐紀
アンチというわけではないけど、単純にかっこいいと思える音楽を
──とりあえず、2018年によく聴いたアルバムを教えてもらえますか?
個人的に好きだったのは、スネイル・メイルの『Lush』かな。あと、カート・ヴァイルの『Bottle It In』も。
──WOOMANに影響を与えた作品となったらどうでしょう?
フォース・ワンダラーズ(Forth Wanderers)がよかったですね。〈Sub Pop〉に所属している5人組で、ボーカルが女の子なんですけど、ギター・ポップとパワー・ポップの間みたいなものをやっていて。それは自分たちのバンドでやりたいこととも似ているので参考にしました。
──なるほど。WOOMANの新作を聴かせてもらって、かなりエモいアルバムだと思ったんですよね。ジャンルとしての“エモ”というよりは、サウンド自体にエモさが滲んでいる感じ。
ああ、そうですね。
──そうなったのは、どんな背景があったのでしょう?
前のアルバムを出したあと、自分たちに合った音の出し方を研究する時期が1年くらいあって。言葉の乗せ方について考えたり、「こういうコードに対して、このメロディーを入れたらかっこいいね」と試しながら曲作りしてみたんです。例えば、「Aメロ → Bメロ → サビ」よりも、「Aメロ → サビ → Cメロ→サビ」のほうが全体の輪郭がまとまって見えるし、構造的でかっこいいな、とか。だから、コードを弾いてメロディーを作るというよりも、先に単語を置いていって、あとからスタジオで(音を)合わせて調整していくという作り方をやってみたんです。そうするうちに、歌詞の内容も変わっていって。
──どんなふうに?
以前はファンタジーや空想に近いものが大半だったんですけど、いまは実体験や哲学的なことを歌詞に入れるようになりました。というのも、WOOMANを結成して3年半くらい経ちますけど、ちゃんと歌に気持ちを込めて、伝えたい言葉を(歌詞に)置いていかないと、ライヴを繰り返しやっていくのは難しいと気づいたんです。自分にとって現実味のある歌詞のほうが、感情も入りやすいじゃないですか。そこからライヴでも感情が出せるようになったし、それをレコーディングしたのでエモくなったのはありますね。
──感情がこもりやすくなるように試行錯誤していった結果、曲作りのスタイルまで変わっていったと。これまでのインディー然とした音楽性とは、だいぶ違う感じになりましたよね。
はい、(意識して)離しました。DIIVやトロ・イ・モアなど、チルウェイヴと呼ばれていた音楽に影響を受けた若いバンドが2010年代後半にたくさん出てきたじゃないですか。でも、自分はそういう音楽が面白いとは思えなくなってきて。
──メロウでドリーミーな感じが退屈になってきたと。チルウェイヴが盛り上がった時、日本で真っ先に反応していたのがJesse Ruinsじゃないですか。そこにいたYYOKKEさんが、現在そういうモードだっていうのは興味深いです。
そうなんですよ。だから、アンチというわけではないけど、(いまの自分にとって)単純にかっこいいと思える音楽に遡って、そのいいところだけ取って今の気分で編集しようと。それこそ、高校生の頃に聴いていたゲット・アップ・キッズまで遡ってみたんです。
──エモのど真ん中じゃないですか。
そうそう。ジミー・イート・ワールド、プロミス・リング──自分たちのルーツになっている音楽のかっこよさを、再編集して作ってみたらあういうサウンドになりました。あとは最近、トラップをよく聴いていて。歪んだギターに乗せてラップするものが多くて、その手触りや感覚を若干意識したところはあります。プーヤ(Pouya)というオルタナを聴いているようなラッパーがいて、すごくかっこいいんですよ。
最近のトラップはとにかくトラックがいいんですよ
──最近のいわゆるエモ・ラップもそうですよね。オルタナとラップを並列に聴いてきた感じがする。
もうグチャグチャになって、面白いことになってきていますよね。トラックを自分で作るラッパーも増えているし、ロック出身の人がラップをしたりもしている。そのなかで、最近のトラップはとにかくトラックがいいんですよ。いいトラックに歌詞を乗せて歌っているだけで、いい曲になるんだなって。
──日本でインディー・ロックが好きな人って、それしか聴かない印象があったんですけど。全然そういう感じじゃないんですね。
趣味はかなり雑多ですね。僕とギターのODAはバンド活動とは別に、もともとDJもやっていて。BIG LOVEやJET SETに毎週行っては新譜を買って、週末にDJする生活を10年くらいやっていたんです。その流れもあってのいまなんですよね。
──なるほど。
で、トラップではない方向でも、〈L.I.E.S.〉周辺のロウハウスや、〈The Trilogy Tapes〉とかのノイジーでロックっぽいハウスがトレンドになっていて。感情的なものがキーワードになってきている気がするんですよね。それこそ、スネイル・メイルもそうじゃないですか。
──それ、すごくわかります!
そのトレンド感をジャンルではなく、姿勢やスタンスから捉えたときに、いまこそロックをやるべきなんじゃないかと。ちょっと歪んだものをやったほうが、いまはかっこいいと思えそうな気がする。そういう読みで、1年くらいかけて作ったのが今回のアルバムですね。
──出だしから最高におもしろい話ですね(笑)。YYOKKEさんはWOOMANを始める前からいろんな活動をされてきたわけですけど、その頃を改めて振り返ってみたときに、自分にとってどういう時期だったと言えそうですか。
いろんな見方があると思います。たとえば渋谷系でいうと、僕自身はリアルタイムでは通っていなくて。コーネリアスと小沢健二さんがそれぞれ活動していて、オリジナル・ラブでいえば田島(貴男)さんだけになっていた頃に音楽を聴き始めた世代なんですけど。当時、コーネリアスが世界に出ていったあと、そこからポップ・フィールドでは何も更新されなかったじゃないですか。
──渋谷系の頃には日本人ミュージシャンが海外進出していく流れがあったのに、しばらくしてパッタリと途絶えてしまった。
そういう意味では、10年くらい何も起きなかったシーンのなかで、僕らは海外リリースをしようと積極的に動いたわけです。当時は若かったので、ピュアな気持ちで自分たちなりのトラックを作って、海外のレーベルに送ってリリースの話がきたり、みんなで競争し合っていましたね。「先週送ったフランスのレーベルから、もっと音源送ってと言われたんだよね」とか、Jesse Ruinsのリーダー佐久間くんから「〈Captured Tracks〉のマイク(・スナイパー)からメールがきた!」とか。その日はさすがに、みんなで集まって呑みました(笑)。
──あの時期の〈Captured Tracks〉は、世界中のバンドが憧れたレーベルの筆頭ですよね。Jesse Ruinsはそんな〈Captured Tracks〉からEPを発表したわけですが。
ただ、レーベルの力を借りるだけでは何も起こらないんだな、とも思いました。アジア圏で初めて〈XL Recordings〉と契約した、ひとりユニットのEyedressってご存知ですか? 彼はフィリピンの出身なんですけど、〈XL Recordings〉(リリースは傘下レーベルの〈Abeano〉)から出したら人生上がりだと思ってサボっていたら、速攻で切られて遊び倒していただけだった、という話をしていて(笑)。
──(笑)。
でも、その経験があるから、誰かに与えられたもので何かを発信するのはナンセンスだと言っていたんです。その話はそのまま共感できるんですよ。結局のところ、シーンというのはローカルなものだし、ローカルなコミュニティってすごく重要なものなんですよ。僕らの音楽はネット上で盛り上がりを見せて、その流れで〈Captured Tracks〉とも繋がることができた。ただ、〈Captured Tracks〉からリリースしても、僕らは現地NYCにはいないわけで。マイクもそのことに気づいて、ぼんやりとしたまま終わってしまった。だから、東京に住んでいるなら東京のシーンを盛り上げるほうが重要なんだなと、考え方の変化が物凄くありました。
──2010年に始動したレーベル / パーティ〈Cuz Me Pain〉の活躍ぶりが、当時の日本国内でしっかり伝わっていたとは言い難いかもしれない。でも、遺したものは大きかったはずで、東京のインディー・シーンにかなり影響を与えていると思うんです。
当時はまったくそんなことは考えてなかったし、ただ自分たちが楽しんでいるだけでしたね。ただ、「高校生の頃にレコード買ってました」「大学生の頃に遊びに行っていて、いまはバンドやっています」みたいな感じで、後になって話が繋がっているところはあります。最近すごく思うのが、かつて自分が作ったものが、また先の未来で自分を助けてくれることってあるんだなーって。いまの自分は、〈Cuz Me Pain〉をやっていた時期の活動に助けられている実感があるので。
──というと?
たとえば、DYGLやミツメは2010年とかの僕らのイベントに遊びに来てくれていて。まだ大学生だった彼らに、「大学に入ってYkiki BeatやDYGLっていうバンドをやっています」「ミツメっていうバンド始めたんです」みたいに話しかけられたり。その子たちがいま活躍していて、そういう繋がりによって生まれたコミュニティがいまも続いている。〈Cuz Me Pain〉はレーベルとしては終わりましたけど、そこにあった精神的なものは、そのときいたメンバーはみんな持ち続けていますね。
洋楽やラップのフックでどういう響きがかっこいいのか
──ある種のインディーの美学が継承されているわけですね。WOOMANというバンドは、どのように結成されたのでしょう?
〈Cuz Me Pain〉に所属していたODAのソロ・ユニット、The Beauty(編注1)のライヴを手伝っていたメンバーによって結成された感じですね。The Beautyはエレクトロニックなスタイルで、その前にやっていたFaron Squareというバンドもエレクトロ・ポップな感じだったから、「なんかロック・バンドやってないな?」ってことで。4人だけの音でやりたくなって(可能性を)探りはじめたのが最初です。
編注1: 現在はKEITA SANOなどもリリースし、世界的な評価も高い、インディー・ダンス〜ハウス〜ニュー・ディスコを中心にリリースする、国内の老舗インディー・レーベルで、渋谷系の震源地のひとつでもある〈Crue-L〉からリリースされていた。
──2014年に結成されて、そこからサウンドの変化も大きかったみたいですね。
まずバンドを組んだあと、いきなり2ヶ月後にライヴが決まったんですよ。なので突貫で5曲くらい作って、あとはコピーをやりました。当時はアイスエイジとかロウワーをよく聴いていたので、その影響は物凄くありました。ベースがめっちゃ歪んでいたり、トリッキーなリフを弾いたり。
──コペンハーゲンのポストパンクが盛り上がってた時期ですよね。
ただ、どうも自分たちのキャラクターには合っていなくて。アイスエイジが彼らにしかできない表現をやっているように、“WOOMANたらしめるものとはなにか”をみんなで考えるようになりました。それを探っていくなかで、トロ・イ・モアのバンド・サウンドのアルバム(2015年作『What For?』)みたいなソフト・サイケとか、キング・ギザード&ザ・リザード・ウィザード、アリエル・ピンクみたいなものをやりたいね、というふうに漠然とした感じで曲作りを進めて。その頃の音源をまとめたのが最初のアルバム『LOST LOVE』です。
──当時をいま振り返ってどうですか?
ちょっと迷走していましたね(笑)。一曲のなかに三拍子、変拍子を絶対入れようとしたり、合唱パートを必ず入れたり、無理やりクセをつけようと考えていた時期で。ドラムのKOUTAがポストロック好きなので、そういう要素も入っていて。それもあって、演奏力の限界を感じるくらい曲が難しくなってしまったので、次に作るものはもっとシンプルにしようと。「3コードくらいでやれたら理想的だね」って話し合いました。弾き語りでも歌えるくらいシンプルなものにしたほうが、ライヴのパフォーマンスも自由にできるし、自分たちに合っているんじゃないかと。
──うんうん。
自分たちがいままで多重録音やDTMで音楽を作ってきたので、とにかく重ねることにこだわっていたんですよね。でも、昔の自分が聴いていた音楽──ビートルズだったり、邦楽だったらTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTもそうですけど、みんなそこまで難しいことはやっていないことに気づいて。そこから音数を減らして曲作りするようになり、洋楽やラップのフックでどういう響きがかっこいいのか歌詞の研究もするようになって、そこから最初にできたのが7インチで先行リリースした「STILL INSIDE」です。あの曲を作ったことで雛形ができたので、そこでの手法を広げていきながら、半年以内で今作の曲を全部書き上げました。
別のバンドみたいになっていますよね
──いや、本当にいいアルバムですよね。フレッシュで勢いもあって。
別のバンドみたいになっていますよね(笑)。
──ご自分のなかで、特に気に入っている曲は?
「LONG STANDING」は、「10代の頃に初めて洋楽いいなと思った曲」のようなものを作ろうと思った曲で。それこそ、グリーン・デイの「Minority」みたいな。前作の頃だったら絶対にありえない曲なので、それもあって7インチのB面にしました。だから、ラジオでかかってほしいですね。中学生がいいなと思ってくれたら嬉しい。
──そうやってモードが切り替わったタイミングで、〈KiliKiliVilla〉からリリースされるというのも驚きました。これはどういう経緯で?
もともと、安孫子さん(〈KiliKiliVilla〉主宰)も与田さん(〈KiliKiliVilla〉A&R)とも全く面識はなかったんです。僕らはずっと淡々とライブをしながら、前作は自主レーベルで作って、流通も自分たちでやっていたので。今回のアルバムも自主で作るつもりだったので、1年半前くらいからレコーディングをはじめて、4曲くらいは録り終わっていたんですよ。
──へぇ。
で、たまたまNOT WONKと対バンさせてもらったときに、与田さんがいらっしゃって僕らのライヴを観てくれて。ライヴが終わって楽屋で、「君たち何者なの!? すごくよかった」とおっしゃっていただけて。僕らはもちろん〈KiliKiliVilla〉のことは知っていたし、所属しているNOT WONKやodd eyesとか個人的にも好きで、やっていることはたしかに近いものがあると思っていましたけど、同じエリアに住んでいるけど 「川の向こう側の街」みたいな(笑)。
──どこか遠い存在だと思っていた。
でも、インディペンデントでしっかり活動していて、この5年でのリリース量も半端ないし、とにかく情熱がすごい。その情熱でもって僕らに声をかけて、ライヴだけで決めていただいた。信頼ができる話じゃないですか。メールで「音源聴いたんですけどウチで出しませんか」ではなくて、観たうえで出そうと言っていただけるのはありがたいですし、僕らが〈Cuz Me Pain〉をやっていたときのスタンスもほぼ同じで。僕らも友達じゃない人のリリースはしなかったし、会ったことのない人は対バンに呼びたくないっていう、尖っていた時期もあったので。だから、〈KiliKiliVilla〉から出すのを意外に思われることもあるんですけど、スタンス的に考えると物凄く近いものが合わさったと思います。
──出会うべくして出会った感じが、またいいですよね。
ローカルのコミュニティを盛り上げる方向でこのリリースに繋がっているので、またそこに返せるといいなと思います。
──いやー、最高にイイ話でした。この先、WOOMANの音楽はどんなふうに聴かれてほしいですか?
今回のアルバムは本当に聴きやすいものになっているので、いろんな人に聴いてもらいたいけど、やっぱり10代の子たちに「バンドって楽しそうだな」と入り口になればいいですね。そこから前作に遡ったときに、「なんだこれは?」ってなるという(笑)。僕の場合はゲット・アップ・キッズがそんな感じで。2ndから入って、1stに戻って聴いたら「音、わる!」みたいな(笑)。でも、そういう楽しみ方もできるんではないかと。
PROFILE
WOOMAN

YOSUKE TSUCHIDA(ex-White Wear, ex-Jesse Ruins)、YUJI ODA(The Beauty)、YUUKI YOKOYAMA(ex-AAPS)、KOUTA WAKATSUKI(Mad Gets)にて2014年に結成。2015年に入りライブ活動を本格化、60sサイケ~80sパンク、90sロックとユーモアをクロスオーヴァーさせたサウンドはシーンにおいて異質の存在感を放つ。2016年8月に自主レーベル「HERHEADS」を立ち上げ1stカセットEP「WOOMAN」をリリース。同年12月、初のスタジオ録音となる1stアルバム「LOST LOVE」、2017年7月「Still Inside EP」、2018年6月にTシャツシングル「Magenta Ring」をリリースしている。
公式tumblr
http://woomanmusic.tumblr.com/