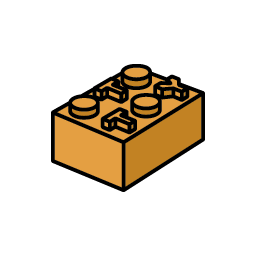はじめてたどり着く“いまの時代のレコード”──現在進行形のポップ・バンドとしてのスカートを証明する新作

映画やドラマ主題歌への抜擢やアーティストへの楽曲提供など、これまで以上に広く活躍を見せる、スカートが2019年6月にメジャー2ndアルバム『トワイライト』をリリースした。今作には『高崎グラフィティ。』主題歌「遠い春」や、大泉洋主演映画『そらのレストラン』の主題歌・挿入歌の「君がいるなら」「花束にかえて」をはじめ、11曲を収録した。澤部自身「これはいまのレコードだ」と語った今作。では澤部が考える“いまのレコード”とはどういった作品だったのだろうか。リリースから2ヶ月以上経ったいま、改めて今作を振り返ってもらった。
スカート、待望のメジャー2ndアルバムも配信中
INTERVIEW : スカート
スカートのアルバム『トワイライト』がリリースされたのは今年の6月19日。もうなんだかんだで2ヶ月以上前のことになる。その後、スカートはツアーに出て、〈フジロック〉にも出演し…… と相変わらず東奔西走していた。このインタヴューはそんなリリース後の忙中に行われた。発売からしばらく経過し、澤部はこの新作をどう受け止めているのか、冷静になったところで話をしてみたいと思ったからだ。具体的には筆者が大阪梅田クラブ・クアトロでのライヴを観たあとの余韻を残していた、まだそこまで暑くない7月上旬の雨の東京で澤部に話を聞いた。
ところで、7月6日に行われたそのスカートの大阪公演は本当にすばらしかった。筆者がこれまでに観てきたスカートのバンド・セットでのパフォーマンスの中では、ダントツに良かったと言ってしまってもいいかもしれない。バンドの演奏は極めてホットで跳躍力に溢れたものだった。でも、そうやって感極まり、途中何度も目頭が熱くなり、何度も胸が熱くなっても、ふとポツンとひとりで見ていることに寂しさが心をよぎる。そんな自覚が今も生暖かく体に残るライヴだったのだ。帰り道、「今宵のこれこそがスカートというバンドのライヴの醍醐味だ!」と反芻するその一方で、「すごく地味かもですけどすごいいい作品ができました」と言って澤部が最初に音源を送ってくれたことを思い出していた。「地味かもしれない」。いや、そうか? と。『トワイライト』はたしかに派手とは言えないが、後半に向かうにつれ滲み出てくる一定のダークネスに裏側に見える豊かな情緒、そしてそれを驚くほど厚みと高低差のある音像で伝える録音の良さ、その芳醇な仕上がりが、「地味」などという陳腐な表現を最初から全く寄せ付けないアルバムだ。そして、明らかにこれは2019年の作品であるというヴィヴィッドな手応えを伝えてもいる。カジュアルだけど薄っぺらくなく、重量感はないけど厚みがある、そんなポップ・アルバムは正直言って他にあまり思い浮かばない。そういう意味では2019年を相対的に象徴した音楽ではないかもしれないが、いまの時代に虎視眈々と勝負に出た作品としてこれほど強い爪痕を残す1枚もないと思うのだ。
そんなアルバム『トワイライト』からの曲をたっぷりと披露したライヴを見て、「これこそがスカートだ」と思えた事実、これが『トワイライト』の録音物としてのすばらしさと無関係であるはずもなかった。それは今年の〈フジロック〉のステージを配信でしっかり見届けて感じた確信でもある。だから、いまこそスカートの『トワイライト』を聴こう。もういまの澤部はこの取材の時とはまた違うモードに入っているかもしれない。でも、『トワイライト』というアルバムが今年を代表する1枚であり、スカートが現在進行形のポップ・バンドであることを証明する1枚であることに変わりはないのだから。
インタヴュー : 岡村詩野
編集 : 鈴木雄希
写真 : 作永裕範
『20/20』の頃に比べたらアコギ主体の曲が増えた

──この半年ほどの間で、アコースティック・ギターを弾いてステージに立つような形が増えていますよね。響いてくる音の感触からも、同じ楽曲なのにこれまでのイメージとかなり違って聴こえます。
そうですね。新しくアコギを買ってもうすぐ1年くらいじゃないかな。秋くらいに買ったと思うので。
──その理由を聞いてもいいですか?
単純に弾き語りでライヴするときにいままでずっとエレキを使っていたんですよ。これはなんでかっていうと、自分が持っているアコギが古い国産のものでピックアップが付いていないんですね。だからマイク立ててやるとなると直立不動でライヴをやんないといけなかったんです。それが嫌だなあと思っていて。プラグが刺さってないと、ちょっと動きたいときに動けないじゃないですか。それでずっとエレキを使って弾き語りのライヴやっていたんですよ。でも、弾き語りのライヴも増えてきたので、じゃあ新しいアコギを買おうかなと。というところでいま使っているMartinのD-35Eっていうやつを買ったんですよ。それがね、思いのほかいい具合にはまっている感じはしますね。
──アコギを使わなかった理由っていうのは、ライヴでマイクから離れることが多いっていうそれ以外の理由っていうのは?
ないです。全くないです(笑)。
──お家にはアコギあるんでしょう。
プラグドのものはないですよ。本当に純粋の生アコースティック・ギターしか持ってなかったので。
──じゃあ、アコギで曲を作ることも?
ありますあります。新しいアコギを買うちょっと前から割とアコギ主体の曲ができていて。「遠い春」もそうですし、「花束にかえて」とかもそうだったんですけど、だからすごい自然な流れでアコギをバンドにも投入したって感じですかね。うん、『20/20』の頃に比べるとやっぱりアコギ主体の曲、増えたかな。
──それは自分ではなぜだという風に感じていますか?
なんでなんだろう。あんまり自覚はないんですよ。どこだったんだろうなあ、なにがきっかけだったのか。それはちょっと僕にもまだわかんないですね。でもなにかこう…… 『20/20』の先を考えたらアコギに行っていたのかもしれないですよね。『20/20』がわりとエレキギターで、カラッとした感じができたんで、なにかそうじゃないことって考えていたとしたら、アコギに行き着くっていうのは自然っちゃ自然かなという感じはしますね。たとえば自分の中で『CALL』はアコギのアルバムなんですよ。だからそこにちょっと戻った感じもあるのかなあ。自分じゃコントロールしきれない部分の話で、アコギに持ってかれたって感じはします。
──たしかに新作は『CALL』に近い感じ、正直ありますね。
そうですね、わかります。『20/20』みたいなああいう抜け感じゃない抜け感になった感じはするんですけどね。でも、そう考えるといままでのスカートのアルバムって、内向き、外向きを交互にやっている気がしますね。『エス・オー・エス』を内向きではじめて、『ストーリー』、『ひみつ』、で『サイダーの庭』が外向き。まあ『ひみつ』は外向きって言う人もいるかもしれないけど、僕からしたら内向きですね。
──で、『CALL』でまた内向きに。反動、反動みたいな。
ですね。そんな感じはあるのかなあ。でも、考えてやってるわけではないんです。
──アコギの音がある種その「内面性」みたいなもの、内向きな部分っていうのを引き出すのにいいきっかけになったというか、あるいはそれを象徴する音としてのアコギっていうのが、まず『CALL』と今回のアルバムの共通するところかもしれないですね。実際アコギって内向きなものを感じる楽器だっていう認識はあります?
あります。でも、使い分けた感じはします。ガッと外に向かせたい「ずっとつづく」とか「トワイライト」とかはね、外向きな、わりと明るい音のするものとして扱えた感じはします。
──そういう意味では『CALL』よりもうちょっと複雑な内向き、外向きの組み合わせが新作では実践されているわけですね。
そうなんですよ。『CALL』はそのままストレートな内向きっていう感じがするんですけど、今回の曲の中でも内向き、外向きが同時に存在している感じにできた手応えはあるんですよね。自分的には。こういうことはできあがってから気づくことが多いですね。作っているときはもう夢中なんで、細かいことはあんまり気にできないですね。できあがって、歌詞とか書いて、「ああ」みたいな気分になることの方が多いかな。逆に「この曲はこうだからこういう歌詞を書かなきゃ」ということももちろんありましたけど。
──たとえば『20/20』には「視界良好」という曲があって、アルバムの中で大きな推進力が働いている曲だと思うんです。それに対して今回のアルバムの中だと「それぞれの悪路」がそれと対称の関係にあるような気がしますね。「視界良好」に対して、視界「不良」とは言わないけど。
あ、でも「不良」です。そういうことです。
──あの曲は、サン=テクジュペリの『夜間飛行』がモチーフになっていますよね。『夜間飛行』という小説も、踏み込む勇気と、そこになかなか踏み込めない感じが表れた小説で、しかもバッドな結末になっていますけど、「それぞれの悪路」も見通しが悪くて踏み込めない感じが表現されている。そういう意味でも前作の「視界良好」とは対照的で、新作と前作との対比が象徴的に現れた曲だと感じます。
いやあ、全く意識していなかったですね。いまはじめて、そうか、「視界良好」のある種の対なんだなっていうのに気づきましたね。
──「それぞれの悪路」を作っている段階で、「やっぱり視界良好じゃないな」って気づくような不安なり、焦燥なりがあったのですか?
ああでも、思いますね。30歳過ぎて、不安なことが増えましたね。シンプルに。でもそれは音楽っていうよりは日々の暮らしとかそっちの方が大きいかな。「生きづらいなあ」みたいな(笑)。

普段の暮らしに必要ない贅沢品
──どういうときに生きづらさを感じますか?
だって生きづらいでしょう(笑)! いままでわりとフラフラ生きていたんで、フラフラ生きてたなりの暮らしだったんですけど、30歳過ぎていよいよ現実がこっちに向かってくるなっていう感じ。生きていくのにはいろいろお金や知恵が要るんだなってことに直面して。そういうことを体験してきたから、「それぞれの悪路」もそうなんですけど、「ずっとつづく」とかも昔だったら書かなかったような歌詞になりましたね。
いまこれがネガティヴな意味かポジティヴな意味かわからないですけど、「年を取ったな」ってちょっと思いました。たとえば同級生で結婚して子供がいる人とかいるけど、「僕には無理なのでは」っていうのが現実味を帯びてきてしまった(笑)。現実がこっちにどんどん向かってくるんですよ(笑)。じゃあ、せめてライヴで「楽しいー!」みたいになれたらいいけど、うちはそういうバンドじゃない(笑)。
──そうかな?
そうなんですよ。ライヴでみんなが求めるのって「一体感」だとか、ある種の大きい意味での「共感」だったりすると思うんですよ。やっぱりスカートってよりそこにいる人を独りにさせる音楽だと思うんで、そこに価値を見出すのって結構ニッチなんだろうなぁ、って。自分としてはもちろん開けたもののつもりではやっているんですけど、やっぱり「ああ、時代遅れの音楽をやってるんじゃないか」みたいに思うことはね、最近ある。
でも昔と1個違うのは、昔って『エス・オー・エス』とか『ひみつ』にしろ何にしても、作って出したとき、「これはいまのレコードじゃないな」ってずっと思っていたんですよ。「これは1993年くらいのレコードかな」とかね。でもこの『トワイライト』を作ったときに、「これはいまのレコードだ。2019年のレコードができた」と、はじめて思えたんですよね。
だから『トワイライト』でツアーをやると、自分なりにとてもいい景色が見えたんですよ。本当に楽しかった。お客さんもそこにいい気分を見出してくれたと思います。ただ、果たしてこれがいまの社会に必要な音楽だったのかなっていうのはちょっとまだわかんない。レコードとしては絶対いまの物ができたっていう自信があるけど、ライヴが時代遅れなんじゃないかなとも思えて。お客さんを独りにして、そこに浮かび上がるそれぞれの情景にみんながグッとくるようなライヴっていまじゃない気がするんですよ。誰かと共通のなにかを共有して、そこのコミュニケーションが炸裂する方が気持ちいいんじゃないですか。
──そうかなあ。こないだ見せてもらった大阪でのライヴでも、曲が終わって、みんなワーッと拍手はするけど、すぐシーンとなって澤部くんがもくもくとチューニングするみたいなあの感覚って独特で逆にいいなと思いましたよ。
僕もあの感覚はすごい良かった。(ツアーの)大阪公演は特に良かったですね。たとえば誰かと観に来ていても曲のどこかで一瞬「はぁ。自分はいまひとりかもしれない」とか思ってくれるのが僕のライヴではあると思うんですよ……。まあ、ライヴに関してはいま、脂が乗った、という気がするんでまだまだこれからですね。
──では、今回のアルバムではじめて2019年のレコードだって思えたのは、具体的にそれはどういうところから感じるのでしょう?
まだ自分なりの答えは出てないんです。そこを考えてるんですよ。いまの音だっていう風に思ったのか、思ってしまったのか。やってることは、いまの時流と反対の事なんですよ。反対のことをやって、極端なことを言うと「過激なことができた」っていう達成感がちょっとはある。だって、ここまで徹底している人はあんまりいないというかね。マスタリングからミックスから、全部が内向きで外向きなんですよ。それらが内在しながらも同じ方向を向いた。っていう達成感があったんだろうな。
実はマスタリングもめちゃくちゃ迷ったんですよ。国内にするか海外にするか、小鐡(徹。JVCケンウッドのベテラン・マスタリング・エンジニア)さんにするのか、それ以外の人にするのかも含めてね。いろいろ迷って小鐡さんになったって感じでしたね。マスタリングは3日間やったんですよ。(初回版CDについている)弾き語りヴァージョンの方も小鐡さんにお願いしたんで。じっくり仕上げましたね。こういう内向きと外向きが混在したような音楽をやっても、結局マスタリングはいまの時代はサブスクを基準にするんだろうから多少大きく、派手に聴こえないと…… とかいう話も出たんですが、そういう方向性に僕は従わなかった、というか作品が従えなかったんですね(笑)。

──でも、サブスク公開に踏み切った。逡巡したらしいですね。
(笑)。サブスクのことで悩んでたのは絶対にあります。たとえば、定価2,600円の物を売って5,000枚売れて、じゃあ次がやれるね、みたいなやり方でずっとやってきたので、その流れはわかってるんですけど、サブスクで入ってくるであろうお金じゃまかなえないだろうなと思うんですよ。僕らみたいな音楽って、普段の暮らしに必要ない贅沢品だと思うんですよね。もっと必要なのは、さっき話したみたいな共感とか機能的な音楽だと思うんです。
サブスクでなんとなく聴いてくれる人は増えるかもしれないけれども、その先のヴィジョンが見えないし、そうなったときに1番最初に飲み込まれていくのは僕たちだろう、と。シンプルに未来がないなって思ってしまったんです。〈ポニーキャニオン〉の人とか〈カクバリズム〉の人とかも必死に「そんなことないよ」って言ってくれるんですけど、それは自分の望む言葉じゃないんですよ。僕もどういう言葉を望んでいたかわからないですけど…… まあ、それならやろうかと。100%晴れた心で最後まで言えなかったけどね。新しい音楽に出会わせてくれる場としてのサブスクに期待してるんですけど、贅沢品としての我々はやりようがなくなっていくと。
だからね、「『いまの時代の作品になった』とはじめて思えたのはなぜ?」というさっきの質問の答えに戻ると、すごく贅沢を尽くして作れたってことなんですよ。こんなにしっかり生の楽器の鳴りとかね、そういうのを録音できたっていうのはね、本当に贅沢なことなんですよ。鳴っている音はシンプルでもね、すべての楽器の雑味がしっかり入っている。
──録音をした葛西敏彦さんとの信頼関係がより意味を持つようになってきたということですね。つまり、これまでの作品にはどこかその「信頼関係に基づく贅沢な作り」が欠けていたっていうことですか?
そういう言い方もできるかも。スカートのこれまでの録音を振り返ってみると、葛西さんと最初に作った『CALL』あたりからちゃんとやれるようになったかな。『エス・オー・エス』のときも妥協はなかったけど。『ストーリー』と『ひみつ』は予算の関係が1番大きかった。本当にお金がないただのアルバイト、フリーターだったんで。『ストーリー』はメンバーやエンジニアへの経費は別として録音にかかった費用は2万とかですよ。本当に勢い任せでしたね。でも、それが2011年、2013年には正解だったし、エンジニアの馬場(友美)ちゃんと「ああでもない、こうでもない」とつくりあげたそれぞれの作品はいまでも好きです。
それでだんだん聴いてくれる人も増えて、お金を出してくれる人も出てきて、『CALL』を作ったときはとにかく「言い訳のきかない音源を作ろう」って社長(角張渉)が言ってくれて。そこでものを作る気持ちも少し変わった感じはしますね。「もっとこういうところにこだわりたいんですけど」みたいな話をできるようにはなったし。
──そういうことが全部追いついてきて、2019年の音になった。では、逆の見方をすると、澤部くんが好きな1970年代前半の音の良さっていうのはどういうところにあると考えていますか?
僕もまだわからないんですよ。たとえば、すごい好きなヤングブラッズの『Ridethe Wind』はライヴ盤だし、ブロッサム・ディアリーの『Sings』もローバジェットで作られたアルバムだし、キンクスの『The Village Green Preservation Society』もめちゃくちゃハイファイかっていうとそんなことないんだけれども。でも当時の最新とまでは言わないけど、どれもそのときの最善の音じゃないですか。『CALL』とか『20/20』くらいの頃までは、少しそういう古いものを作りたいっていう気概があったんだと思うんですよ。
で、「オータムリーヴス」(『20/20』)っていう曲をレコーディングしたときに、モノ・ミックスにしたんです。そのミックスはすごい気に入っているし、大好きなんですけど、ひとつ引っかかった。たとえばビートルズとかゾンビーズのモノ盤とかが好きなんで、そういうのに倣ったつもりでやったんだけど、なんかどこかで、古いものを目指そうとしていることが、間違いとまで言わないけど......違うんじゃないかって。それらのアルバムは当時の機材で言えばそれが最新や最善だった。自分の中で「オータムリーヴス」ができたときに、1960年代のイギリスっぽい曲だなあと思ったからモノ・ミックスにしたのが、短絡的すぎた、本質的ではないっていう反省があったんです。すごい気に入っているし、本当に好きなミックスだし、すごいいい演奏なんだけど、それはもしかしたら間違っていたことなんじゃないかって、ちょっと思っていたんです。
──古い音楽が好きならヴィンテージの機材を使えばいい的な発想への疑問ですね。
そう。古い機材を使って憧れのサウンドを鳴らしても、古いものができるわけじゃないし、ましてや新しいもの作ったから新しいものができるわけじゃないんだなっていうのをね、この2、3年で気づいたんですね。実はビートルズを語る取材があって。そのときにしゃべりながらハッと気づいて、自分はとんでもなく恥ずかしいことをしてしまったんじゃないかみたいな気持ちになっちゃったんですよ。ビートルズがもしいまこの「オータムリーヴス」という曲を作ったとして、彼らはさてモノ・ミックスにしたかっていうと絶対しないと思うんですよね。それにハッと気づいてしまって。それが大きかった。昔の機材を使っても昔の音楽をシミュレーションするようなことはやめようとどっかで思っていたんだろうな。ヴィンテージの機材使えばヴィンテージの音になるって思っていたけど、そうじゃない。
すごくなだらかなアルバムになった

──でも、そういう経験があったからこその『トワイライト』。
そう。それに気付いたのが大きかったんだな。いままでそれに気付いていたことも、アルバムには影響ないと思っていたんですけど、それがでかかった気がする。つまり、『トワイライト』は昔っぽいレコードを作る、っていうところには意識は働かなくなったということなんです。あと僕らが『エス・オー・エス』とか作っていた頃より、昔っぽい音を作ることが簡単になったのかもしれない。『エス・オー・エス』作っていたときって貧乏学生だったからというのもあるけどプラグインも貧弱だったので、結構いろんなことをして、わけわかんないような音にしなきゃとかね。いろいろやったんですよ。「Taroupho」っていう曲もリズムボックスのパターンを1回カセットに落として、それを再生してスピーカーの音拾って混ぜたりして。そういうのがプラグインとかでもっと簡単にできるようになっちゃったから、あんまりロマンを感じなくなっているのかもしれない。
あと、葛西さんが最初から、「今回は明るめの音、前よりも開けた音にしよう」って言ってくれて。そこが外向きの要因として残っている最大の部分だなとは思っています。もちろん、そうじゃない曲もあるけど、何か録り音とかミキシングはめちゃくちゃ外に向いている曲っていうのは何曲かあって。それがうまい具合に成り立っている、絶妙なバランスで成り立っている所以だろうなあと思いますね。
あとは、もしかしたらサブスクの台頭によって、いままでの自分の音楽の聴き方を少し肯定されたような気もしていたんですよ。いろんなものが並列になって、いまも昔もないみたいなね。そういう音楽の聴き方になるんだとしたら、自分としてはやりやすいかもしれないとか思ってた時期もあった。それも影響してるかな。もちろん、サブスクへの思いに関してはまだ結論は出ないですけど、でも、すごくなだらかなアルバムになったな、そこがいまのレコードだって思えるところかもしれないです。
──「なだらか」といういうのがアルバムの、少なくとも澤部くんの考えるいまの時代のアルバムという概念を伝える言葉のひとつなんですか?
なのかもしれない。たとえば、『エス・オー・エス』も『CALL』もどっかで「そりゃその曲はそこに置くしかなかったよね」みたいなのがなくはないアルバムなんです。でも、『トワイライト』はとにかくこの曲入れたいっていう情熱が無理せず納まった。そういう意味でなだらかですね。今回タイアップもあったし、最初はもっと寄せ集めだと思っていたんですよね。でもたとえば『CALL』よりもぜんぜんアルバムっぽいアルバムになった。自分の歴史の中で好きなアルバムをあげろって言われたらやっぱ『エス・オー・エス』と『CALL』をあげちゃうんですけど、そのどっちの2枚よりもアルバムとしてはなだらかだなって。
──今作は歌詞も「なだらか」かもしれないです。
そうですね。めちゃくちゃ強い言葉は出てきていない。「沈黙」と「それぞれの悪路」にちょっとあるかなくらいな感じですね。なんか歌詞が出来ていく過程も苦労した曲もあるけど、すごく自然だったんですよ。たとえば、「四月のばらの歌のこと」の最初の一行を最初は「ガラス“瓶”」にしていたんですよ。でも、歌入れしてプレイバックしてみると、何度聴いても「ガラス瓶」に聴こえない。「カラスミ」に聴こえちゃう。これは良くない、何か違う言葉で......って思ったんだけど、聴いてくれるみなさんの頭の中に「ガラス」が出てこないとダメなんだと思って。じゃあ「ガラス“戸”」にしようって。これなら「ガラス」に聴こえると思って、1回目がガラスに聴こえたら2回目も聴こえるだろうと思って、それで最後は「ガラス“瓶”」にしたんです。

あと、「高田馬場で乗り換えて」はマルコメのタイアップだったんですけど、「どんな曲を作っても構わないけど、ただ、タイトルにマルコメをかすめた言葉を入れてくれ」って言われて。で、ここはもう東京のローカル・バンドとして、マルコメの東京本社が高田馬場にあるっていうのは知っていたんで、それにしようと。だから、「発車のベルが」って歌詞、あれはJRの鉄腕アトムの音楽じゃなくて、西武新宿線の発車ベルのことなんです。西武新宿線ではマルコメの曲が乗り換えの音楽なんですよ。そういうのを描いたりするっていうのはいままでやらなかったことですね。
──「なだらか」だから、アルバム・タイトルの『トワイライト』も昼でもなければ夜でもないグラデーションの時間帯を象徴する言葉ですね。
いや、ほんとうにそれに気づいて。スカートの書いてきた歌詞とか言葉とか、曲もそうだと思うんですけど、全て起承転結のどこかなんですよ。その全てを明確に描ききった曲はたぶんひとつもなくて。そういう意味で昼でもなければ夜でもないみたいな、そういうものは非常にスカートらしい。だから意外と、「トワイライト」ってスカート全体を象徴する言葉になるかもしれないと思いましたね。昔言ってた曇天の美学みたいな話にもつながるなと。晴れてもいないし雨も降っていないみたいな。その中間みたいなね。そういうものは非常にスカートらしいなと思ったんですよね。
『トワイライト』のご購入はこちらから
過去の特集記事はこちら
過去作はこちらにて配信中!
PROFILE
スカート
どこか影を持ちながらも清涼感のあるソングライティングとバンドアンサンブルで職業・性別・年齢を問わず評判を集める不健康ポップバンド。強度のあるポップスを提示し、観客を強く惹き付けるエモーショナルなライヴ・パフォーマンスに定評がある。
2006年、澤部渡のソロ・プロジェクトとして多重録音によるレコーディングを中心に活動を開始。
2010年、自身のレーベル〈カチュカ・サウンズ〉を立ち上げ、1stアルバム『エス・オー・エス』をリリースした事により活動を本格化。これまで〈カチュカ・サウンズ〉から4枚のアルバムを発表し、2014年には〈カクバリズム〉へ移籍。アルバム『CALL』(2016年)が全国各地で大絶賛を浴びた。
そして、2017年10月にはメジャー1stアルバム『20/20』を発表。
昨年にはメジャー1stシングルとしてリリースした「遠い春」が映画「高崎グラフィティ。」の主題歌、カップリング「忘却のサチコ」が高畑充希主演のドラマ「忘却のサチコ」のオープニング・テーマに起用された。
そして、2019年にリリースした最新シングル「君がいるなら」には大泉洋主演映画『そらのレストラン』に書き下ろした主題歌と挿入歌を収録。
また、そのソングライティング・センスからこれまで藤井隆、Kaede(Neggico)などへの楽曲提供、ドラマ・映画の劇伴制作に携わる。更にマルチプレイヤーとしてスピッツや鈴木慶一のレコーディングに参加するなど、多彩な才能、ジャンルレスに注目が集まる素敵なシンガー・ソングライターであり、バンドである
Twitter : https://twitter.com/skirt_oh_skirt
Official HP : https://skirtskirtskirt.com/