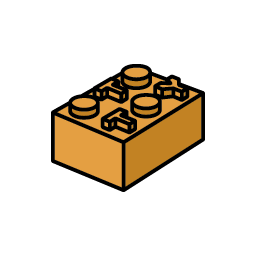“歌に哲学を”──4年ぶりフル・アルバム『Arche』から上北健の表現の原点を探る

メッセージ性の強い歌詞と高い歌唱力で 多くの人を魅了してきたシンガー・ソングライター、上北健。別名義“KK”としても活動し、2014年にはメジャー・デビューを果たした彼が、このたび上北健として2枚目のフル・アルバム『Arche』をリリースした。前作から4年の歳月の中で新たに築き上げてきたアーティストとしての哲学が詰まった作品となった。完成され尽くしたサウンドと、より強力な言葉で紡がれる歌たち。そんな上北健の表現の原点をインタヴューで探る。
4年ぶりフル・アルバム配信開始!
INTERVIEW : 上北健
上北健に話を聞くと、アーティストである前に思想家なんだと思った。『Archē』は孤独、苦しみ、自分の存在証明と向き合った作品であるが、収録された15曲すべてに「その問題がどうして起きたのか? どう向き合っていくのか?」を示しているように思う。上北は「いまは争うよりは考えるタイプになりましたね。この苦しみや悩みは、何で起きたんだろう、って」と話す。彼の表現はどこから来ているのか、そしてどこへ向かっていくのか。上北の歩んだ道のりと、これからの行き先を聞いた。
インタヴュー&文 : 真貝聡
衣装で黒い服を選ぶようになったのは、そこに情報が要らないと思ったから
──今日は帽子から靴まで全身黒でまとめてますけど、普段から黒い服は着ているんですか。
普段というか、上北として外出するときは黒を着てます。
──…… えっと、それはいつからですか。
いつからだろうな、ここ1年くらいじゃないですか。
──去年から黒い服を好きになったと。
好きとか嫌いというよりも、黒しか着ないと決めたんです。「こだわっているけど、こだわっていない」みたいな感じです。
──洋服で個性を出さないように。
ライヴを含めて、人前に出るタイミングで何を着ようか考えるじゃないですか。衣装で黒い服を選ぶようになったのは、そこに情報が要らないと思ったから。そうこうしているうちに、ステージ上から私生活まで、その感じが侵食してきて。
──(スマホの画面を見せて)ちなみに今年の3月、こんなツイートをしていたじゃないですか。
はい。
──黒を着るようになったことも含めて、この1年のいろんな変化を形にしたのが今作『Archē』なのかなと思って。
そうですね。これまで「漠然とした定まらなさ」をずっと感じていたんです。だけど、アルバムを作るとなればゴールが一応できるわけで。作品にすることで、その事実を越えているものになったんじゃないかなとは思います。
──いつから「漠然とした定まらなさ」を感じていたんですか。
「蓄積していった」という表現がいちばん良いのかなと思うんですけど。2015年に上北健がはじまって、2017年までの3年間は漠然と男性シンガー・ソングライターというジャンルの中をウロウロとしていた気がするんです。自分なりに、その当時の持っているもので作曲やライヴをしてきたけども、なんかこう……「貫いているもの」というものに自信がなかった。それを誤魔化しというか、考えてはいるけど解決策に至ろうとはしてないというか。それが2017年まではあって。

──どのタイミングで変わろうと思ったんですか。
2018年から一旦、活動がフリーという形になって。完全に全部を自分でやってみることをはじめたんです。制作もそうだし、配信をするにしろ、ライヴを打つにしろ、ほぼ全部を自分だけでやる。そうすると、それまでやってこなかったことも考えるようになった。たとえばプロモーションをする立場に立ったときに、上北健というコンテンツがなにもこう…… 歌唱力とは言ってもらえてましたけど、個人的にはないなと思って。そこから、もう一度立ち戻ったときに「いままで自分が考えていなかった」「感じようとしていなかった部分」が大いにあったなと気付いたんです。
──そこから変化がはじまっていたんですね。
行動に移したというよりは、自分の通ってきた道を思想にして。そこを軸に作品や、アーティスト像を作っていけるかもしれない、と思ったのが2018年の後半です。
──その作業って相当しんどくないですか。目を伏せたまま活動することもできたはずだけど、自分の足りてなかったことを見つめ直すのは精神的にも苦しかったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。何も掴めてはいない時期ですから。それに目には見えない内側のことだから、周りの反応もないわけですし。
「命題と証明」をどのように導くかの作業をしているんです
──そんな苦難を経て生まれたのが『Archē』で。聴いた印象としては「世の中に自分は必要とされているのか」「本当に自分じゃないといけないのか」そういう対社会との葛藤。あとは30歳になって、自分の踏み出す一歩で世界が変わらないこと、克服できない自分の弱さもわかっているけど、それを受け入れたことで希望を見出すアルバムかなと思ったんですけど…… どうですか?
それもありますよね。だけど、それを嘆きたいわけでもなくて「そういう前提の下で考えてみようよ」と。「自分が動いたところで世界が変わらない」という当たり前がある上で、どうやって生きるのか。「どうやって自分として歩んでいくの? ということを考えてみよう」という提言をしているんです、自分はいま。だから聴いた人が何か考えてもらえる作品になっているのであれば、良かったなと思います。「漠然とこの山を越えれば次の扉は開く」とか、それは曖昧できちんと考えてないんですよね。自分が考えるための動機にはならないというか。考えることって現状を並べることとか、当然の前提条件を確認して、そこから見極めることじゃないですか。「こういうことがあるんだから、次の一手はこうだ」とか。なので、あまり遠くの希望を歌いたくはなくて。『Archē』は身の回りにある自分自身の定義とか、悩んでいることとか、感情の部分とか、いまの前提条件を書いた。そこを見ないと、これまでと同じで漠然としてしまうから。
──その漠然っていうのは、何を指しているんです?
「もっと良い曲を書けば」と言っても、そもそも良い曲はなんだ? という話だし、「良いパフォーマンスをすれば」「歌がうまくなれば」とかもそう。なんで、それをすると良いのか現状が分かっていないと、何のためにする必要があるかわからないわけです。そもそも「何のためにライヴをするの?」って、2018年はずっとそんな状態でした。やってもやるだけ、という気持ちがすごくあった。自分のことを考えはじめたことで「こういうパフォーマンスだったら、自分がやる意味があるな」という方向に繋がっていった。なので、みんなにもそのためのツールにして欲しいんです。このCDだけじゃなくて、ライヴも含めて。
──お話をしていると感情的ではなくて、すごく冷静な人という印象なんですけど。いま、表現をする上でいちばんのエネルギーになっていることは何ですか。
自分の命題を決めてしまったので、ただそれに向き合っているというか。僕はどちらかと言うと、理論的にやるタイプなので「命題と証明」をどのように導くかの作業をしているんです。たとえば「新曲を作らなきゃ」というよりは、自分が決めた正しいかわからない命題に対して、どう切り込んでいくか考える。それが正しいかわからないから、エネルギーになっているんじゃないでしょうか。もっと探っていけるかもしれないって。

「この苦しみや悩みは、何で起きたんだろう」って。それを作品に落とし込むのが今はできるようになった
──最初にお聞きした黒い服を着るようになったこともそうですけど、音楽以外で変わったことってあります?
髪を切らないことにしました。
──え、それはどうして?
作品を生み出す以外の部分をかなりそぎ落とすようになってしまったというか。たとえば「好きな物を食べること」「髪を切ること」「服を選ぶこと」とか普通の生活の中で、みんなが選択していることをそぎ落とすようになってきてしまった。これは良いこともあれば、悪いことも多いにあるんですけど。
──もはや仙人というか…… 自由でもあるけど、かなり不自由な生活ですよね。
そうしないと曲が作れなかったですね。作れなくなってきているんだよな、というか。変わったことといえば、そんなことでしょうか。
──「KK」名義で動画投稿サイトを中心に活動していたときは、「KKをキャラクターとして捉えてた」と話してましたけど。
はい。
──それとは180度違った向き合い方をされてますよね。
作品に対して「自分」の純度が高くなったんだと思います。KKのときは曲を自分で書いてないですし、いろんな視点から織り混ざって“声だけ僕”みたいな。いまはその構図と違いますよね。先ほど「良い悪いがある」と話しましたけど、悪いといえばいまのやり方に酔いはじめてしまうとダメで。それって思想が宗教になってしまうんです。
──はいはい、そうですね。
要するに逃げ道がなくなるし、相手を洗脳しはじめてしまう。僕は今回の作品で「いま、世の中の人は洗脳されている」という表現を使いましたけど、僕こそ、そういう立場になってしまう危険性はある。なのでKKだけじゃないですけど、どこかで誰かと共演するとか外的なメスを入れていかなければいけない。そうしていくと考え方も洗練されていくじゃないですか。だけど、それをするにも自分に軸がなければできないわけで。ようやく、その軸が作れたという感じです。
──先日、KKとして欅坂46の「黒い羊」をカヴァーされたじゃないですか。どうして4年ぶりに再始動されたんですか。
何故あれをはじめたのかについて、理由付けはあるんです。それは先ほど話した、思想をより高めるため。洗脳にならないため、別の視点から自分の言ってる考え方に提言をもらうというような狙いです。
──メスを入れるために。
そうです。KKも、僕の中の大きな流れのひとつであることは間違いないと思っていて。ただ、カヴァーを発表したときに僕の予想していたものと違った反響も大きかったので、その進め方が正しいかは慎重に検討していますが。
──予想外の反響?
4年も経って突然「黒い羊」を歌ったことに、違和感を抱く人は一定数いると思っていたし、僕は違和感があると思ったんです。そこの部分がイメージと違った。
──「おかえりなさい」という声が多かったですもんね。大多数の方と同じく、僕も欅坂46の「黒い羊」を歌ったことは腑に落ちたというか。ピッタリだなと思ったんですけど。
それは「黒い羊」のカヴァーを聴くより前に、上北健の思想を一度考えた人だからこそ感じたと思います。真貝さん(インタヴュアー)は、上北健の思想に引っ張られた上で解釈したからこそ、違和感がなかったはずなんですよ。それはそれで良いと思います。曲の新しい発見を感じさせることもできるし、「黒い羊」をきっかけに僕の思想を考え出す人もいる。
──いや、僕はアイドルの方とも仕事するので「黒い羊」はリリース前から知ってた上で腑に落ちたんですよ。
なるほど。
──僕は同い年だからこそ、上北さんの音楽に共感できているんだと思っていたんですけど、「黒い羊」のカヴァーを聴いて「そうじゃないのかも」って。「黒い羊」にも『Archē』にも感じた虚無感は年齢に限らず、ずっと根本にあったんじゃないのかなと。
「生活する」とか「生きる」とか漠然としたものを考えたときに、前提ってすごく大事だと思うんです。それを段々と感じなくなってくるのはしかたがないことで。だけど、文章や音楽を通して「そうだよな」と思うだけでも違くて。年齢でいうなら、若いころははじめてその前提に出会うタイミング。だけど僕らはもう、その前提には出会っていて、時間が経って停滞してくるこの世界で「それは感じなくて良いよね」と思うようになっていた。だけどいま、真貝さんが『Archē』を聴いたことで改めて感じたということは、1回知っていた前提をもう一度、理解したことに過ぎない。
──まさにそうですね。
その経験こそ、僕はして欲しいと思っていて。忘れていたことが当たり前にあるということを、生きることの前提があるということに気付いた。それが僕としてもエネルギーになったし、他の人にとっては、たとえば仕事を頑張ろうというエネルギーに変わる。いまこそ、その経験をひとりでも多くの人がするべきだと思います。“ごく普通”の僕がそうだったですから、「みんなもそうでしょう」という感じです。
──なるほど。ちなみに上北さんって、自分のことをずっと普通だと思ってました? それとも特別だと思った時期はありました?
「普通」と「特別」も考え出すと難しいんですけど。
──ふふふ。まあ、そうですよね。
自分が何かに秀でてると思ったことはないです。普通とは言わないですけど、僕は真ん中くらいの人間で。そこから下に落ちるのが嫌だけど、上にいく力もない。真ん中でいかに馴染むというか、波風立てずにいられるかという…… まさにそこが僕だったんです。それでずっとやってきたので、全くもって特別ではないです。普通と言えるのかどうかはわからないですけど。

──アーティスト・上北健は音楽で評価をされてるし、ライヴを心待ちにしてる人も多くいるじゃないですか。だから特別な人間だと思うんですけど。
たとえば、グラフがあったとして。僕の値が上がったのなら、一緒に上限も上げていくような人間なんです。だから、ずっと真ん中にいると思い込んでいるんですよ。
──なるほど。昔からそういうタイプでした?
たぶんそうです。上限を広げることによる安心感もあるのかもしれない。上にいく恐怖もあると思うんです。僕はそうなってしまったら、何もしなくなってしまうんじゃないかなって。それこそ何も考えなくなってしまう人間に成り下がってしまうと。
──じゃあ音楽がなくなったとしたら、上北さんはどうなるんですか。
せっかく見つけたツールなので、それがなくなると悲しくなりますね。僕からすれば音楽って思想表現とか、命題と証明をするためのツールで。ようやく自分の使いこなせるものに出会ったから、それがなくなると手段を見失うので非常に困ったことになると思います。
──音楽がなくなったとしたら、難しく考える必要がなくなって、生きるのが楽になるのかなと思うんですけど。
僕は何かしらで、アウトプットにもっていかなければと思う。そのための工程を考えるんだと思いますよ。どういう手段があるのか、その世界はどういう風に成り立っているのか、自分は何から手をつけたら良いのか、とか。思想が作れている前提ならば、それを落とし込むことをするんじゃないでしょうか。
──ちなみに、幼少期や青年期を振り返って「これが表現の根幹になっているな」と思うことは何かあります?
「明確にコレです」とは言えないですけど、幸せなものではないですね。フラストレーションとか、そういうあまり目を向けたくない出来事とか感情の蓄積。それがひとつの根幹にあると思う。
──それは何歳からはじまりました?
10歳くらいじゃないですか。
──何か出来事があったんですか。
自分の置かれた環境に気づいたんです。「こういうところに自分はいるんだな」と。もっとわかりやすく言えば、ストレスを感じ始めた時期かな。結構そこに縛られました。
──そのストレスに対して、争うタイプでした?
学生の頃は、そこを見ないようにするタイプの人間だったんです。だけど高校3年生になってから「これは自分で何とかしなきゃ、ずっとこのままだ」とシフトできた。…… それはたぶん、度を過ぎていたんでしょうね。「自分の現状をちゃんと見ざるをえないぞ」という。それを経て、争うよりは考えるタイプになりました。「この苦しみや悩みは、何で起きたんだろう」って。いまはそれを作品に落とし込むことができるようになったんじゃないかなと思います。

──何が自分を苦しめているのか、ひとつひとつ理由を考えることで解消していく。
そう。発生源の整理と普遍性の分析ですよね。僕はそれを言葉にして、「このタイプの苦しみをこういう経緯で考えました」というのが曲になっているんじゃないかと。…… あまりに理論的ですね。
──そうですね。
だから絶対に自分のことを作詞家とは言えないです。こんな理詰めで書くものじゃないですから。僕は主張をしてるだけなので。
──逆に、シンパシーを感じる人はいます?
シンパシーではないのかもしれませんが、相対性理論のやくしまるえつこさん。「ああ、なるほどな」と最近思いました。
──ご自身の詞に救われることってありますか。
いまのところはないです。救われる、といえば、聴いた人に「この曲の歌詞に救われた」と言われた瞬間がそれです。
──『Archē』を完成させて、これから上北健はどこへ向かっていくんですか。
楽曲とライヴはセパレートになっていて、楽曲は僕の掲げた命題の前提を説明しているもので、ライヴはその前提をもとにどうやって僕が命題を解き明かしていくのかストーリーを魅せています。2019年の春はまさにそのストーリーがはじまりを迎えました。だから今年はその内容を深めつつ、次の場面と、その場面を演じるための楽曲を作るのだと思います。
編集 : 鈴木雄希
『Arche』のご購入はこちらから
過去作もチェック!
新→古
PROFILE
上北 健

もともとはインターネットに投稿したカヴァー楽曲が注目され、2014年9月に当時の別名義“KK”でメジャー・アルバム『心音(こころね)』を発表。翌年には上北健として、自身の作詞作曲によるオリジナル・アルバム『SCOOP』をリリースし、同作品に収録の『DIARY』は代表曲として支持を集める。
そのほかの作品に『TIDE』『LAYERED』『ビューティフル』などがあり、これらの作品では楽曲の原案にあたる短編小説を執筆、書籍化した。ライブでは脚本、演出を自身で手がけるほか、コンテンポラリーダンサー・平原慎太郎氏や華道家・塚越応駿氏といった他分野のアーティストとの共演を行いながら、物語性のある独創的な舞台を作り上げる。
近年では韓国や中国での単独公演を成功させ、YouTube、SNS等で海外からの注目度も高まっている。
【公式HP】
https://kamikitaken.com
【公式ツイッター】
https://twitter.com/kk_dk