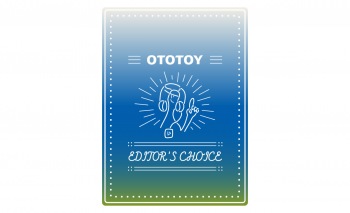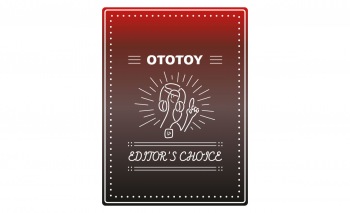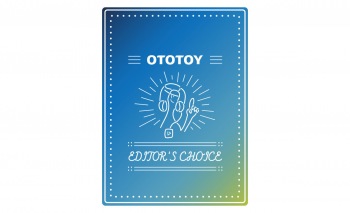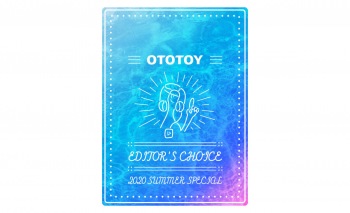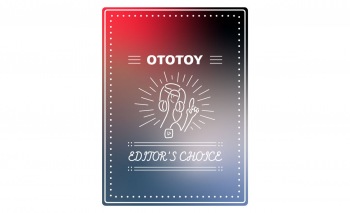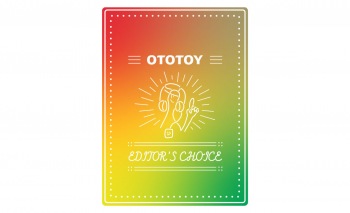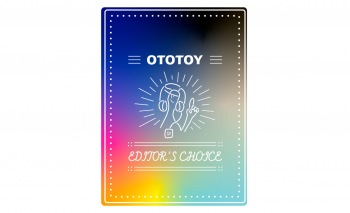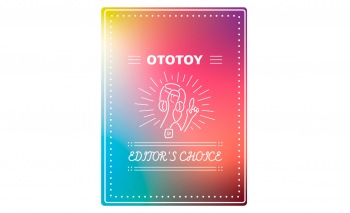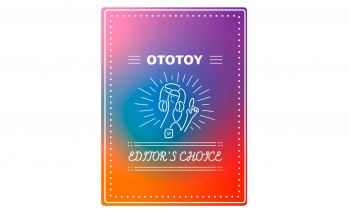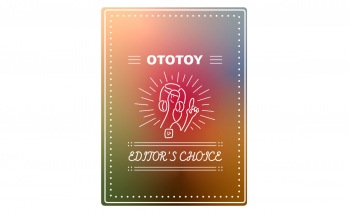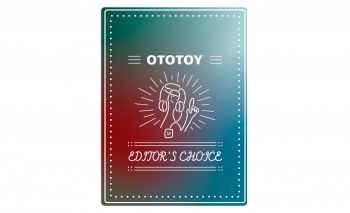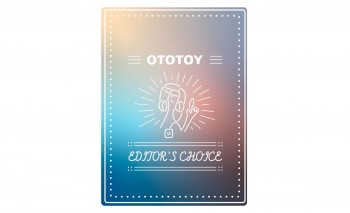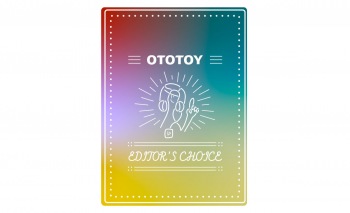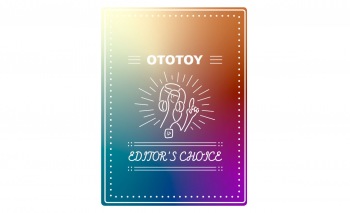OTOTOY EDITOR'S CHOICE Vol.144
OTOTOY編集者の週替わりプレイリスト&コラム(毎週金曜日更新)
音による没入
イメージ・フォーラムで上映されていた映画『カナルタ 螺旋状の夢』に、映像体験を塗り替えられた。アマゾン熱帯雨林の先住民であり、かつては首狩族として恐れられていたシュアール族と、映像作家で文化人類学者の太田光海が1年間生活をともにした上で作られたドキュメンタリー。というか、ほとんどサイケデリック映画と言っていいだろう。覚醒植物であるアワヤスカが引き出すビジョンを見つめる視線と誘発される嗚咽、手の痺れを直すために大量のアリを這わせる様子、チチャと呼ばれる口噛み酒の製作工程…このように並べると視覚的にも内容からも、神秘的で自分からは遠い世界のシーンのように思えるが、鑑賞中はそれがごく自然のことかのように見ることができる。
『カナルタ』にはBGMたるものが一切ない。背景で鳴っているのはその現地の音のみだ。ほとんどのシーンは森の中で撮られているため、常に森の中にいるようなあの静けさとわずかに聞こえる風に揺れる葉の音に覆われている感覚に陥る。釜で作られる口噛み酒がグツグツと煮立つ音、家の隣にある草を薬草としてすり潰す音、虚しいからと歌われる歌…彼らは資源が減っていく森の中、工夫をして食材を探し、医者の処方箋を捨てて自分の体で確かめてきた薬草を使う(そして本当にそれで治ってしまう)。独自の生活に誇りを持ち、粛々と生活を進めていく。それは作中のシュアール族・セバスティアンが言うには、若い頃にアワヤスカを通してみたビジョンに向かって生きているからであり、おそらく他の人々も同様の体験をしているのだろう。後半のシーンではアワヤスカの儀式のため、セバスティアンは先祖へ呼びかけるために歌い、器をこちらに渡す。シアターの外に出る頃には、自分が見るビジョンは何か?と言うことばかりが頭を渦巻いていて、それはまるで体験した後のような感覚でもある。先住民たちの語りや映像の色味によるものでもあるだろうが、やはりのめり込ませるフィールド・レコーディングの比重が大きかったように思う。
音楽作品においてもフィールド・レコーディングは、『カナルタ』でみられるような文化の記録という側面から離れて、その作品のテーマを伝えるためのメタファーとしての要素だったり、ミニマルハウスに形式的に使用されていたりする。というくらいのことは知ってはいたが「わかって」はなかった。改めて耳をすませば、没入のための媒介であったり、ほとんど聴こえないがその雰囲気を助長するためだったり、フィールド・レコーディングにも様々な役割がある、ということはプレイリストにあるいくつかのトラックからもわかることだろう。『カナルタ』は自分にとって、映像作品における音の重要さを教えてくれただけでなく、そもそものフィールド・レコーディングについて考えるきっかけをくれた作品だ。もうイメージ・フォーラムでの上映期間は終わってしまったが、機会があったらシアターで見ることをお勧めする。