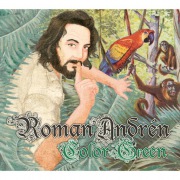デビュー作『The Dreamer』で世界中に名を轟かせたホセ・ジェイムス。ジャイルス・ピーターソンに、「15年にひとりの逸材」と見いだされた奥行きのある歌声は、マーヴィン・ゲイなどの先達を思い起こせる。先日行われた日本ツアーでも、ビルボード・ライヴ東京に集った観客たちを魅了していた。ショーを観て驚いた事は、彼の紡ぐ音楽がジャズという枠組みをいとも簡単に飛び出しながら、それでいてジャズへの回帰性も強く感じさせることである。自分を「トラディッショナルでピュアなジャズ・シンガー」と言いながら、ビート・メイカーとして注目のフライング・ロータスやDJ ミツ・ザ・ビーツ、ムーディマンなどとも違和感なく共演してみせる。その触れ幅の広さを自然に昇華した『blackmagic』について、ホセ・ジェイムス本人に話を伺った。
インタビュー & 文 : 西澤裕郎
Jose Jamesのニュー・アルバム『BLACKMAGIC』をまとめ購入頂いた方に、特典としてジャケット画像をプレゼントします。アルバムをダウンロード後、こちらのリンクからダウンロードしてください。

ムードがある音楽は、それを聴くことで色々な場所に連れて行ってくれる
——アルバム冒頭曲「code」はリフレインが印象的なループ感の強い曲で、ジャズ・シンガーであるあなたの声に対して"水"と"油"の関係にも思えるのですが、どのようなことを意識して歌われているのでしょう?
「code」は自分の声に関して言えば、テクスチャーに近い感じで歌っているんだ。マイルス・デイヴィスが『Nefertiti』でやっているように、同じフレーズの繰り返しが何回もあって、そこにリズム・セクションが少しずつ変わっていく。そんなイメージを自分でも実践してみたんだ。それと、ループさせることでムードを作ること、聴いている人をトランス状態にさせることを意識した。ヒップホップにも繋がる部分で、「code」はもちろん「warrior」でも意識してやっているよ。
——そうした要素は、前作『The Dreamer』にはあまりなかったですよね。L.A.在住のトラック・メーカーであるフライング・ロータスとの出会いは、こうした変化の大きなきっかけとなっているのでしょうか?
フライング・ロータスとコラボレーションした「blackmagic」に関して言えば、同曲だけで15ものトラックを受け取っていたんだ。それを元に、どちらか一方がコントロールするっていうわけじゃなく、同等のパートナーシップを目指して作っていった。だから、「フライング・ロータスからの影響は?」との質問には、肯定することも否定することも難しいんだ。何でかっていうと、僕にはやりたいことが先にあったからね。ループ・ベースで音楽を作って、そのループの上に自分の歌を乗せたいっていう。もちろんフライング・ロータスから影響を受けた部分はあるけれど、お互いに曲のイメージを意識して作っていったので、彼の影響でループ・ミュージックが出来たとは思ってはいない。もっと詳しく説明すると、ジャズ・プレイヤー(シンガーの場合)は普通曲を作る時、ピアノ・プレイヤーの隣にいて一緒に作っていくんだ。ループ・ミュージックの場合はそれと違って基本的にはずっと同じフレーズだからね。だからループする音楽でどう やっておもしろいことをするか、それをどうやっておもしろくするかを考えて取り組まなきゃいけなかったんだ。そこにどうやって自分の声やハーモニーを乗せるかを考える作業もやってみたかったから、ロータスと一緒にやり始めたっていう理由もあるね。
——先ほど、歌に「テクスチャー」としての意味をもたせているとおっしゃっていましたが、ジャズ・シンガーとしての発声法とは対極的な声の使い方ですよね。そこに対して抵抗はなかったんですか?

まず一番大切なことは、「フィーリング」や「スピリット」。つまり、雰囲気やそこにある魂みたいなものなんだ。僕は基本的にはすごくトラディショナルでピュアなジャズ・シンガーだと思っている。尊敬しているアーティストには、レオン・ウェア、アル・グリーン、マーヴィン・ゲイ、そういったアーティストたちがいる。彼らに共通しているのは、ジャズのセンシティヴィティを持っているけど、その枠組みに留まらず新しいことを色々とやっていて、むしろジャズの可能性を押し広めようとしていることなんだ。僕はそういう人たちをすごく尊敬している。「code」でやった、声をテクスチャーとして使ったこともある種のエクスペリメンタルなことで、同じようにジャズの枠を押し広めるって意味で捉えてもらえれば嬉しいな。その根底にあるのがヒップホップ。僕はずっとヒップホップが好きだったから、そういった要素を入れたかった。「code」では、カーティス・メーフィールドがやっている「フィーリング」や「スピリット」を取り入れたかったんだ。そこから、レイド・バックなスタイルを構築することで、ムードを作り出すことをやってみたんだ。だから、自分のヴォーカリゼーションのことばかり考えているわけじゃなくて、「どうしたらムードがでるか」とか「どうやってジャズじゃない要素を取り入れるか」など、色んなことに集中しているよ。
——「フィーリング」や「スピリット」を表現するためにはムードが重要なのですね。
そうだね。ムードがある音楽は、それを聴くことで色々な場所に連れて行ってくれるからね。それは僕自身が音楽を聴いていてすごくいいなと思う事でもあるんだ。色々考えた結果として「code」にムードを作るためには、ループが最適な要素だと思ったんだ。
昔は自分の声を使って何でも出来ると思っていた
——デビューが決まるまでなかなか認められなかったとお聞きしたのですが、昨日のライヴ(2010年2月14日(日)@ビルボード・ライヴ東京)を拝見した限り全く信じられませんでした。その期間があったからこそ、現在の幅の広いヴォーカリゼーションがあると思うのですが、音楽をやりはじめた時と現在で変わった部分、変わってない部分があれば教えて下さい。
そうだね…。一番変わったことは、音楽に対する許容範囲だと思う。昔は自分の声を使って何でも出来ると思っていたんだ。だけどやっぱり自分の声は自分の声だし、ピアノ・プレイヤーがピアノを変えるように自分で自分の声を変えるってことは出来ないことに気がついたんだ。もちろん風邪をひいた時とかは勝手に声が変わったりするけれど、基本的には出来ないだろ? 音楽を続けていく中で、自分に出来ることがわかってきた。それはマインドの面でも大きくて、自分が出来ることがわかってくるのと同時に、その範囲でどうやって一番おもしろくできるかということを考えるようになったんだ。自分にはこれしか出来ないとわかることは、逆に言えば幅を広げる事になるから、すごく自信もつくし、演奏していて気持ちよくもなれる。そういった意味でいうと今の方が可能性は広がっていると思うから、今までの自分は間違っていなかったと思うよ。もちろん若い頃のように自分は何でもできると思っていた時期も必要だったと思うけどね。
——今自分が出来ることの中で、一番の強みは何だと思いますか?
…… (しばし考える)。ブレンディングする技術、というか能力かな。色んなものをブレンドして、一つの形にすることが自分の強みなんじゃないかな。ただ、もっとパーソナリティの部分での意味合いが強いけど。どういうことかっていうと、自分はトラディショナルな音楽を、すごくリスペクトしている。それと同時にアヴァンギャルドなものも好きなんだ。その2つの中間をとって形にしていくっていうのが自分の目指していることだし、自分がうまく出来ていることだと思う。僕はリスナーから遠すぎたり、難解すぎることはやりたくない。かといって、すごくわかりやすいものを作って、近すぎるところにも行きたくない。どっちにも行きたくないんだよ。常にチャレンジしているようでありたい。だから、トラディションとエクスペリメンタルの丁度真ん中をやっていきたいと思っている。そうした意思でやったのが、チコ・ハミルトンとのコラボレーションだったり、フライング・ロータスやミツ・ザ・ビーツとのコラボレーションなんだよ。一方でジャズの巨匠を迎え、他方で若くてしかもエレクトロニック・ミュージックのミュージシャンたちと共演している。それも、中間をとって形にするブレンディングの考えに基づくところで、それが今の自分の強みじゃないかな。

ある程度リミテーションを設けることが重要
——イタリアのDJ/プロデューサーであるニコラ・コンテが「音楽と文学の結びつきの重要性を示したかった」という趣旨の発言をしています。音楽と歌詞(文学)の関係に関してどのようにお考えですか?
僕にとって、音楽と言葉どちらが先に来るかといえば、音楽が常に一番だね。例えていうと、家と家具どちらが先にあるかという質問に対して家って答えるのと同じなんだ。自分の音楽と歌詞っていうのも常にそういう関係としてある。例えば「code」とか「blackmagic」はアブストラクトな部分がすごく強くて、基本的に自由な解釈をみんなにしてもらいたい。人によって色んな解釈が出来たり、音楽に好きに入ることができるようにしたいんだ。100%説明している音楽が悪いとは全然思わないけれど、自分はちょっとミステリアスな部分を残しておきたいと思う。音楽を解釈するというのは、自分にとっての解釈っていう意味も強くて、1つの音楽から1000の違った解釈が出てくるっていうことは、僕にとってすごく普通のことなんだよ。だから自分の音楽もそうでありたいと思っているよ。

——昨日のライヴでスキャットのような歌い方をしていましたが、あれは音楽ありきということを強調するための歌い方だったんですか?
あれはスキャットだね(笑)。ヴォーカリストは不幸なことに、ピュアなサウンドを出す事が出来ない。出来る事ならピュアなサウンドを出したいんだけど、トランペットのようにそれが出来ないからああいう歌い方をしたんだよ。
——ピュアな音がイメージとしてあるのであれば、楽器隊を増やすことも出来るじゃないですか。ベース、ドラム、ピアノ、ヴォーカルという最小限の構成でやられているのはなぜなのですか?
リミテーションっていうのが自分の中で重要なキーだと思っているんだ。僕は自分のことをトラディショナルなジャズ・シンガーだと思っている。それと同じで、ライヴのスタイルは基本的にヴォーカルとベース、ドラムス、ピアノ、ゲスト・ヴォーカリストといったクインテットで構成しているんだ。新しいことももちろんやりたいけれど、おもしろくすることを考えると、ある程度リミテーションを設けることが重要なんじゃないかと思っているんだ。
——では最後に。トラディショナルでありながらコンテンポラリーである音楽を作り続けているあなたが、次作でやってみたいことがあれば教えて下さい。
ジョン・コルトレーンがやっているような感じで、スタジオじゃない場所でアイデアをスケッチに書き溜めていって、一気にスタジオに入って完成させることとか、シンガー・ソングライターとしてちょっと変わったことをやってみたいな。あと(ロバータ・フラックの)「Killing Me Softly」のような曲を書いてみたいね。
Jose James PROFILE

2000年、偉大なジャズ・ミュージシャンが活躍した時代と同様に、彼はニューヨーク・シティへ活動の場所を移すことを決意。しかしそれは非常に厳しい経験となった。いいコネクションを作れず、歌への純粋な情熱すら失いかける事態に直面した。3年もの間、彼は歌うことをせず、ライティング作業に創作意欲を傾けた。ガール・フレンドでさえ、彼のヴォーカル・スキルがどういう状態か分からなくなったほどだったという。その間実際に彼が歌ったのは、ミネアポリスへ帰った際、彼の師でもある元高校教師のDennis Malmbergとコラボレートした時だけだったが、彼女はその歌声の素晴らしさに驚嘆した。ニューヨークに戻った彼に、彼女は再び歌うことを強く勧めた。2004年、ホセは「THELONIOUS MONK INTERNATIONAL VOCAL COMPETITION」に出場し、"New School For Jazz & Contemporary Music"のスカラシップを獲得する。(本校の卒業生には、ロイ・ハーグローヴ、ロバート・グラスパー、ブラッド・メルドーなど錚々たる面々が含まれている。ホセのデビュー・アルバムにも参加したジュニア・マンスやチャールズ・トリヴァー、ジャネット・ローソン、アンドリュー・シリル、レジー・ワークマンなどの現役ミュージシャンがチューターを務めていることでも知られている。)06年にロンドンで行われた「LONDON INTERNATIONAL JAZZ COMPETITION」に参加するため、ロンドンに滞在した際、ジョン・コルトレーン「Equinox」のヴォーカル・カットとセルフ・プロデュース作「The Dreamer」を含むデモEPを抱え、各街のクラブ・セッションを回った。そしてロンドンのクラブCARGOで「Radio 1 Worldwide」のDJにして、のレーベル・オーナー、ジャイルス・ピーターソンにデモを渡し、同レーベルと契約。そこから現在へと繋がるキャリアがスタートしたのだ。
- official site : http://josejamesmusic.com/
伝統と最先端をブレンドする
ニューヨーク・ヘルソニック・バレエ/ 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール
ニューヨークの、地獄の音響で踊るバレエ。菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラールの、北米、オペラ、バレエ、サルサへの第一接触。ミニマルやモントゥーノ、パンク・ロック、そしてソプラノ歌手を起用したオペラを用い、クラブ・ミュージック・マナーとクラシック・マナーの見事な融合を実現。
Tango: Zero Hour / Astor Piazzolla
世界的バンドネオン奏者であるアストル・ピアソラ自身はこのアルバムが「生涯最高の録音」であり、「魂を捧げた」と言う。歴史的名盤にして新五重奏団の最高傑作。時に燃え上がり、時にしっとりと奏でる情熱的なアルゼンチン・タンゴ。
Shaved EP / Babe Rainbow
スウェーデンのデオダート再び! 現代のブラジリアン・クロスオーヴァー名盤として記憶された『Juanita』から2年、再び届けられたパーフェクトなブラジリアン・ジャズ・オデッセイ! 前作よりもジャズ/クロスオーヴァー度高め。