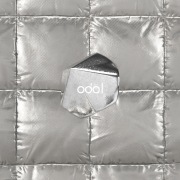バンドという“小さな社会”が形成される
──今作は内省的で静かな曲が多いですね。
森山 : 狙っていたわけじゃないんですけど、結果的にそうなっていたというのは僕も感じてます。ライヴ感とは違うというか。リズム主体ではなくて旋律とか響きが前に出てきてる。自己分析としてあるのは、リモートの時代になって、それまでは制作もスタジオを使っていたけど、その時期は全部自宅で、大きな音も出せないからヘッドホンで制作していて、その影響は少なからずあると思ってます。自分の部屋でヘッドホンでギター・ロックを作っても……正直100dBぐらい出さないとギター・ロックの気持ち良さ、かっこよさってわからないところがあるんですよ。
──エレキはアンプ通して爆音で空気を振動させなきゃ! みたいな(笑)。
森山 : (笑)。想像することはできるんですよ。かっこよさそう、みたいなことは。でもそれだけで本当に成立しているかどうか。たとえば3ピース・バンドのアレンジってDAWでやるとめちゃむずいんです。スカスカになっちゃうし。でもスタジオで3人で合わせると十分豊かだったりするじゃないですか。クラッシュ・シンバル一発叩けば10秒間ぐらい埋まっちゃうみたいな。そういう体感が、ヘッドホンとDAWだとない。そんな状況の中で、フィットする音を探して辿り着いた結果だと思います。
──今作は現状でできるベストに近い作品だと思いますよ。
森山 : 本当にそうですね。なにかを我慢させられたとは思ってないです。
──バンドで集まって一斉に録るんじゃなく、DAWを使ってひとつずつ音を重ねていく作り方だからこそ出来た音って気がしました。録音めちゃくちゃいいいですよね。
森山 : ああ! 嬉しいです。最初からステレオという確立されたフォーマットの中で作業ができたので、それが大きい気がします。普通だとライヴとか、バンドで演奏したものを2チャンネルに落とし込む作業になるんですけど、最初からこの制限のなかで作ってるので、大事にしたいことが明確にわかってきてる。

──3曲あったリワーク・シリーズで“虹の端”だけがアルバムに収録されていますね。
森山 : 今年聴きたい、と思ったからですね。このアルバムと一緒にこの曲を聴きたいと僕らは思った。特に歌詞とか聴き返してみると2020年を過ごして、聴こえ方が変わった曲の筆頭でもあるっていうか。
ミゾベ : “虹の端”は去年の12月に1回だけライヴでやったんです。その時……自分の曲じゃないような……過去の自分に「こういう音楽のあり方ってあるよね」って教えてもらってるような感覚になれたっていうか。
──新しい発見があったということですね。
ミゾベ : ライヴでやるたびに曲をアレンジし直す、ということはodolにとって普通だったので、リアレンジ自体は特別なことではなかったんですけど、“虹の端”をやったその時は、最後のサビを歌ってる時に、ちょっとだけ涙が出そうになって。そういう感覚って、いままでなかったんです。
森山 : “虹の端”は、「バンドって何だろう?」って考えてた時期の曲だった。でも結局そういうことばっかり歌ってる気がします。
──ふむ。では、バンドって何でしょう。
森山 : 社会ですよね。小さな社会。
ミゾベ : 曲を作る時などに、自分たちの感じたことを相互に発信することでバンドという“小さな社会”が形成されるんですよ。それを僕らからほかの社会に向けて発信しているだけなんだなっていう。当たり前のことなんですけど、改めて言葉にしてそれに気付くことができましたね。
編集 : 梶野有希
新作音源はこちらから
Odolのその他過去作品はこちらから
新→古
PROFILE : odol

福岡出身のミゾベリョウ(Vo.)、森山公稀(Pf./Syn.)を中心に2014年東京にて結成した5人組。ジャンルを意識せず、自由にアレンジされる楽曲には独自の先進性とポピュラリティが混在し、新しい楽曲をリリースする度にodolらしさを更新している。近年は、アース製薬「温泡」、映画『サヨナラまでの30』」、UCC BLACK無糖、radiko、森永乳業など、様々な企業やクリエイターからオファーを受け、立て続けに書き下ろし楽曲を提供している。東京藝術大学出身の森山公稀が全楽曲の作曲を担当。ソロ名義でも舞台や映像作品の劇伴、また他アーティストへの楽曲提供、プロデュースなども行なっている。
■公式ホームページ:https://odol.jp
■公式Twitter:https://twitter.com/odol_jpn