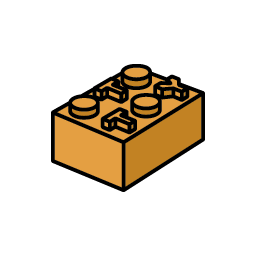0か1かだったら1を取りたい
──歌声自体にはこれまで以上に芯を感じますが、併せて、歌い方のバリエーションもかなり幅が広がったんじゃないでしょうか。“悲しい運転手”では、こぶしのようにあえて声を揺らしている部分があったりとか。“ゲームオーバー”では、トーキング・ワーズまではいかないんだけれども、言葉を投げ飛ばすような感じで歌っていますよね。
歌い方のバリエーションは意識しています。今までもできる限りは意識しているつもりでしたけど、表現力が足りていなかったと思います。無表情な印象のある歌だとよく言われることがあって、それを良さとして捉えてくださる方もいると思います。でも、私は歌も曲の中の役割としては楽器の一部だと思っているので、今回はいままでと違う工夫を施す努力をしたかったんです。今作をリリースするまでの間にいくつかの楽曲を共作したり客演したのもあって、依頼してくださった方の要望を汲んで、歌声にニュアンスをつけることにトライしたのも大きかったと思います。
“悲しい運転手”に関しては、なかなか最後のほうまで歌詞ができていなくて、メロディーをキーボードで打ち込んであるままだったんです。なので抑揚もなくなかなか退屈に思えて、余計に歌詞をあてはめるのにも時間がかかり悩んでいたんですが、でもメロディーを変えることで解決するとも思えなかったので、歌い方を工夫することで変化を出そうとしました。
“ゲームオーバー”はタイトルの通りゲームをイメージしたアレンジの楽曲で、スーパーファミコン時代のポップで軽快な雰囲気を出したいと思いましたし、歌詞の内容が聞こえ方によっては少々重いのもあってああいった歌い方にしています。“ゲームオーバー”を制作したあたりから、徐々に歌い方について考えていったと思います。
──音作りの仕上げの面では、ミックスはファーストと同じ中村督さん、マスタリングは〈ストーンズ・スロー〉周りの作品をよく手がけているジェイク・ヴィアターという布陣になっています。
中村さんはファースト・アルバムでご一緒して以降、セカンド・アルバム以外の作品は全て中村さんとと共にしています。実際にセカンド・アルバム以外の作品は中村さんと制作していますし、ご一緒し続けたことで段々とチームワークもできてきていたので、今作でも引き続きお願いしました。今年の2月から、私はツアーでアメリカに2ヶ月ほどいたので、出国前にある程度のミックスを中村さんと終えて、ツアー中に完成ミックスを受け取る予定になっていました。でも私がその場にいない状態でのミックスに難航して、結果的に遠隔でミックス作業を進める必要がでてきました。
さきほども言ったように、今回宅録的な方法アレンジを考えていった結果、実際のバンドで演奏するとなるとデモとは印象が変わって軽い音像になりました。その軽さを程よく厚くしていくための作業がミックスに求められている部分があり、過度に着色することなく、よいミックスにするにはどうしたらいいか中村さんと話し合いを進めていたんです。時差があるなかで、中村さんと電話をつなげた状態で十何時間も一緒にミックス作業を進めていくのは大変でした。滞在先でいろいろな環境を使ってミックスのチェックをしていたんですが、聴く環境や場所、デバイスによって聴こえ方が異なってしまって、どれを信用して中村さんにフィードバックをすればいいんだろうと、結構悩みながらの作業になりました。
──LAで一緒にマスタリングを手がけたジェイクの印象はどうですか? アナログっぽい質感でありながら、でも音がこもってるわけではなく、一つ一つの楽器や声の輪郭はパキッとシャープ、だけどなんとなく浮遊感もある……という独特な音作りだと感じました。それこそ、ジェイクがマスタリングを手がけたジョン・キャロル・カービィの作品の音像を彷彿とさせられもしましたが。
アナログ感のある質感は、レコーディングとミックスをしてくれた中村さんのアイデアが反映されているのではないかと思います。そのアナログ感は、さきほど言った軽さを程よく厚くしていくための手法でもあったと思うのですが、デモの段階では想定していなかった質感でしたし、少しぎゅっとしてコンパクトになったようも感じたので、作品の印象という点で結果的にどう転ぶかわからないなとは思っていました。でもそれが、ジェイクがマスタリングしたことによって広がっていって、縦にも横にも奥行きが出たと思いました。例えば先ほど名前をあげてくださったトッド・ラングレンの“A Dream Goes On Forever”の空間は、シンプルなんだけれどギミックによって奥行きが感じられていいなと思います。ジェイクの仕事によって、作品が開けた音像になったのは、私にとっていままで経験したマスタリングとは違った体験でした。
“A Dream Goes On Forever”収録、『Todd』
──室内的な響きがありつつも奥行きがある、70年代のAOR的な音像にも近いというか。それこそ、eharaさんのルーツや趣味嗜好をジェイクが敏感にキャッチしてくれたということなんですかね。
そういうものが好きだとか、そうして欲しいということは全く伝えていませんでしたし、他にも好きなジャンルはたくさんあるので、彼が何を思ってマスタリングをしてくれたのか、聞いてみないとわからないです。海外の方と自分の作品でご一緒するのははじめてのことだったので、どうなるんだろうという期待があって、当日はただただ楽しみに彼の背中を見ていました。私がミックスで出たアナログ感がどう転ぶか不安だったのは、ただの踏襲にしたくなかったからでもあります。ある特定の年代やアーティストの音像をそのまま目指すのではなく、今の音楽として作品を作りたいんです。今作は、ジェイクの仕事のおかげで音像が開けたのと同時に、今の音楽であるというよいバランスに、うまく着地できたんじゃないかと思います。
──この取材の後(取材日は8月下旬)、またすぐアメリカ・ツアーに行かれるということで。フェイ・ウェブスターに帯同してこれまで2回アメリカでツアーを回られていますけど、アメリカの観客のノリや反応は実際どんな感じでしたか? アメリカでツアーをしてみて思ったことや、海外進出について今感じていることもお訊きできたらと。
フェイのライヴは会場がとても大きくて、どこもかしこもほぼ完売の状態でした。私のことをフェイが見つけて連絡をくれた当時は彼女がSNSに私の曲載せてくれたりしていたので、長くフェイのファンをしている人は私のことを知ってくれていたんです。だから「やっと見られた!」と歓迎してくれている雰囲気もあったので、とにかく恵まれていて、楽しく演奏できたことが嬉しかったです。
ただ今回のツアーはどんな雰囲気になるのかは行ってみないと分からないです。前半の日程はSE SO NEONの前座としてソロで出るのですが、まずSE SO NEONのファンの人たちが私のことを知っているが不明ですし、ジャンルも違います。弾き語りなので本領を発揮できる体制でもない。その後控えているバンド編成のヘッドライン・ツアーでは、フェイの存在や、守ってくれるものもありません。チケットを買ってくれた人たちは少なからず私のことを好きでいてくれているとは思うんですけど、期待が高いかもしれないですし、実際に私たちの演奏を観てがっかりするかもしれない。だから、ここからがスタートだと思っています。いろいろな不安はありますが、たとえ結果が100じゃなかったとしても、0か1かだったら1を取りたいと思うので、私は行こうと決めました。本当にやってみないと分からないですね。

『All About McGuffin』の購入はこちら
ロスレス版はこちら
編集 : 高木理太
DISCOGRAPHY
Album、EP
Single
PROFILE
mei ehara
学生時代自主映画制作をはじめた流れで宅録に手を出す。複数の自主制作音源を制作した後は、インディレーベルKAKUBARHYTHMより1st album 『Sway』(2017)、2nd album 『Ampersands』(2020)を発表。2021年Faye Websterの2nd album “I Know I'm Funny Haha”にボーカル、作詞で参加。また、Cornelius「変わる消える(feat. mei ehara)」にもボーカルで参加している。細野晴臣氏のアルバム 『HOSONOHOUSE』のカバー作品 『HOSONO HOUSECOVERS』に参加。他にも参加楽曲多数。2024年9〜10月、2025年2月〜3月にかけてFaye websterの全米ツアー22ヶ所のサポートアクトを担当。2025年 FUJIROCK Festival に出演。
■Instagram : @mei_ehara
■X : @mei_ehara
■HP : http://www.eharamei.com/