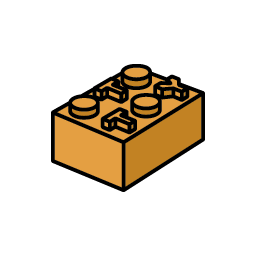原点回帰、3つのルール──mei ehara、5年ぶりのアルバム『All About McGuffin』に辿り着くまで

シンガー・ソングライター、mei eharaが5年ぶりとなるアルバム『All About McGuffin』を〈カクバリズム〉よりリリース。シングルのリリースを重ねつつ、フェイ・ウェブスターやCorneliusとの客演などを経て完成した今作。演奏は前作の録音も担当し、現在もライブのサポートとして脇を固める鳥居真道、浜公氣、Coff、沼澤成毅が参加。録音はファースト・アルバムでもタッグを組んだ中村督、マスタリングは〈Stones Throw〉関連作品を手がける、Jake Viatorが担当、ソングライティング、歌唱、アレンジのすべてに進化と洗練が宿る名盤が誕生した。コロナ禍を挟んでの5年という期間を経て、今作はどのように生まれたのか? 制作の過程を本人にじっくりと訊いた。(編集部)
自身3枚目、5年ぶりとなるアルバム『All About McGuffin』
ロスレス版はこちら
INTERVIEW : mei ehara
今作のリリースにあたって「ある時期から、普遍的で不器用な一人の人間として今作を素朴な作品にしたいと思いはじめました」とコメントを寄せていたmei ehara。その素朴という言葉とは裏腹に、今作にはこれまでになくリッチで濃密、コンパクトなのにどこまでも遠くまで連れていかれるような感覚を抱いた。けれどもそれでいて、限りなく風通しがいい。まるで「余計なものはすっかり手放しました」とでも言うように。今回本人に話を聞いてみると、その風通しの良さの正体とはつまり、高い評価を受けたセカンド・アルバム『Ampersands』(2020年)からの5年をかけ、自分自身にじっくり向き合ったが故に辿り着くことができた「成熟という名の正直さ」なのではないかと思えてくる。
「今持てるものを全て注ぎ込んで、これで第一章を終えるようなつもりで」と語り、音楽家として、ひとりの人としてのmei eharaをまるっと凝縮したような今作。ネオ・ソウルのようでもある。彼女の愛するビリー・ジョエルやトッド・ラングレンにも聴こえる。でも「そんな感じの音楽」として簡単に規定しようとすればたちまち手のひらをすり抜けていって、ただ手元に残るのは音楽を作ることがシンプルに楽しいという素朴な感覚だけ── そんなアルバムだ。本人は「ポップではないし、華やかでもない」と語るけれど、でもその感覚こそが紛れもなく、「ポップ」なんじゃないだろうか。
インタヴュー&文 : 井草七海
写真 : Naoki Usuda
常に自分が作るものに対して新鮮な気持ちになりたい
──この『All About McGuffin』は、これまでになくサウンドにふくよかな奥行きを感じる作品になっている一方で、リリースの告知にあたってのeharaさんのコメントには「素朴なものを作りました」という言葉があって。今回はその辺りのお話を掘り下げていけたらと思います。そもそも前作『Ampersands』はちょうどコロナ禍に入ったばかりのタイミングでのリリースだったので、5年ぶりの今作に至るまでがすっぽりコロナ禍の期間とほぼ被る訳ですよね。
そうですね。リリースまでに5年という長い時間がかかってしまった理由は、コロナ禍の影響が1番大きかったと思います。セカンド・アルバム『Ampersands』が出た後は、レコ発ツアーができなかったり、そもそも音源を購入できるCDショップ、レコードショップなどのお店が開いてない、という状況だったので、精神的にも落ち込んでいました。一方で、自分が抱えてる個人的な問題に目を向けて解決しようとする期間にもなって、そうしているうちに時間が経っていった部分もありました。解決していくこと自体はいいことだったと思いますが。
いざ「サード・アルバムを制作していこう」となったら、周りの人たちから「サード・アルバムはアーティストのキャリアにとって重要だ」と言われることがあり、自分でもそうなのだろうと思って張り切っていたらプレッシャーになりました。それでさらに時間がかかったりなどするうちに、結果的にリリースまでに5年かかりました。今作は数年の間にシングルでリリースした曲を軸に、自分の中でのテーマを決め、新しい曲を制作、選曲してアルバムにしていきます。
──今作には全体を通してどこか一貫したトーンがあると感じました。バンドメンバーは前作から変わらずですが、メンバーが各々の役割を果たすようにしてミニマルでカチッとアレンジされた印象のあった前作に対して、今作はそれぞれの楽器が絡み合っていくようなアレンジになり、それゆえにギュッと濃縮還元されたようになったというか。
私個人としては真逆の印象です。前作『Ampersands』は、ファースト『Sway』のリリース後にライブ活動をしていたスリーピースを経て、編成を組み直して集まった今の5人で制作しました。集まってすぐに制作がはじまったので、それぞれのパーソナリティや好みも十分に分かっていなかったんです。だから制作していくと同時にバンド内で自己紹介し合うような時間にもなりました。私はデモを作りながら自分で考えたアレンジを守ると同時に、メンバーそれぞれの持ち味を確認して作品に活かしたいと思っていたので、その結果としてメンバーの演奏が伸び伸びとしていて自由で少しポップな印象になったと思います。
一方今作に関しては、デモの段階で私ひとりでアレンジをほとんど完成させた状態でメンバーに共有、演奏してもらっています。なぜそうしたかと言うと、前作リリース以降メンバーの生活環境が変わったり、それぞれが他の活動で忙しかったという理由に加え、私がアルバム制作におけるテーマの選定や自分はどうしたいのか具体的にすることに難航していたので、より楽曲と向き合う必要があったということがあります。アレンジを自分ひとりで詰めていくと、どんどん原点回帰するようなところもあり、音の重なりとしてはここまで以上にシンプルでミニマルなものになったのではないかと思います。ひとりで制作したことによって、宅録的な感覚が盛り込まれていることも、音の重なりが前作と違う1番の理由かもしれません。「ギュッと濃縮されている」と表現してくださったのは、そのことが大きいのではないかと私は思います。

──アレンジ自体は、宅録的に多重にレイヤードされたことでむしろ密に作り込まれたがゆえの華や濃さがあると思うんですよ。ただ一方で、メロディーや歌、言葉の面で、eharaさん自身のスッと一本芯の通った存在が、曲の真ん中にはっきりと感じられもする。そういうところがeharaさんの言う「素朴さ」にもつながってくるのかなと。
そのコメントを書いたのにはいろいろな意味があるのですが、そのうち一つあげるとすれば、「今作は前作に比べると華やかではない」と思ったということがあります。宅録的にデモを作っていったと言いましたが、私の制作環境はシンプルで必要最低限の機材しかないので、DAWのプラグイン音源を使うことが多いです。限り無くリアルの楽器に近い音が鳴りますが、そういう環境で作ったデモを実際のバンドで演奏するとなると印象が落ち着いて聴こえたりするし、完全に再現するのは難しいです。実際、バンドメンバーにもデモを忠実に再現するように頼むと、その落ち着きに対して少し不安がっている気がしましたし、そういう意見もありました。なので私も方向性を考え直すべきか悩んだこともありました。ただある段階から「それでもいいから突き通したい」というモードになっていたので、結果、今作は私の嗜好を反映したような作品になり、そういう意味でも「素朴」という言葉を使ったわけです。
──個人的にeharaさんの音楽には元々メロウな印象は持っていたんですが、今作はアーバン・コンテンポラリーや、ブルーアイド・ソウルやAOR、平たく言ってしまうと白人がやるような70年代のソフトなタッチのソウルの影響をより一層色濃く感じ取れました。スティーリー・ダンなんかも思わせる瞬間もありますし。もともとeharaさん自身、ビリー・ジョエルやトッド・ラングレンが好きだと過去のインタビューでも語っていますが、今言っていたような自身の「嗜好」としての音楽を今作では強く意識した側面もあったんでしょうか?
うーん、確かに好きではありますが、そこに寄せていこうと思いながら作ったわけではないです。ただそう感じてくださったなら、その片鱗が滲み出てしまったのかもしれませんね。私は普段から「あの好きな曲をモデルに曲を作ろう、アレンジを考えよう」という曲作りをすることがないんです。なぜなら常に自分が作るものに対して新鮮な気持ちになりたいからです。作っていくうちに自分の好きな曲や培ってきたもののが影響が滲み出てしまうことは仕方がないことですし、それがなければ音楽を作れていないかもしれないし、さまざまな影響からキメラ的なものが生まれるのはよいことだと思いますが。意識的に誰か好きなアーティストの曲に寄せていくのはあんまり楽しくないんです。