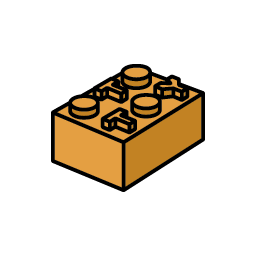新たな音楽の遊び場を求めて──堂々の1stアルバム、ハイレゾ配信! lovefilm、そのドラマティックな始まり

モデル・女優としてキャリアを積む江夏詩織をフロントに、現在活動休止中であるthe telephonesの石毛輝と岡本伸明、高橋昌志(The Pat / PINK POLITICS)の4人による新たなバンド、lovefilm。90年代のUSオルタナインディーのローファイなフィーリングを下地にしたサウンドに、パンク・ロック由来の直線的なリズムとポップなメロディ。メイン・ソングライターである石毛が紡ぐ"日本語"のリリックを、バンド経験0だったという江夏が初々しくもその感情の機微を表現する。そこで生まれたのは胸をさらうような"終わりなき青春の響き"。
イノセントな輝きが詰まった堂々の1stアルバムをハイレゾ配信。メンバー4人揃ってのインタヴューとお届けします。
lovefilm / lovefilm
【Track List】
01. Alien
02. Don't Cry
03. Kiss
04. Vomit
05. BIG LOVE
06. Holy Wonder
07. Honey Bee
08. Goodbye,Goodnight
09. Our Dawn
10. Hours
【配信形態 / 価格】
24bit/96kHz(WAV / ALAC / FLAC) / AAC
単曲 300円(税込) / アルバム 2,800円(税込)
lovefilm / Kisslovefilm / Kiss
INTERVIEW : lovefilm

現在活動休止中のthe telephonesの石毛輝と岡本伸明が女性ヴォーカルを迎えて新バンドを結成したと聞き、3月に新代田FEVERで行われた初ライヴを観に行ったときの印象は、「純粋に音楽を楽しもうとしてるんだな」ということだった。もちろん、これはlovefilmというバンドの核でもあるし、「純粋に楽しむ」ということが「真剣に向き合う」ということとほぼ同義であることを説明すれば、より本質に近づくと思う。しかし、裏を返せば、「シーン」ということに対しては、あまり意識をしないようにしているのではないかと思った。何せthe telephonesというバンドは国内と国外、オーバーグラウンドとアンダーグラウンド、フェスとライヴハウスを何とか繋げるべく10年間駆けずり回り、だからこそ同年代のバンドよりも早く消耗してしまったバンドだからだ(と、僕は思っている)。しかし、彼らは何もあきらめてはいなかった。だからこそ、彼らは洋服ブランド「sise」の衣装に身を包み、今度はカルチャー全般を繋げて、新たな遊び場を作ろうとしている。もちろん、かつてに比べれば、肩の力は抜けているだろう。しかし、その生真面目さは何ら変わることなく、だから僕は彼らのことが大好きだ。そして、このバンドに加わったのが、シンデレラガールの江夏詩織と高橋昌志。ファースト・アルバム『lovefilm』を発表するまでのこの1年弱の間には、すでに映画のようにドラマティックなストーリーが綴られていた。
インタヴュー&文 : 金子厚武
写真 : 作永裕範
当時よく話してたのが、「本質忘れてねえ?」ってことだったんですよね
──lovefilmの構想はどのようにスタートしているのでしょうか?
石毛輝(以下、石毛) : the telephonesが活動休止することになって、次をソロにしようかバンドにしようかいろいろ考えたんですけど、僕のソロはthe telephonesと並行してやるのがおもしろいと思ってたんで、じゃあ、新しくバンドをやろうと思ったんです。そのときに、ソロの次のアイデアがもともとあって、それは女の子ヴォーカルをフィーチャリングしたり、いろんな人に歌ってもらうっていうテーマだったから、じゃあ、それを新しいバンドでやろうと。で、ノブとは一時期週5くらいで会ってて、siseのデザイナーとか、音楽以外の分野の人と飲みながら、「いろんなカルチャーを巻き込んでおもしろいことできたらいいね」ってよく話してたんです。だから、ノブをバンドに誘った記憶はないんですけど、「やるよね」って感じでしたね。
──ノブくんはthe telephonesの活動休止以降についてどう考えていたんですか?
岡本伸明(以下、岡本) : そもそもthe telephonesが止まるってなる前から、石毛とはさっき言ったような話をしてて、the telephonesをやりながらでも、何か新しいことしたいなっていうのは漠然とあったんです。lovefilmの原型になってる曲も何曲かは聴かせてもらってたし、すでにビジョンはあったんですよね。
──「何か新しいことをしたい」と思っていたのはなぜなのでしょうか?
岡本 : 何て言うか、the telephonesでいろんな経験をする中で、シーンっていうか、今の音楽とかに対して、「うーん」って疑問に思うことがたくさんあって。
石毛 : 当時よく話してたのが、「本質忘れてねえ?」ってことだったんですよね。フェスとかにしても、最初の頃はもうちょっと貴重な祭典で音楽的でもあったと思うんですよね。あえて悪く言うと今は毎年の年間行事になってしまって、「フェスティバルって何だっけ?」とか。別に今のフェスが全部悪いわけじゃないけど、ポピュラリティを得てしまったから、敷居もすごく下がって、「夏はフェスに出るのが当たり前」みたいな感じになっちゃってると思うんです。それってサラリーマンみたいでなんかつまらなくて。「フェスでうける曲」みたいな曲も書かなきゃいけない気もしてたし。まぁでもそういうのも別に嫌いじゃないから好きでやってたけどね。あくまで。
岡本 : 周りがそうなっていった感じもちょっとあって、前はもうちょっとガツッて感じがあったんですよ。
石毛 : 自分たちが先輩から受け継いだ世界とは、ちょっと変わってきてるなって。だから、別に何かを悪いと言いたいわけじゃなくて、それはそれであっていいんだけど、「自分たちが楽しめる別の遊び場をもう1回作りたいね」って話をよくしてたんです。そのためにはバンドだけじゃなくて、洋服、映像、写真とか、いろんな人を巻き込んでいけば、これまでとは違う遊び場ができるんじゃないかなって。
──フェスがカルチャーとして定着してマスになったのは決して悪いことではないけど、それによって多様性が失われた感じがする。そこに対して、選択肢を提示するってこと?
石毛 : うん、そういうことですね。あと今ってフェスをひとつの基準としてバンドのことを考えてしまってるから、そうじゃなくて、もっと音楽を追求して、音楽がいいからフェスに出るっていう、そういう純粋なものにできればなって。ロックって1個「こういうもの」っていうのが完成したら、「これはやっぱちげえだろ」っていうのが出てくる。その繰り返しだから、そういうカウンターになりたい気持ちもありますね。

──では、昌志くんはどんなつながりだったんですか?
石毛 : 昌志は下北沢のTHREEで働いてて、Teen RunningsとかThe Patでドラムを叩いてるのは知ってたから、あるとき酔っ払って、「スタジオ入ろうよ」って誘って、ノブと3人で入ったら、その感じがよかったんですよね。
──結構前から知り合いだったんですか?
石毛 : いや、共通の友達はいっぱいいたんですけど、ちゃんと会って話すようになったのはここ1~2年かな。
岡本 : Teen Runningsがすごく好きで、いいなって思ってたんです。
──昌志くんは誘われてどう思いました?
高橋昌志(以下、高橋) : 正直、最初は仲良くなる人じゃないと思ってました。結局、それって単なる色眼鏡だったんですけどね。でも、片や人気バンドで、「フェスと言えばthe telephones」って感じだったし、僕は下北の地下で働いてて、「住む世界が違う」とまでは言わないけど、でも「違う人」みたいな感じで。だから、その人たちから誘われたのは最初は驚きでしたけど、単純に嬉しかったです。求められるっていうことは。
──実際に飲んで話して、一緒にスタジオに入ってみたら、「全然変わんねえじゃん」って感じだった?
高橋 : そうっすね。自分の色眼鏡を反省しました。決めつけってホントよくないなって。最近ホント毎日自分に言い聞かせてます(笑)。
──最初に石毛くんとノブくんが話してくれたフェスのことって、普段昌志くんがいるライヴハウス界隈からはどんな風に見えてました?
高橋 : やっぱり、カウンターカルチャーってずっとあると思うし、何に対しても絶対敵っているじゃないですか? だからこそ、自分らのことを楽しくやれるというか、それが日々の糧になったりもするし。だから、僕はそっちには行けない人だし、行かない人だと思ってて、フェスに出てるような人と会う機会もほとんどなかったから、正直「僕らは僕らでやってます」みたいな感じでした。なので、(石毛と岡本に対して)こんな男らしい人だと思ってなかったし、器でかいなって。
石毛 : 俺ももともとライブハウスの店員だし、現場から出てきた人間だから、根は一緒じゃんって話をして、それで仲良くなった記憶がありますね。
「何気にしてるの? まだ二十歳でしょ? なんでおじさんたちのこと気にしてるの?」って
──そこに詩織さんはどうやって加わったのでしょうか?
江夏詩織(以下、江夏) : 共通の知り合いから突然連絡が来て、「the telephonesの石毛さんとノブさんから話がある」って言われて、「何だろう?」と思いつつ、もちろんthe telephonesのことは知ってたから、ワクワクしながら会ったら、単刀直入に「バンドに興味ありますか?」って聞かれて。そこで「こんな音楽をやりたい」って話だったり、さっきのカルチャーを含めた活動の話を聞いて、私もまったく同じようなことを思ってたんです。私は女優やモデルの仕事をしてるから、自分がバンドをやるつもりは全然なかったんですけど、「こんなバンドがいたらいいな」っていうのはすごく考えてて、それとドンピシャのことを言われたから、「わかります!」って、全同調みたいな(笑)。そうしたら、「それを私がやるの?」って話で、驚いたんですけど、でも嬉しかったです。

石毛 : バンド経験がない方がいいと思ってたんですよね。スリッツとか、衝動だけ爆発させるみたいな。俺とノブは10年間the telephonesをやってたから、新しい刺激を欲してて、だから、メンバーのことも「感性だけで決めよう」って思ってて。それで、しっし(江夏)のインスタを見たら、すごくいい写真を撮ってたんですよ。しかも、siseと一緒にやりたいと思ってたから、服を着て絵になる人がいい。それでなおかつバンドが好きってなると、結構条件厳しいんですよね。なので、「そんな子いないよなあ」と思いつつ、ダメ元でしっしに会ってみたら、お互い全同調…… って言い方悪いな(笑)。
──意気投合ね(笑)。
石毛 : それです(笑)。で、最初は音楽的なことはまったくわからなかったんですけど、歌声を聴かせてもらったらいい声で、初めて4人でスタジオに入ったときに、男3人とも「これだ!」って表情になって(笑)。だから、難航すると思った紅一点の女性メンバー探しが、まさかの一人目で決まるっていう、運命的なものを感じましたね。
──その最初のスタジオで、メンバーになることが決まったわけですか?
石毛 : 「一緒にやろう」っていつ言われたか覚えてる?
江夏 : それは結構やんわりだったんですよね(笑)。
岡本 : 石毛っぽいなあ(笑)。
江夏 : そこまでのストーリーがあまりにドラマみたいじゃないですか? ただ、そこに一個欠けてたのが「よし、バンド組もう」みたいなことで。でも、そのおかげで変に構えることなく、ただ音楽を楽しむために何回かスタジオに入れて、「じゃあ、バンド名決めますか」みたいな、ゆるく組んだ感じです。
──モデルや女優業と並行して活動することに関して、迷いはありませんでしたか?
石毛 : 1回「私やっぱりできません」ってなったよね。スケジュールのことをすごい気にしてくれて、「私じゃない方が」って。みんなで集まってたときに、そういう話になって、そのときうちの事務所の社長とかもいたんですけど、みんなあきらめモードで。
江夏 : サヨナラの会みたいになってましたよね。
石毛 : トランプとか始めてね(笑)。
江夏 : 気を紛らわせるために(笑)。もともとは「これからのスケジュールを決めよう」っていう前向きな話をするために集まったんですけど、「やっぱり、できないかも」って話になって、途中からトランプとかして……。
石毛 : そこに現れたメシアが、POLYSICSのフミさんときのこ帝国のサトちゃん。
江夏 : 「すごくやりたいんですけど、私のスケジュールに合わせて活動するのは申し訳ないから、私が辞退した方がみんなのためだと思う」みたいな話をおふたりにしたら、「何気にしてるの? まだ二十歳でしょ? なんでおじさんたちのこと気にしてるの?」って。
石毛 : ハハハ、言いそう(笑)。
江夏 : 「せっかくのチャンスなんだから、大人のことなんて気にせず、やりたいことやりなよ。何なら振り回すぐらいでいいんだから」って。しかも、私おふたりにはその場で初めてお会いしたのに、状況を聞いて、事務所の社長の遠藤さんを説得しようとしてくれたんですよ。私が続けられるようにするには、どうスケジュールを組めばいいかとか、そういう話を真剣に遠藤さんと話してくれて、私はそれに心を打たれてしまって。
石毛 : その隣で、何もできないおじさんたち(笑)。
──めちゃめちゃいい話(笑)。
江夏 : それで私泣きながら「やっぱり続けたいです!」って言って、その後私の事務所の人に、「どうしてもバンドをやりたいから、スケジュール1年だけください」って言って、説得して、それでオッケーをもらえたんです。だから、「やれることになりました!」って報告して、みんなで「よかったー!」ってなったときに結成したみたいな気持ちですね。
今回俺にとって人生で初めてギターソロがないアルバムなんですよ。曲が必要としてなかったから、弾かなかったんです。
──lovefilmの音楽的な方向性はどんなアイデアからスタートしているのでしょうか?
石毛 : 僕のイメージでは、DIIVとかWavvesとか、Best Coastとか、あの辺のアメリカのインディー・バンドが醸し出す90’sのリバイバル感って、まだオーバーグラウンドにはあんまり出てきてない気がしたので、これはチャンスかなって。シューゲまで行かないけど、ちょっと荒々しい、勢いのあるオルタナっていうテーマが大本で、ファーストに関してはそういうシンプルなロックにしようと思ってました。やっぱり、カウンターカルチャー好きなんで、「今こういうバンドいないよね」っていうのが好きなんですよ。今オーバーグラウンドで8ビートってあまり見かけなくて、ロック的解釈の4つ打ちがまだ多いから…… 先陣切ってやってましたけど(笑)。
──当時は4つ打ちの方がカウンターだったってことだよね。
石毛 : 最近は音楽にゴチャゴチャ理由をつけ過ぎな気がして、ロックはシンプルでいいと思ったんですよ。今回クリックは使ってなくて、ベーシックをテープでレコーディングしてるんで、いい感じによれてるし、テープコンプもかかってるし、それは狙ったところです。まあ、もしこの4人のグルーヴがもっときっちりしてたら、きっちり録ったと思うんですよ。でも、今この4人で出すべき音は衝動だと思ったので、そういう作品にしたっていう方が強いかもしれない。
──昌志くんはlovefilmの音楽性をどのように見ていますか?
高橋 : オーバーグラウンドとアンダーグラウンドを行ったり来たりできるバンドだなって。「俺はインディだよ」みたいな人たちのところにも行けるし、メインストリームでやっている人たちのところにも行けるし、それって大事だと思うんですよね。偏っちゃうのはよくないから、どっちも行けていいなって思います。
石毛 : まあ、根がそういうタイプというか、欲張りなので、どっちもある方がいいし、でもオーバーグラウンドとかアンダーグラウンドって、やってる方が決めることじゃなくて、リスナーが決めることだと思うから、どっちでもいいんです。僕は両方好きだし、シンプルにかっこよければいいと思うんですけど、さっきも言ったように、最近はそこに理屈をつけ過ぎで、シンプルにかっこいいものが評価されるのが当然だと思うんですよ。the telephonesをやってたときは、オーバーグラウンドとアンダーグラウンドっていう考え方をしてたけど、もはやそれはないなって思います。
──さっき「4人のグルーヴ」って話がありましたが、ノブくんがベースっていうのは最初から決まってたんですか?
石毛 : 3人でスタジオに入ったときに、消去法でベースだったんですけど(笑)、でもthe telephonesをやる前のバンドでもともとベースを弾いてたんで、実は12年ぶりに戻ってきたっていう。
岡本 : the telephonesで鍵盤をやった後だから、楽器に対する考え方が全然違うんです。
石毛 : リズムの捉え方がわかるようになったからか、上手くなってたんですよ。lovefilmのPAはthe telephonesの時にもやってもらってた方なんですけど、この前ライヴの感想聞いたら、「ベースはよかったけど、シンセが中学生」って言われて、武道館とかさいたまスーパーアリーナやってんのに中学生って奇跡だなって(笑)。だから、一周してベースが天職なんじゃないかって思うんですよね。

──ノブくんはlovefilmでベースを弾くにあたって、どんなことを意識していますか?
岡本 : 僕はもともと海外のベーシストが好きで、日本のベーシストよりもメロディーを大切にしてるなって思うんで、僕もそれを心がけて、基本シンプルに弾こうと。
石毛 : 今回は曲自体シンプルだし、ベースに守ってもらうというか、昔のパワーポップ、WeezerとかFuntains Of Wayneとか、ああいう感覚でやってもらいました。いい意味での「何もしなさ」って、このアルバムのいいところだと思うんですよ。単純に、歌とビートで疾走感が味わえる。他に変な色が入っちゃうと、そこに耳が行っちゃうけど、最後までバンドとして聴けるから、そこはすごくいいと思う。
岡本 : 自分のことをベーシストとは思いたくないっていうか、固まりたくないんで、開いてたいんですよね。
石毛 : そう、みんなにコンポーザーみたいな感覚を持ってほしい。
──「楽器を弾く」じゃなくて「曲を弾く」みたいな?
石毛 : そうそう、そこはこっそり目指してて…… って、今言っちゃいましたけど(笑)、その方が曲が生きるし、そういうのが好きなんです。だから、今回俺にとって人生で初めてギターソロがないアルバムなんですよ。曲が必要としてなかったから、弾かなかったんです。ギタリストとしてのエゴはなく、バンドとしてすごくいいなって、そういうアルバムだと思います。
──「フェスで盛り上がる」みたいな、何かの目的が先にあって作るんじゃなくて、まずはとにかく「いい作品を作る」っていう目的だけがあって、いい作品さえ作れば広がるはずだっていう自信がある。だからこそのシンプルさでもあるというか。
石毛 : そうだと思います。あと、ライヴ一本だけやってすぐレコーディングに入ったから、お客さんの顔を想像しなくてもよかったっていうか、自分たち4人のことだけ考えて作れたんですよね。そういう意味でも、貴重なファーストだと思います。もうちょっとライブをやれば、もっといろいろ考えるようになるかもしれないけど、今回はホントに4人だけのことを考えて作った、ピュアなアルバムだと思いますね。
最初に話をして、「この子は歌う資格がある」って思ったんです
──詩織さんにとっては、歌もギターも本格的にやるのは初めてだったわけですよね?
江夏 : 一応ギターは5年くらいやってたんですけど、ホントに趣味レベルで、誰に聴かせるでもなく家でポロンと弾くレベルだったし、歌はカラオケに行くぐらいだったから、ホントに初めてで、弾きながら歌うことも最初はすごく苦戦しました。
石毛 : こういう話を聞くのが嬉しいんですよ。「そりゃそうだ!」って(笑)。
江夏 : みんなバンド経験者なので、最初は焦って、「私だけできない」みたいな感じだったんですけど、今みたいにそれを楽しんでくれるから、私はすごくやりやすくて、ありがたい環境でした。
石毛 : それを承知で誘ってるしね。エフェクターのつなぎ方もわからないから、教えてたら、奥の方から「俺もわかんないんだけど」って(笑)。
岡本 : ハハハ(笑)。
石毛 : ホント最近ですよ、ちゃんと自分でセッティングできるようになったの。途中でしっしに追い抜かれてましたもん。
岡本 : 穴が二つあるのがうざいんですよ。どっちかにしてくれって感じなんですよね。
石毛 : 何言ってんの(笑)? しっしの面倒見るのはいいんですよ、楽器初心者なんで。何で俺がベースの面倒も見なきゃいけないんだっていう(笑)。the telephonesでもシンセにエフェクターつないでましたけど、それはローディーがつないでくれてたから、過保護ってよくないなって(笑)。

──lovefilmの青春感を担ってるのは詩織さんだけじゃなくて、ノブくんの存在も大きいんでしょうね(笑)。詩織さんはlovefilmの持っている世界観、「青春」とか「少年性」みたいなイメージについてはどう感じていますか?
江夏 : 最初に石毛さんから曲のデモをもらって、最初の印象は青春っていうか、色で言うと「青」って感じだったんです。ただ、それを目指して作ったというよりは、勝手に印象がついてきたっていうイメージで、何かを狙ってる感じは全然ないんです。
石毛 : そう、最初から青春性を狙ってたわけではないんですけど、4人でスタジオで話した会話で覚えてるのは、「ポカリスウェット飲みたくなるよね」ってことで、色が青っていうのもそうだし、その感じを共有してたから、こういう作品になったのかなって。
──the telephonesを休止して作った新しいバンドの一作目だし、詩織さんにとっては人生初のアルバムで、フレッシュな作品になるのはある意味当然だと思うんですよね。ただ、このアルバムはそれだけじゃなくて、後半の曲からは現実の苦みとかも感じられて、そのグラデーションが作品をより魅力的なものにしてると思いました。
江夏 : この4人は少年っぽいところもあるし、ちょっと暗い面もあるので、みんなの人間性が集まってできたアルバムだと思います。
石毛 : そこがあるから、後半の曲みたいなのもできるんだと思う。これがただの青春バンドだったら、そういう曲を作る必要はないし、酸いも甘いも…… って言うと、ホントおっさんみたいだけど(笑)、僕とノブは単純にしっしよりも長く生きてるから、その人生経験が出てると思うし、逆に言うと、そういう曲を歌いこなせるしっしはすごいなって。「Hours」とかって、自分が二十歳だったら絶対表現できないと思うから、そこはしっしのポテンシャルを実感したし、やっぱり、ちゃんと陰と陽のどっちもがあるのがいいと思うんですよ。
──詩織さんは今回のアルバムの中でどの曲が1番想い入れが強いですか?
江夏 : 今日もスタジオで自分で演奏しながら泣きそうになってしまった「Goodbye,Goodnight」ですね(笑)。明るさの中にちょっと切なさがある気がして、そこがすごく好きなんです。「Alien」とか「Vomit」とか、ハチャメチャに明るい曲もあるけど、「Goodbye,Goodnight」は明るいけど切なくて、なぜか泣きたくなるんです。最初に話した「やっぱりバンドできないかも」って思った時期に、それまでやった曲を聴き直してて、涙が出たのが「Goodbye,Goodnight」で。
石毛 : 泣きながら外を走ったって言ってたもんね(笑)。
──さっき石毛くんも言ったように、やっぱり陰と陽とどっちもあるからこそ泣けるんでしょうね。
江夏 : そうだと思います。このアルバムを聴いてくれる人たちも、みんなそれぞれ抱えてるものがあると思うんですけど、そこに響いて、心が動いたらいいなって。私はこの曲に動かされたので。
岡本 : 素晴らしい!
石毛 : 身が引き締まるね。何かわかんないけど泣ける曲って、僕ももともと好きなんです。
──詩織さんが「みんなの人間性が集まってできたアルバム」って言ってたけど、やっぱりそういうパーソナルな部分を共有できたことはバンドにとってすごく大きいですよね。
石毛 : 偉そうな言い方になっちゃいますけど、最初に話をして、「この子は歌う資格がある」って思ったんです。変な意味じゃなく、ちゃんと闇を抱えてるなって思って、やっぱり闇を知らないと光もわからないと思うんですよね。借り物の闇っていうか、「私暗いんです」みたいなのって簡単だけど、しっしは本物だなって。ジョン・フルシアンテも言ってたらしいじゃないですか? アンソニーが心の闇を直そうとしたときに、「アンソニー、心の闇があるからいいんだよ。それがクリエイティヴなものを作るんだ」って。あれを最近知って、調子に乗って言うと俺とジョンは考え方近いなって勝手に思って(笑)。しっしはそういう人だってちゃんとわかって、そうじゃなかったら、信頼して曲を預けることはできなかったですね。
LIVE INFORMATION
AWESOME LOVE TAPES
2016年8月10日(水)@渋谷WWW
出演 : Awesome City Club / lovefilm / LUCKY TAPES
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016
2016年8月14日(日)@茨城県 国営ひたち海浜公園
UKFC on the Road 2016
2016年8月16日(火)@新木場STUDIO COAST
MONSTER baSH 2016
2016年8月21日(日)@香川県 国営讃岐まんのう公園
SWEET LOVE SHOWER 2016
2016年8月27日(土)@山梨県 山中湖交流プラザ きらら
RUSH BALL 2016
2016年8月28日(日)@大阪府 泉大津フェニックス
BAYCAMP 2016
2016年9月3日(土)@神奈川県 川崎市東扇島東公園 特設会場
New Audiogram ver.10 -New Audiogram 10th Anniversary-
2016年9月10日(土)@渋谷TSUTAYA O-EAST、O-WEST、O-nest、O-Crest
BIGMAMAnniversary 2016~2017 MAMonthly Special「Autumnend Magic Tour!!
2016年11月4日(金)@仙台CLUB JUNK BOX 出演 : BIGMAMA / lovefilm
lovefilm 1st tour "livefilm”
2016年11月18日(金)@愛知ell. SIZE
2016年11月19日(土)@大阪Shangri-La
2016年11月23日(水・祝)@代官山UNIT
PROFILE
lovefilm
現在活動休止中のthe telephonesの石毛輝・岡本伸明を中心に江夏詩織・高橋昌志の4人で結成。2016年3月14日に初ライヴ「preview of film」を開催。8月3日に1stアルバム『lovefilm』をリリース。