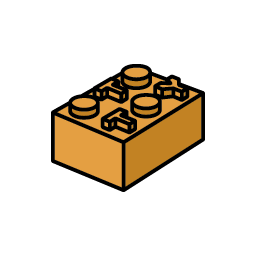口コミで驚異的な売上を記録したmatryoshka。2nd albumを配信開始!
前作『zatracenie』から5年ぶりとなるアルバム『Laideronnette』をリリースしたmatryoshka(マトリョーシカ)。前作も様々な要素が有機的に絡みあい唯一無二の世界観を築きあげていたが、『Laideronnette』ではそれがさらに深みを増し、神々しい輝きを放つ“聖”までをも身にまとうに至っている。煉獄を意味するパーガトリー(Purgatory)やオブリヴィオン(Oblivion)といった、聖書などの宗教本でよく見かける言葉が頻出するのも面白い。話を聞いた限りでは、そこまで宗教的世界観に興味はないようで、曲名も言葉の響きで決めたそうだけど、その結果が『Laideronnette』だとすれば、それをもたらした感性そのものがとても興味深いものとなる。アニメーション作家の銀木沙織が制作した「Monotonous Purgatory」のMVが端的にmatryoshkaの持つ感性を表現していると思うが、今回はメンバーであるSenの言葉によってその感性の正体をあぶりだしてみようと試みた。
インタビュー & 文 : 近藤真弥
綿密に配置されたノイズが響く! 全10曲を高音質で!
matryoshka / Laideronnette
【配信形態】
HQD(24bit/48kHz)、MP3
【配信価格】
単曲 150円 / アルバム 1,500円(MP3とHQD共に)
2007年にリリースされた1stアルバム『zatracenie』は、まだ無名ながら口コミで広がり驚異的な売上を記録。5年ぶりとなる待望の2ndアルバム『Laideronnette』は荘厳なストリングスと柔らかなピアノ、無機質ながらも有機的なリズムが鳴り、憂いを帯びた唄、綿密に配置されたノイズが響く。
NTERVIEW : Sen(matryoshka)
——アルバム・タイトルの『Laideronnette』ですが、これはラヴェルの組曲マ・メール・ロワ「パゴダの女王レドロネット」からとったそうなんですね。ラヴェルはお好きなんですか。
ラヴェルは好きですが、その組曲と本作は特に関係なくて、たまたま名前の響きが気に入ったという感じですかね。
——クラシックはよく聴かれるんですか?
けっこう聴きます。気に入ったのを何回も聴いています。
——ラヴェルはドビュッシーなどと一緒に“印象派”として語られることが多いですが、ドビュッシーとかも?
ドビュッシーは好きですね。
——最近ドビュッシーが好きって言う人が多いですよね。
僕もそういう“にわか”だと思います(笑)。
——他にはどういう音楽を聴かれるんですか。
正直、ふだんはあまり音楽を聴かないんですよ。レーベルメイトのアーティストの作品は、レーベルからいただいて聴いたりはしますけど、他に聴くものといえば、古いやつがほとんどですね。
——昔のですか?
昔といっても、90年代のやつです。レディオヘッドの『OK Computer』とか。あとはビョークの『Homogenic』、マイ・ブラッディー・ヴァレンタインもよく聴きます。
——matryoshkaはよくポスト・ロックと言われたりもしますが、いまの話を聞いた限りでは、ポスト・ロックは聴かないほうなんですね。
あんまり聴かないですね。
——ポスト・ロックやポスト・クラシカルと呼ばれることに対してはどう思います?
どうですかね…。あんまりピンとこないです。

——Senさんなりに、「こういう音楽をやっている」と具体的に説明できる言葉はありますか。
そういうのがないんですよね。だから、エレクトロニカって言われても、ポスト・ロックって言われても、受けいれてもらえない感じはあります。「なんかお前は違うだろ」って言われてるような気がします。
——その口ぶりから察するに、周りの評価はあまり気にしないほうなんですか。
まあ、気になりますけどね。
——これまで話を聞いてきたアーティストさんのなかには、メディアのレビューをすごく気にしたりする人もけっこういたので訊いてみました。
気になるっちゃ気になる、という程度ですかね。
——自分の作品が載ってる音楽雑誌とか読むんですか。
読むのが怖い部分もあります。だから、良い意見だけを斜め読みしていく感じです(笑)。
結論にこだわるほうではない
——では、『Laideronnette』についていくつか訊かせてください。タイトルは響きが気に入ったから名付けたとおっしゃいましたが、曲名は聖書によく出てくる言葉が多く使われています。これには明確な理由はあるんですか。
言葉遊び的なものはあるかもしれないですね。直接歌詞の内容とあまり関係なくても、名前の響きが面白いとそのままタイトルにしちゃうこともあります
——特に宗教や聖的なものに興味があるというわけでもない。
そうですね。
——こういった言葉はどこから仕入れたりするんですか。
日々の暮らしのなかで、気に入った単語とかがあったらメモってます。
——でも、日々の暮らしのなかでよく見かけるような言葉ではない気もします(笑)。本はよく読まれたりしますか?
本はよく読みますね。マンガも好きなんで、面白いとされているマンガは結構読んでますね。
——これは『Laideronnette』を聴いて思った僕の直感なんですけど、世界観がループのようになっている点で、ジョジョの奇妙な冒険の第6部『ストーンオーシャン』ぽいと感じました。
ジョジョは全部そろえて持ってます。
——ジョジョの第6部は東洋思想の特徴である“循環”を思わせる要素もありますが、『Laideronnette』もそれに近いもの、ひとつの輪みたいなのが聞き終わったあとに漠然としたイメージで湧いてきたんです。
いまのところ、『Laideronnette』からの曲でMVが2つあるんですが、その2つとも始まりと終わりがループしているような映像なんです。特に意識したわけじゃないんですけど、聴いた人にそういう印象を持たれることは多いですね。たぶん、問題を提示するだけして、ハッキリと解決しないで終わってるからかもしれません。
——言いきってないというか、matryoshkaの音楽って、聴き手の想像力が入りこむ余白が多いですよね。そういうのは意識してるんですか。
あんまり結論にこだわるほうではないですね。
周りの事件や出来事から影響されることはないです
——前作は解放的なエネルギーが強くて、エイフェックス・ツインに通じる強いビートが前面に出ていましたが、『Laideronnette』の世界観は、ひとつひとつがトータルとして整えられているなと感じたんですけど、前作から今作に至るまで、matryoshkaの中で変化はあったんですか。
前作は、けっこうバラエティに富んだ音の使い方をしているんですが、今回はピアノと弦楽四重奏とビートっていう使いたい音の基本形みたいなのが割とすぐに決まってきて、それに基づいて全部作られています。
——『Laideronnette』を作るにあたって、影響を受けたアーティストやアルバムはありましたか。
制作中はあまり音楽を聴かないようにしているので、誰かのアルバムに影響されたというのはないですね。
——あと、けっこう内観的というか、箱庭みたいだなあとも思ったのですが、それはmatryoshkaのパーソナルな部分から生じてきたものなんでしょうか。
自分の内面にある要素を基に作ったっていうのはあるかもしれないです。
——その内面とは、具体的にどういうものなんでしょうか。日々の生活から得るものなのか、それとも日々の生活とは別の非日常的なものから影響を受けてのものなのかが気になります。
あんまり、周りの事件や出来事から影響されることはないです
——それは面白いですね。Senさんなりに、ハッキリと「音楽を作ろう」って思ったキッカケはありますか。
自分の好きなアーティストがいくつかいて、それらを混ぜたような、究極的に自分が聴きたい音楽を1曲でも作りたいなっていうのがあって。すごい漠然としてるんですが、なんとなく断片的なイメージみたいなのがあったんです。そうやって少しずつ探っていって、ようやく「これが近いな」と思えるものを作りあげたのが前作のときくらいです。それで、せっかくできたんだから、みんなに聴いてもらいたいという感じで、それを続けて今に至ってしまいました。
ようやくやりたいことが見えてきた
——そういえば、前作から『Laideronnette』までけっこうな時間がありましたよね。
たどり着く場所がいつもぼんやりしているので、いつも迷いながら制作しているというのがあって。曲を作っていく過程でも、「これが正解なのかな」っていうのが常につきまとっています。「やっぱりこれは違うんじゃないか」って戻ったり、そしてまた進んだりとか、そういう常に手探りな感じだったんです。作っては壊し作っては壊しの繰りかえし。だから『Laideronnette』では、ボツになった曲もたくさんありましたし、これだけ時間がかかってしまいました
——『Laideronnette』用に作った曲はどれくらいあるんですか。
数えきれないくらいあります。まあ、曲って呼べるレベルではないものもありますけどね。ひとつのループだけとか、すごく断片的なものとかも含まれています。でもすべてを捨てたわけではなくて、その断片を他の曲に使ったりしています
——Senさんはmatryoshka以外でも音楽活動をされていますが、「作っては壊し」の繰りかえしはmatryoshkaのときだけそうなんですか。
そうですね。matryoshkaだと特にそういう傾向があります

——それはなぜですか?
前作が自分の予想よりも評価が高かったから、というのはあります。前作は自由に、プレッシャーもなくやっていたんですが、『Laideronnette』はプレッシャーみたいなものを感じながら作っていたところもあります。
——そういうプレッシャーが『Laideronnette』にはハッキリと音として反映されていると思いました。
前作が好きな人は、こういうのが好きだろうなっていうのをある程度は想像して作ってますね。
——先ほども言ったんですが、前作が解放的で、外へ向かうエネルギーが多かったのに対し、『Laideronnette』は内観的でパーソナルな雰囲気が強いと思います。それはいろいろ考えながら作ったからっていうのも関係してるんですかね。
そうかもしれないですね。前作のときは失敗も成功もなかったし、ただ好きなようにやればよかったので、そういう面ではけっこう自由にできたんです。でも『Laideronnette』は、前作で好きになってくれたファンに向けて作ったんで、そういう意味ではじっくり考えて作った気がします。
——『Laideronnette』はmatryoshkaを好きになってくれた人に向けて作ったということですが、Senさんなりに「matryoshkaをこういう風に捉えてほしい」というのはあるんですか。
なんとなくですが、ようやくやりたいことが見えてきました。前作のときは、なんでもごちゃごちゃ入れちゃってる感じだったんですけど、ようやく、ある程度まとめられるようになったとは思います。
——そのすっきりした感じが『Laideronnette』では“余白”となって顕在化しているように感じます。それはやはり、matryoshkaとしてある程度やりたい方向性が見えてきたがゆえの余裕なんでしょうか。
まあ、そうですね。
——だから『Laideronnette』のジャケは、白が目立つデザインになっているとか?
ジャケは、特にリクエストしたわけではないんですよ。いつもうちのアート・ワークをやっていただいてる方なんで。音源を聞いてもらって、「こんな感じなんです」っていうのを伝えたら、今回は白が合うんじゃないかっていう意見があったんです。その意見を聞いて、言われてみればそうかなと思いました。ただ、中ジャケは黒にしてるんですよ。開いたときは黒が全体に見えるようにして、閉じた時は、白が目立つようになっている。外側が白で内面が黒。それでまとまったんです。
音楽って、楽しいときになくていいんじゃないかって思うんですよ
——歌詞についても訊きたいんですが、具体的なテーマはありましたか。
テーマというか、その状況みたいなのはあります。
——具体的にはどういう状況ですか。
例えば、「Sacred Play Secret Place」では、日が沈む夕日があって、丘があって、川原みたいなところ。草原がそよいでて、なんとなくそこに寝転んでいる感じです。
——その状況を言葉にしていく?
そうですね。すごい抽象的なんですが。
——ここまで話を聞いていると、Senさんのなかには「音楽にはこうあってほしい」みたいなものがある気もしてきました。そういう強い願いはあったりしますか。
音楽って、楽しいときにも必要だとは思うんですけど、楽しいときになくていいんじゃないかって思うんですよ。楽しいときは「楽しい」で完結しているし、へこんでいるときとか、暗い気持ちのときにあったほうがいいなと思います。悲しいときはとことん悲しいほうに誘う感じですかね。音楽を聴いて、逆の方向に感情を持っていくというよりは、自分が向いている感情のほうへさらに誘っていく。
——もしかして、「君のこと好きだからこっちむいて」みたいなラブ・ソングとかは好きじゃないですか?
虫酸が走りますね(笑)。
——あはははは(笑)。最初のほうで話したレディオヘッドもそうですもんね。「もう嫌だ」っていうことを素直に表現するというか。J-POPとかもダメですか。
悪寒がします。
——悪寒(笑)。Senさんの毒が見えてきましたね。
(笑)。テレビとか観てて、そういうのが流れてきただけで悪寒がしますし、観てるこっちがヒヤヒヤしてきちゃうんで、チャンネルを変えます。
——よくファミレスとかで、有名な曲をオルゴール風にアレンジしたやつとか流れたりするじゃないですか、ああいうのもダメですか。
ダメです。あと、ずっと同じことを言っているカセットをリピートする店があるじゃないですか。「いま100円です! お安くなってます! 」みたいなのを、3秒おきにずっと流しているような(笑)。ああいうの、よく耐えられるなと思います。
——(笑)。今日はありがとうございました。こう言うのもなんですが、チャーミングな方ですね。もしかしたら気難しい人なのかなって勝手に想像していました。
僕の日常を知ってる人が自分の音楽を聴くと、全然違うって言われますね(笑)。
RECOMMEND
Magdala / Magdala(HQD ver.)
Magdala(マグダラ)と名付けられた超重要プロジェクトが彗星の如く現れた。夢中夢のボーカリストとして活躍するハチスノイトと、Aureoleのリーダーであり、今話題のkilk recordsを主宰する森大地。この二人が化学反応を起こし、正に大傑作と断言できる芸術的かつ衝撃的なデビュー作を送り出してきた。
Kashiwa Daisuke / Re:
「Re mix」「Re harmonize」「Re arrange」「Re mastering」、これらの方法論を総括、また、「リスナーへの返信」という意味を込めて「Re:」というアルバム・タイトルが冠された作品。2006年~2012年までのKASHIWA Daisukeの軌跡を集めた、これまでで最もポップでバラエティに富んだ作品。
world's end girlfriend / Starry Starry Night - soundtrack
WEG主宰レーベルVirgin Babylon Recordsよりリリース! 湯川潮音がゲスト・ヴォーカルとして参加したリード・トラック「Storytelling」ほか、ストリングス、ピアノ、チェレスタやシンセサイザーなどを用い、儚く美しいメロディーと共に少女と少年の憧れと冒険、喪失と希望をやさしく描き出した全12曲。OTOTOYでは、高音質版のHQD(24bit/48kHzのwavファイル)で販売。
>>>world's end girlfriendの特集はこちら
Soyuz Project / perspective
80年代〜00年代テクノ・ミュージックの躍動感とアンビエントにも通ずる清涼感を併せ持つサウンドは、フロアに対応しつつもリスニングにこそその真価を発揮。また、その繊細なシーケンス・パターンと相まって、昼夜、場所を問わずスペイシーな音像を浮かび上がらせる。
PROFILE
matryoshka
2006年、Sen(track maker)とCalu(vocal)によって結成。幽玄なストリングス、無機質なリズム、憂いを帯びた女性ヴォーカル、冷たくも優しげなピアノの音色、幾百のノイズ、それらすべての闇と光をやさしく霧で包んだような音像の彼方から現れるは圧倒的甘美な世界。