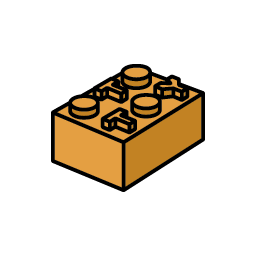バイノーラル化された自然音が誘う時空の旅──evala 『聴象発景 in Rittor Base - HPL ver』

ソロの音楽家、サウンド・アーティストとして活動するほか、渋谷慶一郎や真鍋大度など数々のアーティストとコラボレーションを行ってきたevala。彼が、今回およそ10年ぶりとなる音源『聴象発景 in Rittor Base - HPL ver』を配信リリース。ラップトップ・ミュージシャンから今回のようなフィールド・レコーディングを前面に押し出した作品制作へと変異していった経緯とは? また、今回の作品の原型となっている香川県、〈中津万象園〉でのサウンド・インスタレーションからアルバム制作へと至ったプロセスについても語ってもらった。ぜひ、このインタヴューをきっかけに彼の作り出すバイノーラル空間に没入してもらいたい。
10年ぶりとなる音源作品!
24bit/96kHz版はこちら
24bit/48kHz版はこちら
INTERVIEW : evala
音楽家、サウンド・アーティストのevalaは、稀有な音への感受性と、卓越した技術力によって唯一無二のサウンド体験を送り出している。ソロとして活動するほか、渋谷慶一郎や真鍋大度、そして建築家やダンサーなど、多くのアーティストとのコラボレーションを行ってきた。2016年からは新たな聴覚を創出するプロジェクト〈See by Your Ears〉を始動。立体音響を核としたサウンド・インスタレーション作品の制作を行い、音が生き物のようにふるまう“空間的作曲”を提示している。そんな彼が音源としてはおよそ10年ぶりとなる『聴象発景 in Rittor Base - HPL ver』をリリースする。フィールド・レコーディング素材が見事にコンポジションされたこの作品、元々は香川県丸亀市の日本庭園で展示したサウンド・インスタレーションを、〈RITTOR BASE〉で上演作品として再構築し、それをさらにHPLというバイノーラル・プロセッシングによって、ヘッドフォンでの全天球聴覚体験を実現したものだ。この作品発表に至るまでの過程について、evalaにじっくりと話を聞いた。
インタヴュー&文 : 國崎晋(RITTOR BASE)
写真 : 新津保建秀、宮脇慎太郎、國崎晋
実は僕がやりたいのは、空間を作り上げることだったのかもしれない
──evalaさんの活動が世の中に知られるようになったのは、2000年代の初頭、渋谷慶一郎さんの作品のコラボレーターとしてだったと思います。
コラボレーターというかプログラマー的なかかわりでした。渋谷さんの〈ATAK〉レーベルで主にインスタレーションの音響プログラムを担当していました。当時僕自身も〈port〉という小さなレーベルを運営し始めてましたが、そのころはちょうどCYCLING’74 Max/MSPといったプログラミング・ソフトウェアを使ってコンピューターの中でサウンドを扱えるようなった時期で、世界同時多発的に音響系と呼ばれるシャンルの音楽作品が生まれてましたね。また公演では、渋谷さんが弾いたピアノをコンピューターでどう面白く加工できるか、ということも一緒にやっていました。それこそ渋谷さんが清水靖晃さんと作った『FELT』っていう、OTOTOYさんが世界初のDSD配信としてリリースした音源でも、ライブ公演の際に僕がピアノにマイクを仕掛け、Max/MSPを使って会場全体に音を回すということをやっていましたね。
──その後、evalaさんはソロアーティストとしてアルバムを発表するようになりましたが、Max/MSPを使った電子音楽…いわゆるラップトップ・ミュージシャンというイメージが強かったと思います。それが今回の作品のようなフィールドレコーディングを前面に押し出した作品制作をするようになったのは、いつくらいからでしょう?
フィールドレコーディング自体は高校生のころからSONYのDATウォークマンを持ち歩いてやっていたんです。マイクロフォンを通して録音した音を、後でヘッドフォンで聴いたときの体験が面白い…それこそ世界を再認識させられるくらい新鮮だったんですね。
──その場で耳を澄ませて音を聴くのとは違った体験だと?
はい。録音した音の方がフラットに聴けるんです。カクテルパーティー効果ってありますよね? 例えば渋谷の雑踏の中で「evalaさん!」って言われたら、ぱっと振り向くけど、他の人は振り向かない。人間の耳はそうやって無意識に不必要ないろんな音をカットしているんですが、マイクロフォンを通すとフラットになって、全部の音が聴こえるんです。

──マイクはカメラのレンズに例えられることが多いですが、レンズは焦点を絞っていろんな情報をカットしていく。マイクを使ってフィールド・レコーディングされたものは、それとは反対に全部フラット化していくというのは面白いですね。
新宿駅でフィールドレコーディングした音なんて、あまりに低音がエグくてもう聴いてらんないですよ(笑)。いつもは耳が無意識にローカットしているものが立ち上がって、違う世界が見えてくるから面白いんです。
──そうやって録り続けていたフィールド・レコーディング素材を、作品として提示しようと思ったのはなぜですか?
コンピューターの中で音を扱うとツルツルとかザラザラとか、テクスチャー的な立体感は出しやすいんですけど、空間的な立体感っていうのは出せない。それこそマイク1本でしゃべっている気配感とか、そこから立ち上がってくる空間性っていうのをコンピューターで作り出すのは難しい。それに気付いたとき、実は僕がやりたいのはコンピューターで音をジェネレートすることだけではなく、空間を作り上げることだったのかもしれないと。それで録りためていたフィールドレコーディング素材を聴き返し、2010年に『acoustic bend』っていうアルバムを作ったんです。
──“acoustic bend”…生音を湾曲するという意味ですよね?
はい、人工でも自然でもない響きっていうコンセプトですね。冒頭の曲では雨音がいつのまにかホワイトノイズに変わっているという…フィールドレコーディングを、ある空間の疑似体験へと導くような効果音として使用するのではなくて、完全に音響的な特性にのみにフォーカスして作った作品です。面白いのは、フィールドレコーディングした素材をコンポジション……構成していく際に、「この録音のここが好き、あの録音のあれが好き~」っていう瞬間だけを集めて並べて聴いてみると、びっくりするぐらい好きじゃないものが出来上がるんです(笑)。何ていうか、「この目が好き、この耳が好き、この口が好き~」というのを集めたら全くタイプじゃない顔になるみたいな(笑)。“この瞬間が好き”というのは、そこに至るまでの時間発展があってこそなんですね。
──前に何が鳴っていたかによって変わるわけですか?
はい。だから、フィールドレコーディング素材を扱うのは大変。簡単に切り出せないんですよ。ずっと生きている音だから、安易に切ると死んでしまう。音楽構成とはまた別の作曲能力が必要となるんです。
求めているのは空間の質であって、HPLはそれがとてもよく表現できる
──『acoustic bend』では人工でも自然でもないような音ということでしたが、今回の作品は録音された素材をあまり加工せずに配置しているように聴こえます。湾曲するというプロセスはもう行わなくなったのですか?
2013年に、東京・初台の〈ICC〉にある無響室で『大きな耳をもったキツネ』という立体音響作品を作ったときに、録った素材はそのままに音の反射だけをゆがめることをしたんです。音色の加工ではなく、空間を湾曲していく。例えば、波がチャプチャプする音を自分の左半分からだけ聴こえるようして、右半分には都市の雑踏があるとか、自然界ではあり得ない音響反射をつくりコンポジションしました…音色は一切変えずに空間配置によって響きだけを変えてみたんです。そしたら、ものすごいファンタジーが立ち上がってきたんですね。知っているようで全く知らない、という新鮮な世界がそこに生まれて。
──『acoustic bend』はCD作品であったのに対し、〈ICC〉はサウンド・インスタレーション作品なので、フィールド・レコーディングした素材自体をいじらず、空間配置だけで作品として表現できるようになった?
そうです。だから僕はそこからCDを出さなくなって、リアルな空間での作品しか作らなくなったんです。
──今回の作品も、もともとは一昨年に制作されたサウンド・インスタレーション『聴象発景』がもとになっているのですよね?
はい。香川県丸亀市にある日本庭園〈中津万象園〉で、鈴木昭男さんと一緒に展覧会をしたときの作品がもとになっています。僕は〈中津万象園〉内の3つの場所で立体音響作品を展示したのですが、その中で一番コアになったのが、観潮楼という現存している最古の煎茶室に設置した作品。中津万象園はゆっくり歩くと1時間くらいかかる広大な庭園なんですが、いろいろなポイントにマイクを仕掛け、鳥が鳴いたり池で魚が跳ねたりする音を小さな観潮楼にすべて集めて、それらをリアルタイムでプロセッシングしていったんです。観潮楼にたどり着いた人は、自分がこれまで歩いてきた庭園のさまざまな音が幻聴のように聴こえつつ、窓を開けてあるので、いま、外で鳴っている音も聴こえ、それらが互いに響き合う。現実と幻想の境界が曖昧になるような作品です。「一体なにが現実なのかを考えさせられるね」という声を多くいただきました。それまでの美術館や劇場での閉じられた空間での作品に対して、外の音と共存している点も大きな違いですね。

──そのサウンド・インスタレーションが今回の作品につながったということですが、その前に昨年の2月に〈RITTOR BASE〉で〈“耳で視る”サウンド・スケープ 聴象発景 Rittor Base Ver.〉という音のみの上演を、5日間にわたり各回20名限定という形で行いました。あれはどういう位置づけだったのでしょう?
〈中津万象園〉内でフィールドレコーディングした音と、インスタレーションのときに観潮楼に仕込んでいたもの、さらには観潮楼以外の作品で作った音源を集め、40分くらいの立体音響作品として再構成したんです。観潮楼で体験できる響きをもとにしながら、構成し直したものです。〈RITTOR BASE〉は僕のスタジオと同じ、アコースティックフィールドの久保二朗さんが考案した立体音響システムが組まれていて、ステレオ+サブウーファーに、上に4ch、下に4ch、計8chのスピーカーが足されることで、音を前後左右上下に自在に定位することができる。僕が自分のスタジオ内で作っている立体音響音源をそのまま、より多くの人に体験してもらうことができたんです。
──その上演という形でできた立体音響作品を、今回、音源化できるようになったのはなぜでしょう?
さっきも名前を挙げたアコースティックフィールドの久保さんが、HPL(HeadPhoneListening)という高音質のバイノーラル・プロセッシングを開発して、それを使うとマルチチャンネルの立体音響をヘッドフォンで再現できるようになったんです。もちろん、これまでもいろいろなバイノーラル技術はありましたけど、ほとんどが音源をいかに動かして定位させるかに力点を置き過ぎていた。僕が求めているのは空間の質であって、HPLはそれがとてもよく表現できる。やっと満足できるテクノロジーがそろったので、10年ぶりに音源を出せることになったわけです。
広いのと狭いのを混在させたい
──スマホ+ヘッドフォンで音楽を聴くのが普通になったいま、ASMRのブームもそうですが、バイノーラルを使った音源が増えてきましたよね。
バイノーラルを使ってヘッドフォンで聴くというのは、極上の素材を耳に直接届けることができるので、ものすごくメリットがあるんですね。もちろん、スピーカーから出した音を空気を通して聴く面白さはありますけど、今のリスナーはみんなヘッドフォンでしか音楽を聴かなくなってきてるから、バイノーラルが普通になると、より健全な意味で音楽にもっと返ってくるんじゃないかな、そして革新的な作品も生まれてくるんじゃないかという希望的観測をしています。
──欧米のメジャーな音楽にもヘッドフォン前提とした音楽が増えてきて、音数がものすごく少なくなったりとか低域をものすごく出したり…それこそビリー・アイリッシュみたいにベースと歌しかないものもありますよね。
それでもう十分ですよね(笑)。マスタリングにおいても、ヘッドフォンは携帯電話やSNS用マスタリングとは違う視点がある。
──でも、それとevalaさんのアプローチは真逆で音が近くない。ヘッドフォン向けなんだけれども、近くでささやいたりとか、頭の中で低域がゆれるのではなくて、世界がぱーっと広がっていく感じです。
本作は庭園そのもののスケープですが、広いのと狭いのを混在させたいというのは考えています。ヘッドフォン・ミュージックの狭さ…デッドでアーバンなところと、原始の広い世界をぐちゃぐちゃにしたいんです。
──OTOTOYさんでの記事っぽい質問で恐縮ですが、そういう世界をちゃんと届けるにはやはりハイレゾの方がいいのですか?
絶対にそうですね。フォーマットが落ちていくとだんだん情報量は失われていきますから。僕が〈See by Your Ears〉というプロジェクトで出してる作品はホントそうです。“ちゃんとした音じゃなければ聴いてほしくない”って言うと、なんか自己顕示欲が強いアーティストみたいに思われるかもしれないけど、違うんですよ。本当に作品の本体が抜け落ちてしまう。単純に作品として成り立たなくなってしまうからです。言葉にも楽譜にもならないものを作品にしているわけですから。
──実際に今回の作品をヘッドフォンで通して聴いてみると、不思議なトリップ感が味わえました。いろんなところに連れて行かれ、そして戻ってくる感じです。
実は最初の方のパートと最後のパートがほとんど一緒の音源なんです。庭園へつながる橋を渡り、現存最古の観潮楼に行き、そこを出て庭園を一周して、また観潮楼に戻ってくるという構成です。
──フィールド・レコーディングのときのお話と共通しますが、耳が慣れてくるとフラットに提示された音のなかから取捨選択をするようになり、最初の曲と最後の曲が違うものに聴こえてきました。
僕は時間と空間がゆがむのがすごく好きなので(笑)。知ってたはずのものがなにか違うものになっていく…音楽やアートの魔法みたいなものってそういうとこにあると思っているんです。

編集 : 百瀬涼
『聴象発景 in Rittor Base - HPL ver』のご購入はこちらから
24bit/96kHz版はこちら
24bit/48kHz版はこちら
過去作はこちらにて配信中
PROFILE
evala
音楽家、サウンドアーティスト。
新たな聴覚体験を創出するプロジェクト「See by Your Ears」主宰。立体音響システムを楽器として駆使し、独自の“空間的作曲”によって、先鋭的な作品を国内外で発表。 近作に、SONY Sonic Surf VRを用いた576ch音響インスタレーション『Acoustic Vessel Odyssey』(2018年/SXSW,USA)や、映画を「耳で視る」をコンセプトにインビジブル・シネマ『Sea, See, She ーまだ見ぬ君へ』(2020年/スパイラルホール)を世界初上演し、大きな話題を呼ぶ。
現在公開中のインスタレーション作品に『Haze』(十和田市現代美術館/~2021年8月31日まで)、『Grass Calls』(銀座GSIX屋上庭園)/~2021年2月23日まで)。
■HP : https://evala.jp/
■Twitter : https://twitter.com/evalaport
■Instagram : https://www.instagram.com/evalaport/