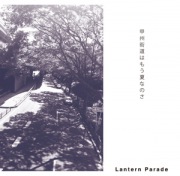そうそう、あの日はちょうど雨が降っていたんだ。ランタンパレードが久々にリリースするアナログ7インチ・シングル『甲州街道はもう夏なのさ』を手に入れるため、僕は雨のなか、意気揚々と下北沢のレコード店に足を運んだのだ。
ところが、だ。店頭にはお目当てのレコードが並んでいない。店員さんに尋ねると、すでに在庫はなくなったという。ああ、なんてこったい。だって発売日だぜ? まさかランタンパレードの新作7インチがもう手に入らないだなんて。限定枚数とはいえ、こんなに早く売り切れるとはさすがに思ってなかった。そういえば、僕のあとにもおなじことを店員に尋ねて肩を落としていた女の子がいたな。やっぱりランタンパレードを取り巻く状況は確実に変わってきている。7インチ・レコードを買えなかったことにガックリしながら、自分はそんなことを実感したのであった。
ランタンパレードこと清水民尋は、もともと同業者からの人気が高いミュージシャンではあった。それがここ最近は彼よりも若い世代のあいだでランタンパレードのファンを公言するミュージシャンが増えていて、また、それをきっかけにあたらしいリスナーがランタンパレードの音楽に触れるという、とても健全なサイクルが出来上がりつつあるようだ。ファースト・アルバムのリリースから10年が経とうとしているいま、ランタンパレードはようやくその才能に見合う評価が与えられようとしているのかもしれない。
そこで今回は、ランタンパレード9作目のオリジナル・アルバムにして、彼の真骨頂ともいえるサンプリングを主体とした作品『Orange Moon Soul』、そして前述した7インチ・シングル『甲州街道はもう夏なのさ』のリリースにあてて、現在のランタンパレードがどんな状況にあるのかを清水本人の発言から探ってみることにした。今の彼を取り巻く環境についてはもちろん、作家としての清水がとても充実した時期を迎えているということも読み取ってもらえるインタヴューになったので、ぜひたのしんでいただきたい。
インタヴュー & 文 : 渡辺裕也
9作目のオリジナル・アルバム、バンド編成によるシングルを同時配信開始!
ランタンパレード / Orange Moon Soul
【価格】
mp3 単曲 150円 / まとめ購入 1,500円
WAV 単曲 200円 / まとめ購入 1,800円
1. マイムジーク / 2. 夏の扉 / 3. ブルーソウル ブルービート / 4. 鏡張りの部屋の中で / 5. オレンジムーンの向こう側 / 6. 美しいなれのはてに / 7. なぜかを君は / 8. どっちが先 / 9. もうひと雨ありそう / 10. ファンキーフィードバック / 11. アガメズ / 10. のろけのサンバ / 11. 名言を言おうとしない
ランタンパレード / 甲州街道はもう夏なのさ
【価格】
WAV配信のみ 単曲 200円 / まとめ購入 400円
1. 甲州街道はもう夏なのさ / 2. スター・フルーツ・サーフ・ライダー
【参加ミュージシャン】
光永渉(チムニィ) / 曽我部恵一 / 荒内佑(cero) / 高田陽平(ホテルニュートーキョー、 stim)
ランタンパレード周辺のアーティストたちを勝手に相関図にしちゃいました!
インタヴューから明らかになった、ランタンパレードをとりまくアーティストたちの相関図を編集部が勝手に作成。インタヴューと合わせて、お楽しみください。

INTERVIEW : ランタンパレード

ファーストなんかをいま聴いても、おもしろい音楽だなと思える
ーーこれはあくまでも僕の実感に過ぎないんですけど、最近は若いバンドからランタンパレードの名前を聞く機会が多くて。
それはうれしいですね。最近というと、僕、スカートと対バンを組まれることがめちゃくちゃ多くて。スカートのほかにも、王舟くんやAlfred Beach Sandalと共演する機会が、なんだかものすごくたくさんあるんですよね。
ーーこういう言い方もアレですけど、ランタンパレードはいま、同業者からすごくモテてますよね(笑)。いつ頃からそんなに声をかけられるようになったんですか。
2008年ごろだったかな。ドラムを叩いてくれているチムニィの光永(渉)くんも、DJをやっていたときに「バンドをやるときはドラム叩きます」と声をかけてくれたんですけど、たぶんそれが最初だったと思う。
ーーなるほど。では、その光永さんも参加しているランタンパレードのバンド・メンバーがどういう経緯で揃ったのか、教えてください。
まずは僕と光永くんでスタジオに入っていたんですけど、そろそろアルバムをバンドで作ってみようという話になったときに、曽我部(恵一)さんが「じゃあ、ベースは俺が弾く」と言ってくれて(笑)。で、僕がコンガを入れたいと話したら、今度は曽我部さんが高田陽平さん(ホテルニュートーキョー、stim)を紹介してくれたんです。で、ピアノはアルバム(11年作『夏の一部始終』)のときは横山(裕章)くん(曽我部恵一ランデヴーバンド、L.E.D.)に頼んでいたんですけど、今回は荒内くんが光永くんを介して「弾かせてほしい」と手を上げてくれて。こうして集まってもらえたのはすごくありがたいし、本当に恐れ多いことですね。
ーーオリジナルでは大貫妙子さんの楽曲をサンプリングしていた「甲州街道はもう夏なのさ」ですが、この曲をバンド形態で再録しようというアイデアはどのようにして生まれたんですか。
そもそもサンプリングでつくった楽曲をバンドでやるつもりはまったくなかったんですけど、これもまた曽我部さんからの提案で「やったほうがいいよ」って(笑)。で、ライヴでやったらすごくお客さんもすごくよろこんでくれるので、「ああ、これもこれで楽しいな」って。きっと曽我部さんも、お客さんが求めているものがなにかを考えてくれたんじゃないかな。
ーーそして7インチ・シングルにはもうひとつ、コーネリアス「STAR FRUITS SURF RIDER」のカヴァーが収録されています。この選曲は?
これも、練習のときに曽我部さんから「じゃあ、カヴァーでもやってみる?」と提案されて(笑)。最初はちょっとした冗談から始まったんです。この曲、生演奏でやってみたらおもしろいんじゃないかって。ホントに思いつきですね。
ーーそういえば、清水さんはツイッター上でもこの2曲についてすこし解説されていましたよね。たしか、「甲州街道はもう夏なのさ」が「ファラオ・サンダース的な祝祭土着感ある、ファンク 'n' サンバ」で、「STAR FRUITS SURF RIDER」は「マイルス・デイヴィスのアルバム『GET UP WITH IT』に収録されている「Maiysha」、「Rated X」などの曲を意識したアレンジのつもり」だって。
ああ、確かにそんなことを書きましたね。「甲州街道はもう夏なのさ」については、結果的にそうなったという感じなんですけど、「STAR FRUITS SURF RIDER」に関しては、最初からマイルスのCDを持っていって、バンドにこういうイメージだと伝えて臨みました。

ーー新しい作品に着手するときは、やはりそのときどきに聴いている音楽からインスピレーションを受けることも多いんでしょうか。というのも、ランタンパレードはサンプリングを基とした制作が多いというのもあってか、ヘヴィ・リスナーのイメージがすごく強くて。
うん、サンプリングの作品に関してはそうですね。でも、バンド編成の場合はすこし違うかもしれない。「昔、こういうのも聴いていたな」とか、そういう感覚なのかな。正直、バンドでつくるものについては自分でもよくわかってないんです(笑)。でも、そもそもサンプリングで音楽をつくりはじめる前は、僕もバンドでやっていくつもりだったんですよね。メンバーが見つからなかったから、しょうがなく始めたのがサンプリングで(笑)。でも、いざ始めたらサンプリングがすごくおもしろくなってしまって、だんだんバンドへの執着がなくなっていったんです。「バンドやりたいな」みたいな気持ちがまた沸いてきたのは、けっこう最近のことで。それも、ギターでつくったシンプルな歌ものをやりたいという気持ちがあったからなんです。昔からジェイムス・テイラー(注1)やジュディ・シル(注2)、ティム・バックリィ(注3)なんかが大好きだったので。
注1 : アメリカのシンガー・ソング・ライター。結婚と離婚、薬物中毒からの克服、兄の死などプライベートなものを題材にしたり、人々の悲哀を描き出す独特の作風で数々の名盤を残している。
注2 : アメリカ出身のシンガー・ソング・ライター。デヴィッド・ゲフィンの設立したアサイラム・レーベルの第1号アーティストであり、音楽シーンから消えた後、1979年に薬物の過剰摂取によって他界するまでに2枚のアルバムを発表した。
注3 : アメリカのシンガー・ソング・ライター。フォーク歌手としてデビューした後、先進的な音楽に挑戦し続けるが、オーバードースにより早世。息子のジェフ・バックリィもシンガー・ソング・ライターとして成功を収めている。
ーーなるほど。そのバンド形態でつくった前作『夏の一部始終』から、今回はおよそ1年半ぶりのリリースになりましたが、基本的にランタンパレードはものすごくリリースの間隔が短くて、とにかく多作ですよね。曲のストックはあるんですか。それともつくったものは残さずに全部リリースしているのかな。
いや、サンプリングの作品は現時点で出していないものがまだ2枚分あるんです。バンドでやる曲に関しても、1枚分はできているかな。
ーーえ、そんなに貯まってるんだ!?
うん、曲づくりはあまり考えずにやれるので。でも、何もやりたくない時期はまったくつくらないんですよ。やりたくなったら集中して一気につくるような感じですね。
ーー自分がつくった音楽って、あとから聴き返します?
けっこう聴きますよ。いま聴いても大丈夫かどうかを確認したくなるので。で、けっこうどれもいいなと思えるんですよね(笑)。自分でいうのもアレですけど、ファーストなんかをいま聴いても、おもしろい音楽だなと思える。自分がつくったものにはけっこう思い入れがあるんです。
一時期はパンクにまみれていました(笑)
ーーちなみに今回こうして届けられた最新作『Orange Moon Soul』って、いつ頃につくったものなんですか。
これはもう1年以上前につくったものですね。
ーーじゃあ、この『Orange Moon Soul』をつくっている時はリスナーとしてどういう気分だったか、思い出せますか。
この時はなにを聴いてたかなあ。そのころに好きだったのはラス・G(注4)かな。ロー・エンド・セオリー周辺にいる人なんですけど、僕はフライング・ロータス(注5)とかよりも断然好きで。
注4 : L.A.を拠点にBrainfeeder、Low End Theory、Poo-Bah、Dubla、に関わり、L.Aビート・シーン随一の強烈な個性を放つ。
注5 : カリフォルニア生まれの音楽プロデューサー、ディスクジョッキー。おもにヒップホップ音楽を手がけるが、ジャズや電子音楽、ブラジル音楽の影響をつよく受けており、強い重低音と特異なリズムが特徴的である。
ーーあ、最近のLAビーツなんかもチェックされるんですね。
うん、やっぱり新しいものは聴きますよ。そのなかですごくいいなと思えるものとなると、やっぱり限られてくるけど、一応チェックはしてます。あと、『Orange Moon Soul』に関してはラヴァーズ・ロックとかをネタにしているので。
ーーランタンパレードがラヴァーズをネタに使うのって、けっこう珍しいような気がする。
うん、これがはじめてですね。これはツイッターで聞いた話なんですけど、『Orange Moon Soul』はiTunesだとジャンル名が「ラテン」と表示されるらしいんですよ(笑)。アメリカの昔のソウルとかもサンプリングしてるんですけどね。
ーー「ラテン」か(笑)。でも、さっきみたいにランタンパレードが好きだと公言しているミュージシャンの名前をうかがっていると、たしかに彼らの音楽とランタンパレードのあいだには、なにかしらの共通項や通じ合う部分があるような気もします。清水さん自身から見て、自分と近いものやシンクロニシティを感じるミュージシャンっていますか。
やっぱりやけさん(やけのはら)と鴨田(潤)さん(イルリメ、(((さらうんど))))には、勝手に共感しています。同じ方向を向いているわけではないかもしれないけど。ヒップホップやハウスなんかが好きで、それを日本語のロック、ポップスの文脈に落とし込んでいるところとか。
ーーつまり、ランタンパレードは日本語のポップスを起点としたものでありたいという気持ちがつねにあるということですか。
サンプリング作品に関しては、ブラック・ミュージックが日本に伝わってきて奔放に解釈されたようなものにしたい、という思いがあります。好き勝手にやってる感じというか。ブラック・ミュージックをそのまま模倣しようとはあまり思ってないんです。そういう意識はありますね。
ーーでは、そんな清水さんがこれまでに最もどっぷりハマった音楽というと、なにになるんですか。
それはやっぱりセオ・パリッシュかな。初期のハウス・ミュージックなんかはセオ・パリッシュ経由で掘り下げた感じなんです。
ーーそういえば、清水さんとやけのはらさんの対談記事を読んだことがあるんですけど、そこで影響を受けたバンドとしてTHE BLUE HEARTSを挙げていましたよね。
ああ、それはもう本当に最初の頃ですね。13歳とか、そういう頃。そこもセオ・パリッシュからハウスを掘り下げたのと同じで、THE BLUE HEARTSからセックス・ピストルズとかに派生させていくと、ジョニー・ロットン(注6)が好きだと言っているカン(注7)とかキャプテン・ビーフハート(注8)なんかに興味が沸いていったりするじゃないですか。クラッシュ(注9)にしても、『サンディニスタ! 』とかでいろんな音楽をやってるし。そうやってパンクから入ってニューウェイヴに流れていくと、結果的に音楽の興味がバーッと拡がっていくんですよね。そこが自分の起点になったところはあると思う。
注6 : 本名ジョン・ライドン。ジョニー・ロットン(「腐れのジョニー」の意)の愛称でパンク・ロック・バンド、セックス・ピストルズのリード・ヴォーカルを務め、解散後はパブリック・イメージ・リミテッドを結成した。
注7 : 1968年に西ドイツで結成されたロック・バンド。のちのパンク、ニュー・ウェイヴ、オルタナティヴ・ロック、エレクトロニック・ミュージック、ポスト・ロックなどに大きな影響を与えた。
注8 : アメリカ合衆国のソングライター、シンガー、ミュージシャン、アーティスト、詩人、作曲家、プロデューサー、映画監督、画家。1960年代後半のアメリカ西海岸におけるサイケデリック・ミュージック・シーンにおける最重要バンドのひとつ、「キャプテン・ビーフハート・アンド・ヒズ・マジック・バンド」のヴォーカル・リーダーとして著名。
注9 : 1976年 - 1986年にかけて活動した、イギリス・ロンドンのパンク・ロック・バンド。セックス・ピストルズと並んで、最も成功したパンク・バンドの一つであり、また時代を象徴するロック・バンドでもある
ーーやっぱりパンクから培ったものは大きいんですね。
そもそも僕はハードコア・バンドをやっていましたしね。一時期はパンクにまみれていました(笑)。その頃の僕、envyとかあのへんのバンドが活躍しているシーンの目立たないところにいたんですよ。
ーー目立たないところ(笑)。
つまり、envyとかと比べるとまったく人気がなかったということですけど(笑)。YOUR SONG IS GOODなんかも初期の頃から見ていましたね。あとはCOMEBACK MY DAUGHTERSとか。ちょっとややこしい説明になっちゃうけど、僕、カムバックのギターのCHUN2くんが前にやっていたバンドのドラムと一緒にバンドをやってたんですよ。そのへんの人たちがいまだに活躍しているのは、すごくうれしいことで。

ーー一方の清水さんがその界隈と離れて活動するようになったのは、単純に母体がバンドじゃなくなったから? それとも意識的に距離を置いたところもあったんですか。
そこは単純に聴くものが拡がっていったことの影響が大きいかな。ヒップホップとかも好きになった時期なので。
ーーじゃあ、一時期までライヴ活動をされてこなかったのも、そのあたりの趣向性の変化と関わっているのかな。
ライヴはべつにやりたくなかったわけではなかったんですけど、サンプリングで作った音楽に関しては、あまりライヴで再現したいという欲求が沸かなかったんですよね。リスニング用のものとして割り切っていたところがあったので。ライヴをやらなくても自分の欲求は満たせたんです。
これはたとえばの話ですけど、いつか人類は滅亡するじゃないですか
ーーやっぱりそうなんだ。きっと録音物への愛情が特別に強い方なんだろうなとは思ってたので。
たしかにそうですね。でも、いまはけっこう頻繁にバンドや弾き語りでライヴをやっているんですけど、やってみるとライヴもいいものではあるんですよね。それに、これはたとえばの話ですけど、いつか人類は滅亡するじゃないですか。
ーーいきなり会話のスケールがでかくなりましたね(笑)。
(笑)。そうすると、録音物は一気に意味のないものになってしまうんですよね。そう考えると、やっぱりその場の空気のなかで自分の身体から音を出して、聴いてくれる人になにかを感じてもらうことって、やっぱりなによりも大切なことなのかなって思うこともあって。僕、いま38歳なんですけど、やっぱりそういうことはやれるうちにやっといたほうがいいなって最近はよく思うんですよね。
ーーなるほど。でも、録音物は自分の肉体がなくなっても残すことができますよね。ランタンパレードがすごいスピードで作品を重ねていくところを見ていると、録音物に対する執念みたいなものも感じるんですが。
それはもちろんありますよ。生きた証というか(笑)。でも、たとえばCDって、持って100年くらいだって言いますしね。そういえば僕、キャプテン・ビーフハートの『トラウト・マスク・レプリカ』を高校生の頃にCDで買ったんですけど、そのCDが腐ったんですよね(笑)。US盤だったんですけど、内側から茶色くなっていったんですよ。
ーー変色したんだ(笑)。では、清水さんが理想とするリリース形態となると…。
それはやっぱりレコードですね。
ーーじゃあ、自分にとっての理想的な音源作品をひとつ挙げるとしたら、なにになりますか。
単純にフェイバリットでいいんですよね? それはアルトゥール・ヴェロカイが72年に出したアルバムかな。ブラジルの作曲家/アレンジャーで、当時ちゃんと店頭に並んだのかどうかもわからない作品なんですけど、03年にリイシューされてるんです。それを聴いたときはすごく感動して。ソウル/ファンクなんですけど、アメリカのものとはまったく違うんですよね。ストリングスにもフランジャーみたいなエフェクトがかかってたりして、とにかくおかしな音楽なんですよ。それは僕にとってすごく大きな作品だな。

ーー南米もアフリカも含めて、やはり清水さんはひろく黒人音楽への愛着があるんですね。黒人音楽のどんなところにそこまでの魅力を感じるんですか。
やっぱり野性味と荒々しさかな。そういう要素もありつつ、ソウルやディスコの流麗なストリングスなんかを聴くと、ものすごい気高さも感じるし。そういう野性味と美しさが同居しているところに、ものすごく惹かれるんですよね。
ーーさっき、「日本人が好き勝手にやってる感じ」とおっしゃってましたが、たとえばその背景には黒人音楽へのコンプレックスなんかもあるんですか。
それはまったくないんです。僕は日本で音楽をやれていることがすごく楽しいことだと思ってるんですよね。海外が羨ましいとはまったく思っていないんです。たとえば日本のヒップホップの人とかだと、そういう思いが強かったりするのかもしれないけど。日本人がこうして好き勝手にやると、自ずと他と似たものにはならないんですよね。それこそおかしな音楽が生まれるんです。もしかすると、そういう音楽って欧米の人から見るとダサく聴こえるのかもしれないけど、僕からするとそういうところがすごく楽しくて。ちょっとした違和感のある音楽がたくさん生まれるから、日本はおもしろいと思います。
ーーなるほど。では、話もそろそろ終わりにしていきましょう。現在も新しい音楽を作っているということですが、清水さんはいま、どんな音楽に関心が向いていますか。あるいは、制作面で今後どんなアプローチを試みたいと思っているんでしょう。
そうだなあ。ここまでサンプリングでたくさん作ってきたし、いつかはパソコンを使った制作もやってみたいんですよね。もうちょっとハイファイな音づくりにも実は興味があって。まあ、実際にやるかどうかはわからないけど(笑)。今はパソコンで作るのが普通だけど、僕はいまだにハードディスク・レコーダーでやってるんです。ヒップホップの人たちがよく使うMPCとかにも、あんまり興味がわかないんですよね。もう6~7年くらい、KORGのELECTRIBEっていうサンプラーでやってるんです。
ーーバンドに関してはなにか新しい展望が見えていますか。
いつかは生バンドでディスコっぽいものもやりたいですね。メンバーの都合もあるのでどこまでやっていけるかわからないけど。ドラムの光永くんなんか、いまホントにいろんなところで叩いているし。荒内くんも陽平くんもいろんなところに参加しているし、それこそみんなモテまくってますから(笑)。
ーーランタンパレードの周辺はどんどんにぎやかになっていきますね。
うれしいことです。いますごく楽しいですよ。共演者にもすごく良いバンドとかがたくさんいるし、そのなかに自分もいれることがすごく幸せだなと感じてます。たとえば、70年代の日本のロックとか、80年代のインディーズとかって、話を聞いているとすごく楽しそうじゃないですか。でも、羨ましくはならない。いまの音楽がすごく楽しいから。お客さんもすごく優しくしてくれるし(笑)。

>>以前のOTOTOYでのインタヴュー記事はコチラ
RECOMMEND
Flying Lotus / Until The Quiet Comes
歴史的金字塔『Cosmogramma』は序章に過ぎなかった…。フライング・ロータス最新作『Until the Quiet Comes』が遂にその全貌を現す! 前作に続き、トム・ヨーク、サンダーキャット、そして本作にはなんとエリカ・バドゥ参加!! 歴史はまた、フライング・ロータスによって塗り替えられ、世界は再び、未知なる旅へと誘われる
Ras G / Back On The Planet
L.A.とアフリカと宇宙を繋ぐ唯一の男、ラスGが地球に帰還。サン・ラー、リー・ペリー、ジョージ・クリントン、ドレクシヤ、フライング・ロータス、、、綿々と続くブラック・サイエンス・フィクションの歴史は、 ラス・G によって更新される!
can / Future Days
自由奔放で強烈な個性を放つ日本人ヴォーカリスト、ダモ鈴木をフィーチャーした最後の作品でもあり、カン最高傑作の誉れ高い73年発表作品。正確なアフロビートに導かれ、鳥が鳴く声や水流など自然音のSE、繊細な楽器パート、つぶやくようなダモ鈴木のヴォーカルが交差し、徐々に昇りつめていくタイトル・トラックは、たとえようがないほどにメランコリックで美しい!アンビエントなオープニング後、20分にもわたって怒涛の展開を見せるM4まで首尾一貫してトータルの空気感が素晴らしく、正しく傑作と呼ぶに相応しい作品だ。
ランタンパレードの過去作はこちら
LIVE INFORMATION
チムニィ ファーストアルバム発売記念ライヴ「東京のど真ん中」
2013年9月15日(日)@渋谷0-nest
OPEN 18:00 / START 18:30
w/ チムニィ、セノオGEE、藤井洋平&VERY SENSITIVE CITIZENS OF TOKYO
風知空知 7th Anniversary~avanzare vol.1~
2013年9月20日(日)@下北沢 風知空知
OPEN 18:30 / START 19:30
w/ MOROHA、やけのはら+ドリアン+VIDEOTAPEMUSIC
PROFILE
Lantern Parade

煩雑な生活の諸々が波のように押し寄せるぼくらの毎日。それらは砕け散り、日々の泡となってぼくらを包む。そんな風景のなかを漂うランタンパレードの調べ。 2004年のアルバム・デビュー以来、硬い石に言葉を刻み込むようにして、黙々と音を紡ぎ続けて来たランタン・パレードこと清水民尋。浮ついたところのない彼の硬派なメロウネスに、ぼくは惚れている。優しくこぼれ落ちるピアノの音は、だれかの涙のように切実だ。ハードコア・パンク出身の彼のそんな風情にシンパシーを持ってくれるひとたちが、全国にゆっくりと増えて来ている。そのことがすごく嬉しい。 ランタンパレードの音楽。そこには、いつものぼくたちの気持ちが、想像もつかない色を付けられて、いっぱい転がっている。都市の新しい音楽。スウィート・ソウル・ミュージック。(text by 曽我部恵一)