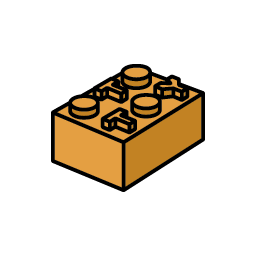サックス奏者・松丸契は「言葉」を音で表現する──『Nothing Unspoken Under The Sun』

千葉生まれパプアニューギニア育ち、バークリー音大卒という経歴をもつサックス奏者・松丸契。ツイン・ドラムス編成・THINKKAISMでのデビューから約1年を経て、ニュー・アルバム『Nothing Unspoken Under The Sun』をリリースした。今作は、デビュー作から大幅にサウンドが変化し、「言葉を発する」というコンセプトを打ち出した作品となっている。インストゥルメンタル作品における“言葉”とはなんなのだろう? と疑問に思うかもしれない。そこには彼自身が伝えたい想いがある模様だ。自身のアイデンティティや、バークリー音大での学び、石若駿はじめ国内アーティストとの共演…一聴しただけでは明瞭にならない、作品を構成する要素/その元にある背景を、節々から読み取ることができるインタヴュー内容となっている。
※『Nothing Unspoken Under The Sun』のCD版は12月9日より発売、M3.“虫籠と少年”とM9.“暮色の宴”はCD限定の楽曲となります。
INTERVIEW : Kei Matsumaru

松丸契はじっくり話を聞いてみたかったミュージシャンの一人だ。1995年千葉県生まれ。3歳から高校卒業までパプアニューギニアにある人口400人程度の村で暮らしたあと、バークリー音大を首席で卒業。日本に帰ってくるタイミングで石若駿にフックアップされ(日本一多忙なドラマーは次世代への嗅覚も鋭い)、彼が率いるSMTKに参加。ほかにも様々なアーティストと共演しながら、凄まじいサックスの腕前を披露してきた。すでにジャズの世界では「驚異の新人」と評判だが、ジャンルを超えて引く手数多となるのは時間の問題だろう。
『Nothing Unspoken Under the Sun』は実にコンセプチュアルな作品だ。ここでは石若と金澤英明(Ba)、石井彰(P)が10年以上活動を共にするピアノトリオ「BOYS」を迎え、フリーかつメロディアスな演奏でもって、このカルテットにしか表現できない世界観を提示している。音楽そのものはインストだが、楽曲に込められたメッセージは雄弁そのもの。自身のグローバルな生い立ちもテーマの一つで、ミツキやセン・モリモト、リナ・サワヤマなど日本にルーツを持つアーティストと同様、松丸も揺れ動くアイデンティティと向き合っている。彼はどのようなことを考えながらアルバムを完成させたのか?
インタヴュー&文 : 小熊 俊哉
写真 : 大橋 祐希
サックスではできないことに惹かれていく

──松丸くんが日本に帰ってきたのが……。
松丸契(以下、松丸):ちょうど2年前ですね。
──僕は昨年12月にSMTK、今年2月にm°feのライブで松丸くんの演奏を見させてもらって。前者はフリージャズとかパンク寄りのカルテット、後者はアンビエントとか音響ノイズ系のトリオで、どちらも驚きましたよ。「すげーカッコイイな」「サックスってこんな音出せるんだ」みたいな(笑)。
松丸:小熊さんにそう言っていただけて嬉しいです。あとは今年に入ってからサックス一本の独奏によるライブも何回かやっていて。今はもうちょっと表現力が増えたかなと思います。
──新しいアルバムでも、「サックスってこんな音出せるんだ」と思った瞬間が何度かありました。
松丸:冒頭からマルチフォニック(※)を使ってますしね。ギミック的とも言えるけど、あえてそれくらい衝撃のある演奏で始めてインパクトを出そうと思って。
※本来1つの音しか発音しないシングル・ノート楽器で、同時に複数の音を出すテクニックのこと。
──松丸くんのサックスは「上手い」の一言だけで語り尽くせない魅力があるけど、自分ではどんな特徴があると思いますか。
松丸:フィジカルのスキルは大前提としてあるべきものだと思っていて。スキルがある程度あったほうが表現の幅が広がるから、それを確保したくてめちゃくちゃ勉強と練習をしてきたんです。例えば、サックスで演奏するのは厳しい音の跳躍とか、それを繰り返し演奏することで聞こえてくるものがある。そういうのは技術がなければ表現できないことですよね。そういう意味で、この先もある程度は伸びると思うけど、スキルの面で追求できることは結構カバーできるようになったかなとも感じていて。日本に帰ってきてからはその先にある表現を追求しています。
──なぜサックスにそこまで惹きつけられるんですか?
松丸:いや、僕は他の楽器や音に対する憧れのほうが強いのかもしれないです。サックスを練習していくにつれて、この楽器ではできないことに惹かれていくというか。ピアノだったらコードが弾ける、ドラムだったら一度にいろんなテクスチャーを作れる、歌や声だったら言葉がくっついてくる。どれもサックスにはできないことだけど、それに近いものやそれを錯覚させるものをどうやったら表現できるのか。サックス自体よりもそっちへの憧れのほうが強いですね。
──面白い話! いつからそんなことを考えるようになったんですか?
松丸:いつからかははっきり分からないんですけど、こういう考えに近いものを感じたのがアンブローズ・アキンムシーレの『When the Heart Emerges Glistening』(2011年)というアルバムで、高校生の時に確か初めてお小遣いで買ったんですよね。卒業するまでひたすら聴いてました。
──彼はトランペッターですよね、サックス奏者ではなくて。
松丸:そうそう。トランペットを使って色んな音を作り出すようなアルバムなんです。人の声とか動物の鳴き声みたいなものも聞こえるし、イントネーションも自由に変えていたり、それがすごく不思議で。最新作もすごくよかったけど、あのアルバムを当時聴いたことで、さっき話したような考え方をするようになったのかもしれない。
──高校生となると、まだパプアニューギニアにいた頃?
松丸:そうです。だから、親戚からCDを送ってもらって。届くのに3〜4ヶ月かかりました(笑)。
──生まれは千葉県だけど、3歳から18歳までパプアにある標高1500メートルの小さな村で暮らしていた。危ない地域で有刺鉄線で囲まれていたと、以前話してましたよね。
松丸:危ないという事について一言で説明するのは難しいですが、有刺鉄線に囲まれながらも自由な環境だったと思います。雨が降ったら水がたまる、降らなかったら貯水タンクが空っぽ。自然任せの生活でしたね。
──そういう環境で育ったことは、自分の人格形成にも影響を与えている?
松丸:パプアにいた頃は「ここから出たい」ということしか考えてなかったです。インターネットもなかったし、エンターテインメントがとにかく少なかったから、「映画館に行ってみたいな」と想像してみたり、ずっと外側ばかり向いていました。でも、いざそこから出てみると、パプアにいた時は世界がどんなふうに見えていたのか、当時はどういうものを大事にしていて、その頃に気づけなかったものはなんだったのか……地味にずっと考え続けています。そういう意味では、影響を与えているんだと思います。
──その後、バークリーを首席で卒業するわけですが、音大時代の大きかった学びは?
松丸:ドラマーのテリ・リン・キャリントンからレッスンを受けていて、ある日デュオで演奏してたんですけど、僕を招き入れてくれているような叩き方で。彼女との間にはとてつもないレベルの差が存在するのに、一緒にやってるだけでどんどん音楽が良くなっていくんですよ。その場の音楽をより良いものにするための演奏というか。あれは衝撃的だったし、不思議な体験でしたね。僕もそんなふうに演奏したいなと思いました。
──石若くんはSNSで松丸くんのことを発見したそうですね、バークリー時代の演奏を見かけて。
松丸:そうらしいですね。『songbook』は聴いてたし、すごいドラマーだというのは知ってたので、メッセージをもらったときはビックリしました。最初は日野皓正さんのギャラリーライブで2、3曲くらい一緒にやったんですけど、そのときのバンドには石若さんに、今回のアルバムにも参加している石井彰さん、SMTKのマーティ・ホロベックもいて、一緒に演奏しながら物凄くしっくり来たんです。自分のやりたいことが全部できるし、それこそ招き入れられている感覚になって。あの日が日本での活動の原点になりました。
──そして去年、松丸さんはTHINKKAISMという5人組のリーダーとしてデビューを飾ったわけですが、ここに参加していたのが石若駿・金澤英明・石井彰による「BOYS」の3人でした。今回の『Nothing Unspoken Under the Sun』も、このトリオとの共演作になっています。
松丸:プロデュースも自分でやりましたし、アルバム全体の構成とか、コンセプトを持ったインタールードを2曲入れることは最初から頭にあって。大半の収録曲も自分で作ったので、そういう意味では僕の作品なんだけど、自分だけの表現という感じではないんですよね。
──というと?
松丸:THINKKAISMと同じ精神をキープしつつ、この4人でしか作れない音楽を表現するというのが大前提としてありました。4人の個性が合わさって何かが生まれるというよりも、このメンバーで一緒に曲を解釈していく感じ。この4人じゃないとこういう空白ができないとか、メロディの形がこうはならないとか。リズムの噛み合い方も違うものになると思う。3人はBOYSとして14年くらい活動してきたから、サウンドや曲に対するアプローチも確立されているんですよ。そこに一昨年から僕が度々加わるようになって、一緒にやってきたことを表現するために(アルバムの)曲を書いた部分もあって。この4人でやることの意味を最大限に生かすための曲作りと即興を意識しましたね。さらに、石若さんと金澤さんは曲も提供してくれて、アルバムのコンセプトにもすごくマッチしたので、最終的にこの10曲になりました。
「言葉を発する」っていうアイディアを表現したかった

──アルバムのコンセプトは?
松丸:「言葉を発する」っていうアイディアを表現したくて。インストではできないことだからこそ、それを表現することが大事だと思ったんです。
──ということは何か表現したいこと、伝えたいことがあったわけですか。
松丸:そうですね。1曲目の「harim tok」はトク・ピシン語(パプアニューギニアの公用語)で「話を聞け」という意味で。そのあと曲名に(for West Papua)って添えたのは、パプアと同じ島の西半分がインドネシアの一部で、文化も人種もインドネシア本土とは全く違う人々が昔から暮らしていて、60年くらいずっと独立運動をしているんです。もともとインドネシアも(1800年代から)オランダ領だったじゃないですか。そこからインドネシアが独立するタイミングで(1949年)、オランダは西パプアを独立させようとしたけど、結局インドネシア領のままになって。それ以来ずっと独立運動が続いてるんですけど、それを取り上げるメディアはかなり少ないし、ほぼ知られていなくて。だからこそ、それについてパプアニューギニアにいた頃西パプアの話を聞いていた自分自身の目線で曲を書きたかった。
※西パプアの歴史的背景については、この記事を参照。
https://globalnewsview.org/archives/10519
──2曲目の「ignorance is bliss」は、「知らぬが仏」という意味ですよね。
松丸:「知らぬが仏」が正しい場合もあるけど、違和感を感じることもあると思うんです。「本当に知らない方が仏なのか?」みたいな。それを曲で表現しようと思って。だからこの曲では、全然違う2つのメロディラインがあって、最初は上と下に分かれているのが噛み合うことでハーモニーの錯覚を起こしていくんですけど、最終的には急にトーナルになって、ひとつの音で終わっていくんです。ある意味バカっぽいエンディングにしたのは、「結局そういうところに落ち着くのか」っていうツッコミで。二極化したメロディラインの間はあえて埋めず、そこは解釈の余地があるように作った感じです。
──曲の旋律や構成にもそれだけの意味が込められていると。5曲目の「it say, no sé」は?
松丸:「いっせいのせ」なんですけど、日本語で書くと子供っぽいじゃないですか。でも、英語とスペイン語にしたら、まるで深いことを言っているように見える。ダジャレですけど、同時にそういう意味も見えてくる。
──この曲はイントロからサックスがすごいですね。音響的なアプローチというか、よくこんな音色が出せるなって。
松丸:結構凝った作りの曲ですね。あえてよくあるファストスウィングのリズムと、ジャズっぽいメロディにして、Aメロは特に使ってる音の種類もそんなに多くはない。即興の部分を元にしつつ、4人の表現の限界をよりクリアに見せるっていう。単に最初から最後までフリーだと、それに対してリファレンスするものがないので、こういう下地があるとより鮮明に見えてくるものかなと。
──リズムやアクセント、音が被る瞬間。聴くたびに発見がある曲です。
松丸:そうですね。僕と石井さんが同じハーモニーをやる瞬間が何度もあったり、石若さんと金澤さんがファストスウィングでもリズムをキャッチしながら、リズムの歯車的なものを作っていって。サックスでも音と音の間の音を使っていたり、僕が考えた運指を入れていたりして。それがないとメロディが成り立たないような書き方をしている。そこもこだわりポイントですね。
──2曲挿入されているインタールードについてはどうでしょう?
松丸:「言葉を発する」というコンセプトを思いついた時点から、僕と石若さんのデュオでインタールードを作ることは決めていました。タイトルの横にあるのは発音記号で表記していて、「ˈkænsl̩?」はキャンセル、「kji̥ɕikã̠ɴ」は既視感と読むんですけど。
──言われてみればそうですね!
松丸:前者は「キャンセルカルチャー」のことで、後者の「既視感」は何度もそういうやり取りを見てきたなということ。それに対する違和感を「言葉で発する」のがテーマにあって、まったく同じ音列を4テイク録ったうちの3番目が「ˈkænsl̩?」、4番目が「kji̥ɕikã̠ɴ」になりました。最初に「こういう音列を吹きます」というのを石若さんに聴いてもらったあと、(スタジオの)違うブースに入って、お互いが見えないような状態で一緒に演奏したんです。拍子も決めずに即興でやったんですけど、最後は同じタイミングでバッチリ終わりました。
──さすが。
松丸:このインタールードでは、コミュニケーションのヒントみたいなものを表現したかったんですよね。特にコロナ禍で直接会いづらくなり、SNSだったりオンラインで人と接する機会が多くなった。コミュニケーションの形も変わってきているけど、今までの関係性があればこんなふうに対話することもできる。顔が見えなくてもSNSで論破したりお互い意図が掴めなくて誤解し続けるのとは違うプロセスで、もっと有意義なコミュニケーションができるというのを示したかった。これは石若さんとじゃなかったらできなかったと思います。2年間いろんなところで一緒にやってきて、沢山話してきたからできたことです。
──そういった時代性も反映されていると。垂水佳菜監督による「kʲi̥ɕikã̠ɴ」のミュージックビデオでも、登場人物の顔が最後まで映らないですよね。それも今の話と関係ある?
松丸:そうですね。最後まで顔が映らないのは僕のアイディアだったんですけど、今の話を伝えたら編集の仕方などでうまく取り入れてもらえて、短い映像ですけど強い作品になったと思います。ジャケ写を撮ってくださった廣田達也さんとデザインしてくださった村尾雄太さんにも同じようにアルバムコンセプトの説明をしていて、それをベースに撮り方や文字の配置などを考えてくださり、全体的にとても統一性のあるものに仕上がっています。実際手に取って感じてもらいたいですね。
──このアルバムをざっくり括るなら「ジャズ」になるんでしょうけど、それよりはジャンル性に囚われていない、自由で固有の音楽という印象を受けました。
松丸:どこかに括ろうとしても括れないような曲作りをしたかったんですね。もし括る人がいたら、その人は「しっかり聴けてないな」と思えるくらい。新しい音楽を作ろうとなったとき、「融合」みたいな足し算的な発想になりがちだし、引き算と言いながら結局足し算になってるものも多かったりする。足し算引き算って言葉も嫌いなんですけど、あえて分かり易く使うとして。このアルバムでもどこまで達成できているのかわからないし、すでに存在するリズムや拍だったりをベースに作曲と即興のアプローチでどうやって結果として聴こえてくるものの印象やその機能を変えていけるか。今回はちょっとずつ変えることによって生まれてくる新しい表現に触れようとする作品が完成した気がします。
──「ハイブリッドな表現だから新しい」というのは、ジャズやそれ以外の音楽でも盛んに言われてきましたよね。「ロバート・グラスパーは、ジャズにヒップホップやR&Bの要素を持ち込んだから新しい」みたいな。もちろん一つの正解ではあるけど、新しさの形はそれだけではない。松丸くんはジャンルの融合とか越境というよりは、すでにある表現をもっと研ぎ澄ましたり、4人でやることの制限とか組み合わせの妙みたいなところから、新しいパースペクティブを見出そうとしているのかなって、今の話を聞いて思いました。
松丸:文脈だけで語ることができない表現をしたいんですよね。「この曲はこういう人から影響を受けているから、ベースやドラムはこうなっていて……」みたいに、バックグラウンドを語るだけで片付く音楽にはしたくない。ただ単にフリーだったらフリー、アンビエントだったらアンビエントというふうに片付けられない演奏の仕方がしたかった。あえて語るのが難しい表現をしたかったし、そのスタンスは常に意識しています。
僕はアイデンティティがわからないんです

──ヌバイア・ガルシアというUKのサックス奏者が、「自分のアイデンティティとリコネクト(再接続)したかった」と語っていて。彼女の母はガイアナ共和国、父はトリニダード・トバゴ共和国の出身で、最新アルバムの『SOURCE』ではアフロ・ディアスポラとして育った自身のルーツと向き合っている。社会の多様化が進むなかで、海外のポップカルチャーでは「アイデンティティ」が近年大きなテーマとなっているし、松丸くんの今回のアルバムもそうだと思う。自分のバックグラウンドと向き合うことについては、改めてどんなことを思いますか?
松丸:僕はアイデンティティがわからないんですよ。日本で育っていたならそこがルーツになるし、パプアに実家があったりしたらそれがルーツだと言えるけど、僕は1歳の時に日本を出て、それからずっと「外の人」なんです。「外の人」が3歳から高校卒業までパプアに住んで、その間も他の国に住んだりを繰り返していたので、バークリー卒業の直前まで自分のなかに葛藤がありました。胸を張ってどこかに属していると言える事に憧れる時もありましたが、でもそうではないのが自分のアイデンティティなんだと気づいて、そこからはそれを受け入れるようになりました。もちろん今まで住んできた場所、特にパプアニューギニアは自分の中で大切にしています。アイデンティティとの向き合い方に関しては歳を重ねる毎に少しずつ変化していったりもすると思います。
──「アイデンティティがわからない」ということが自分のアイデンティティであると。
松丸:そうですね。日本に来てからの2年間ではそういう気持ちで活動しています。だから、音楽でもそういう表現がしたいのかもしれない。僕だから表現できるものはそこにあるんじゃないかなと。
──最後に、このアルバムをどんなふうに聴いてもらいたいですか。
松丸:こうやって話してきたことも意識しながら聴いてほしいですね。アルバムのタイトルを直訳すると「太陽のもとで語られていないことはない」となるけど、英語としてコンプリートな文章ではないので、「語られていないことは残されていない」とも「語られていないことはなくても、知られていない・聞かれていないことはある」とも捉えられる。それと同じように、アルバム全体もオープンな解釈ができるようにしたつもりなので、このタイトルがどんな意味を持っていて、なぜこういう曲順になっているのか考えてほしい。ただ聴いて完結するのではなく、聴いた人のクリエイティブな何かに繋がればいいなと思います。
『Nothing Unspoken Under The Sun』のご購入はこちらから
LIVE SCHEDULE
2020年11月26日(火)
at 公園通りクラシックス
(sold out)
2021年1月8日(金)
at 新宿PIT INN 夜の部
詳細はこちら
PROFILE
松丸 契

サックス奏者。1995年千葉生まれ。パプアニューギニア出身。2014年に全額奨学金でバークリー音楽大学に入学、2018年に首席で卒業。2017年度ヤマハ音楽奨学生に選ばれ、2018年に第47回Downbeat Competitionで自身のトリオ・オリジナル曲で全米1位を獲得するなど権威ある賞を多数受賞。2019年にデビューアルバム『THINKKAISM』をリリース。ドラマー石若駿率いるバンド「SMTK」では2019年に東京ジャズフェスティバルやTOKYO LAB等の企画に参加し、2020年の春に1st EPと1stアルバムを続けて発表。2020年11月に自身のカルテットでの新作『Nothing Unspoken Under the Sun』をリリース。現在都内を中心に様々な場で活動中。
■公式HP
https://www.keimatsumaru.com/bands-projects
■公式ツイッター
https://twitter.com/keimatsumaru
■Instagram
https://www.instagram.com/kmatsumaru/