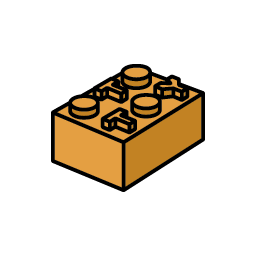平均年齢20代前半というから、全員MUTE BEATが活動していた時期に生まれた世代。東京のレゲエ、ダブ・バンドのなかでも最若手の部類に入るであろうTam Tamのファースト・アルバム『Come Dung Basie』は、ルーツ・レゲエ、ダブの伝統に囚われることなく瑞々しい音楽世界を構築した力作となった。そこにはメンバーそれぞれの多様なバックボーンと新世代ならではの自由奔放さがあり、東京のレゲエ、ダブ・シーンの未来を感じさせる力強さがある。今回は5人のメンバーのうち、黒田さとみ(ヴォーカル)、小林樹音(ベース)、高橋朋之(ドラムス)の3人にインタヴュー。加えて、彼らをサポートしているレーベル、maoの主宰者であり、Tam TamのライヴPAも務めている石本聡にも参加してもらった。取材場所は中野の沖縄料理屋。鍋をつつきながら、ゆったりと取材は進められた。
インタヴュー & 文 : 大石 始
平均年齢22歳の新世代DUBバンドに刮目せよ
Tam Tam / Come Dung Basie
音楽への愛を高らかに歌いあげる黒田さとみのボーカルとバックのステッパーズリディムが絶妙のコンビネーションを見せ、一気に彼等の世界へ引きこまれること間違いなし。スカ調にアレンジされたレゲエ・クラシック「None Shall Escape from the room」でジャマイカへの愛を表明し、ボーナス・トラックとなる2曲のDUBWISEチューンへ突入。石本聡によるヴィンテージ・テープ・エコーやスプリング・リバーブを多用したKing TubbyマナーのDUBが炸裂し、浮遊感漂う余韻を残しエンディングを迎える。
古くさい音楽ばかり聞いてました
——まず、それぞれのリスナーとしての音楽遍歴を教えてほしいんだけど。
小林樹音(以下、小) : ベースを始めたのは大学からなんですけど、それまではクラブ・ミュージックとかヒップ・ホップを聴いてました。大学で入ったサークルがレゲエやスカ好きが集まる中南米研究会だったんで、ベースを弾き始めたのはそれからですね。
——高校の頃は何を聴いてたの?
小 : デトロイト・テクノやイギリスのワープの音源とか。ヒップ・ホップはニンジャ・チューンとかビッグ・ダダ、そのあたりですね。その頃からAUDIO ACTIVEとかクラブ・ミュージック流れのダブを聴いてたので、大学に入ってからはワケの分からないまま「ダブをやりたい! 」って思うようになって。ダブの未来的な部分がデトロイト・テクノと繋がる感覚があったんで、そこからルーツとしてのダブ盤を聴くようになりました。
高橋朋之(以下、高) : 高校時代は吹奏楽部に入ってたんですけど、高校3年の時に新宿のピットインに行ってフリー・ジャズを聴くようになったんです。その頃からインプロとかノイズをやるようになって、友達とノイズ・イヴェントにも出てたんですよね。同時にTHINK TANKを聴きはじめて。それで(THINK TANKが主催しているパーティー)「エル・ニーニョ」に遊びに行ったら、THE HEAVYMANNERSが出てたんですよ。そのライヴを観て「これだったら僕のやりたいこともできるな」と思ったんです。フリー・ジャズの反社会的なところに惹かれてた僕にはしっくりきたんでしょうね。それで中南米研究会に入ろうと。

——高校の時にやってたノイズ・ユニットはどんな感じだったんですか。
高 : シンバルの上にモノを置いてみたり、スネアの上にお金を広げて叩いてみたり、そういうことを延々やってました。僕のなかでダブとそういうものが繋がってる感覚があったんですよ。
——黒田さんは?
黒田さとみ(以下、黒) : 私は10歳上のお兄さんがいるんですけど、東京でラッパーをやってたんですよ。その兄の影響でソウル、ファンク、ヒップ・ホップ、R&Bあたりを広く浅く聴いてて。あと、私は北海道が地元なんですけど、地元のラジオ局でレゲエのコーナーがあったんですね。中学生の頃、ちょうどショーン・ポール(とサーシャ)の「I'm Still In Love With You」が流行ってて、それから元ネタのアルトン・エリスが好きになって。それ以降はルーツとかロックステディ、ラヴァーズ、スカばかりを買うようになった感じですね。MUTE BEATとかDRY&HEAVYを聴き出したのは高校卒業するぐらいの頃。それまでは古くさい音源ばかり聴いてました。
——北海道にいた頃は歌ってなかった?
黒 : カラオケに行くぐらい。中学生の時に一番好きな歌い手は都はるみでした(笑)。
全員 : 渋い(笑)。
——で、みんな大学のサークルで出会ったわけだけど、バンドを結成するにあたってどんなものをやろうと思ってたの?
黒 : なんだろう? 「ダブをやりたい」っていうのはあったと思いますけど。
小 : まずは黒ちゃんとバンドをやろうって話になったんですよね。黒ちゃん、最初はトランペットを吹いてたんですけど、「私、歌が歌いたい」って言いはじめてね。
黒 : そうだっけ?
小 : そうそう。お互い好きなものも分かってたし… ま、勢いですよね。「レゲエやりたいね、ダブやりたいね」っていう。
——同じような趣味の人が周囲にいたっていうのもレアな気がするんだけど。
小 : それはありますね。
高 : 僕はダブが好きでサークルに入ろうと思ったんですけど、最初は「どうせチャラチャラしてるんだろうな」と思ってたんですよ(笑)。
——だって、それまではノイズを聴いてたんだもんね(笑)。
高 : しかも部室もオシャレだし… それで部室に入ってみたら、そこにいた部員がMUTE BEATの曲を練習してたんですよ。しかもPAで音をトバしてて。
黒 : 私も最初はスカ・バンドをやりたくて、大学の外でメンバー募集をチェックしてたんですよ。そうしたら、だいたい4、50代、若くても30代。そのなかにひとつだけ平均年齢が20代のバンドがあって、最初はそこでトランペットを吹いてたんです。そうしたら、そのバンドの人にサークルを紹介されて。サークルに入ってみたら、いきなり『ラフンタフ』の話ができたから嬉しくて…。
小 : オレもサークルに入ったのが(コンピ)『Studio 1 Ska』を聴いてた時期だったんで、サークルの人とスタジオワンの話ができた時に「話が通じる人がいる! 」っていう喜びがありましたね。
——じゃ、それぞれにディープな音楽話をできる仲間ができたという喜びがあったわけだ。
小 : そうですね。ウチら3人は大学が違うんですけど、サークルが大学関係なく入れるところだったんで、ヘンなものを好きな人たちが集まってたんですよね。
不自然なのが1番よくないから
——で、Tam Tamが結成されたのはいつになるの?
小 : 2008年の12月ですね。最初はダブ色が薄くて、今よりもルーツ、ロックステディ寄りでしたね。
高 : カヴァーしてたのはそのへんの曲でしたね。ただ、僕がノイズ時代に買ってたカオスパッドを導入したあたりから変わってきて…。
小 : そうそう(笑)。最初は「ダブをやりたいけど専属PAに入ってもらうのは厳しいよね」っていうこともあって、彼(高橋)がドラムにカオスパッドをかけたりしてたんですよ。

——えっ、どうやってたの?
高 : 横にカオスパッドを置いて、スネアだけにかけてました。
石本聡(mao/以下、石) : 凄いんですよ。叩きながら自分でカオスパッドかけてたっていう。
——最初のレパートリーはカヴァー・オンリー?
黒 : オリジナルもやってましたけど、カヴァーもいろいろやりました。ジェイコブ・ミラーとかソウル・シンジケートとか…。
小 : オーガスタス・パブロ、ホレス・アンディ、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズとか。Tam Tamを結成する前から、サークルのなかではずっとルーツを演奏してたんですよ。だからルーツの定番曲はだいたい演奏してますね。アビシニアンズの「Satta Masagana」とかジュニア・マーヴィンの「Police & Thieves」とか。レゲエのキモであるドラム&ベースとしては、レゲエ特有のノリを出す難しさを感じたこともあったんじゃない?
小 : どうも自分のなかでは「レゲエっぽさ」というものが漠然としすぎてて… それは今も分からないですね。特有のノリというか。
高 : DRY&HEAVYって、レゲエを今っぽく表現していたと思うんですよ。ジャマイカっぽいノリの、訛ってる感じのレゲエっぽさがあるとすれば、そういうものじゃないレゲエの形があるっていうことをDRY&HEAVYからは感じましたね。そういうものをやってもいいんだと思えるようになったし。それと、スライ&ロビーも今の時代まで引き寄せてくれるモダンさがあると思う。
——オリジナルはどうやって作り始めた?
小 : 一番最初に作ったのが、今回のCDの1曲目に入ってる「RIDDIM」なんですよ。黒ちゃんがMDか何かにベース・ラインを入れてきて、歌詞を僕が書いたんですよ。友達に英訳してもらいながらね。
——他の曲も歌詞は樹音くんが書いてる?
小 : いや、最初は黒ちゃんが「歌詞は書けない! 」って公言してたんで(笑)。今は普通に書いてますけどね。
黒 : 歌詞を書くのが恥ずかしかったんですよ。それと、私は温室育ちだと思うんで(笑)、社会に対する鬱々とした感情ってあんまりないんです。だから、何を書けばいいのか分からなかった。何よりも、ジャマイカのレゲエの歌詞って、どうも私の普段の生活とフィットしないところがあって… 最初の頃は「そこから離れるとレゲエじゃないのかな? 」みたいな葛藤はありましたね。でも、今は関係ないと思ってます。不自然なのが一番良くないから。ルーツ・レゲエが持つ精神性よりも、ザラザラとした肌触りに惹かれてたのかな。
黒 : そうですね。昔はあんまりピカピカした音だとダメだったんです。古いもの好きだったんですよ、ヒップ・ホップにしてもオールド・スクールが好きだったし。日本のものでもマヒナスターズとか江利チエミが好きで。
——あ、歌い方に少し影響あるかも。夜の匂いがするところが。
黒 : (笑)
——いずれにせよ、レゲエの精神性を突き詰めたところでやっているわけじゃないっていうことだよね。
高 : ラスタのことについては本を読んで知ってるんですけど、もともと好きだったものがラスタ感のないものだったんですよね。THE HEAVYMANNERSとかREBEL FAMILIAとか。僕の場合、音楽的な構造の部分に惹かれてたんで。
小 : 僕自身は精神性のほうが強いですね。もともとデトロイト・テクノとかが好きだったんで… ただ、ラスタの思想そのものを信奉してるというわけじゃなくて、脳内変換で東京という場所に置き換える、そういう感覚。バビロン・システムというものをデトロイト・テクノ的に置き換えるというか。
黒 : 私にしてもそういう精神性を毛嫌いしてるわけじゃないし、本も読んでますけど、それをそのまま自分でやるのは不自然だと思うんです。
石 : 不自然だからという理由で、盲目的にラスタを信奉してないところが彼らのいいところだと思うんですよ。
——石本さんが最初に彼らのライヴを観たのは?
石 : 去年の8月末ですかね。その前に僕が出ていたイヴェントに遊びに来てくれて、デモをくれたんですよ。それを聴いてみたらすごく良くて。まず、歌に惹かれましたね。その次にリズム隊。デモって最初の1分聴けばだいたい分かるんですよ。Tam Tamの場合、デモを聴いた瞬間にライヴを観たくなりましたね。
——ただ、単なるDRY&HEAVYのフォロワーだったら反応しなかったわけですよね。
石 : そうですね。ライヴを観た時、まずは「この人たちはレゲエ原理主義者じゃないんだな」と思ったんですよ。自分自身そうだし、共通する匂いみたいなものを感じたんですね。で、話してみたらやっぱりそうで。
——じゃあ、Tam TamのライヴPAをやるようになったのはいつ頃からだったんですか。
石 : 去年の10月ぐらいからかな。彼らは演奏がしっかりしてるから、(ダブを)乗せやすい。それと「ここでこうくるよね」っていう共通認識があるから、やってても楽しいんですよ。
小 : ダブPAはずっと欲しかったんですけど、ハコとの関係性もあってなかなかできなくて。そんななかで石本さんがやっていただけるようになって…。
黒 : 最初に石本さんとやった時はハコの人に怒られたんですよ。「ベース出しすぎだよ」って(笑)。
石 : オレはゲラゲラ笑ってたんですけどね。「これがレゲエですから」って(笑)。

——なるほどね…。とりあえず泡盛いきます?
石 : そうですね、ボトルでいっちゃいましょうか。
(しばし全員分の泡盛を制作、分配)
黒 : 昔はヘンにルーツに固執してたのかもしれない。ホレス・アンディとかジェイコブ・ミラーを目指して録音してたから、どうも自分の声の軽さが気になっちゃって。でも、今はいい意味でルーツをやる限界を実感してて、「自分なりのルーツをやればいいんだ」と思えるようになりました。
石 : 黒ちゃんはルーツに対するリスペクトが強いんだろうね。
黒 : そうですね、メチャクチャありますね。だから、最初の頃はジレンマがありました。
——今回のアルバムを聴いていると、それぞれのジレンマを吹っ切ったところで作ってる感じがするんだよな。いい意味で悩んでないというか。日本人がレゲエをやるうえで誰もが抱えるであろう葛藤みたいなものが、このアルバムからは感じられない。
小 : ジャマイカやルーツに対する愛っていうのは個人個人で持ってると思うんですけど、それに固執はしない。それは世代もあると思うし、これまで各自でいろんな音楽を聴いてきたから、ごく自然にミクスチャーになってるんですよ。
黒 : キーボードの川村(知未)はラテンを聴いてきたし、ギターの笠間(涼央)はプログレッシヴ・ロックがルーツだったりして、曲を作るにしても全員持ち寄る要素が違っていて面白いんですよ。
ややこしさがなくて、無邪気にやっている
——今回の収録曲は、ライヴでやってきたものが多い?
小 : そうですね。なおかつライヴの感じをそのまま録ろうと。
——「None Shall Escape From The Room」はレゲエの定番リディム「None Shall Escape The Judgement」のリメイクだよね。
小 : この曲は結構前からやってますね。
黒 : Tam Tamのなかで「リディムものをやりたいね」っていう時期があったんですよ。で、ネットにリディムをいくつかアップして、その中からみんなでセレクトしました。
小 : レゲエの定番リディムをやるのは楽しいんですよ。
黒 : いい意味で予定調和というか。演奏する側も歌う側も楽しいんですよね。
小 : 日々のライヴでもちょっとやってるんですよ。少しダンス・ホール・マナーというか。半分勉強、半分遊びっていう感じですね。
——「長い雨」は収録曲中唯一の日本語詞で。
小 : これは僕が書きました。…東京って寂しくないですか?
——えっ、そうかな?
小 : 僕は長崎が地元なんですけど、どうもそういう感覚があって。この曲ではその感じを盛り込みました。日本語の歌詞って、やっぱりお客さんに伝わりやすいんですよね。それで「ちょっと日本語の曲をやってみよう」と。

——この曲、黒田さんのムード歌謡好きがちょっと入ってる気がする。
黒 : そうですか? 私からすると、昔のムード歌謡ってコミカルに聴こえるところもあるんですよね。言葉遊びみたいなところもあって。この曲はあえてそうしようと思ってたわけじゃないんですけどね。
石 : マイナーのコード進行がジャマイカっぽくないのかもね。ベース・ラインがムード歌謡ぽいというか。
小 : でも、それも無意識なんですけどねえ。
——でもさ、「この曲はムード歌謡ぽくしようぜ」ってやったらサムイわけでしょ?
全員 : あ〜(笑)。
——知識がつきすぎると、音楽をやるややこしさみたいなものが出てくると思うんですよ。でも、Tam Tamはそういうややこしさがなくて、無邪気にやってる。そこがいいと思うんだよな。
石 : そこが若さだし、いいところですよね。
——あと、今回は石本さんの強烈なダブも入ってますよね。もう、やりたい放題で(笑)。
石 : (笑)。今回のアルバムに関しては、僕のなかで「ルーツぽい作品にしたい」と思ってて、それでルーツ・マナーのダブをやろうと。僕はそういうものしかできないんで(笑)、キング・タビーみたいなダブをやりました。
黒 : ダブの現場はかなり刺激的でしたね。
小 : スプリング・リヴァーブを持ち上げて落としてみたり。
石 : そういうことをやると喜ぶんですよ(笑)。今までもそういうダブはやってたんですけど、Tam Tamほどしっくりくるバンドはなかった。だからね、僕もすごく楽しませてもらってますよ。倍以上歳が違うのに。
——いいなあ、僕もバンドをやりたくなってきたな。
全員 : やりましょうよ!
RECOMMEND
microshot / 『ECHO SATELLITES』
ルーツ・レゲエに敬意を表しつつも都会的でクールな質感を醸し出すサウンドで、日本のレゲエ・シーンにおいて独自のポジションを築き上げている、インスト・レゲエ、ライヴ・ダブ・バンドmicroshotが、3年ぶりとなる新作『ECHO SATELLITES』をHQDで配信中です!!
V.A / 『ambrosia DUBWISE』
11組のアーティストによるダブワイズ・アルバム『ambrosia DUBWISE』インスト・レゲエ、ダブ・バンドmicroshotが、 6月にアルバム『ECHO SATELLITES』をリリース。それに合わせてアルバム収録曲「ambrosia」のダブワイズ・コンテストを実施し、ダブワイズ・アルバム『ambrosia DUBWISE』を完成させた! 元CULTIVATORのベーシストsahnty nob、自身のバンドMASやツジコノリコへのトラック提供でも有名なTyme.、自身のレーベル術の穴の運営や、トラック・メイカーとしても最重要アーティストであるfragment、d.v.d.やトクマルシューゴ・バンドでも存在感を放つイトケンの作品を収録。
microshot×こだま和文×石本聡(mao)によるDUB座談会の様子はこちらから
LIVE information
「GuruGuru」
2月19日@中津 Vi-code
出演 : AFNICA、OCTAVIO、YANEKA、soco soco
Bar Live : guitar noiz orchest、ASAYAKE01
異空間演出 : コタケマン
Candle Lighting : match poin
「Come Dung Basie Release Party」
2月25日@青山 月見ル君想フ
出演 : Soul Dimension 、アラゲホンジ、pasadena with poundhip upsetters
PROFILE
2008年12月結成。メンバーは黒田さとみ(vo,tr)、小林樹音(ba)、高橋朋之(dr)、笠間涼央(gu)、川村知未(ke)からなる5人組新世代DUBバンド。ダイナミクス溢れるソウル・フルなボーカルを軸に、強力なリディムセクションがボトムを支え、ギター、キーボードが彩りを添えるバンド・サウンドは、メンバーの年齢からは想像できない完成度をほこり、レゲエを土台にしつつそこにクラブ・ミュージックの良質なエッセンスを注入した音楽性も相まって、ライヴ・ハウスで対バンとなるレゲエ・バンドのみならず、ロック・バンドからも熱い支持を受けている。2010年5月に制作したオリジナル2曲、リミックス3曲入の自主制作CDRが局地的に話題となり、噂を聞きつけた「あらかじめ決められた恋人たちへ」や「World’s end girlfriend」のライブ・ダブPAもつとめる、maoレーベルのオーナー石本聡がライブを見に行き一目惚れ。自ら志願しPAを担当するなどレーベルをあげて全面的にバック・アップしはじめる。