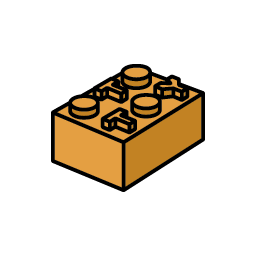活動15周年を迎えるGRAPEVINEの過去作14アルバムのレビュー
2012年にデビュー15周年を迎え、9月19日にキャリア初のベスト・アルバムをリリースするGRAPEVINE。特設ページでは、ベスト・アルバムに収録したい曲を、全ての過去作から選曲出来る「魂の選曲」を開催。この企画に合わせて、OTOTOYでは過去14アルバムをレビューで紹介。歴史を振り返ると共に、全曲試聴もスタートします。デビュー・アルバム『覚醒』から、新作『MISOGI』まで、GRAPEVINEを大解剖! 一緒にGRAPEVINEの活動15周年をお祝いしましょう!

アルバム・レビューを大公開!
『覚醒』1997.9.19
GRAPEVINEの作品目録はここから始まる。ミニ・アルバムでのデビューというのは当時としては珍しい。それは主流だった8cmシングルでも12cmシングルでもない形でメジャーの世界に飛び込みたいというメンバーの意向だった。つまりそのキャリアのスタート地点からGRAPEVINEの作品にはある種の反抗的意図が込められている。だが、もしあなたがこのアルバムからそのような反抗を感じ取れなかったとしたら、それは完全に正しい。ここには天邪鬼に奇をてらってやろうとする音楽はひとつも収められていない。むしろあまりにも素直に歌われた歌だけがある。甘ったるいボーカルの背後には隠しきれないセンチメンタリズムがあり、ザラついたギターの背後には驚くほどウェットな感受性が見え隠れする。だけど、それが最高に心地いい。まだはっきりと形をとっていないGRAPEVINE的世界のプロトタイプ。この作品にはそんな若い感性が凝縮されている。(text by アンドレ川島)
『退屈の花』1998.5.20
関西からやってきた4人組の初フル・アルバムである本作は、的確に彼等の魅力を伝えている。冒頭の「鳥」に顕著な、英語的な発音を意識して子音を強調する田中和将の歌を最初に聴いた時、かつて大瀧詠一や桑田圭祐が”発明”したものに続く新しい日本語唱法と思ったものだ。またマーヴィン・ゲイの曲からバンド名をつけただけに、ロックやR&Bへのこだわりを感じさせる骨太な演奏が、甘めのヴォーカルを中和して好バランスだ。4人とも曲を作るのも、メロディ・歌詞の両面でバンドの輪郭を大きくしている。インディーズ時代から好評で先行シングルになった「そら」「君を待つ間」をはじめ、洋楽好きらしいメロディと、読書家の田中らしい厚みのある歌詞が、このバンド独特のニュアンスを醸し出している。矢野顕子の「ひとつだけ」へのアンサー・ソングめいた「I&MORE」や最後の隠しトラックなど、遊び心にも初作らしい意気込みが伺えて今も初々しい。(text by 今井智子)
『Lifetime』1999.5.19
先行シングル「白日」「スロウ」のヒットも牽引力となって、彼等の人気を不動のものにした2作目。根岸孝旨をプロデュースに迎えての録音は、シングル曲では落ち着いたバンド・サウンドを生かしながら弦や鍵盤を加えて華を添え、一方「SUN」などでは歪んだギターやベースでオルタナティヴ色を出して起伏のある流れを作っている。曲のヴァリエーションも豊富だ。あらきゆうこが打楽器で参加しているインスト2部作「RUBBERGIRL」、田中がブルースハープも披露する「25」、金延幸子のカヴァー「青い魚」、アンプラグドな演奏の「大人」など、自分たちの振れ幅を試しているよう。まるで耐久テストのような流れに、『Lifetime』というアルバム・タイトルが納得できるというものだ。「一生」「生涯」であり、「有効期間」といった意味でもあるこの言葉を、田中が選んだのもうなづける。バンドの可能性が広がり覚悟が決まった作品だったのだろう。(text by 今井智子)
『Here』2000.3.15
2作目からの上昇気流に乗っている、密度を感じさせる作品。前作から8ヶ月で完成させた加速っぷりは、詞・曲にも演奏にもありありと織り込まれている。どの曲もザックリしながらブレはなく、ついて来れるなら来いと言わんばかりの確信に満ちているのだ。シンプルな演奏で歌を生かす「想うということ」を幕開けに、伏せ字が思わせぶりなスロー・ナンバー「ダイヤグラム」からシニカルな視線をアップテンポで拡散させる「Scare」、足踏みオルガンが鳴る「ポートレート」にファルセットで歌う「コーヒー付」。「リトル・ガール・トリートメント」から、この半年前シングルで出た「羽根」、タイトル曲「here」とスケール感のある展開に。だがここで終わっちゃ恰好良すぎると言いたげに、いなたい「南行き」で締めるところが、このバンドらしい。何気ないジャケット写真だが、後に西原が脱退するため4人揃ってのものはこれが最後となった。(text by 今井智子)
『Circulator』2001.8.1
西原が病気の治療中で、先行シングル「ふれていたい」など3曲を除きプロデューサーの根岸がベースを担当。そうした状況のためかシリアスな空気漂う作品である。田中がの作曲も増えて曲のバリエーションが増えたこともあるのだろうが、打ち込みを使うなど新基軸も取り入れつつ試行錯誤しているような緊張感がある。そのためか、ビートルズ中期を連想する、コンセプチュアルな手応えの作品になった。怒りや虚無感が漂う曲から癒しのサイケデリックなブルースへと誘う曲たちを、プロローグ風の「Buster Bluster」と最後の「I found the girl」がコーラスで繋がり包み込む。作品自体が循環しているイメージで、アルバム・タイトルのデザインに∞が入っているのがわかるというものだ。スリーブにある3人だけの写真は寂しそうだが、自分たちは止まらない、という切実な覚悟が本作には込められているように思える。(text by 今井智子)
『another sky』2002.11.20
病気療養のために一時バンドを離脱していたベーシストの西原誠が本作で復帰。そして結果的にはこれが西原の在籍時では最後の作品となった。このバンドのリーダーであり、同時にコンポーザーとしても大きな役割を担っていた彼の不在を受け止めて臨んだ前作『Circulator』を経たことも手伝ったのか、改めてこのバンド本来の親密なアンサンブルに立ち返ったような、清々しくもスリリングな演奏を堪能できる快作だ。また、前作のツアー時からサポート・キーボードを務めていた元benzoの高野勲がレコーディングにも参加するようになったというのも本作の大きなトピックだろう。バンドがそれまでのソリッドな演奏から、よりきめ細やかなバンド・アンサンブルへと移行し、彼らが最大の影響源としているアメリカン・ルーツ・ミュージック的な土臭い音作りをさらに突き詰めていくまでの過渡期を捉えた、現体制の伏線と言えるようなアルバムでもある。(text by 渡辺裕也)

『イデアの水槽』2003.12.3
冒頭の「豚の皿」が放つボディ・ソニックでいきなり圧倒される。西原の脱退によって3人になった彼らは、サポート・メンバーとして高野勲と金戸覚を迎え入れた5人編成でのアンサンブル構築に腐心し、ライヴで得た成果をそのままダイレクトな形で落とし込むことに挑戦。初のセルフ・プロデュースにして、洗練に向かうよりも先にバンドの高いテンションを反映させることを選んで完成させた本作は、まさに新生GRAPEVINEの誕生を告げる会心の一撃となった。特に田中の作詞作曲による「11%MISTAKE」から始まる後半からの展開は白眉で、ミニマルな骨組みの楽曲を音の抜き差しによってゆったりとビルドアップさせていくアンサンブルからは、バンドが次のステップに駆け上がったことを否応なしに痛感させられる。骨の太いグルーヴから空間をねじるようなサイケデリア、そして田中のリリックにいたるまで、とにかく全編にわたってヘヴィな感触と深い余韻を残す作品だ。(text by 渡辺裕也)
『Everyman,everywhere』2004.11.17
GRAPEVINEはこれまでに3枚のミニ・アルバムを発表しているが、それらはとても象徴的なタイミングでリリースされている。1枚目の「覚醒」は1997年のデビュー作として。3枚目の『MISOGI EP』はデビュー15周年となる2012年の最新作として。そして2枚目のミニ・アルバムである本作『Everyman,everywhere』はその中間地点にあたる2004年に発表されているのだ。そんな『Everyman,everywhere』は、15年にわたるGRAPEVINEのキャリアのヘソに位置する作品として、きわめて重要なアルバムと言えるだろう。特徴的な歌い方や言葉遊びのスタイルが確立された一方で、ウェットでドラマチックな感性は驚くほどデビュー当時から変わっていない。つまり、このアルバムはGRAPEVINEの過去と現在とを結ぶ橋として機能している。ここに彼らのキャリアを読み解くカギが隠されていると言ったら、それは大げさすぎるだろうか。(text by アンドレ川島)
『déraciné』2005.8.24
この年の彼らはスキマスイッチやつじあやのといった、音楽的にはあまり接点が見えないアーティストの作品への客演などにも果敢に挑んでいたが、そうしたトライアルは彼らのアーシーなサウンドが国内ポップ・シーンにおいて如何に特異なものかをわかりやすく浮かび上がらせてもいた。ミニ・アルバムを挟んで完成させた本作は、これまでになく性急なビートでひっぱる「その未来」や、くぐもったカントリー「スカイライン」の印象も強いが、むしろ作品の肝となっているのは、砂埃を巻き上げるようなグルーヴと嗚咽のようなスライド・ギターを聴かせる「KINGDOM COME」や、デルタ・ブルーズにおける孤高の天才ロバート・ジョンソンをモチーフとした「GRAVEYARD」のような、漆黒のブルーズ・ナンバーだろう。もともとニヒルな性格を持つ彼らは、ここにきてさらにその倦怠と厭世観を強めていく。尚、本作から始まった長田進によるプロデュースは『真昼のストレンジランド』まで続いている。(text by 渡辺裕也)
『From a smalltown』2007.3.7
短いスパンで新作を発表するだけでなく、そのたびに何かしらの新機軸を打ち立ててきた彼らは、ここにきてまたしてもバンドの可能性を押し広げる挑戦に打って出た。過去最長の制作期間を設けて臨んだ本作で、彼らは初めてメンバー5人のセッションによる楽曲制作に着手している。果たして完成した作品は、これまでのキャリアで培った強靭なアンサンブルをこれでもかと見せつけるような楽曲から、控えめなリズムとアンビエントな音像の中で内省を深めていくミドル・チューン、はたまたシティ・ポップ風の粋なオルガンまでもが聴こえてくるという、バラエティ豊かな作風となった。あくまでも自分たちのルーツには従順でありながら、マンネリ化一切なしで常にバンドをフレッシュな状態に保っていけるこのバンドの強さを垣間見るような1枚だ。マイ・ペースなようでいてどこまでも野心的な彼らは、またしても未来を切り開いた。(text by 渡辺裕也)
『Sing』 2008.6.18
「芸術としてのロック」について語る時、きっと私は黙ってこのアルバムを手渡すだろう。メジャー・デビュー10周年を飾る『From a smalltown』から1年。彼らが積み重ねてきた経験と、半世紀以上かけて育まれてきたロックのワード・ローブは、『Sing』という傑作として実を結んだ。幻想的なサウンドと神秘的な言葉が空間を満たす「Sing」ではじまり、指さばきや息遣いまで鮮明に映し出した「Wants」で終わる12曲。レディオヘッドのような実験精神とオアシスのような大衆性を兼ね備えた彼らは、夢の世界から現実の世界へと続くグラデーションを、アルバム全体を使って緻密、かつ大胆に描ききった。また、各曲にパンク・ロックやポスト・ロックなどの要素を埋め込み、アルバムに自然な起伏を与えている点も見逃せない。本作は『サージェント・ペパーズ』や『ペット・サウンズ』と同列で語るべき、ロックの金字塔である。(text by 高野裕介)
『TWANGS』2009.7.15
楽曲、演奏技術、アルバム構成、その全てにおいてロックの臨界点に到達した『Sing』から1年。本作が世に送りだされる間に、彼らはSWSXのステージに立ち、ニューヨーク公演を実現するなど、さらなる高みへと踏み出していた。だが、そんな彼らによる『TWANGS』が描いたのは、意外にも「ロックの原点」だった。セッションを通して生み出された、飾らないメロディとダイナミックなアレンジ。その上で、今まで以上に鮮烈な言葉を放つ田中和将からは、ステージの上で生き生きと振る舞う姿が容易にイメージできる。一方、サイケデリック・ロックやプログレッシブ・ロックの要素をさりげなく盛り込んだり、ストーリー性の強い歌詞や英語詞、弾き語りといった今までのイメージを打ち破る手法でさえ、違和感なくアルバムに組み込む姿からは、初期衝動を巧みに操る老練さも垣間見える。「彼らのライヴにいきたい! 」そう思わせるアルバムである。(text by 高野裕介)
『真夏のストレンジランド』2011.1.19
「オリジナル・アルバムなのにベスト・アルバムのように楽しめる」。2011年に発売されたアルバム『真夏のストレンジランド』に僕が抱いた感想は、この一言に尽きる。ポスト・ロック、リズム&ブルース、スワンプ・ロックにグランジ。様々な音楽を吸収、咀嚼してきた彼らだからこそできる、個性豊かなサウンド。そこに、田中和将による物語性の高い歌詞が加わり、それぞれの楽曲はまるでシングル曲のように明快な独自性を確立している。また、各曲はメンバー、プロデューサーらによって何度も練り直され、個性を保ちながら「GRAPEVINEの音楽」として「一枚のアルバム」として、違和感なく楽しめるよう磨き上げられている。陽気さの中に一抹の哀愁を秘めた「真昼の子供たち」や、野外フェスが似合いそうな壮大さが魅力の「風の歌」を聞くと、「日本語っていいなあ」「ロックっていいなあ」と改めて感じる。そんな説得力が彼らにはあるのだ。(text by 高野裕介)
『MISOGI』2012.2.15
ここがGRAPEVINEの最先端だ。ギターへの絶対的な信頼から出発した彼らの音楽は、いまやピアノ、シンセサイザー、打ち込み音などのあらゆる響きを呑みこんで精密な音楽機械と化した。絶妙な言葉遊び、シンプルなようでいて計算し尽くされた展開、一筋縄ではいかないギターソロなど、ここにはGRAPEVINEの妙技がこれでもかと示されている。だが、それらのひとつひとつに意識を向ける前に、まずはアルバム全体を貫くグルーヴに身をまかせてほしい。徹底してドライなサウンドは職人を思わせるが、一方で核心には熱いヴァイタリティを宿しているのが感じられるはずだ。デビュー15周年という節目の年に発表された本作。たった6曲きりのミニ・アルバムではあるが、そこにはGRAPEVINEの15年が集大成されていると言っても過言ではない。思えば彼らのデビュー作もミニ・アルバムだった。その意味では、GRAPEVINEが踏み出した新たな一歩として本作を理解することも決して間違ってはいないだろう。(text by アンドレ川島)
LIVE INFORMATION
GRAPEVINE 15th ANNIVERSARY LIVE
2012年9月19日(水)@大阪・NHKホール
2012年9月26日(水)@渋谷・NHKホール
PROFLE
GRAPEVINE
1993年から大阪で活動を開始する。
結成メンバーは田中和将(Vo/Gt) 西川弘剛(Gt) 西原誠(Ba) 亀井亨(Dr) 。
Marvin Gayeの「I heard it through the grapevine」からバンド名を名づける。
セルフ・リリースのカセット・テープが話題となり、1997年にポニー・キャニオンと契約。
1997年9月、ミニ・アルバム『覚醒』でデビュー。
2002年に西原誠が脱退し、金戸覚(Ba)、高野勲(Key)がメンバーに加わる。
現在までに12枚のフル・アルバムをリリース。2011年には長田進氏をプロデューサーにむかえたアルバム『真昼のストレンジランド』をリリース。
2012年9月には、ベスト・アルバムを発売予定。