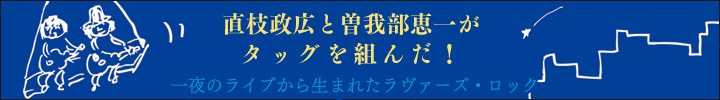
夢のタッグが実現! 直枝政広&曽我部恵一からの今年最後の贈り物
直枝政広&曽我部恵一『流星』
作詞・作曲 : 曽我部恵一
演奏 : 直枝政広&曽我部恵一
プロデュース : 直枝政広(カーネーション)
Comments
曽我部くんの「流星」弾き語りデモはレゲェ調のカッティングだった。
だからこのリズムは必然。
お客さんたちの前で歌ってからスタートする曲、
そういうのはきっと長持ちすると思うんだ。
音の組み立てがすんなり終わって、夏の終わりに会って
「真冬にスウィートなレゲェを出したい」と話をして、いまここ。
昨日も今日も、ああだこうだと歌や気分をちょこちょこ送信しあっている。
この歌う二人組、今後も夜中に「あのレコード好きでしょ」と会話を交わすような感じで
ゆったりと続くといいなと思っている。(直枝政広)
直枝さんと真冬の夜空で待ち合わせ。
とろけるソウルをクールなレゲエにたっぷりかけて
クリスマスパーティの始まりです。(曽我部恵一)
ちょうど1年前に『Velvet Velvet』が見事オトトイ・アウォードに選ばれた、カーネーションの直枝政広。そして今年、サニーデイ・サービスで10年ぶりの新作をリリース、ソロとしても「サマー・シンフォニー」のフリー・ダウンロード、そこから間髪いれずに弾き語りアルバム『けいちゃん』をリリースと、まさに今年の顔役と呼ぶにふさわしい活躍を見せた曽我部恵一。なんとこの二人がタッグを組みました。オトトイがお届けする、今年最後にして最大のビッグ・サプライズはこれです。
結成のきっかけは今年の9月11日、恵比寿リキッドルームで行われたカーネーション主催イヴェント『Eternal September』でのこと。曽我部恵一ランデヴー・バンドとして、11人というかつてない大所帯で登場した曽我部は、最後に直枝をステージに招き、この日のために書いてきたという新曲を二人だけで歌った。この「流星」という曲は、そもそもリリースの予定も何もなかったが、後日来場者からの関する問い合わせが殺到し、ついにレコーディングが決定。夢にも思わなかった両者の共演は、同時に好運にもこの日リキッドルームで聴くことが出来た方々にとっては、まさに待望の音源化だったはず。
そういうわけで、ちょうど流星群がピークを迎えた翌日に、両者をお呼びしました。直枝さん曰く、共に「厄介な乙女座」であるこの二人。どうやら親交が深いどころか、昔から他人の気がしなかったのだそうで。話は1年を振り返るところから、気がつけばお互いの作詞作曲論に。是非、今年最高のクリスマス・プレゼント「流星」と共に、二人の会話を楽しんでください。
インタビュー&文 : 渡辺裕也
INTERVIEW
——今オトトイでは年間アウォードを決める投票が行われているところなんです。曽我部さんの『けいちゃん』もノミネートされていますよ。
S : いいですよ、ノミネートさせなくて(笑)。僕はこっそりやってるんだから、競争させないでください(笑)。
——もう発表しちゃったんで(笑)。で、昨年投票で選ばれたのが、カーネーションの『Velvet Velvet』だったんです。
S : あ、あれはユーザーの投票で決まったんだ? すごいな。カーネーションって他にも何かの賞もらってませんでしたっけ?
N : もらったことないよ(笑)。そういうのとは一切無縁だったから、嬉しかったよ。
S : いいなー。クリスタルの楯ですよね。
——(笑)。よく知ってますね。
N : (笑)。そういうの、けっこう気にするの?
S : それはカーネーションのツイッターで見たから知ってたんですけど、雑誌とかの年間ベストはかなり細かくチェックしますよ。でも、ああいうのってだいたいどこも評価が揃っちゃうじゃないですか。軒並み好評価みたいなのを見ると、いつも疑問に思うんだよな。もっとそれぞれの評価があっていいと思うんだけど。
——ではお二人から見て、今年を象徴する作品はなんだったと思いますか。
N : ファンクラブの会報に自分の年間ベストを書いたんだけど、そこに曽我部くんの12インチは入れたよ。ジャケットも含めて仕上がりが美しかった。もちろん『けいちゃん』もそうだし、曽我部君の出すものは、ひとつひとつにひっかかるものが必ずあるんだよね。
S : ありがとうございます。俺は何かな。PSGはやっぱりよかったですね。
——まず直枝さんに振り返って頂きたいんですが、今年はツアー・ファイナルをユーストリームで生中継したり、ソロ・アルバムの再発があったりと、新作のリリースこそなかったものの、動きの多い1年だったように見えました。
N : そんなに派手な年ではなかったですよ。でも『耳鼻咽喉科』の再結成ライヴと10年前のソロの2枚組のデラックス・エディション『HOPKINS CREEK』を出しました。その中で出来る限りのライヴやツアーをやっている感じでした。曽我部君みたいに動き回ることは出来なかったね。だからもうここで言い切っちゃうけど、来年はカーネーションの新作をリリースします。
——一方の曽我部さんはリリースがたくさんありましたね。
S : 今年はがんばりました。「サマー・シンフォニー」のリリースもあったし、サニーデイでもソロでもアルバムを出した。
——「サマー・シンフォニー」をリリースする段階では、まだソロ・アルバムのレコーディングはやっていないと聞いていたので、まさかあんなに早く完成するとは思いませんでした。

S : 急に決めたからね。おかげで世間からは無反応(笑)。それに、やっぱり弾き語りっていう時点で反応が薄かったんだろうな。
——「サマー・シンフォニー」の反響はものすごかったですよ。
S : イレギュラーな出し方だったしね。12インチも飛ぶように売れたよ。もちろんオリコン・チャートに入るような売れ方ではないんだけど。店頭に出ると一瞬でなくなるっていう現象が起きてた。だから極地的にはすごく売れているんだけど、普通に暮らしている人たちはその存在すら知らないというか。ネットとかで音楽を能動的にチェックしているような人達にはひっかかったみたい。こういう売れ方もあるんだなって思いましたね。
——オトトイに来る人は、やっぱりツイッターをやってる人が多いみたいです。「曽我部恵一の新曲がフリーで」っていう情報がツイッター上で流れると、そこからサイトにバーッと集まってくる感じでした。でも、実はそれも一部の層ではあるんですよね。
S : うん。だから、いろんな販売方法を試してみたいよね。通販限定とか、ライヴ会場のみとか。
——フリー・ダウンロードは実際にやってみてどうでした?
S : 今は1曲あるいはアルバムの価格がもう崩れちゃってるでしょ。例えば最近はフライヤー置き場にデモCD-Rを置いてるバンドもいるよね。つまりあれも0円で配ってるってことだから、じゃあ自分の新曲はいくらなんだろうっていうのが知りたくなったんだ。そこでまず無料で出してみて、そこから数週間後にパッケージでお金を取ると、どれくらいの差が出るのかを見てみたかった。無料っていうのは、パブリシティとしてすごく大きかったですね。そのあとでパッケージを出した時の勢いが半端じゃなかった。普通に新曲を出した時よりもリアクションは大きかったですね。鴨田さん(イルリメ)も夏に自分のサイトで新曲をフリーで配信していたんだけど、彼も僕と同じような発想だったみたい。自分の音楽がどういう風に広がっていくのか実験してみたいっていう気持ちですね。
N : 新しい人達に届いている手応えはあった?
S : ありましたね。「あ、何か新しいことをやろうとしてるんだな」っていうのがうまく伝わったみたいです。今は音楽の売り方に正解がないから、いろんなやり方を模索せざるを得ないんですよね。自分達のような立場からすると特にそうですね。
——一方で、リスナーにはカジュアルに受け取ってほしいということも強く言ってましたよね。
S : だって、俺達の生活や収入のことをリスナーが考える必要はないよね。無料でもらったら悪いとか、思わなくていい。でも、僕はライヴをユーストリームで流すのはあんまりやりたくないんです。お金を払って来てくれた人達との差が付けづらいような気がして。でも、これは考え方にもよるのかな。
N : 僕は投げ銭にすればいいと思ってるんだけどね。それでバランスがとれるんじゃないかな。
S : そうですね。俺はユーストリームに限らず、すべて投げ銭でいいような気がしてます。自分の活動自体がそもそも投げ銭のようなものだし、それがこれからもっと顕著になってくると思う。
——直枝さんは、実際にユーストリーム中継をやった時の手応えはどうでしたか?
N : やってる時の手応えみたいなものは特にないんだけど、ついこの前のツアーでは、珍しいお客さんがきてましたね。「10年ぶりに来ました」みたいな人達が地方で少し増えていました。それはたぶんユーストリームがきっかけだったんじゃないかな。
——ちゃんと窓口になったんですね。
S : でも、ライヴってどうなるかわからないものだから、あまりひとつひとつを残しておきたくはないですよね(笑)。
N : 自分達のライヴ音源なんて、本当はあんまり聴きたくないよ(笑)。奇跡的によかったやつだけを僕らはリリースしてるんだからさ。
S : 今年、トラッシュキャン・シナトラズっていうスコットランドのバンドと東京で一緒にやったんですけど、彼らはその日のライヴ音源を自分達のロゴが刻印されたUSBに入れて、その日の物販で売ってるんです。つまり、ついさっき観たライヴ音源が、その日の帰りに手に入る。ライヴが終わってからUSBに保存するのに多少時間がかかるから、本数は限定らしいんですけど、オープンの時に予約を取るとすぐいっぱいになっちゃうんだって。海外をツアーで回ってる人達はけっこうそのやり方で売り上げをとってるらしいです。「けっこう普通だよ」って言ってましたね。
N : (笑)。それはすごいね。
完璧だと思ったものって、意外とつまらなかったりする
——そういえば、直枝さんはアドミラル・ラドリーのライヴを観に行ったそうですね。
N : うん。よかったよね。でも、それこそ物販でTシャツを買おうと思ったのに変なサイズしかなくてさ(笑)。
S : 僕、そのバンド知らないです。
——元グランダディのメンバーがやってるバンドです。
S : そうなんだ! あの辺りの、派手ではないんだけどいいアメリカのバンドって、日本で紹介していくのが難しいよね。
——今のアメリカって、ちょっと土臭い感じのいいバンドがたくさん出てきているんですけど、その熱がなかなか日本には伝わってこないんですよね。さっきの弾き語りアルバムの反応が薄いっていう話も、そこと関わっているような気がしました。

N : 寂しいね。
S : 俺の場合は出すタイミングがよくなかったっていうのもあると思う。
N : いや、最高のタイミングだったよ。「やられた」っていう感じだった。
S : ヒップホップのトラックを出したあとにトラックのないアルバムを出すっていうのが、自分としてはすごくいい流れだと思ったんです。
N : 僕も弾き語りのアルバム作りたいなと思ったよ。でも弾き語りのアルバムって、実際は作るのにけっこう時間がかかるんだよ。
S : 最初は二日くらいでいけるかなと思ってたんですけどね。
N : やっぱり曲の純度が高くないといけないし、体力だって必要だよね。あと、スタジオに一人で入る時の寂しさが、なんとも言えないんだよね。難しいよ、弾き語りの録音は。
S : 途中で判断基準がわからなくなってくるんですよね。歌詞と歌声とメロディだけで説得力を出さなきゃと思ってやっているうちに「なにやってるんだろう」っていう気持ちになってくる(笑)。でもそういうのがたまにあると、またアレンジがある作業に戻った時に「あ、アレンジってこういうものだったな」って気づいたりもするんですよね。
N : 羨ましいな。僕も作りたいよ。
S : 是非。ていうか、みんな一回は弾き語りのアルバムを作ればいいのに。そういえばこの間、直枝さんの『HOPKINS CREEK』のリマスター盤を聴いたんですけど、最高でしたね。
N : あ、本当? ありがとう(笑)。
S : 直枝さんはその前に本(『宇宙の柳、たましいの下着』)も出してたから。俺からすると、あの本もソロ・アルバムみたいなものでしたね。
N : うれしいな(笑)。それこそ『HOPKINS CREEK』から10年経ったところで、ソロ・アルバムを作りたかったんだけどね。
S : HMVでイベントをやった時に直枝さんにも弾き語りをやってもらったんですけど、それがめっちゃくちゃよかったんですよ。歌はもちろんなんだけど、ギターがすごかった。ドラムとかベースの音がアコギから聴こえてくるようなアレンジで、びっくりしましたね。
——アレンジで思い出したんですけど、直枝さんは「メンバーを選んで誘う=アレンジだ」とおっしゃってましたね。今回の「流星」はどのようにしてアレンジの作業を行ったのですか?
S : トラックは直枝さんがすべて作ってくれました。僕が曲を投げた段階ではただの弾き語りだったので。
N : 曽我部君のアコギのきざみ方がレゲエっぽい雰囲気を出していたから、もう最初からこれはレゲエだなって思ったよ。その時のイベントでも曽我部君のバンドはガレージにロックステディが混ざった感じの演奏をしていたし。だから、曽我部君は最初の段階で既にアレンジしてるんだよ。つまり僕に「レゲエとロックステディ」っていうキーワードを投げたの。それが「流星」を聴いた時のイメージと繋がったんだよね。それでとりあえず僕がトラックを作ってみたんです。
S : (笑)。無意識に発注してたんですね。ライヴで演奏した後に、カーネーションのファンの人達から「リリースしないんですか? 」と言ってもらえたのは嬉しかったですね。
N : 反応がすごくよかったんだよね。
S : 直枝さんの声に合う曲だとは思っていたんですけど、カーネーションのファンに受ける曲だとは思ってなかったんです。カーネーションって、シンプルなものをこんがらがせながらポップにしていくような方法論のバンドだと僕は思ってたんです。でもこれは本当にシンプルでひねりのない曲だから、あまり受けないかなと思ってた。
N : すごく親しみやすいメロディだよね。それって誰もが求めているものだから。それが曽我部君の色っぽい声で歌われたら、もうメロメロですよ(笑)。
——お二人はいつ頃から親しくなったんですか?
N : 93年頃だったっけ? すごいやつがいるっていう話をディレクターから聞いていたんです。
S : 直枝さんが松江潤君のプロデュースをやっていた辺りですよね? 松江君と僕らのディレクターが一緒だったんです。
N : そう。それで僕も気になっていて。あと僕ら誕生日が同じなんだよね。8月26日。
S : 青山陽一さんも同じなんですよね。深夜に車の中で『EDO RIVER』聴いていたのをよく覚えています。あれは衝撃的でしたね。カーネーションのことはもちろん既に知っていたんですけど、もっとポップというか、歌のイメージが強かった。それがスライ(&ザ・ファミリー・ストーン)みたいな感じになってて、もうびっくりしましたね。あのループ感というか、ミニマルなサイケデリック感にはやられました。あんなこと、日本で誰もやってなかったから。
N : 当時はヒップホップにハマってたんだ。それを生演奏でやるっていうコンセプトはあったよ。
S : そのサウンドがバンドにばっちりハマってましたからね。
N : ちょうどバンドの質が変わってきた時期だったしね。
S : 僕は『天国と地獄』と『EDO RIVER』で、一期と二期に分かれているような印象ですね。あそこから今のカーネーションに繋がってきているような気がします。
N : そうだね。2002年にもメンバーが抜けて3人になるっていう変わり目があったんだけど、そこからも8年経って、今また新しいモードに来ているかもしれないですね。
——ではお二人が現在どういうモードなのか教えてください。
S : 僕は今、完全にスランプですね。ソロ・アルバムを作っているところなんですけど、全然曲が出来ない。そういう時期ってありました?
N : (笑)。しょっちゅうあるよ。
——初めてのことなんですか?
S : 毎日デモは作ってるんですけどね。僕はレーベルをやっているから、定期的なリリースが必要なんですよ。ここで台所事情を話すのもなんですけど(笑)。だからちょっと困ってます。納得出来ないんですよ、自分の曲に。
N : つまりそういう時期なんじゃない? 乗り越える時期が来たのはいいことだよ。
S : パソコンのハードディスクに曲のデモがバーッと並んでるんですけど、その中でOKだと思ったタイトルには紫色をつけているんです。その曲を次の日に聴いて、紫色を消すっていう作業を毎日続けてます(笑)。
——以前「ある程度長く音楽を作り続ければ、誰でも及第点はすぐに出せるようになる」とおっしゃっていたので、スランプとは無縁なのかなと思っていました。
S : うん。無意識に及第点を取りに行っちゃってるのかもしれない。だからすごくいい曲だと思ったものも、ただ及第点を超えただけなんじゃないかっていう気がしてきて。マジックを感じないんですよね。直枝さんは、前作を作っている時に作詞ですごく苦労したと言ってましたよね。
N : 僕はいつもホーム・デモが気に入っちゃうんだよね。つまりラララで歌っている状態が一番いい気がしてきちゃうんだ。そうなるともう歌詞がまったく乗らなくてね。曲は5月に作ったのに、歌詞が乗るのは10月とかになる(笑)。喫茶店を何件も回ったり、小旅行に出たりしながら、なんとか風景を捕まえようとしてみたりして、もう死にそうになってますよ。
S : そういう時って探す気満々の状態だから、降りてこないんですよね。女の子をナンパしに行く時と一緒で、ギラギラしたオーラが出過ぎてるとだめなんです(笑)。何でもない時にフッと出てきたりするんですよ。コントロール出来ない。
N : ポロッと出て来るものもあれば、とてつもなく長い時間をかけてもなかなか出来ないものもあるから、焦るんだよね。
S : でも、そのとてつもなく長い時間をかけたものも、ちゃんと完成形に持っていって、作品に入れてるんですよね。それがすごい。それって力技ですよね。
N : (笑)。そうだね。力技だね。
S : 僕はそういうのは諦めちゃう方なんです。これは無理だなと思ったらすぐに紫色を消しちゃうから(笑)。確か直枝さんと同い年の小西(康陽)さんも、ボツ曲がないって言ってましたね。僕は変にナチュラリズムみたいなのを重視しちゃって、力技で作ったものを拒んじゃうところがあるんですよね。いや、そもそも力技までいってないか。「なんとしてもこの1曲を完成させる」っていうスキルが僕にはないんです。だって、ラララで歌ったものって、それで曲が出来ちゃってるんだから、そこに歌詞を無理にはめこむと曲のクオリティが下がってしまうような気がしちゃうんです。だから僕はラララでは作れないんですけど、直枝さんはそれを上げる作業としてやってる。

N : 最初の段階で歌詞を乗せるのが一番なんですよ。でも、そういう時って曲を書くだけで疲れ果てちゃってて、歌詞を書く体力が残ってないんだよ。それで寝ちゃったらもう終わり。その時に30分だけでも頑張って歌詞を書けばよかったのに。そこでやらないから、ラララ地獄にはまっちゃうんだ。あとはデタラメ英語地獄とかね。
S : (笑)。でもそのラララ地獄とか、デタラメ英語地獄にはまった後でちゃんと完成形に持っていく、その方法論を僕は知りたいです。
N : 自分が気に入っているラララの状態を、そのままで聴かせる訳にいかないんだから、最後はもう開き直りだよね。あとは自分が慣れるのを待つ。他の人は歌詞がついた状態で初めてその曲を聴くんだから。
S : 細かい質問で申し訳ないんですけど、それってラララ・バージョンを何回も聴いて風景を見つけてくるんですか? それともまた別のアイデアをはめ込むんですか?
N : 無理矢理はめ込むことの方が多いよ。そこで違和感がでてきたら、捨てることもあるかもしれない。でも、ギリギリでぶら下がっているような状態のものを出す勇気も必要なんだと思う。付け入る隙を与えておくことはじつは悪くないことなんだ。それは何十年か音楽やってきて感じることだね。完璧だと思ったものって、意外とつまらなかったりするんだよね。それより自分でも分からない部分とかいやな部分を残しておくのが大事なのかも。
S : だから前作は直枝イズムみたいなものがあまり濃くなかったんですね。フレッシュなカーネーション・サウンドだと思った。
——では、直枝さんは現在どんなモードなのでしょうか。
N : 今はこの曲の作業が楽しくて、すごくワクワクしながらやってます。その一方で、レコード鬱っていえばいいかな。レコードを買うのがあんまり楽しくない時期かもしれない。最近は定番のボックスとかばっかり出てるじゃない? 中学とか高校時代の思い出に浸るのがこんなに辛いことだったのかっていう感じがあって。
S : あ、じゃあ買ってはいるんですか?
N : 買ってはいるよ。負けたくないからさ。
S : (笑)。誰と戦ってるんですか?
N : わかんないけど、たぶん運命とだね(笑)。だから残金とか考えないで、とにかく買うんだけど、レコード鬱に入っていくと、もうレコード屋に行きたくないし、聴きたくないし、見たくもないっていう状態になるんです。レコード屋に行きにくくなったっていうのは、この10年で変わったことかな。インターネットが便利になったこの時代に、アマゾンからもこれを買いなさいっていうメールがどんどんくるじゃない? そういうのでどんどん気持ちが落ちていくんだよね(笑)。でも、作ってる時は楽しいね。すごく集中出来ている。来年には今回の曲をなんかしらの形でまとめることも考えないとね。小さいアルバムでもいいからさ。
S : そうですね。またお互い何曲か出し合って、作りたいですね。
——ではこのユニットにはまだ続きがあるということですね。
S : そうしたいですね。
N : 焦らずにキャッチボールを続けていきたいよね。
S : 例えばブラジルとかだと、デュオ・アルバムみたいなのがたくさん出るじゃないですか。カエターノと誰か、みたいな。
N : (笑)。ジョルジ・ベンとジルベルト・ジルとかね。
S : そうそう。ああいうのがいいなと思いますね。中には「やらなくてもよかったんじゃないの? 」っていうのもあるんだけど。
N : (笑)。
S : でもそれを出来ること自体がすごく風通しがいいような気がして。ミュージシャン同士で曲作りのやりとりをするのってけっこうやりづらいことだと思うんだけど、俺は直枝さんとだったら出来るんだよね。
N : 昔からよく「他人とは思えない」って周りから言われてたしね(笑)。
S : 誕生日も干支も同じですからね。最終的には二人でジョイント・ライヴをやりたいですね。そこが着地点になったら最高だな。あとはもう、飲みましょう(笑)。
PROFILE
カーネーション
1983年12月耳鼻咽喉科を前身にカーネーション結成。当時からのオリジナル・メンバーは、直枝ひとり。 1984年シングル「夜の煙突」(ナゴム)でレコード・デビュー。以降、数度のメンバー・チェンジを経ながら、時流に消費されることなく、数多くの傑作アルバムをリリース。練りに練られた楽曲、人生の哀楽を鋭く綴った歌詞、演奏力抜群のアンサンブル、圧倒的な歌唱、レコード・ジャンキーとしての博覧強記ぶりなど、その存在意義はあまりに大きい。2008年に結成25周年を迎え、2009年1月、ドラマー矢部浩志が脱退。現メンバーは、直枝政広(Vo.G)と大田譲(B)の2人 に、サポート・ドラマー中原由貴(タマコウォルズ)を迎えて活動している。
曽我部恵一
1971年生まれ。香川県出身。ミュージシャン。<ROSE RECORDS>主宰。ソロだけでなく、ロック・バンド<曽我部恵一BAND>、アコースティック・ユニット<曽我部恵一ランデヴーバンド>、再結成を果たした<サニーデイ・サービス>で活動を展開し、歌うことへの飽くなき追求はとどまることを知らない。プロデュース・ワークにも定評があり、執筆、CM・映画音楽制作やDJなど、その表現範囲は実に多彩。下北沢で生活する三児の父でもあり、カフェ兼レコード店<CITY COUNTRY CITY>のオーナーでもある。
















































































































































































































































































