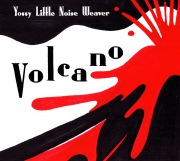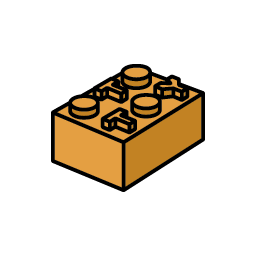世武裕子のセカンド・アルバム『リリー』が到着。本作は、全曲の作詞/作曲を自身で担当したセルフ・プロデュース作品で、ヴォーカル楽曲を中心に収録。レコーディングは、ロック・バンドCHAINSのラリー藤本(Ba)、伊藤拓史(Dr)のリズム隊を迎えた、初のバンド編成。ロック〜民族音楽〜クラシックなど幅広い音楽趣向を見事に昇華したポップ・アルバムの誕生です。ototoyでは、アルバムの発売に先駆けて、収録曲「恋するリリー」を、高音質HQD(24bit/48KHzのWAVファイル)で販売します。軽快なピアノと跳ねるようなヴォーカルが可愛い、春らしい楽曲。購入者には、特典としてオリジナル壁紙をプレゼントします。
購入特典 :
「恋するリリー(HQD ver.)」をご購入いただいた方に、特典のオリジナル壁紙(1920×1200px)をプレゼント。楽曲購入後、こちらのリンクからダウンロードしてください。
世武裕子/ 恋するリリー
2010年3月24日(水)販売開始
1. 風船飛ばす / 2. 市民になる / 3. メトロ / 4. タワー / 5. 恋するリリー / 6. 鳩ぽっぽ / 7. オオカミ少女I / 8. オオカミ少女II / 9. ピエロは踊れなくなったとか / 10. 海 / 11. まぼろしを見た / 12. 航路
INTERVIEW
世武裕子の新作『リリー』が素晴らしい。フランスで映画音楽を学んだ後、2008年に小編成の弦楽器とピアノのみで綴られたデビュー作『おうちはどこ?』を、くるりのレーベルNOISE McCARTNEYから発表、くるりの『魂のゆくえ』のレコーディング、およびアルバムに伴うツアーへの参加を経て発表される『リリー』は、全編歌もののポップ・アルバム。クラシックと民俗音楽を背景に持つ多彩なサウンド・ボキャブラリーが、表情豊かな歌声と映像的な歌詞によって見事にポップ・ミュージックに落とし込まれ、なおかつ作り手の顔がはっきりと伺える、実に理想的な仕上がりになっている。さらに言えば本作は、クラシックやワールド・ミュージックを基盤とした海外の音楽シーンの潮流とも、期せずしてリンクを果たしている作品でもある。そう、意識的にしろ無意識的にしろ、素晴らしい音楽は国境を越えるのだ。2008年ウリチパン郡、2009年ザ・ビーチズ、そして2010年は世武裕子。それぐらいの作品である。
インタビュー&文 : 金子厚武
占い師に「完璧主義過ぎると後々苦しくなりますよ」って
——『リリー』、素晴らしい作品ですね。
ありがとうございます… 褒められるのは苦手なんで(笑)。でも嬉しいです。
——いえいえ(笑)。ではまずアルバムの話の前に、去年の話をしたいんですけど、くるりのアルバムやツアーへの参加は世武さんにとってどんな経験でしたか?
レコーディングに参加させてもらう前にプリプロをやってて、好きなようにやっていい感じだったので、ホントに好きなように、自分が弾くピアノをそのまま弾いたって感じです。洗礼を受けるというか、スタジオ・ミュージシャンみたいに「こうやれ! 」といったことはなく、私はバンドというものを今まで知らないというか、全く関わったことがなかったんですが、特に辛さはなかったです。
——全く?
高校のときにコピー・バンドはやってたんですが、それは置いておいて(笑)。
——ちなみに何をやってたの?
ビーズとかジュディマリのカバー(笑)。人がいなかったんで召集されただけなんですけどね。

——そうなりますよね(笑)。
私はひとり家で黙々と楽譜を作って、ピアノを弾いて曲を書いてきたので、バンドのように一つの場所に集まって、みんなでアレンジメントをするのが「へぇ、なるほど」みたいな。私の中で曲を作るということは、一番最後の作業まで全部一人でやるって感じやったから、違ったやり方で作るんだなって。今回のアルバムをCHAINS(くるりやLimited Express (has gone?)と同じ、立命館大学のサークル、ロック・コミューン出身のバンド。ベースのラリー藤本、ドラムの伊藤拓史が参加)のお二人に手伝ってもらって、少しはその前提が自分の中にできてたから、コミュニケーションをとる時に、あまり自分が「こうやってほしい、ああやってほしい」ってことを… 結局は結構言ったんですけど、性格上(笑)。だけど、こうこうこうで、譜面があってやってください、というやり方とは違うこともやってみたり。まあ、CHAINSのお二人は上手いので、私ばっかり録り直してたんですけど(笑)。
——僕の勝手なイメージで、世武さんみたいに色々できると、完璧主義的なところがあるのかなって思ってたんですけど、やっぱりそう?
占い師に「完璧主義過ぎると後々苦しくなりますよ」って言われました(笑)。あかんと思いながらも、結局すごいこだわってしまうんですよ。PV作るにしても、レコーディングにしても、ジャケット作るにしても、すっごい細かいところが気になるんです。
——じゃあ今回も全部自分でやるっていう選択肢もあったと思うんですけど、バンドと一緒にやることにしたのはなぜですか?
すごい根本的な問題で言えば、ベースとドラムができないっていう。
——弾き語りは考えなかった?
私のピアノも打楽器寄りになりがちだと思うんですけど、とにかく私はパーカッションが好きで、まずはドラムやパーカッションが必要で。選択肢として弾き語りはなかったですね。
——そもそも前作がインストで、今回歌ものにしようと思ったのはなぜ?
日本はインストの土壌がそんなに根強くないので、キチッと音楽家としてやっていくんだったら、歌ってた方がわかりやすいんじゃないかなと思って。決断したときの動機がいつも曖昧なんで、よく覚えてないんですけど…。
スタッフ : ライブの影響もあるかもですね。インストの曲は弦が必要だったりするので、それで歌ものを演奏するようになって、段々シフトしていったっていう。
それです(笑)。
——(笑)。歌ものはチャレンジっていう意識が強い?
そういうわけでもなくて。結構昔に書いて、でも自分の声は好きじゃないから、歌うのは違うなと思って置きっ放しにしていた曲もあるんです。それでライブをやるようになって、「だいたい、自分自身の声って本人は嫌なものだから、そこは気にしないで」というアドバイスをもらった。自分の声は変わらないので、もうちょっとマシにできないかなってことで、ボイス・トレーニングを実践したりしました。
——歌もの自体は結構前から作ってたんですか?
フランスで、ポップスとかゴスペルの子達がいるクラスで歌も習ってたので、その時に作ったりしていました。
——ポップなものを作ろうっていうのは意識的だったの?
私の音楽はわかりにくいと言われることがあるので、自分なりになるべくわかりやすくしています。多分、フランスに留学した経歴とか、1枚目『おうちはどこ?』がインスト作品で、アカデミックに受け取られがちなので、そういう風に言われてたのかなと思っていて。でも『おうちはどこ?』も、音楽を勉強してる人からみれば、そんなにアカデミックなものじゃないと思うんですよね。自分の立ち位置が良くも悪くも中途半端なので、どっち側からもアウト・サイドに見られてしまって、「うーん」というところがあった。それならなるべく自分なりにポップな感じに、みんながわかりやすい歌詞と曲にしてみようと思って書いた曲もあります。
——ポップスとか歌もので影響を受けたり好きだったのってどんなのがありますか?
あまりポップスと呼ばれているものは聴いてなかったです。どちらかといえば洋楽は少し聴いていました。でも、ほとんどは近代音楽、インストばっかり。あと民俗音楽ですね。

——となると、やっぱり日本語の歌ものってチャレンジだったんじゃない?
あまりそういう意識はないんですけどね。「歌もの作るんやったらどんな感じでやろうかな? 」みたいな。自分が「こうしたい」というよりも、「1回やってみよう」的な軽い感じで。
——今は色々なアウト・プットを試してる段階なのかな?
音楽とひとえに言っても、すごくいろんな種類があるので、それぞれに好きなものはあるんですよね。民俗音楽が好きでも、その中で好きなものとそうじゃないものがあるし。だから、どんなものでもやりたいのやろうかなという感じ。あと、自分としては歌ものでもインストでも一緒だと思っていて。どれも自分から自然に出てきているもの。ただ、アレンジのときに、自分の趣味に走ってはいるけど、もうちょっとわかりやすく、ダーク・サイドな方に行かへんようにっていうのは気をつけました(笑)。
——CHAINSのお二人との共同作業であることで、ある程度は委ねることができた?
そうですね。1回プリプロやってみて、二人ともめっちゃ上手かったから、それを使わなかったら損だなと思って… 言い方悪いですけど(笑)。そんな上手い人なのに、誰がやっても一緒だと思われることをやってしまったらもったいないと思ったんです。イトチュウ(伊藤)さんのドラムのジャジーな感じとかカッコいいので、ホントはこういう人と一緒にできるんだったらもっとこういう曲入れたいとか思ったんですけど、全体のバランスを考えました。
——自分の中だけで完結しないっていうのは大きな変化でしょうね。
そうですね。自分の中で「こんな感じかな? 」ということを、誰かが叩いたり弾いたりしてくれると、表現方法が変わってきて、別の可能性もあるという会話は、すごいよかったです。「オオカミ少女1」は、ホントは中近東の感じでやろうと思って「土着の感じ」と言っていたら、Mix直前にラリーさんから「アフリカじゃないの!? 」と言われたりして。「違いますよ! 中近東ですよ! 」となって、だから私がこういう位置にこういう音を入れたがったのか、ようやく相互理解に至りました。イメージの中で踊ってるのが女か男かっていう男女の差っていうのがあった。
——なるほど、その差って面白いですね。あとボーカルなんですけど、さっき自分の声は好きじゃないという話でしたけど、僕はすごくいいと思いました。世武さんは演劇もやられてたから、それで表現力豊かなんだろうなって思ったりもしたんですけど。
一応歌ものアルバムっていうと、歌手の人が歌ってると思うんですけど、私の場合はあくまで自分が歌ってても、それは参加してる一人の誰かとしか捉えてないというか。ベースでやってもらってる、ヴァイオリン1パートの人に来てもらってることと、同じ感じなんですね。だから声も、この曲に声として参加してる感じなので、世武裕子という歌を歌う人ありきの音楽じゃない。そんなことはどうでもよくて、音楽ありきなんです。でも自分の能力以上のことはできないので、その中でなるべくニュアンスなり、ニーズに沿った歌い方をしてもらわないと困るというか(笑)。
——世武さんよりも世武さんが思い描くとおりに歌ってくれる人がいたら、その人に歌ってもらう?
その人の方が全然いいです。
——自分の声であることに対するこだわりっていうのは…?
全くないです。
——そうなんだ。じゃあ言葉はどうですか? 詞は自分の言葉じゃないとダメ?
詞を書くときは、演技をしてるのと同じ感じで書いてるので、例えば曲によっては「いやいや、私全然そんな風に思ってませんけど」ってことも書いてたりするんですね。はじめに主人公を作って、年齢設定して、彼女が今までどうやって生きてきたか、どこの国にいるのか、とか想像して、それを踏まえた上で、彼女の気持ちを書いたり。それは演劇学校にいたときの、そのプロセスが楽しかったからなんですけどね。
——確かに、すごく演劇的なストーリー性を感じるものと、自分の半径5メートル以内を歌ったような歌詞があるなと思ってたんだけど、後者にしてもそれはその曲の主人公の半径5メートルなのか。ちなみに、自分のことを歌ってる曲もある?
うーん、説明が難しいんですけど、私は映画監督になりたかったので(笑)、映画監督的なポジションでやってます。映画監督は自分の映画で表現してるけど、演じてるのは自分じゃなかったり、脚本があったり、いろんな人の手が加わってるじゃないですか。演出をする立場というか。私もそういう感じで、自分が表現したいことをやりたいようにやってるけど、作品の直接的なところは自分じゃないというか。
——なるほど。日本語の歌詞を書くようになったのはいつから?
歌詞は書いてなかったんですが、映画監督になりたかった流れで(笑)、散文詩や脚本を書いたりしていたので、そこから作っていくような感じでしたね。すごい前からあるやつを歌うために直したり。あと「オオカミ少女」は、ひとつの歌詞でいろんな曲を書くという訓練をやっていたら色々できたので、その中の二つをピック・アップしました。
——「市民になる」には寺山修司からの引用があるじゃないですか?
よかった、気づいてもらえて。

——(笑)。文学に対する興味は以前から強いんですか?
音楽は好きなんですけど、「何が好きですか? 」って言われたら、絶対に映画や本だったりします。昔から、登下校の時間ももったいなくて、歩きながら本を読んで先生に注意されたりしてましたし(笑)。
——じゃあ、何度も聞かれてるかもしれないけど、なぜ今は音楽なんでしょう?
例えば高校のときに「映画監督になりたい! どうしよう? 」という気持ちになって、とりあえず映画の何かをやりたいと思ったときに、監督になるにはどうしたらいいかわからないことが多過ぎる。音楽が簡単ということでは全然ないんですけど、昔から音楽をやってたので、映画音楽やったらできるかもしれないという感じで、今の手持ちのカードなら、それが一番できるかなっていう。今回のアルバムも私の中では映画監督をしてるのと同じ感覚でやっているので、ものすごい満たされてるんですよ。
——「メトロ」とか「恋するリリー」とか、すごく映画的ですもんね。描写がすごく細かいけど、ノン・フィクションの部分があったりなんてことはないの?
いや、全然フィクションです。
——ああ、じゃあホントに脚本家的ですね。
こういう子がいてこういう感じで、というように想像するのって楽しいじゃないですか。そういう子を自分の中で動かして、その子が動いてる情景にサウンド・トラックを自分でつけるような。口で言うとすごく暗い作業ですけどね(笑)。
——(笑)。でもそれってすごいですよね。自分で監督・脚本した映画のサントラまで自分でやっちゃうんだから。
ホントは映画音楽がやりたいんですけどね(笑)。
——それは将来的に全然ありうる話だと思いますよ。
がんばります。
そこからの人生は分かれている
——あともう一つ、僕がこのアルバムから感じたのはコスモポリタンな感覚なんですね。前作の『おうちはどこ?』っていうのは、文字通り世武さんのホームっていうのを再確認するアルバムだったと思うんですけど、今回のは滋賀でもフランスでも東京でも、意識次第でどこだってホームになるっていう、それこそ地球に住んでるっていうような、開かれた印象を受けたんです。
ライターの人ってすごいですね(笑)。あんまり深く考えてないんですけど、『おうちはどこ?』っていうのは滋賀県で生きてきた感じがものすごいあるんですよ。実家に住んでいて、学校行ってバイトをしてましたけど、フランスに一人で行ってから、一人暮らしで、自分がやらなきゃどうしようもない。0歳の赤ちゃんと同じ状態というか、良くも悪くもいろんなものを吸収したし、すごくそこで変わったと思っています。あたしの中でそれまでの人生とそこからの人生はちょっと分かれていて、そこからの人生はホントに好きで、すごい大事。それを表に出すにはそれまでのことがちゃんと清算されてないとという思いがあって、1枚目は清算の意味も込めて作ったんです。それ以降は自分の意識のしがらみもなく、自分の好きなようにやっていけばいいという気持ちがあるので、いろんな国のいろんな景色を限定せずに書こうと思っていたんですけど、私の中ではパリにいる自分っぽい音楽なのかなと思うところはあります。
——日本に戻ってきてからも?
日本で活動してるんですけど、パリに行ってからというのは、まだあたしの中でフランスなんです。だから東京にいても、あたしの中ではフランスの方向という感じがありますね。
——今回歌もので日本語詞でバンドとやったことで、この先は見えてきた?

もっと高みを目指したいというか、常に前進したいというか。私が好きな音楽家の天才がいるわけで、たまたまちょっと前にその人が音楽を担当している映画を見たんですけど、「なんでこんな人いるんやろ? 」って思った。自分が音楽やってる意味ないやんって思う位すごいんですけど、自分は自分の持ってるものしかないわけで、その中で作ることを止めたらおしまいだなって。
——ちなみに天才って?
ストラヴィンスキです。
——なるほど。まあでもホント自分の持ってるものでやるしかないですよね。自分の声が好きじゃないってことにしても、その中でいいところを見つけて、あとはライブとかでお客さんの反応とかもらえばまた色々見えてくると思うし。
そういうことを考えつつも、自分の持ってるもののここがいいというわけではなくて、自分は持ってないという諦めが全然まだないので。血の気が荒いだけやと思うんですけど(笑)。欲しいものを手に入れられるように、もっとがんばりたいと思っています。自分の訓練が足りなかったり、努力してるつもりで大してしてやってないんじゃないかと感じるので、そういうところはキチッと、自分に甘くならないように常に気をつけたいと思ってるところです。
——あと今回って弦が入ってないのが気になったんだけど?
1枚目を弦で出して、2枚目を歌もので出したときに、「ああ、やっぱ弦は入ってるわな」と思われたら嫌だったので、わざと入れなったんです(笑)。なんとかして、弦じゃない方向で弦的なことをしようと。1枚目のアカデミックな感じをむやみに引きずりたくなかったし。あと歌ものに弦が入るのはすごい危険なことだと私は思ってるんです。容易に走りがちなところが、映画を見ていてオーケストレーションでファーってなる感じと同じだと思うんですけど、そういう取り扱いが難しい楽器だと思ってるんです。人がどう思うかっていうのはあまり意識してないですけど、弦のことに関しては頭をよぎった(笑)。でも弦の曲はやりたいです。オーケストレーションやりたいですし。
——では最後に、世武さんの表現の根本にあるものを教えてもらえますか?
難しいですね…。何も気にせんと、ホント純粋にあることですかね。例えば友達といるときに、「この人がこの世の中にいるだけですごいよな」ってことに急に感動したりするんですよ。急にこみ上げてきて、「あんたどうしたん? 気持ち悪い」って(笑)。「だってここにいることがすごいよな、ここにいる全員すごいよな」みたいなのがあるんですよ。そういうことを音楽でやってるつもりなので、それをずっとやっていきたいと思います。
PROFILE
せぶひろこ。滋賀生まれ、京都育ち。5歳で初めて曲を書く。02年、音楽を学ぶためにフランスへ渡る。パリ・エコールノルマル音楽院映画音楽作曲科へ入学。在学中、96年公開アカデミー賞受賞作品「イングリッシュ・ペイシェント」のスコアを手掛けたことで有名な作曲家ガブリエル・ヤレドと、ジャン=リュック・ゴダール監督「気狂いピエロ」を手掛けた作曲家アントワーヌ・ドュアメルと知り合い、その作曲能力 に賞賛を得る。民族音楽への造詣も深い世武はモロッコ、アイルランドへ数週間渡り、民族音楽を学んだ。05年、同校を首席で卒業、活動拠点を東京へと移し、作曲活動を開始。08年、デビュー・アルバムとなる『おうちはどこ? 』をNMRよりリリース。各所で高い評価を得て、いまも尚ロング・セールス記録中。09年、くるり8th Album『魂のゆくえ』や全国ツアーに、鍵盤/コーラスとして帯同。10月に発売した、『くるり鶏びゅ〜と』に東京を弾き歌いで参加。10年3月、ボーカル曲をメインとしたアルバム『リリー』を発表。
鍵盤の音色が織り成すメロディ
Gnossiennes No.1,2 live 09.12.25 / keiichiro shibuya
2009年12月25日(金)、26日(土)にラフォーレ・ミュージアムで行われた渋谷慶一郎によるピアノ・ソロ・ライヴ「for maria concert version Keiichiro Shibuya playing piano solo」のライヴ音源シリーズ第6弾。エリック・サティ「Gnossiennes No.1,2」のカバー。繊細な感性に満ちたしなやかなメロディが、東洋的な響きを生み出し、静かに繰り返される。クリスマスに行われた演奏から配信されるこの楽曲は、会場の熱気と緊張が入り交じる空気感までを忠実に再現した演奏になっています。
VOLCANO / Yossy little noise weaver
キーボーディストYOSSY(ex. BUSH OF GHOSTS、DETERMINATIONS)が、トロンボーンicchie(ex. BUSH OF GHOSTS、DETERMINATIONS)と共に開始したユニット。2005年に1st.アルバム『PRECIOUS FEEL』、2007年にスパイラル・レコードfarloveより2枚目のアルバム『WOVEN』をリリース。様々な「今」を感じる音要素を組み合わせ、ドリーミーでダンサブルな音世界を描き出す。バンド編成でのライブでは、強力なメンバーによるダイナミズムが加わり、YOSSYもファニーに歌いまくり、HAPPYなサウンドを展開しています。
THIS IS MUSIC / 大橋トリオ
2008年7月に発売された2ndアルバム。前作の音楽性を踏襲しながらも、エレクトロニカやヒップ・ホップなどの貪欲に新しいスタイルも取り入れ、更に洗練された楽曲を丹念に作り上げた作品。アルバム全体が大人のための絵本のような雰囲気をもった、心穏やかになる名盤です。