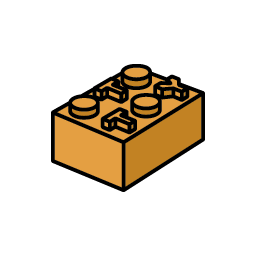待望のニュー・アルバム『23区S』からフリー・ダウンロード配信開始
大都会東京のど真ん中に、Sを付けるだけで、とても曖昧で捉えどころのないイメージが生まれてしまう。擦れ違う人の顔なんて、いちいち覚えちゃいないけれど、なんだか視線が釘付けになる瞬間も都会には溢れている。VIDEOは、USオルタナティヴを始めとした中毒性の高い音楽を大量に摂取し、消化した結果、溢れ出てくる音と言葉で、そんな都会の景色を描き出す。耳から脳内へと浸食してくる『23区S』の景色の数々は、捉えどころがないのだけれど、何故か素通りすることができない。大谷學は、それをエッジだと言い、違和感だと言う。そして、それはきっと、この『23区S』がポップ・ミュージックであることの証だ。
VIDEOの大谷學、柴田学そして、今作のリリース元のNICE-RECORDSを主宰するTOKYOHELLOZの加藤淳也とのインタビューもまた、こちらの期待や想像をあっさりと飛び越えていく瞬間の連続だった。捉えどころのない、しかし、飽きることのない時間をまとめながら、違和感を抱えたまま、また『23区S』を再生している。
インタビュー&文 : 佐々木健治
>>>フリー・ダウンロード曲「illmatic chance」はこちらから(10/06~10/13迄)
東京24区。ニュー・タウン的オルタナティヴ!!
VIDEO / 23区S
【Tlack List】
01. ー / 02. BROKEN / 03. free time / 04. Transport / 05. shubiduba / 06. SLOWMOTION / 07. illmatic chance / 08. 屋上/夜 / 09. ペガサスフォーメーション / 10. FURRYS
ラップ・ユニットWEEKENDのラッパーとしても活躍するフロントマンの大谷學の独創的すぎるリリックと歌声に、盟友達のアンサンブルが絡み付く。名も無いニュー・タウンで新しいアルバムはいつの間にか育まれた。混沌とした虚無感と、無関心が氾濫する既成事実との訣別。
ちゃんとお客さんに届くように(加藤)
——まずは、VIDEOが始まったのはいつですか?
大谷學(Gt、Vo/以下、大谷) : 19歳の頃に、根岸達朗(B)と別のバンドをやっていたんですが、そこにギターとドラムが入ることになって、VIDEOという名前にしようと決めたんです。その二人は今のメンバーではないんですけど、しばらくしたら、そのギターが抜けてしまった。それで、3人になった時期に、TOKYOHELLOZの加藤君と出会ったんです。それで、下北沢のリハーサル・スタジオを使ったスタジオ・ライヴ・イベントや、西麻布のラウンジ、下北沢のWEDGE(現THREE)を使ったパーティをマンスリーでやるようになって。
加藤淳也(以下、加藤) : それが全部で50ヶ月くらい続いて。最初は、僕がライヴ・ハウスで働いていた時に、共通の知人の紹介で、VIDEOっていう変なバンドがいるから、デモ・テープを聴いてあげてよと言われて。ある日、メンバーの誰かが、カセット・テープを持ってきたんです。もうCDRの時代なのに、カセット・テープ(笑)。
大谷 : そうそう。
加藤 : デモ・テープの段階では、店長や他のスタッフは首を傾げていたんですが、僕は絶対にこのバンドはかっこよくなると思ってて。日本人離れした部分もあったし。それで、一回観てみたくて、自分でイベントを組んだのがきっかけです。自分たちでシーンを作ってシーン全体でVIDEOを盛り上げていこうという気持ちになって。周りの仲の良いバンドも巻き込んで、全部で50ヶ月。その間にNICE-RECORDSというレーベルを自分たちで立ち上げてCDRで音源を出したり、前作の『CAMPFIRE』を流通させたり。メンバーの入れ替えもありつつね。
大谷 : うち、ドラマーがもう5回変わってるんですよ。
——これまでのメンバーの名前が全部書いてあるWEBページを何かで見つけたんですけど、確かに、ドラムの方がやたらと多かったですね(笑)。
大谷 : (笑)。今回も、前作から2年半経っているんですけど、ドラムだけが変わってますね。

——ドラムが変わってしまう理由は?
大谷 : 何なんですかね。辞めさせたとかは、一回もないんですよ。でも、自ら辞めていくんですよね。それぞれ、人生の転機がたまたま重なることが多かったのもあります。
——ちなみに、柴田さんはいつ頃入ったんですか?
柴田学(Gt/以下、柴田) : 『CAMPFIRE』の一年半前くらいですかね。
加藤 : 柴田君もそのイベントに別のバンドで出てもらっていたんですよね。
大谷 : 輪で選んでいたというか、知り合いとか、友達に入ってもらうんですよ。本当に即戦力の人が入っても、話ができない方が問題になっちゃうし。逆に、下手な人でも、長いことやればうまくなるから。
——(笑)
大谷 : でも、今考えると、最初の頃は、周りが盛り上げようとしてくれているのに、バンドを真剣にやっていなかったですね。自分に責任感がなかったんでしょうね。今のドラムは、音楽以外でも、何をやるべきかという社会性を持っているから(笑)。
加藤 : 倫理とかね。
大谷 : 僕なんかはあんまりないというか、社会的になりたいと思うけど、分かってなかった。
加藤 : 本当に今のメンバーになってから、変わってきた感じはあるんですよ。ちゃんとお客さんに届くようにやろうとしている。ドラムの村上真実が真剣にそこを考えるタイプだしね。例えば、ライヴ・ハウスに行って、友達を作って、ネットワークを作るというか。そこで挨拶をして、じゃあ、次は何か一緒にやろうみたいな、そういう波には何年間かずっと乗っていなかった。自分たちの手が届く範囲だけで小さくまとまってやってた。
大谷 : そうだね。前は、他のバンドがどうやっているか、全く分かっていなかったからね。あれは、バックが付いているから売れるんだよとか言ってね。バックを付けるまでに何をやっているかを、全く分かってない(笑)。
柴田 : 最近、ようやくそこが分かるようになってきたよね。
大谷 : いやらしいとか、うまいとか、全部込みでこうやると、自然と人と繋がれるんだと。そこを全く理解していなかった。
加藤 : でも、今の五人になって、CDも出して、やっぱり一人一人の生活もあるし、年も重ねてきた時に、そういうところと関わることで届く人も見えてきて。好きと言ってくれる人も増えてきて、メンバーもモチベーションがあがっていって。だから、そういう人たちに届けるという意味でも、ライヴ・ハウスのようなスペース大事がなんだということが分かってきたというか。
大谷 : 今、まさにそうだよね。外に開く為の動きになってきたのかもしれないですね。ドラムの村上が、「知らない人に向けて、ちゃんとやった方がいいよ」とか言ってくれるから。でも、最初の頃は、僕個人が、その意味は分かるけど、そういうことをやる気になれなくて。それでも、周りが引っ張ってくれて、そういう動き方をして、初めての人の前でライヴをやって「いいじゃん」という反応があると、やっぱりやる気になるというか。… 当たり前なんでしょうけど(笑)。
——(笑)
大谷 : それに気づくのに、何年かかってんだという(笑)。
——新鮮でした?
大谷 : 新鮮でしたね。バンドとか、音楽のことしかやっていないから。そこを何か「よくないね」とか言われると、異様に落ち込むんですよ。それ以外の、人間性だ何だってことをどう言われても別に落ち込まないんですよ。でも、音楽は真剣にやっていることだから、それが怖かったんでしょうね(笑)。自信がなかったんですよ。それに、あくまで、自分のペースを守ることが大事だったし。
——なるほど。
大谷 : でも、その中でも広げるように活動をしてみて、徐々に反応も出てくると、前よりはいいかなと。10年目にして、バンドを始めた最初の2、3年で皆がやるようなことをやっている(笑)。
加藤 : 若いバンドが最初に頑張ることを10年目にしてやってる(笑)。自然といいと言ってくれる人も増えてきて、いい感じの人たちが周りに集まってきたよね。
大谷 : そうだね。うん、人としても開くようになりました。
一同爆笑
——じゃあ、『23区S』は、バンドとしても人としても開いた上でのアルバムなんですね。
大谷 : 間違いなく、開いた。それが何でかって言うと、今のメンバーで固定できたことが一番でかいかもね。これまでは一番長くて、1年半とかだったから、革命的と言ってもいいくらいのことですよね。
加藤 : ツアーとか、遠征もやったし、結束も強くなったよね。
大谷 : うん。バンドになった。
加藤 : 10年かかって(笑)。でも、本当に、今のメンバーは黄金比というか。たまに喧嘩もするし、すべてが順風満帆というわけでもない感じもね。

——バンドとしてあるべきことがある?
加藤 : そうですね。2、3年目のバンドが感じていることをちゃんと感じている(笑)。
大谷 : だから、今回の作品も成長記録というか(笑)。
加藤 : いや、本当にそうだよね。
——ずっと付き合ってきた加藤さんから見て、今の大谷さんはどうですか?
加藤 : よくも悪くもエッジはなくなったかな。出会った頃の初期衝動的にかっこいいと思った時のエッジが凄まじかったから。カセットで音が割れて、ブーストしまくっていてもOKというか。とにかく歌詞もサウンドも衝撃だったから。
大谷 : そう?
加藤 : 今は、綺麗に録ろうとか、挨拶しようとかね、それはそれで(笑)。
大谷 : ああ。でも、それはそれで何か嫌だなあ。
加藤 : でも所々に変わらず鋭い部分もちゃんと残ってるから、その魅力が、両方共存しているアルバムなんじゃないでしょうかね。
大谷 : 俺はエッジあると思うけどな。
加藤 : うん、あるんだよ。ルーツとか言葉選びとかは、変わらない部分だしね。
——じゃあ、今回のアルバムでエッジあるだろ! と大谷さんが言うとしたら、どんなところ?
大谷 : そもそも、エッジが何かって話にもなるけど… 例えば、どこでもいいですけど、この部屋で流すとか、友達に聴かせるでもいいんですけど。何というか、ちゃんと聴いちゃうのがエッジかなと思っていて。邪魔な人もいるんですよ。このアルバムが嫌いな人も絶対にいるんですよ。好きな人もいるだろうし。どちらにしろ、BGMには絶対にならない。無理矢理でも気になるものを作っているから、それがエッジかな。
——なるほど。それでは、今回のアルバムのコンセプトは?
大谷 : 前作は、僕ありきだったんです。だから、今回はバンドでやろうと。バンドの合わさり方、バンドのメンバーがいる意味がちゃんとある。バンドありきで、そこに歌をのせるみたいな。アンサンブルというか。この2年くらいバンドで作ってきた思い出、歴史。2年間のスケッチみたいな作品にしたかった。だから、今回は、俺はこうやりたいから、無理矢理こうやってくださいというのはあんまりなかったと思う。
柴田 : 前のアルバムの時は、本当に大谷君が「これやって、これやって」という感じだったんです。練習とか無しで、いきなり録りっていうのが多かったしね。
大谷 : 当日、アレンジ決めたり(笑)。
柴田 : (笑)。今回はそれがなかったから。ちゃんとスタジオに入って、アレンジも決めて練習して、レコスタに行くぞみたいな感じがあったよね。練習したしね。
大谷 : バンドとして見られたかったんですよ。前作も、評判は良かったですけど、ソロっぽいんです。でも、やってみて思ったのは、ソロっぽいことは5人も率いてやることじゃない。
——そうでしょうね(笑)。
大谷 : (笑)。バンドは、細かい楽しみがあるじゃないですか。グルーヴとかね。そこに気づき始めた。
加藤 : 本当にバンドが最初に気づくようなことをようやく(笑)。
大谷 : 本当、そうだよね(笑)。ギターがうまくなる喜びとかね。
一同爆笑
——え、今までなかったの?
大谷 : なかったですね(笑)。音作りとか考えたことなかったですよ。
加藤 : だから、ちゃんと録音したからこそ浮き彫りになったエッジみたいなものは今回あるんですよ。言葉が聞き取りやすくなって気づく世界観の危なさとか、世界観を広げる為のギターがちゃんと鳴っていて、ボトムもしっかりあって。そういう部分は前作よりは再現できている。
大谷 : 人によっては聴きやすいとか普通に感じるかもしれないけど、冷静に考えたら、なかなかないアンサンブルになっている。フォーマットが違うから、分かりにくいかもしれないけど。他のバンドとはやり口が違うんですよ。
——それはどういう意味?
大谷 : ライヴ仕様じゃないんですよ。分かりやすい上げとか、最後こうなってとか、そういうのがなくて。再生ボタンを押したら、曲が始まって、終わって音が止まって、次の曲が始まる。ベタなことも取り入れているんですけどね。何だろう。売れる為の展開じゃないというか。曲にとって必要な展開をバンドでやっている感じなんです。
——ああ、なるほど。
大谷 : サビがあって、Aメロ、Bメロ、サビみたいな。そこに自分のセンスだけを付けて曲として完結させる。それが、一番分かりやすいし、個性も出やすいんでしょうけど。それ以外の部分で、一瞬こういう音を入れた方が楽しいとか、細かいことをやっていると思うんですよね。伝え方が難しいな。
「とりあえず行っちゃう」みたいのが好き(大谷)
——でも、曲の作りにしても、感触にしても、近いのはUSオルタナ、インディの作法というか。まず聴いて、ルー・バロウとか思い浮かんだから。
大谷 : ああ、そうですね。ルー・バロウはめちゃくちゃ好きですね。うん。そういう話で言うと、『23区S』には着想があって。スフィアン・スティーヴンスが、ディスカヴァー・アメリカって、アメリカの50州全部のアルバムを作ると『イリノイ』というアルバムを出して。『イリノイ』の前にも一枚別の州の名前(『ミシガン』)で出しているんですけど。その後、ブルックリンの高速をテーマにしたインスト『BQE』を作ったんです。で、その頃にTraks Boysのcrystalさんが、『Made In Japan "Future" Classics』というMIXを出したんですよ。そのジャケットが、郊外の音楽キッズがずっと音楽を聴いて、窓を開けたらこんな景色だったみたいな。そういう感じが、ここ2年くらいずっと好きで。作家性が強すぎない、景色を描くというか。バンドでやっているけど、唯一僕が個人的にこの『23区S』に投影できるコンセプトはそういうものです。俺の話を聞けみたいなものじゃなくて… 今時、あんまりないか。
——ハハハハ。
大谷 : フロントマンが一人前に立って、カリスマになってみたいなことを俺がやろうとしても、持続しない。そういうことじゃなくて、作品として表出させるとしたら都市とか場所。それで、自分はここ2年くらい23区で遊んで、ライヴをして、思い出があるから。BGMにはならないだろうし、具体的にどうというわけじゃないんですけど。今日は板橋区を音にしてみましたというものでもないし。
——うん(笑)。
大谷 : 僕らが見ている23区というより、もう一枚フィルターが入っている、外国の人から見た23区みたいなイメージですかね。今回は結局、深いところまで行けなかったんですけど、何となく都会の人の空気が出ればいいなと。都会が全部かっこいいなんてことはないと思うし、ある程度ダサい部分も出ていると思う。都会を生活圏にしている人間の音楽になっているんじゃないかな。ホテルニュートーキョーの『トーキョー アブストラクト スケーター ep』とかのストリート感。自分も、そういうストリート感が微量に出るなと思っている。
——ストリート感が出るのはどうして?
大谷 : VIDEOは、こういう音楽をやりたいとか、ロックンロールをやろうぜ!みたいなルーツがあって集まったバンドではないから。人がいて、集まって、思うところがあって、ギターが弾きたくて、そういう下からの立ち上がりで曲が出来てくるから。そうなると、絶対にどんな形でもストリート感は出てくると思っているんです。
——大谷さんの言葉選びやメロディへの言葉の乗せ方って、独特ですよね。
大谷 : でも、今回は言葉もあまり立ちすぎない方がいいのかなと。ちょっと油断すると立ちすぎてしまいますから。バンドとしても、あんまり誰かが立っているとかもないんじゃないかなと思うんですよ。
加藤 : でも言葉は変と言われているよ。いい意味で。
大谷 : そうだよね。でも、僕は言葉をコントロールできてないんですよ。
——出るに任せている?
大谷 : 出るに任せて、後から削って、削ると意味が分からないから、そもそもここで伝えたい空気をぜんぜん違う言葉で書き直すみたいな。「illmatic chance」「Transport」は、曲のオケを(柴田)学君が作ってきたんですよ。それにメロディを付けて、歌をのっけるのは苦労しましたね。ぜんぜんできなくて。
柴田 : 悩んでたよね(笑)。
大谷 : それって、ある意味、職業作曲に近いじゃないですか?
——まあ、そうですね。
大谷 : そんなことできるのかなと思って。でも、何とか着地はしたという感じ(笑)。
柴田 : 大谷君は、追いつめられても、最終的にはどうにかするのがいいよね。最終日にどうにかする(笑)。
大谷 : 恥かきたくないから(笑)。そんだけかもしれない。
——今まで、そういうことはやったことなかった?
大谷 : なかったですね。そんな作り方がありえるのかと思っていましたからね。ラップだったら、メロディを考えなくても、ノリ、空気をつかんで、言いたいことをラップすればいいけど。そのトラックに当てはまるメロディが全然立ち上がってこないから難しかった。でも、職業作曲の本とか見たら、負けな気がして。
加藤 : まあ、でもその2曲がいいけどね。
大谷 : そう(笑)? レーベル・オーナー曰く、そうらしいです。新機軸(笑)。

——加藤さんは、この『23区S』をどう捉えていますか?
加藤 : 前作『CAMPFIRE』は、売れなさそうだったけど、感度の良いやつは絶対ひっかかる。気持ち悪くて、かっこいい。万人に広がるものではないけど、キャッチできるやつはキャッチできる。でも、今回はいろんな人に気持ちいいと思ってもらえるんじゃないかな。違和感も残しつつだからセンスある人は中毒起こす。
——その違和感というのは、具体的にどういうものだと思います?
大谷 : うーん… 違和感… 。何にしても違和感があった方がいいとは思っていますね。気になるということだから。でも、気になる理由がはっきりしない方が好きなんです。例えば、派手だから気になるとかそういうことじゃなくてね。「これは美味しいから食べたい、好きだ」じゃなくて、「何でなのかは分からないけれど、とりあえず行っちゃう」みたいなのが好きなんです。
——曖昧な方がいいんだ。ピントが合いすぎているのは苦手?
大谷 : あ、それはそれでいいんですよ。だけど、興味が持続しない。
——なるほど。
大谷 : おもしろい人がいて、その人が芸人ならそりゃ面白いじゃないですか。でも、友達とか知り合いだと、「何だろう? 」と気になるじゃないですか。僕らの音楽も、そういう音楽かもしれないですね。
柴田 : 例えば「ここが聞きどころです」みたいな、楽しみ方が限定された娯楽ではなくて、幅広い楽しみ方ができる娯楽になっていると思いますね。
大谷 : ここをこう聴いて欲しいとかじゃないよね。逆に、アルバム全体を聴いて、どんな楽しみ方があったか、教えてほしいですよね(笑)。とりあえず、曖昧さとか、違和感みたいなものをこれからも濃くしていきたいですね。そうすれば、一つの特徴になるんじゃないかと。そうして、モノリス調の物体みたいな、何だかわからないけど、とりあえず気になるというものができていけばいいなと思いますよね。でも、その上で、たまたま売れたとかは嬉しいですけどね。ラッキー・パターンみたいなのは、甘んじて受け入れます(笑)。

——大歓迎なんだ(笑)。
大谷 : そこは、本当に楽しみですよね。そういうことがあったら、嬉しいなと(笑)。
——今後の予定は決まっていますか?
柴田 : とりあえず、10月、11月はライヴはたくさんありますね。
加藤 : 『23区S』のリリースもあるし、VIDEOを中心に、TOKYOHELLOZとしてまた面白そうなイベントをどんどんやっていきたいですね。この間、透明雑誌(台湾のバンド)を日本に呼んで久しぶりにイベントをやったんですけど、いろいろ思い出したというか、大好評で、またやろうと心の底から思いました。
大谷 : あとは… 海外に行きたいね。上海とか、台湾とかシアトルでもいいし。
柴田 : ここで、USツアーとか言えないところがあれだよね(笑)。
加藤 : まあ、日本でも、全国各地いろいろと東京以外に行きたいですね。CD聴いて、少しでもいいと思ったら、呼んで欲しいですね。
大谷 : 生まれてからほとんど東京らへんにしかいないんですよ。地方も、ツアーで行ったところがほとんどだし。海外も行ったことないから。それでいいのかなと思っていて… いっぱい移動して、いろいろな所に行った方が、人としてはいいんだろうなと、最近思っていますね。… 胡散臭い学生みたいなこと言ってるな(笑)。
一同爆笑
大谷 : 世界に目を向けてやっていきたいと思っています(笑)。
RECOMMEND
遂にthai kick murphがその全貌を現す! 都内を中心に活動を続け、その類まれなポップ・センスとダンサブルなサウンドで多くのファンを獲得してきたタイキック・マーフ待望の初の全国流通盤となるニュー・アルバム。
90年代が落とした一粒のティアー。これが世田谷系ノスタルジック・ヒップ・ホップ・ポッセ!!! これまでに発表した自主制作盤が全てソールド・アウトを重ね話題となっている、中毒性抜群の3MC"ウィークエンド"のデビュー・アルバム。
収録曲は既に一部ではお馴染みLUVRAW&BTBのクラシック「ON THE WAY DOWN」のALTZ REMIXをはじめ、そのLUVRAWとBTBの各々の良さがダラダラ溢れ出るソロ曲をはじめ、PPPのコア・メンバーの甲乙付け難い良曲、またゲストとしてWORLD FAMOUS、YAKENOHARA、DJ KENTA from ZZ Production、CRYSTAL from TRAKS BOYSが参加。
LIVE INFORMATION
10月13日(木)@新宿レッドクロス
10月20日(木)@新宿モーション
10月28日(金)@下北沢THREE
10月29日(土)@下北沢CAVE BE
11月01日(火)@下北沢BASEMENT BAR
11月13日(日)@渋谷LUSH
11月24日(木)@新宿レッドクロス
11月25日(金)@天王寺Fireloop
11月27日(日)@京都Voxhall
PROFILE
VIDEO
大谷 學(g,vo)、根岸 達朗(b)、柴田 学(g)、村上 真実(Dr)、近藤 哲夫(g)
2002年に現在のメンバー大谷學、根岸達朗を中心に結成。自主制作により、「FUGEN ep.」「PUBLIC ATTACK GAIN FULL」「ASSHOLE / 午後の日々」「SOLID FOLK」を定期的に発表。同時に自主イベント「第三セクター」「空地」を開催。2009年に発表したアルバム『CAMP FIRE』より、ギター柴田学、近藤哲夫が加入し5人体制へと変化。トリプル・ギターとなる。その後、ドラム村上真実の合流、加入により、1年のライヴ活動を経て、2011年アルバム『23区S』発表。
VIDEO official HP
VIDEO 『23区S』 特設 HP