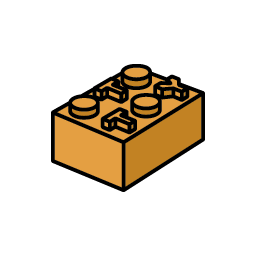一ノ瀬響 / Earthrise 2064
生楽器の音と電子音を融合させた独自の豊穣な世界を探求する音楽家、一ノ瀬響。ジャンルを越境するユニークな作・編曲・演奏活動に加え、インスタレーションにおけるサウンド・デザインなど活動の領域を広げながら、常に高い評価を受けてきた彼のソロ4作目となる本作では、透明感溢れる神田智子(元 Anonymass)のヴォーカルを取り入れ、高純度な器楽曲のストラクチャーの上でエレクトロニカのエッセンスが霧散する独自の世界観にさらなる新鮮な叙情を加えている。宇宙に立った我々が見る、地球の出。未来や過去、遥か遠くから鳴り響く音。
★OTOTOYではボーナス・トラックつきでの販売です!
一ノ瀬 響 INTERVIEW
インタビュー、構成、写真 : 安永哲郎(安永哲郎事務室)
——今回の作品で端的に印象深かったのは、とても良い意味で「迫力が無い」ところでした。それはつまり、一方的にグッと迫ってきたり聴くことを強いるのとは別の次元で、『Lontano(2ndアルバム)』のテーマだった「遠さ」にも通じるようなスケール感があった、という意味です。複雑さや技巧的な側面を露骨に打ち出しているのではなく、作品全体を通して一つの時間軸を紡いでいくようなイメージを、聴き込むにつれて深く感じました。
一ノ瀬 : 確かに迫力は無いですよね。ものをつくる時に「一過性であるもの」とか「近い距離しか見ていないもの」への警戒感があるのかも。こういう作品をつくる時、例えば5年10年経ってもあまり恥ずかしくないものにしたいと思っているんです。だから、流行とか旬という意識とは正反対のことをやっているんですね。逆に言えば、生々しさや即効力のようなものは無い音楽になっているのかもしれない。
——そうですね、循環できるというか、リピートできるというか。曲が流れていく時間そのものを共有するような聴き方が可能で、聴く側が一方的に受け取るだけの表現ではないという印象を受けました。そういう意味で作家のエゴに通じるような力強さが無いと受け止めたんです。
一ノ瀬 : 案外そうなんですよね。あの……無いんですよね、動機が(笑)。小さい頃いじめられたからとか、音楽教室で悪い点を取ったからとか、誰かを見返してやろうとかじゃない。美術でもそうかもしれないけど、ものを作っている人ってはっきり二つに分かれるような気がしていて。ひとつは何か過去のトラウマと闘っているような、越えるとか打ち勝つとか、オーヴァーカムするという態度があると思うんですけど、僕はそういうことではないんですよね。でも、一方で、理由はどうであれ「やる」(笑)という態度も大事だと思っていて、特にこういう音楽というのは自分がやらなきゃどうにもならないものですし……とすると、やっぱり自分の一番やりたいことを、動機が無いのに何故やっているんだろうということを考えながらやる、ってことなのかもしれないですね。

——自覚的に「やる」というアプローチからも距離を置き、自分を客観視しているということでしょうか?
一ノ瀬 : そうですね……どちらかというと、小さい時から音楽が身の回りに溢れた環境で育ったので、特にある瞬間に決意をして音楽に向かっていったわけでもない人生なんです。気がつけば(音楽を)やっていたというところがあって、この作品もその延長で作っている。それが作品にも出ているのかも。良いことかどうかはよくわからないですけど。
——そういった生い立ちやプライベートと聴く側は切り離されているわけですが、それでも『よろこびの機械(1st)』の頃からの連続性、つまり一ノ瀬さんのパーソナリティという一貫性があって、その先に新作が置かれているように思えたので、作品自体の広がりは感じつつも、すんなり受け止めて楽しむことができました。
一ノ瀬 : なるほど。手法も機材も変わってるんですけどね。録音素材の扱いも。でもそれとは別のところで一貫性があるのかもしれない。ただ、そこを分析的に作っているわけではないので。繋がっていると言われて初めて「ああなるほど」って思うんです。毎回違うことをやりたいとは思っていますけど、完成したものに何らかの共通性が出てしまうというのはよく言われることです。自分でも不思議なんですけどね。
——ある種の「続いている感覚」は自分でも感じますか?
一ノ瀬 : そうですね。(作ることに対する)気持ちは変わってないと思っています。
——そんな中でも「新作をつくろう」と何らかの決意をして取り掛かるとは思うのですが、今作に着手するきっかけはどんなことだったんですか?
一ノ瀬 : 2007年にネイチャーブリスの杉本さん(mondii)からオファーをもらったのがひとつ……それでもすぐやらなかったということは動機にはなってないんでしょうけど(笑)。その前のアルバムを出した前後で、家族の闘病などで取り掛かる余裕が数年間無かったということもあります。2年くらい経って「なんとなくそろそろやろうか」という気持ちになって。それから始めて2010年まで、かれこれ10ヶ月くらいかかりました。
——では最初の時点では「こういう作品を作ろう」というイメージではなく、「新作を作る」というところから始めたと。
一ノ瀬 : そうですね。CDに収まる範囲を前提に、少しずつ自分が何を作ろうとしているかが見えてくるというような進め方でしたね。(アルバム作りは)いつもそうなんですけど。
——まずは音から着手するんですか?それともコンセプトが先行ですか?
一ノ瀬 : 言語的なイメージと音楽的なイメージは不可分で、同時に浮かんでくることが多いです。音符を書きながら何らかの言語や概念的なイメージを同時に想起しているところがある。 いくつかの断片的なイメージが静止画で思い浮かんだとして、それを繋いでいくようにアルバムを構成していくというか。個々の曲はそれぞれ別に発想していっているんですけど、「あ、これはこの後の話かな」とか「これはここに繋がるんだな」というように。スナップショット的なものが一つ一つの曲だとしたら、アルバムはそれらが繋がったストーリーや動画のようなものに近い。 『Lontano』の時は先に素材を録音して、後からパズルのように組み立てるというやり方だったんですね。何度も録り直しをせずに自宅で組み替えていくことが多かったので、自然と素材の再利用のような作り方になります。素材が限定されているという意味で、まとまりの良さがあの作品を構成していた。今作は宅録事情の発展もあって(笑)、録り直して、組み立て直して、譜面を書き直して……というような行き来、つまり録音と素材の構築という作業を何度もやり取りするということになっていたので、素材の一貫性はやや少ないんです。だから曲ごとに聞こえ方の幅も広がっているような気はするんですけど。作るというよりは「こういうことかな」と読み解く、解釈していくというような……置かれた絵の状況を推測してみるようなプロセスに近いかもしれませんね。
——自分の中での対話みたいな。
一ノ瀬 : そう、正に対話ですね。何から何までわかっているものを作るって面白くないわけです。だから「なんでこういうものを作ったんだろう」と考えて、「あ、こういうことかな」って次の曲に反映されるというような。そうやって言語的なイメージやビジュアル的なイメージを行き来しながら作る過程で見えてきたのが今作のタイトルにもある「Earthrise」という言葉です。 いずれ未来になれば、月に行って「地球の出」を見る。それはほとんどの人が体験していない未来の話なんだけど、想像の中では昔から地球を外からの視点で思い描いたり作品にしてるんですよね。実際に行ってないのにそういう視点を持っていたんだなと考えたんです。 その中の一つがバーン・ジョーンズの「The Days of Creation」だったり、ウィリアム・ブレイクの「Little Black Boy」という詩で歌われている「私たちはわずかな間だけ地球に置かれたよ」ということだったりするんですけど。いま環境問題という視点で「地球のことを考えよう」とは言われるけど、普段の生活で地球を丸くて小さいものと考えることはあまり無いはずなのに、昔からみんなやってきていたんだなということがわかったのが面白いな、ということをよく考えていましたね。
——面白いですね。確かにいま地球や環境というと、すごく現実的で自分の行動や生活に即した物差しでの思考になりがちですけど、もともとは情報も無い中で、自然や宇宙というものは思いを馳せる対象として、距離が遠いからこそ色々と想像できるという思考の方が自然だったのかもしれませんね。そういった根源的なイマジネーションが一ノ瀬さんの中に芽生えた、と……。
一ノ瀬 : たぶんそういうことだと思います。エコロジーなら「どうやって節電しよう」という考えに繋がりますよね。そういう社会的な観点も大切ですけど、同時に芸術には「どんな視点でものを見るか」を提示する、ほのめかす、暗示するという役割もあるわけですよね。カート・ヴォネガットが「芸術家は炭鉱のカナリアである」と言っていましたけど、危険を知らせるつもりは無くとも、一番初めに空気の変化に気づく。そんな役割で良いということです。(アーティストが)すべてに自覚的である必要もないと思っているので、僕が音楽を作るときにはなるべく理屈っぽくしないですね。もちろん後から言葉でタイトルを付けはしますけど、結局のところ「何でこんなものを作ったのかよくわからない」というのが正確なところで(笑)。わかっていたら作りませんからね……。

——わかる気がします。作品として形になると、受け止める側はそこに「何らかのメッセージがあるのではないか」「そのためにこんなテクニックを使っているのではないか」等の答えを想定して聴きがちですけど、表現する側にとっては、そこまで規定できるなら作り方が変わったり、別の結果になったかもしれないということが言えると思うので。
一ノ瀬 : 表現する立場からするとそういう思考でしょうね。
——一方で、もともとの一ノ瀬さんの音楽家/作曲家の出自をたどれば、理論や技術といった明確な評価軸がある世界の中で過ごしてきた時間も長かったはずです。そのことと、解釈が何通りもできる感覚が一ノ瀬さんの中に同居しているのが面白いと思いますが。
一ノ瀬 : それはいつも悩まされるところで……。正直、こういう音楽を作っていても「どこがどうすごいの?」と聞かれたら、別にどこかどうすごくもないんですよね。技術的にも別に……。有限の組み合わせのものからチョイスして、まとめている、ただそれだけのこと。手品みたいなことがあるわけでもないし。評価……って難しいですよね。現代音楽の技法の一部を使っているとしても、文脈の中で技法的な優位性を求めてやっているわけではないですから。自分がどういうところでものをつくっているのかということは、いつまで経ってもわからないですね。この前CDショップのニュースサイトでこの作品が「エレクトロニカ注目作」に挙げられていましたけど、「そうなのか……?そう言うならそうなのか……」と思ったんですよ。そんなジャンルに収まらない居心地の悪さはいまだにリアルに感じますけど、しょうがないですね。それでも面白いと思って聴いてくれる人がいるならそれでもいいや、っていうことです。聴き手と自分との関係性がきちんとあれば、ラベリングや業界の問題は作品にとって本質的な問題ではないと思っています。
——そういった可能性がどこに対しても開かれている状態は、ありそうで他に無い気もします。マーケット前提で音楽を説明しようとすれば、クラシックの要素やジャズの要素などがフィールドを越えてミックスされているとした方が説明しやすいし、聴く側もイメージしやすいとは思います。でもそれと一ノ瀬さんのアプローチとは発端から全く違うという点で、すごく面白いし、開かれていると思います。
一ノ瀬 : そこは実は一番難しくて大変なところですよね。自分は「ジャンルを越えてどちらも揃えました」とは違うアプローチで、何とも名づけ得ない微妙なところをコチョコチョと掘り返しているんですけど……。何でこんなことになっちゃったのか自分でもよく分からないけど(笑)、作りたいと思うものを作ったらこうなってしまったという帰結があって……望んだわけでもなく来てしまった。それを面白がってもらえれば良いですけど、何なの?って聞かれると辛いところですよね。「何でもありません」としか言いようがない(笑)。
——とはいえ、作り手としての葛藤はご自身の中にありますよね。同じ「もがく」でも作品の方向性を見出す際に感じるプレッシャーと、完成後に「こういう風に伝えたい」と感じるストレスの二つがあるのではないかと思うんです。どちらが大きいですか?
一ノ瀬 : 「こう伝えたい」という悩みはあまり無いですね。ありのまま受け止めてもらえれば良いというのが前提なので。前者のプレッシャーの方がきついですよね。捨て曲がものすごく多いし、ようやく生き延びた曲が収められるわけで。全然器用ではないと思います。作曲家として仕事を受けている=器用というイメージはあるかもしれませんが、作ることにはすごく時間が掛かります。
——器用だというパブリックイメージがあるからこそ、アカデミックな要素や明確なメッセージを前提に聴かれてしまう可能性もあるかもしれませんね。でもここまでのお話を通して、作品とご自身との距離の取り方が過剰にパーソナルにはならず、極めてオープンな形で聴き手に向けられているように感じました。
一ノ瀬 : そうですね……。「こういう風に世界を見てますよ」と(自分は)言っている気がするんですよね。だからこうしなさい、と言うところまでは行かないんです。そんなこと言いたくもないですから(笑)。「こういう風にも見えますよ」「ここから見るとこうですよ」という発見をしているというか……。それは『よろこびの機械』を作ったときから変わらない、「見ている」という状態です。
——そうは言っても、アルバムタイトルに数字が入っていたり、具体性をほのめかしているようでもありますが。
一ノ瀬 : それは文化史的な読み解きができるものから、完全に個人的な遊びやなぞ掛けまで(笑)。具体的なものに近づいたり離れたり、というのは今回新たなアプローチとして試してみたことです。手法面での違いで言えば、今まで電子音楽を作っているという意識がずっとあったので、生音は素材でしかなかった。生音をロングテイクで使うようになった2007年くらいから「近い/遠い」をより意識するようになりましたね。それが数字や歌詞のような形にも繋がっているかもしれないです。
——タイトルの「2064」というのは…?
一ノ瀬 : これは西暦2064年ということですけど、とても個人的なものです。
——一ノ瀬さんは何年生まれでしたっけ。
一ノ瀬 : 僕は1972年なので、そこから読み取れるものではないです。ちょっと内緒(笑)。
——作品についての具体的なお話に入りましょう。全体を聴き通しての流れも感じますし、曲名も一曲目から十曲目で同じ「Cadetude」に戻りますね。
一ノ瀬 : ここに楽譜がありますが、上向していくだけのメロディと、それを引き伸ばしたり遅らせたりして声が重なっていく構造です。それが「Cadetude」の#1と#2で微妙にスケールが違うので、戻ってくる場所が微妙に変わるんですね。パッと聴くと同じフレーズに聞こえるんですが、四つ目の音がナチュラルになっていて、ちょっと違うんです。同じ地点に戻っても、そこにいる自分はまた別の自分になっているんだというようなこと……それもひとつの読み解き方かと(笑)。解釈はいくらでもできますよね。
——音楽的な展開を抜きにしても、この二曲はアルバムのコアになっているように感じますが。
一ノ瀬 : そうですね。これが一番最初に作った曲です。秩序立った、とても明晰な世界が作りたいと思ったんです。最初は歌詞をつけようとも思ったんですが、ソルミゼーションでやったらいいかなと。音大のソルフェージュっていう時間で楽譜をドレミで読む訓練なんかを思い出したりしながら。カデンツっぽいものとエチュードが組み合わさって「Cadetude=カデチュード」なんですが。このアルバムに入っていくための「練習」という位置づけですね。この曲はきちんと譜面を書いてヴォーカルの神田智子さんに歌ってもらいました。
——生楽器と電子音はどんな配分ですか?
一ノ瀬 : 打ち込みっぽい音はほとんど無くて、オーディオデータを元に作っていくことが多かったです。ピアノのサンプリングから空間的な音を作ったり、アタック成分が無い形にトリートしていくといったような。具体的に録った楽器を挙げると、自分のピアノと神田さんの声が一番多くて、あとはエレキギター、フェンダーローズ、自宅にあるおもちゃのグロッケン、それからヴァイオリン。他にパッド系やシンセマリンバの音も使いましたが、ドローンのような音のほとんどはピアノからですね。
——六曲目のギターは印象的でした。
一ノ瀬 : ハーモニクスだけでできている曲ですね。すごく演奏に苦労しました。
——全体に少ないレイヤーで構成されていますよね。
一ノ瀬 : 曲によってトラックが多いのもあるけど、そうは聞こえないですよね。そこはミックスの時に工夫しました。結局、音楽が一つに聞こえてほしいという思いがあるんです。リズム、ベース、上ものという風にパートが分かれて聞こえてしまうと、なんだか謎が無いように感じられてしまうんですよね。どうなっているんだろう?って思いながら曲の中にじっと居て、精妙な気分を楽しめるような音色を作りたいと思っているので、音の混ぜ方についてはものすごく時間をかけて、気を配って作業していますね。それはパッと聴いた限りでは想像もつかない苦労をしています。 さっきも言った通り、僕はやはりこれを電子音楽だと思っています。どれだけ生楽器が入っていても、それらをコントロールしてひとつに混ぜているのは自分だという意味で。だから、色々な要素が混ざっているものを一つのまとまりとして感じてもらえたのは嬉しいです。

——曲単位で見ると六曲目のギターや九曲目のローズなど、冒頭で使われる楽器の音色に耳を引っ張られますが、それを特定のジャンルに結びつけないで聴く方が、アルバムの全体感を楽しめる気がします。実際にトーンやテンションには一貫性がありますし、ポイントごとの違和感を、単に違和感ではなく全体を形作るための要素だと捉えることができる構成ですね。
一ノ瀬 : 曲の配置にも苦労していて……他の人はどうやっているんだろう?一曲ごとに仕上げて次の曲に移り、全部を広げて並び方を考えるようなやり方は取っていないんです。作りながら他のものをいじって、いろんなプロジェクトを行きつ戻りつ、効率悪いこと甚だしい(笑)。そのうちにだんだん順番も見えてきて、ひとつひとつの曲と全体の曲順が最後いっぺんに仕上がるというような作り方でした。
——確かに、統一感というと単純化されてしまいますが、互いの曲が影響し合っているのは感じられます。そんな中でも、A面B面を思わせるような構成で、ハイライトが五曲目と九曲目に据えられているように聞こえましたが。
一ノ瀬 : 九曲目は割と早い時期にアイデアができていました。ポピュラーミュージックが持つコードやメロディといった形式に近づいている曲です。タイトル曲でもあるし、比較的ストレートな形でアルバムを代表させるとしたらこうなるんですよね。五曲目はロングフレーズを使った曲です。コンサートの曲のように、ヴァイオリンの譜面を前もって奏者に渡して演奏してもらいました。今までのソロアルバムには入っていなかった曲層かもしれませんね。
——ポピュラーミュージックという観点では二曲目もそうですよね。
一ノ瀬 : うん、これは九曲目とも呼応し合っている曲で、素材もいくつか共通しています。使い回しというと聞こえが悪いですけど、外伝のような、手塚治虫の「スターシステム」みたいに別の漫画のキャラが顔を出してくるような(笑)。作品ごとの関係性を自分自身が鑑賞者として意識することがあるんですけど。「これはあっちに出てきたあれだ」というように、注意深く聴いていると発見できるようなものを潜ませています。
——ある種のセルフパロディのようなものでしょうか。
一ノ瀬 : そうですね、自己リミックス的な。共通の音色やフレーズを使うことで、作品としての「通路」が生まれてくる。五線レベルのものから録音されたデータレベルのものまで、そうしたモチーフになり得るというか。その意味で、自分は手法としてジャンルAとジャンルBを混ぜるというのとは別の考え方で素材を扱っていると思っています。例えば多くのリミキサーやDJは、データとしての音そのものが対象になると思うんですけど、自分の場合は五線上のフレーズだとか、環境音の中のある何秒間、そのどちらもモチーフだと考えている。そういう捉え方で作られている音楽ってあるようで無いと思っています。
——確かに、一ノ瀬さんのいう「素材」はパーツのことではないですよね。
一ノ瀬 : それを元に曲を構成していくという意味ではパーツかもしれないですけど、時間的な「部分」という意味で考えてはいないです。
——収録曲に話を戻すと、三曲目は映画の……。
一ノ瀬 : これは横井まきさんという方の依頼で「春のゆらぎ」という映画のために2006年に作りました。自宅でマイクを立てて録ったピアノの音に、深いリヴァーヴをかけています。(他の曲の中に)置いてみると意外にしっくりきたんですよね。いろんなところで作った音をごった煮の作品集として出すのは好きではないので、最初はどうかなと思ったんですけど、うまく居場所があったように感じられたので入れることに決めました。
——そういう情報を知らずに聴いていたので、アルバムのために作られた曲かと思っていました。
一ノ瀬 : (笑)そういってもらえると……逆にクレジットを入れない方が良かったかな(笑)
——他に個々の楽曲で特別なエピソードはありますか?
一ノ瀬 : それぞれ細かい謎は仕掛けてあるんですけど、それは黙っている方が面白いのかな。 四曲目の「Big Sur」というのは地名です。ロサンゼルスとサンフランシスコの間あたりの海岸線一帯のことなんですが、面白いんです。岩がごつごつして海が奇麗で。その岩を見たら「地球の肌」がそのまま出ているんだと感じられて、これも宇宙からの視点の一つなのかなと思ったということです。 五曲目の「Longings and Gravity」は、高いところにメロディが上がりまた下がるところが、重力のせいで飛びきれず落ちてくるということと繋がっている。後から気づいたんですけど、これギリシア神話のイカロスなんですよね。別にそういうことが分かっていてもいなくてもどっちでも良いし、逆に全然違う意味を見つけ出してもらっても面白いし、いつでも作品は投げ出したいと思っています。 どの曲に対しても、自分では細かい言語的なイメージがありますけど、そのすべてが客観的なことではないし、誤解があっても面白い。受け手の個人的な体験や文化的な資質などと衝突して新しいものが生まれてきても良いと思うので、あまり僕が種明かしをし過ぎても馬鹿馬鹿しいし、面白くないですよね。先ほどの質問にもありましたけど、自分の手を離れた時点で聴き手に対して「こう受け止めてほしい」という葛藤も要望も無いです。
——とはいえ、歌詞がある。そのこと自体かなり具体的ですよね。英語なので主語がどうしても出てきてしまう中で、例えば「We」って誰なんだ?という憶測はかなり具体的なところまで掘り下げられると思うのですが。
一ノ瀬 : 「We」という言葉には日々思うことが色々あって……今の世の中で何かを「嫌だな」と思う時って、「We」が狭くなっている時なんじゃないかと思うんです。「俺ら」って言うじゃないですか。「俺ら」の範囲って、どこですかね?「俺ら」の範囲が狭くなっていくと、人って攻撃的になるんじゃないかと思う。この歌詞では人類全体を言っているとは思うんですけど、そのくらいまで引いて見ている視点はいいなと。自分の身の回りにしか目が行ってない時も必要でしょうけど……やっぱり「We」の範囲が重要な問題だと思いますよ。かと言って「こういうWeが大事だぞ!」ってところまで自分は持ってないんです。ただその範囲について考えてみてもいいんじゃないですかね、という……。
——確かにネガティヴなことを言うときの「We」は日本でいうと村的なイメージだったり、「ヨソとウチ」のような色合いが強まります。
一ノ瀬 : 日本語のヒップホップでも「俺ら」ってよく出てきますよね?

——そうですね。そういうのを聴くと距離を感じるというか、ああ自分はその「俺ら」に入れてもらってないな、という気になりますが(笑)。作り手と聴き手の距離の取り方にも関わる視点ですね。それが地球をテーマにすると「We」はすべてを包括することになりますし。それによって問題点や想像する先のものが全く変わってきますね。 話を戻して……各曲のタイトルも主語が曖昧なところに広がりを感じました。
一ノ瀬 : ああ、そうか、主語を想定してないんだ……。
——でもそれは「わかんない」ということではなく、人それぞれにイメージできるということなんです。
一ノ瀬 : イメージするきっかけですよね。流れていってしまうものではない。ただそれも微妙なところで……このアルバムがイージーリスニングとかニューエイジのコーナーに置かれるわけです。それが、うーん……微妙なんですよ……。パッと聴くと似たものがあるんでしょうけど、その類似点と相違点を意識してもらえると嬉しいなとは思うんですが。
——やはり受け取る側もある種の責任があるとは思うんですが、それにしてもイージーリスニングに置かれるのは、時と場合によっては、熟考された結果というよりも思考停止状態の末にそうなった、とも見えてしまう気が個人的にはしますね。何だろう……あいまいなものや落としどころを見出しにくいものがそこに行きついてしまうような流れが、誰の責任ということではなく、あらゆるところにあるかもしれないですね。
一ノ瀬 : だからitunesに入れると、きっと「Unclassifiable」って出てくる……まあ、それは勲章だと思っているんですけど、簡単な言葉として何かに括られちゃうと「ん?」と立ちすくんでしまう感覚を覚えますね。ただ、それを何とか改善したいかというと、そこまで関心が強いわけではない。自分の音楽がどう名付けられて売られていくかということに関して思いはあっても……自分でレーベルをやっていないこともあって、どうしたら良いかよくわからないところもあります。これから向かい合っていかなくてはいけないと思うんですけど。
——以前と比べて、そういうことがより気になるようになったということは無いですか?
一ノ瀬 : あまり変わっていないですけど、世の中の方が変わってきているかもしれないですね。よりハッキリしたものや、安全なものが求められる傾向が強くなっているかもしれない。ある程度消費可能な流れを作り、そこに乗りましょう、という考え方が増してきているようには思いますね。
——アルバムの話に戻りますが、今作のコンセプトをもう少し聞かせてください。

一ノ瀬 : はい、ここに天使が地球を抱えている絵がありますが……バーン・ジョーンズという人の作品です。自分が音楽を作る際の後押しとして、こういう(地球を外から見る視点の)絵がいくつかありました。あとは、先ほどお話したウィリアム・ブレイクの詩は「経験と無垢の歌」の一節なんですが、他にも過去に読んだいくつかのSF小説などが経験の束になって思い出されてきました。中でも特に、ジャケットにも直接関係しているのがこのバーン・ジョーンズのよる連作絵画「The Days of Creation」の五日目、鳥と魚が創られた日の絵です。これを加工してプロジェクターに投影してさらに写真を撮るなど、手の込んだことをしたものが今回のジャケットです。裏面はそれを水面に映したものですね。
——楽曲を作る過程で、こういったものに徐々に触れていったのですか?
一ノ瀬 : そうですね。もともと知っていた作品もありますけど、記憶を掘り起こす中で、それらが制作を助けてくれているような感覚でした。何もかもが徐々にできていくというか……。こういう作り方、僕にとっては当たり前ですが普通じゃないですかね?
——人それぞれかとは思いますが、揺れ動きながら作ることの難しさはありそうですね。
一ノ瀬 : 揺れますね。最初から見えないところでやっていくので、フォーマットありきとはまったく違う大変さで、気分が乗らないとできないものです。
——だからこそ、聴き手にも一ノ瀬さんのパーソナリティが浮き彫りになって面白いのではないでしょうか。……ということで、だいたい聞きたいお話は伺えた気がします。
一ノ瀬 : 一番答えようが無いのは、新作を「どんな風に聴いてもらいたいか」という問いです。言語的なイメージを表現できるのはタイトルや曲名なので、それ以外をこの場で語るのは後出しジャンケンのようなものだと思いますし。こんな時代にCDという形で出しているからには、言いたいことはパッケージに書かれているということなので、そこからどう掘り下げられていくかは(聴き手に対して)期待して待っているようなところが自分にはあります。
——では最後に、今後のご予定を教えてください。新作をライヴ上演する予定はありますか?
一ノ瀬 : それに関係する話ですが、CDで音楽を作っているって何だ?ということについて……。ライヴでもなく、レコーディング現場でもないのがCDを聴くという体験と考えると、音源を頼りに(聴き手との)関係が成立するということが自分には面白いんです。その上でライヴをどう考えるかというと、原理的に音源をなぞるようにはできないという前提のもと、CDとは別の表現媒体に変換していく作業が必要になるわけです。だから……どこまでできるか今は考えている最中、というのが質問の答えです。そんなにすぐにはやらないと思います……早くても夏前とか。あと、この作品とは別ですが、4月4日に杉並公会堂で、僕の姉の一ノ瀬トニカとデュオピアノのコンサートをやります。全曲オリジナルでお互いの曲をやろうと。それからDaisuke Kashiwaさんの新作にどっぷり関わっています。しばらくはピアノ、ピアノの毎日ですね。
*4月4日のコンサートは諸般の事情により延期となりました。どうぞご了承ください。なお、詳細につきましては、下記、一ノ瀬響サイト(http://www.kyo-ichinose.net/)をご参照ください。
PROFILE
1972年、東京生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業、同大学大学院音楽研究科修士課程修了。大学在学中より現代音楽の作曲家として活動をスタートさせ、以降、生楽器の音と電子音を融合させた独自の豊穣な世界を探求する。これまでに『よろこびの機械』『Lontano』『Protoplasm』の3枚のソロ・アルバムをリリース、UKの音楽雑誌”WIRE”の特集にて年間ベスト・アルバムの1枚に選ばれるなど、ヨーロッパをはじめとして海外から高い評価を受けている。またソロ活動以外にも数々の先鋭的なCM音楽の作曲やアーティストとのコラボレーション、インスタレーションのサウンド・プログラミングまで、常に音と音楽の境界を探るジャンル横断的活動を展開している。