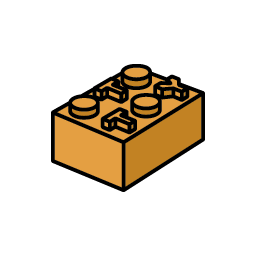カリブ海・コロンビア原産のダンス音楽「クンビア」をクラブ・ミュージック用にデジタル化したデジタル・クンビアは、ZZK recordsの『ZZK Sound Vol.1 Cumbia Digital』の発売がきっかけで一気に広まり、昨年の暮れ頃からクラブで頻繁にプレイされている。そしてこの度、デジタル・クンビアの生みの親「デジタル・クンビアのゴッドファーザー」と呼ばれるディック・エル・デマシアドが来日する(しかもFUJI ROCKでもプレイ! )。彼が創るゆるゆるの2ビート・ダンス・ミュージックは、今まで耳にしたことがない質感のサウンド。強いて言うならカリブ海で火を噴いたバットホール・サーファーズ!? Senor Coconutコンパイルのアルバム「Coconut FM」で紹介され、岸野雄一とパリで共演、ウリチパン郡でもプレイするオオルタイチのremixが日本独自企画編集盤『Sus Cumbias Luna'ticas y Experimentales』に収録される等、名を連ねるアーティスト達の強者っぷりをみても、そのサウンドが未聴の領域で奏でられる音楽であることは、容易に想像出来るだろう。
今回、まさかまさかでインタビューをゲットした。ベールに包まれたディック・エル・デマシアドの紳士的かつ明瞭な解答に、ただただ圧巻! 相当すげーオヤジです。
インタビュー&文 : 飯田仁一郎
INTERVIEW
—あなたが、コロンビア原産のダンス音楽クンビアと出会ったのは、いつ頃ですか? またきっかけは何でしたか?
ディック・エル・デマシアド(以下、D) : クンビアと出会ったのはアルゼンチンで、7歳ぐらいの時。うちにマルタという、とても優しいお手伝いさんの女性がいた。彼女はアルゼンチン内陸部のサンチアゴ・デル・エステロという町の出身だった。僕は彼女がとても好きだった。彼女は知識が豊富で、信じられないかもしれないが、溺れたオウムに人工呼吸して命を救ったこともあるんだ。(僕はこれについての歌も作った)で、彼女の部屋からクンビアが聞こえていた。それはアルゼンチンの中産階級の擬似ヨーロッパ人たちが聞いていた音楽とはまるで違っていた。
—あなたにとって、クンビアの最大の魅力は何ですか?
D : とてもとっつきやすいという点。何も難しいところがない(例えば、名人技が必要なタンゴやサルサと違って)。胎児にうってつけの音楽のように聞こえる。ラテン・アメリカのパーティー・ミュージックに対して一般的にイメージされる昂揚感や激しさがなくても魂を揺さぶるんだ。こういう哲学的な点以外にも音楽的なポイントもある:実験がしやすい構造なのだ。

—電子楽器でクンビアをやろうと思ったきっかけはありますか?
D : ラジオ番組制作を通じて(アムステルダムの海賊ラジオ局Patapoe)、電子機器を使ったり、デジタル/エレクトロニックなエフェクトで即興する機会が豊富にあった。だからこういう機材には慣れていた。その後、スペインの砂漠にあるカランダという村に引っ越したが、その時はアートの仲間とは一緒じゃなかった。一人で制作をしないといけなかったし、周りにミュージシャンがいなかった。その時にエレクトロニクスを使ったクンビアを生み出したんだ。周りにミュージシャンがいなかったが、もし仮にいたとしても役に立たなかっただろう。僕は大胆な実験がしたかったし、ラテン・アメリカのミュージシャンのほとんどはヨーロッパではお決まりのことをやって稼ぐことしかせず、風変わりなことはやらないんだ。なので、電子機器を使い慣れていたことと、ミュージシャンが周りにいなかったことは最高の組み合わせだったんだ。例を挙げると、Sabado Culturalはこのとき、2000年に作られたんだ。
—クンビア以外で、最近あなたが影響を受けたり、注目しているお気に入りのサウンドはありますか?
D : 1978年に初めて耳にし、いろんなLP盤のジャケを見て以来ずっとダブが好きだ。リー・ペリー、キング・タビー、ザ・ケミストや、U-roy、Dr. Alimantadoなどのシンガーといった偉大なアーティストたち。近年はダブの究極のシャーマンで、ひずんでミステリアスなサウンドを何時間も演奏するジャー・シャカをフォローしている。でも新しい音楽の発見にはそんなに一生懸命じゃないんだ。
—2003年の1st『No Nos Dejamos Afeitar』があなたのミュージシャンとしての初作ですね? 執筆やビデオ・アート等も行うあなたが、音楽を制作し始めたきっかけを教えてください。
D : 僕は目の前にある奇妙な道をずっと進んできていて、脱線することは恐れたことがない。脱線、サプライズやアクシデントはアーティストが体験することのなかで最高のことだと僕は思う。僕の全ての作品はその思想において同じ姿勢で作られている。でも僕が音楽を作り始めたのは以下の理由のためだ。
- 映画のように過去の伝統や前例などが幅をきかせていない分野だと思ったから。つまり、自分でプラット・フォームを作れば想像したものをなんでもやることができるんだ。
- 音楽は最も豊かで人間的な芸術形態だと心から思うから。
- 右翼も左翼も、どんなに極端な思想や頑固な姿勢の持主も同じものを耳にして、互いの違いを忘れることができるという、音楽が持つパラドックスな部分が好きだ。
- エクスペリメンタル・クンビアという、オープンで奇妙で前例のない音楽を生み出すことに成功したら、アルゼンチンへの借りを返し、敬意や感謝を示すのにちょうどいい素敵なプレゼント、そしてプラット・フォームになると思ったんだ。だから音楽以外にも小説やフェスティバル(Festicumex)にもたくさん取り組んだんだ。(まるで政治家のような発言だ)
—ZZK recordsの『ZKK Sound Vol.1 Cumbia Digital』によって、日本でもデジタル・クンビアが広く知られることとなりました。このレーベルは、あなたと密接に繋がっているのですか? また、あなたはこのレーベルについてどのような感想を持っていますか?
D : ZZKとはとても親しい。ご存じかもしれないが、僕は彼らのブエノスアイレスでのクラブで何度かライブをしたことがあるし、彼らは僕を「クンビア・キング」と呼んでくれている(これはナイスでフェアなことだ)。彼らは「都会的な」音楽を作るという目的でレーベルを始めた。だから、彼らの視点は主にダンスやヒップホップからのものだ。レゲトンなどに替わるものとしてクンビアのビートがピッタリきたことから、彼らは方向性を変えて今やクンビア・ビートに専念している。父親的な立場から僕の意見を言うと、僕からすれば彼らには若干「輸出志向、プラグ・イン重視、圧縮戦術」すぎる部分がある。これは分かりやすい戦略だが、裕福な人々に称賛されることでZZKのポテンシャルが方向を失う可能性がある。一方、僕は毒やポエトリー(詩)を重視している。でもこのためにはダンス・フロアやファッション的な世界から離れて「リアルな人々」がいる田舎に行かないといけない。アルゼンチンの外でこのジャンルが人気を得ているのは理解できる。クンビア自体はスウィートでエキゾチックな音楽だし、同時にZZKの強力なビートは多くの人が求めているものだから。とても良いのは、彼らが生み出したモメンタムによって彼らだけでなく、今後第二世代のプロデューサーたちも育っていくだろうということだ。こうやって皆がそれぞれのやり方でやっていけばいいのだ。これはスタートであって、一過性のヒットではないのだから。それはいいことだ。
—日本では、去年のくれ頃からデジタル・クンビアがクラブ等でよくかかるようになりました。 ヨーロッパの状況はどうですか? また、デジタル・クンビアが各国で認知されるようになった現状を、どのように感じていますか?
D : たしかに、ヨーロッパではここ1年ぐらいで急にデジタル・クンビアがクラブでかかるようになった。バルカンの音楽やレゲトンに続くものと人々は受け止めているようだ。クンビアは様々な要素がまじりあった、ハイブリッドな(原住民+アフリカ+ヨーロッパ)ラテン音楽のスタイルだ。世界中の音楽を一過性の発見としてもてはやすのは良いことではないが、避けられないことでもある。クンビアはまさにそれになりつつある。一過性の発見。一つの文化が内包する要素には限度があり(一つの文化において10種類の音楽スタイルぐらい? )、我々はそれをファッション工場のような地獄で燃やしているのだ。これは我々が解決しなければならない、とても痛痒いパラドックスだ。つまり「真の発見vs一時的な流行」だ。
—日本ツアーがもう間近ですね。日本で楽しみにしていることはなんですか?
D : 全てが楽しみだ。あらゆるもの、場所。アジアには行ったことがない。日本語の文字のように、ほとんどのことが僕にはナゾナゾのように写るだろう。不思議の国のアリスみたいな気分がすると思う。僕はすべてを理解したいと思うか? 理解したいかどうかはまだ分からない。もっと具体的なことを言うと、僕は日本の音楽のいくつかの側面にとても魅了されている。たとえば、ディストーションへの傾倒と実行だ。最近大阪のバンドのyoutubeを見ているのだが、彼らはまるでいん石や彗星の先端にくっついているような感じがする。アメリカのカルチャーは車のハンドルを握ろうとしている気がするが、日本、少なくとも大阪はレーシング・カーの上や疾走する機関車の先端に立つ方を好んでいる気がする。コントロールに逆らう花火のように。コンセプチャル・アートに対するフューチャリズムだ。しかしもちろん、これはまだ読み始めていない本を開くことを詩的に表現しただけのことだ。日本とその文化に触れることを楽しみにしている。これまでの経験はすべて非常に良い。僕が持ち合わせるどんな温厚さや野獣性をも発揮するためにベストを尽くそうと思う。
—僕も大ファンであるオオルタイチのRE-MIXが、日本盤には収録されていますが、そのRe-mixを聴いてどのように感じましたか? また、彼のことをどう思いますか? 他にあなたが注目している日本のアー ティストがいれば教えてください。
D : オオルタイチの音楽は僕らの共通の友人であるアレハンドロ・フラノフを通じて知った。アレハンドロは僕の音楽活動の最初期、2003年のFesticumexで僕と一緒に演奏してくれた。オオルタイチは、その切り貼りされたカオスやハーモニーを僕が完全に理解できる、世界でもごくわずかなミュージシャンの一人だ。こういうカオスやハーモニーの楽しさをひずませて伝達するにはとても巧妙なレシピが必要で、僕の音楽には歌詞や歌が入っているものの、オオルタイチにも同じ料理方法が見受けられる。僕は今まで誰にも自分の曲をリミックスさせたことはないが、今回は彼と日本に対する良い挨拶になったと思う。ここに僕の赤ん坊がいる、写真を写すなら好きなように髪をなでつけてもらってもいいよ、と。赤ん坊は良い見栄えになり、微笑むのだ。日本で僕らは出会って一緒に演奏する。素晴らしいことだ。このことがすべて、インターネットとmyspaceという、チープでトラッシュな手段を通じて実現したことにとても感動している。人類はあらゆるチープな機会をとらえて友人を作り役に立てる方法を見つけるものだ。他に注目しているアーティスト:もちろん岸野雄一もだ。雄一とは昨年パリで対バンして以来知り合いだ。彼は素晴らしい映像と音楽を作っており、とても強いキャラクターの持主だ。彼と一緒に働けることが嬉しい。最後になるが、大阪の音楽シーンにも非常に感銘を受けている。
—今年で54歳になるあなたのその衰えない創作意欲はどこから湧いてくるのでしょうか?
D : 僕はまるで野生のイノシシのようだ。一度走り出すと有刺鉄線も突破してしまう。僕は自分に起きることをすべてとても楽しいと思う。僕は大勢の人と働くのが好きだが、自分で何かを発明することもできる。それも簡単に。また、制作の原動力だが、僕にはよくしてくれる人が大勢いて、多くのサポートがあり、友達もたくさんいる。一人でも、友達とでも、劇的なことを起こすのが大好きなんだ。運良く、僕には忍耐力がある。100メートル走を走ったことはない。キャリアの最初に最も困難で堕落したアート(映画)を選んだおかげで忍耐力が備わったのだ。 もう一点:僕はたくさんの国に住んだことがある。20歳に至るまでに20回引っ越しをした。状況や環境が常に変化することを楽しむ方法を見つけないと変化による犠牲者になってしまう。運良く、僕は変化を「同じゲームで設定が変わっただけ」だと早期に学ぶことができた。視点の移り変わりという挑戦は中毒的だ。この質問をしてくれてありがとう。というのも、僕の音楽以外にこの側面を伝えることも嬉しいから。成果物だけでなく、それに至る過程ということだ。よく言われる言い回しを使うが、「太く短く生きたいだと?? じゃ75歳でそうしろ! 」と言いたい。年齢とともに得られる経験によって人生はもっと実り多く、楽しいものになるのだ。

—あなたが日本に紹介したい、クンビア・アーティスト、またはデジタル・クンビア・アーティストを、いくつか紹介してください。
D : Marcelo Fabian は日本のクラブ・シーンに非常にしっくりくると思う。それと、アルゼンチンはコルドバ出身のFreakstilers。個人的に、僕のバンド(僕はいつも一人で演奏するわけではなく、伝説的なバンドも持っている)以外で日本に一番ふさわしいと思うのはアルゼンチン内陸部のバンドでサイケロックのSIQUICOS LITORALEN~OSだ。もちろん、クンビアのバンドもたくさんある。例えばクンビア・ビジェラのDAMAS GRATISやPIBES CHORROSなど。メキシコにはToyというとてもいいプロデューサーがいるし。コロンビアにはクンビアの大御所がたくさんいるが、コロンビアでは僕はクンビアよりもチャンペータのミュージシャンの方が好きだ。
—ありがとうございました。来日ツアー、非常に楽しみにしております。東京公演に遊びに行きます!
D : あなたの関心、質問、好奇心、そして仕事に感謝する。日本であなたがたに会えることがとても嬉しい。美しいものを一緒に探そう。
リミックスに参加したオオルタイチの作品はこちら
せん / ウリチパン郡
2003年にリリースされたファースト・アルバム。OORUTAICHIとYTAMOの2人でホーム・レコーディングされ、作風も4人編成の現在とはだいぶ異なる。『ジャイアント・クラブ』は、整然としているようで、キーワードを見つけようとするとなかなか見つけられない不思議さを持つが、『せん』はカオスのような音の融合の中から、民族音楽やエレクトロなど、散々なキーワードを取り出すことが出来る。
ジャイアント・クラブ / ウリチパン郡
セカンド・アルバム。持ち前の原始的な千住宗臣(PARA ex boredoms)の肉体ビートが、本アルバムで開花したオオルタイチとYTAMOの歌と混ざりあい、既存のポップ・ミュージックを10年先まで進化させた、金字塔的な一枚。
Drifting my folklore / OORUTAICHI
ウリチパン郡ではギタリスト、ボーカリストとして活躍するOORUTAICHIの、2002年に発売されたソロ・アルバム。ヴァイナル・レコードで発表され、現在では入手困難になっている曲を含めた6曲から構成されており、初期のトラックから最新の曲までを網羅したベストアルバム的な内容。
LIVE SCHEDULE
- 7月20日(月・祝)@大阪Sound Channel
- 7月23日 (木)@西麻布SuperDeluxe
- 7月26日(日)@Fuji Rock Festival(Cafe de Paris)
LINK
- ディック・エル・デマシアド MySpace : http://www.myspace.com/dickeldemasiado
- JAPAN TOUR 2009 : http://utakata-records.com/dick2009/
- utakarta records : http://utakata-records.com/
PROFILE
オランダ生まれ。父親の仕事の関係で20歳までオランダ、南米、南アフリカ、フランスを転々とする。オランダで映像、テレビ、メディア・アートで活躍したのち、2000年、音楽制作を開始して電子クンビアを生み出す。2003年に1stアルバム「No Nos Dejamos Afeitar」を発表、楽曲La Cebollaがセニョール・ココナッツ・コンパイルの「Coconut FM」に収録され、ライナー・ノーツで「リー・ペリーとトン・ゼーがチャネリングしたようだ」と紹介される。2004年「Pero Peinamos Gratis」、2005年「Al Perdido Ganado」発表。2006年「Sin Pues Nada」をリリース、日本で注目を集める。バルセロナのSonar Festivalにも出演。2008年、5枚目のアルバム「Mi Tu」をリリース。2009年7月、日本編集盤「クンビア・ルナティカ/エクスペリメンターレ」をリリース、来日。