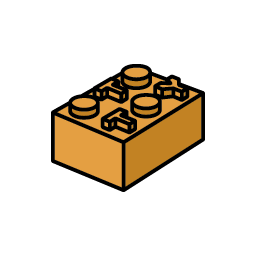90年代グランジ・ムーヴメントの立役者として名を馳せたレーベルサブ・ポップが、00年代後半に来て再びシーンを引率しつつある。ここはひとつサブ・ポップの歴史を紐解いていってみよう! という事で、今回は音楽ライターの岡村詩野さんをお招きし、語って頂きました。お相手は本サイトでもすっかりお馴染み、Limited Express (has gone?)のJJこと飯田仁一郎。振り返っていくと、どうも90年代前半にイメージがよりがちなこのサブ・ポップというレーベルが、実は首尾一貫した活動を続けてきた事が一読してわかる、かなり充実した内容になっております! 時系列に確かな論理を展開しつつ、ルー・バーロウへの偏愛を隠さない岡村さん。バンド名、作品名が挙がる毎に「最高や! 」を連呼する飯田さん。二人の早口関西人に圧倒され、東北出身の僕はほとんど口を挟める余地なしでした(泣)
構成 : 渡辺裕也
偉大なるヴァセリンズの功績
飯田仁一郎(以下飯田) : 詩野さん、ヴァセリンズは観たことあるんですか?
岡村詩野(以下岡村) : あるわけないでしょう(笑)! 日本に来たこともないよ。
飯田 : あ、今回のサマー・ソニックが初来日なんですか?
岡村 : そう。ユージン・ケリーはユージニアスとソロでは来てるけど、そのソロもベル・アンド・セバスチャンの前座だったし。
飯田 : 来てましたねぇ。でも、タイムリーに追ってはいたんでしょ?
岡村 : ヴァセリンズは日本では一部の耳の早いリスナーを除けばほとんどタイムリーで聴かれてなかったと思う。日本で話題になったのはカート・コバーンが"モーリーズ・リップス"や“サン・オブ・ア・ガン”をカヴァーしたのがきっかけ。しかも、元々は53rd&3rdという地元スコットランドのレーベルからシングルが出ていたわけで、正式なアルバムは出てなかったし。このコンピがサブ・ポップから出たのは、ニルヴァーナが『ネヴァーマインド』で人気者になって、“僕の生涯最高のバンド”とカート・コバーンが発言し、「スコットランドにグランジのルーツになったバンドがいる」と言われるようになってからだしね。
—飯田さんの入口はどっちだったんですか?
飯田 : それはもちろんニルヴァーナからだよ。
岡村 : きっとほとんどの人がそうだよね。ヴァセリンズは解散後グランジによって再評価されたんだけれど、その時にはもうヴァセリンズは解散していたから。で、その後にユージンが結成したキャプテン・アメリカ〜ユージニアスっていうのはアメリカのオルタナティヴへのスコットランドからの回答のような存在だった。でも、ニルヴァーナよりもヴァセリンズの方がずっと早い。ヴァセリンズは演奏がユルいから、あまりそうは思われないけど。初期パステルズの影響を受けた感じだからね。
飯田 : パステルズの影響はあるんですよね?
岡村 : もちろん。ティーンエイジ・ファンクラブもそうだったけど、あの時代のすべてのスコットランドのインディー・バンドはみんなパステルズを見習ってバンドをやっていたようなところがある。まあ、でも、『ザ・ウェイ・オブ・ザ・ヴァセリンズ』がサブ・ポップからリリースされたのは92年。でも、サブ・ポップ自体のスタートは86年だから、ほぼ同時にシアトルとスコットランドで同じような動きが起こっていたことになるね。
飯田 : あれ、さっき調べたら79年ってなってたけど。
岡村 : 79年はオリンピアで『サブタレニアン・ポップ』っていうファンジンを出した年だね。その後確か9号位続いたんだけど、最後の方になるとコンピレーションのカセットが付くようになった。それが雛型になって、後の『SUB POP100』に発展していくんだよね。

グランジの勃興〜カートの死
飯田 : ニルヴァーナが登場した時の状況ってどんな感じだったんですか?
岡村 : 当時の日本においてはサブ・ポップってまだそんなに認知されてなかった時代で。もちろんグランジなんて言葉も伝わってなかったし、シアトルもそんなに知られた町ではなかった。89年とか90年の頃っていうのは、メイン・ストリームでのロックと言ったらまだまだスタジアム・ロックの事で、あんまりパンクっぽかったり、ストリートっぽいバンドっていなかった。もちろん、ボストンとかワシントンDCにハードコア周りのバンドはあったし、地方ごとに小さなシーンはあったけれど、オーヴァーグラウンドのものではなかったし、当然チャートに入るなんて事はあり得なかったんだよね。せいぜいR.E.Mとかかな。もちろん、ソニック・ユースもいたけど、今みたいにインディがどうこう言える感じではなくて、まだまだ一部のリスナーたちの愛好物って感じだったから。だから最初の頃は「ちょっとストリートっぽいバンドが出てきたな」くらいのニュアンスでしかなかったと思う。大きくなってきたのはやっぱり『ネヴァーマインド』がチャートを駆け上がってきてからだよ。
—じゃあ『ブリーチ』自体がセールスとしてインパクトを与えた訳ではなかったんですね?
岡村 : それはないね。『ネヴァーマインド』が売れた後でジリジリと累積で伸ばしていった感じだったんじゃないかな。
飯田 : ソニック・ユースはニルヴァーナが出てくる前まではどんな感じでしたか?
岡村 : インディー番長みたいな存在だったよ。でも、ソニック・ユース→ダイナソーJr→ニルヴァーナとメジャーに移籍していった順番で考えると、ひとつの導火線になったのはソニック・ユースの『GOO』だよね。メジャーがアンダーグラウンドのものをすくい上げるきっかけになった。しかも『GOO』はゲフィンでしょ。だからその後ニルヴァーナもあまり抵抗なくゲフィンに移籍出来た。現場にいたA&Rも多分同じだったんだろうし。
飯田 : 日本の音楽好き達はいつ頃から騒ぎ出すんですか?
岡村 : いや、それはもう 80年代からみんな静かに騒いでいたよ。インディー・ロックが商業化されていない、ある意味でいい時代。インディ時代にソニック・ユースは来日してるんだよ、新宿ロフトで。
飯田 : えぇー!! ロフトでやってんですか!?
岡村 : うん。深夜12時開演でね。私も行ったけど、もうギューギューだよ。ほとんどサーストン・ムーアの頭しか見えないの(笑)。ダイナソーJrの初来日は川崎のチッタなんだけど、これもまた超満員。もう寸分の余地もない。ニルヴァーナの初来日はいろんなところでやったけど、もうその頃には日本でもグランジって言葉はファッション雑誌とかにも出てたし、ネルシャツ着てボロボロのジーンズ穿いてっていうスタイルが話題になってたから。マッドハニーの来日公演も超満員だったな。当時はグランジやオルタナという言葉より、まだオルタネイティブっていう言葉で綴られていた。90年代前半から半ば、サブ・ポップ祭みたいなイヴェントが今のO-EASTで何回か開催されてて。その頃はソニーがサブ・ポップをリリースしていて、セバドーとかラヴ・バッテリーとかベロシティ・ガールとかタッドとか毎月何タイトルも、もう湯水の如く日本盤が出たね。ほとんどがそれなりに話題になってた。

—もうその頃には現地とのタイムラグもほとんどなくなってました?
岡村 : うん。ソニーからリリース出来るようになってからは、日本で浸透されていくのは割と早かったと思う。
飯田 : 余談ですけど、大学に入った時にロック・コミューンってサークルに挨拶しに行ったんですよ。それがけっこう厳しくてね。好きな音楽を言わなきゃいけないんですけど、そこで「ジュディ&マリー! 」なんて言った奴には「ふーん」みたいな感じで、雰囲気が凍りつくんです。そこで俺もビビりながら「ニルヴァーナ! 」って言ったらみんなに「おおー! 」って言われて(笑)
岡村 : だから当時はニルヴァーナがイケてるアイテムだったんだよね。
飯田 : 日本のバンドは呼応してたんですか?
岡村 : どうだったかなぁ。あんまり記憶にないなぁ。当時はまだ洋楽って感覚が強くて、今みたいに来日公演の前座に日本のカッコいいバンドが出るってこともそんなに浸透してなったかもしれない。ただ、この時代のサブ・ポップのバンドって何かとグランジでひとくくりにされるけど、実際は、ストリートっぽいけど、メロディがしっかりかけるバンドたちの集まりって印象があった。カート・コバーンの書く曲にしても、私は清々しいメロディックな良さが強いと思ってて。一番好きなニルヴァーナのアルバムは『MTVアンプラグド』だったりするし。結果としては、そういうメロディ・メイカーのいるバンドを多く送り出したんじゃないかと思うんだ。
飯田 : 実際にカートが亡くなった時はどんな感じだったんですか?
岡村 : 大変だったよ。でも当時のニルヴァーナって正直行き詰まり感はあって。初期から追い駆けてた人達からも「次はどうするの? 」っていう雰囲気はあった。このカートが亡くなった94年はベックがデビューした年でもあるんだけど、つまり時代の転換期でもあったんだよね。ベックが出てきた時はやっぱりすごく衝撃的だったし、話題にもなった。ベックをデビューさせたゲフィンも力を入れていたし。新しいヒーローの登場と共にカートが亡くなったというのはすごく象徴的な出来事だった。サブ・ポップ自体はたくさんのバンドをメジャーに送り出していったんだけど、ほとんどのバンドが2、3作で契約がなくなっていったし、次の方向性を模索していた時期だったと思う。で、サブ・ポップもニルヴァーナ以降のヒット・アーティストを探しあぐねていた。でも、そこに関連がないわけではなくて、ベックの『メロウ・ゴールド』はゲフィンからだったけど、本当のファースト・アルバム『ワン・フット・イン・ザ・グレイヴ』はK、つまりサブポップと同じワシントン州の小さなインディーズから出ていた。そこからベックというシンガー・ソングライターのスタイルを取るアーティストが出てきたことで、バンドではなく、一人でサンプラーとかを使ってすべての音作りをやっていくスタイルが広まっていくんだよね。94年はサブ・ポップにとって大きな転機だったと思う。で、実際、90年代後半のサブ・ポップはシンガー・ソングライターっぽい作品が揃っていったしね。
実は90年代後半が最良の時期だった!?
飯田 : 苦しかった時期と言われる90年代後半はどうだったんですか?
岡村 : サブ・ポップってどうもグランジのイメージが強いけど、今話したように実際は良質なソングライター、メロディ・メイカーを有するバンドだったり、歌に機軸を置いた作品作りをするバンドを契約するという一貫していたイメージが私にはある。例えば、ニルヴァーナ移籍後にレーベルの顔になったセバドー。セバドーもルー・バーロウのシンガー・ソングライターっぽさをきっちりと出したバンドとしてこの時期に大きく成長していく。『ベイクセール』もそうだし、『ハーマシー』ももちろんそうでしょ。
飯田 : 『ハーマシー』! もう最高っすよ! どう、セバドー好き?
—よく知らないんですけど、岡村さんからルー・バーロウの話はよく聞きます(笑)
岡村 : 90年代にセバドーを中心にソロやら別ユニットやらであれこれ作品を出しまくっていたルー・バーロウのフットワークの軽い動きは本当に面白かった。アメリカのインディー・シーンの多様化を象徴する人物だったと思う。もちろん、セバドーの『ハーマシー』は本当に名盤だよね。ルーのシンガー・ソングライターの資質が素晴らしく発揮されたアルバム。1曲も駄作がない。そんなセバドーの変化につられるように、90年代後半のサブ・ポップからは、ポップやカントリー、ラウンジ色が強いアーティストが出てきたね。

飯田 : ラウンジっすか?
岡村 : コンバスティブル・エディソンっていうバンドがいたの。当時のアメリカでは他にもシー・アンド・ケイクのアーチャー・プルウィットがやっていたカクテルズみたいにラウンジ系バンドが出てきた時期も一瞬だけどあって。あと、私が当時のバンドで個人的に好きなのがパーニス・ブラザーズ。これはサブ・ポップ90年代後半の個人的最重要バンド。前身バンドのスカッド・マウンテン・ボーイズからパーニス・ブラザーズの最初の数作までサブ・ポップ。彼らは所謂カントリーやフォークからの影響を受けたバンドなんだけど、これが今日のフリート・フォクシーズなんかが出てくる下地になっていると思う。
—すげー!
岡村 : 本当にそう思うよ。とにかくパーニス・ブラザーズの『オーヴァーカム・バイ・ハピネス』っていうアルバムは本当に名盤だから聴いたことのない人はぜひ聴いてほしいな。まだほんの10年ほど前のアルバムだけど。
飯田 : ホンマっすかー(笑)
岡村 : 向こうでもかなり評価が高いアルバム。日本にも来たことあって、私インストア・イヴェントの司会やったよ。今こそ再評価されるべきバンドかもしれない。とにかく『オーヴァーカム・バイ・ハピネス』は奇跡の名盤! あと、もうひとつ今日につながるアーティストとして大事なのはエリック・マシューズ。彼はオーケストラル・ポップ、チャンバー・ポップと呼ばれるアーティストで、今のフリート・フォクシーズとかにつながってると思う。だから90年代後半のサブ・ポップは、所謂ロックっぽい感じではないよね。一般的には話題になってなかったけど、個人的にはUSインディが面白かった時代という印象。方やアップルズ・イン・ステレオとかオリヴィア・トレマー・コントロールが所属したエレファント6辺りのビーチ・ボーイズ・フォロアーの流れがアメリカ中西部で動いていたのとほぼ同時進行で、歌ものや室内楽的なアーティストが多く出てきてて。ニルヴァーナとかマッドハニーはライヴ・バンドでもあったけど、この時期の人達はライヴももちろんやるけど、基本は室内型だった。アレンジやコーラスを重ねて作っていくような作品性の強いバンドを90年代後半のサブ・ポップは送り出していたんだよね。
スコットランド、グラスゴーとの絆〜所属アーティストの多国籍化
岡村 : 2000年代に入るとまた大きな動きが出てくるよね。アルバム・リーフとかポスタル・サーヴィスとか。極めつけはシンズか。
飯田 : この辺って売れると思ってました? アメリカでサブ・ポップのショーケースを観に行った時にポスタル・サーヴィスを観たんですけど、「なんやこれ?」って感じでしたけどね(笑)

岡村 : 音、ぼやーんとしてるからね。でもここでまたシアトルがポイントになってくる。つまりまたスコットランドと符合してくるの。さっき話したように、ヴァセリンズとニルヴァーナは一見は師弟関係みたいなものだけど、実際は同時進行で大西洋を挟んで起こっていたんだよね。これはティーンエイジ・ファンクラブの連中も話していたけど、シアトルとグラスゴーはバンドの体質が似てる、と。例えば、初期のパステルズの動きに影響を受けたビートハプニングがそのパステルズと一緒にライヴをやったり、ティーンエイジ・ファンクラブもニルヴァーナとツアーをしたり。シアトルとスコットランド、グラスゴーの絆みたいなのが明確にあった。で、2000年代にポスト・ロックっぽいアルバム・リーフやポスタル・サーヴィスが人気になった背景には、その少し前からグラスゴーにちょうどモグワイとかアラブ・ストラップが出てきた事実があると思う。方やモグワイがノイジーなインストのバンドとして出てきた時代に、シアトルではないけどサブ・ポップの新しい顔としてアルバム・リーフのようなバンドが出てきた事実。これはただの偶然とは言えないよね。同じように、ティーンエイジ・ファンクラブがニルヴァーナと一緒にツアーをやってた90年代初頭はノイジーな作風だったんだけど、カートが亡くなった後の90年代後半には徐々にルーツ・ミュージック色を強めていったのね。これもまたサブ・ポップ周りの動きと符合してると思う。
飯田 : 素晴らしい! そこでティーンエイジ・ファンクラブが出てくるのは衝撃的だなぁ。そういえばそういう聴き方してましたわ。
岡村 : そうそう。実際にグラスゴーのバンドと話したりすると、シアトルのバンドは他人の気がしないってみんな言うよ。
—なんかロマンチックですねぇ(笑)。じゃあ、CSS辺りまで行くとどうなんですか?
岡村 : CSSはブラジルのバンドでしょ。この辺からはゴー! チームとか、アメリカ、イギリス以外のバンドも多く取り扱うようになってくるんだけど、これはサブ・ポップが組織として大きくなってきたって事なんじゃないかな。
飯田 : まったく違いますからねぇ。
岡村 : まあCSSもゴー! チームも原盤はサブ・ポップじゃないからね。
飯田 : でもここで久々にサブ・ポップらしいのがガツンと出てきましたね。フリート・フォクシーズ。ここからまた動きはありそうですかね。

岡村 : 難しいところもあるけどね。今年の後半か来年にはフリート・フォクシーズの新作が出るはずだけど、ここで大味な作風に行っちゃうと厳しい。前作を踏まえてさらに深化させたような作品がまたヒットするようなら、時代の転機になるよね。彼らが意識しているかどうかはわからないけど、私としてはやっぱり90年代後半の流れがここで一巡りして彼らにやってきた感じはするな。そう考えると、今日的なサブ・ポップを紹介する上で大事なのは90年代後半なんだと思うよ!
キーワードは「サイケとフォーク」
飯田 : 最近のサブ・ポップは、ベティヴァーとかロウとか、僕の好きな感じなやつをまたガンガン扱ってくれてて。
岡村 : ベティヴァー移籍したんだっけ? それこそフリート・フォクシーズのヒットを見て、レーベルも「これはいける! 」と思ったのかな。フォーク系いける!とか。
飯田 : そう言えばノー・エイジもいるじゃないですか! あのバンド最高だと思うんですけど、DJやった時にかけるとあんまり受けないんですよねぇ。
—つまり今のサブ・ポップの柱を簡単に言っちゃうと、サイケとフォークって事ですか?
岡村 : うん、確かにその二つが柱と言っていいんじゃないかな。
飯田 : 今後のサブ・ポップはどうなっていきそうですかね?
岡村 : やっぱりサブ・ポップの伝統=歌ものやっていってほしいよね(笑)。あとは、アコースティック・ギターがちゃんと弾けるようなバンドには注目してほしい。これは自分の希望的観測も含めてだけど、やっぱりアコースティックをテクニカルに聴かせられる人で、尚且つちゃんとバンドでも演奏できる人がこれからはしっかり注目されていくような予感はあるんだよね。そういう意味ではトクマルシューゴがアメリカで評価されるのは象徴的だと思う。ああいう人達をちゃんと評価できる土壌があるならサブ・ポップもまだまだ冒険できるはず。一方のサイケな感じもまだ面白くなっていきそうだよね。この前ディアハンターのブラッドフォードが言ってたんだけど、サイケってともすればエスケーピズム(逃避主義)に行きがちで匿名性が高かったりもするけど、自分達はそうはありたくないんだって。とは言ってもかつてのカート・コバーンみたいな顔役になるような存在が出てくる状況ではなくなってきてて、バンドのメンバーの一人がエゴを出して全体を引率していくような形は成立しなくなってきているよね。でもそれは悪い意味ではないと思う。「ヒーロー不在の時代」みたいに言われるけど、彼らの意識ではヒーローは「楽曲そのもの」なんだよね。フリート・フォクシーズ、ノー・エイジ辺りはその象徴と言っていいんじゃないかな。

—いやーいい話がたくさん聴けましたね。僕なんかの世代だと、サブ・ポップはグランジのイメージが先行してしまいがちですから。
飯田 : そりゃそうでしょ。でもやっぱりセバドーもでかいなぁ。
岡村 : セバドーが何故生き残ってこれたかってことを考えると、やっぱりルー・バーロウがソングライターとしてしっかりしていたってことだと思う。彼はボストン出身でDC周りのハードコア・パンクの影響を受けつつ、ルーツ・ミュージックの要素も併せ持っていた。その両極端が作品に反映されていたからセバドーは面白かったんだよね。
飯田 : 本当に詩野さんはルー好きですよねぇ(笑)
岡村 : “日本で一番僕を好きなライターはたぶんキミだね”ってルーも言ってくれたよ(笑)。それだけに、ダイナソーJr.の再結成にばかり時間をとられてないで、そろそろちゃんとまたソロを出してほしいなあ。セバドーの新作がサブ・ポップからまた出る、なんて日が来るといいね。
サブ・ポップオールタイム・ベスト
岡村詩野
1.セバドー『ハーマシー』 / 2.パーニス・ブラザーズ『オーヴァーカム・バイ・ハピネス』 / 3.エリック・マシューズ『イッツ・へヴィ・イン・ヒア』 / 4.フリート・フォクシーズ『フリート・フォクシーズ』 / 5.ビートハプニング『ジャンボリー』
飯田 仁一郎(Limited Express (has gone?))
1.セバドー『ハーマシー』 / 2.ベティヴァー『タイト・ニット』 / 3.ノー・エイジ『ノウンズ』 / 4.グリーン・リバー『ドライ・アズ・ア・ボーン / レハ・ドール』 / 5. ウルフ・アイズ『ヒューマン・アニマル』
SUB POP CATALOGUE
Sebadoh
1986年結成。ダイナソーJr.のオリジナル・メンバー、ルー・バーロウを中心とした、3ピース・ローファイ・バンド。ローファイをメインストリームに進出させたバンドで、90年代のオルタナ・シーンで最も重要なバンドの一つ。即興的で壊れたメロディーと、ルー・バーロウによるダイレクトでありながら痛烈にロマンチックな歌詞の組み合わせは、まさに芸術作品。本作は、彼らの代表作であり、このアルバムから、「マグネッツ・コイル」、「スカル」、「リバウンド」と言った、ヒット曲が多数生まれた。
FLEET FOXES
2006年結成。シアトル出身5人組ロック・バンド。平均年齢23歳。出身地のシアトルの老舗インディペンデント・レーベル、SUB POPに所属。ロビン・ペックノールド(Vo/G)が、高校時代の同級生、スカイラー・シェルセット(G)と共に創作活動を開始。間もなく、残りのメンバーも加入し、現在の編成となる。海外では2008年2月、EP『Sun Giant』でデビュー。同年6月、デビュー・アルバム『Fleet Foxes』をリリース。 バンジョー、マンドリン、ピアノ、フルート等、多種多様な楽器を使い、壮大なサウンドと美しいコーラス・ワークで、デビューと共に世界中のメディアから大絶賛を浴び、2008年海外主要メディアの年間チャートの上位を独占した。(アルバム・オブ・ザ・イヤー1位獲得7誌。2位獲得2誌。現在、彼らのライヴのチケットは、世界中でソールド・アウトが続いており、現在、最も賞賛と注目を浴びるバンドである。Coachella Music Festivalを皮切りに、2009年、世界各国の主要ロック・フェスティヴァルに多数出演を予定している。
the Vaselines
スコットランドはグラスゴーにて、ユージン・ケリーとフランシス・マッキーによって結成。86年結成し、スタジオ・レコーディング楽曲19曲を残し90年に解散。その後、ニルヴァーナのカート・コバーンが大ファンであったことから世界的に再評価された。ヴォーカル/ギターのユージン・ケリーのエッジの効いたスクラッチ・ギターとフランシス・マッキーのメランコリックな歌詞、ユージンの乾いた声とフランシスのキャッチーで個性 的な声が上手く絡み合ったサウンドは、今もなお時代を凌駕するエヴァーグリーンな 世界。2008年、電撃的に再結成をし、今年のサマーソニック09で奇跡の来日が決定。
Mudhoney
1988年結成。シアトル出身。バンド名はラス・メイヤーの映画「マッドハニー」に由来。グランジ・オルタナティヴシーンの雄として、カート・コバーンやソニック・ユースに絶大な影響を与え、彼らからの尊敬を受ける。シアトル/SUB POPを代表するバンドとして全米のインディーシーンに君臨。92年には”シアトルの最後の大物”としてメジャー・レーベルに移籍するも、99年に再び SUB POPに戻り、結成後20年以上経った今でも、活動を続ける伝説的なバンド。
IRON AND WINE
フロリダ生まれのシンガー・ソングライター、サム・ビームによるソロ・プロジェクト。かつてはマイアミの大学で映画の講義で教鞭を奮っていた。2002年にサブ・ポップより『TheCreek Drank the Cradle』でデビュー。アコースティック・ギターを中心に生楽器で構成された温かみのあるサウンドで注目を集める。2004年にはキャレキシコとのコラボレーション・アルバム『In The Reins』をリリースし、2007年にはキャレキシコとの来日公演ツアーも行なうなど親交がある。2004年『Our Endless Numbered Days 』、2007年『The Shepherd‘sDog』は、合わせて全米60万枚を超える大ヒットを記録。一躍USインディー界の最重要アーティストとして認知されるようになる。2010年には待望のニュー・アルバムをリリースする予定である。
THE POSTAL SERVICE
デス・キャブ・フォー・キューティーのベン・ギバードと、Dntelのジミー・タンボレロからなるエレクトロ・ポップ・ユニット。バンド名は、シアトル在住のベンと、ロザンゼルス在住のジミーが、制作中の楽曲をCD-Rで郵送しあったことに由来する。本作「ギブ・アップ」は発売後ロング・セールスを続けており、Billboard 200では最高位114位ながらも、遂にはアメリカだけで100万枚を超えるセールスを上げ、21世紀、全米で最も売れたダンス・アルバムとなった。 SUB POPの作品としてはニルヴァーナーの「ブリーチ」以来となる大ヒット作である。